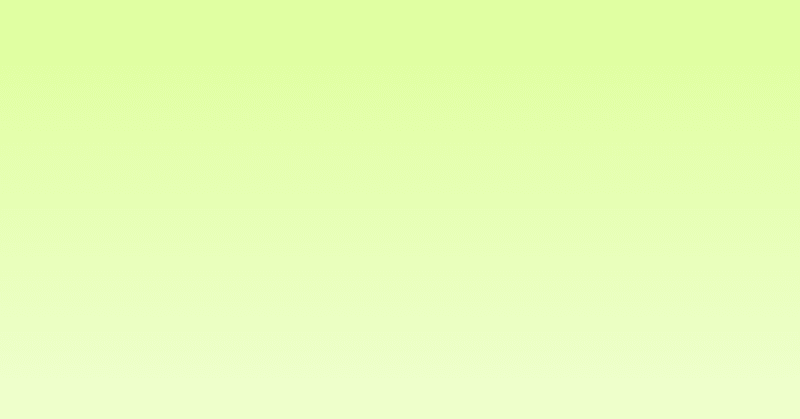
世界の呼吸する響き──庄司紗矢香&メナヘム・プレスラー『《雨の歌》LIVE』【名盤への招待状】第8回
ヴァイオリニストの庄司紗矢香とピアニストのメナヘム・プレスラーの演奏による、ブラームスのピアノとヴァイオリンのためのソナタ第1番《雨の歌》を、久しぶりに聴いた。2014年にかれらが日本で開いたリサイタルのライヴ録音である。
演奏が始まってほどなく、涙が込み上げてきた。光輪のように透明で、赤子を抱く腕のように柔らかいプレスラーのピアノと、濁りのない音色と清廉なレガートで丁寧に歌を紡ぐ庄司のヴァイオリン。感応し合う両者によって、音楽から世界の呼吸する音とでもいうような瑞々しい響きが引き出されてゆく。その息吹が、疲弊した私の身体中に染み渡り、生命力が蘇ってくるような感覚に満たされた。
プレスラーのピアノを聴いていていつも感じるのは、表現の底に透き徹った明るさがあることである。悲しみや苦悩の表現においてさえ、そこには常にその痛みの芯だけを照らすような光があり、音楽が沈潜の方向に向かうことがない。庄司のヴァイオリンは、明快な意志に貫かれながらも、表現が直情的にならず常にある種の抑制があり、その品格がプレスラーの柔らかな明るさと響き合う。クライマックスの場面でも、どちらもあくまでも密やかさを失わず、ブラームスの前に置かれているモーツァルトのソナタK.454とシューベルトのソナタ(二重奏曲)D574も含めて、互いの息づかいに耳を傾け合う親密なアンサンブルとなっている。
アルバム全体を通しては、プレスラーの生み出すあたたかい光に包まれながら、庄司が作品を追うごとに自在になってゆく様が印象的である。それぞれの作品の様式の弾き分けが巧みであるということでもあるが、次第にその抑制から押し出ようとするような歌が込み上げ、それらがせめぎ合い摩擦することで、演奏全体が熱を帯びてくるのである。
アンサンブルとしても、一作ごとに親密さと一体感を深めてゆき、やはりブラームスの演奏は別次元の高みに入っている。プレスラーのピアノはここに至って、その慈愛をスラーとスラーの間や小さな休符にまで染み透らせ、庄司のヴァイオリンも音間に宿る情感を洩らさず掬い取る。表現のどれもが意識的というよりも自然に、音楽に導かれるがままになされ、音楽は前に進んでいても感情は過去へと向かっているようなブラームスの時間が、ゆっくりと流れてゆく。
このソナタ《雨の歌》に限らず、ブラームスの作品は、時の流れに抵抗しているような要素が多い。複合するリズム、交替する強拍、直前の和声を引きずっているような音使い、相反するニュアンスの楽語の組み合わせ、(ピアノにおいて)音楽的に気持ちが逸る場面でも大きな跳躍があることで身体的には急げない…といった具合に。それは、彼の音楽がいつも、訪れるものよりも過ぎ去ったもの、あるいは過ぎ去りゆくものへの想いを抱きながら進んでいるからではないだろうか。
ブラームスは、師であるシューマンの死後、その妻クララ・シューマンと親密な関係にあった。シューマン夫妻の末子で、ブラームスが名付け親となったフェリックスは、結核を患い、二十四歳の若さで亡くなった。このソナタは、ブラームスが、フェリックスの死の報せを受けて、以前クララに送った彼の病状を見舞う手紙に書き付けていた楽想(第2楽章の主部となった)と、彼女が愛していたブラームスの歌曲《雨の歌》と《余韻》をモチーフに、クララのために作曲したものである。
このソナタには、クララを立ち直らせたり、前を向かせようとしたりするような押し付けがましさは全くない。フェリックスとの過去を愛おしむような、クララのあまりに大きな悲しみを、悲しみのままそっと抱きしめているような、大きな優しさだけがある。
私はこの作品を聴く度に、その優しさが、私の存在をも肯定してくれているように思える。庄司とプレスラーの演奏からは、特に、私という存在を「赦してくれている」というように感じられた。
ブラームスが、極めて親しい間柄にあったクララという個人の悲しみに寄り添うために書いた音楽が、時代や文化、あらゆる大きな隔たりを超えて、私という人間の存在をも受け止めてくれる。そして、庄司とプレスラーのデュオもまた、互いの息づかいに耳を傾け合う親密さを深めることで、世界の呼吸する響きを感じさせるほどの大きな境地に達している。それはつまり、最も個人的なもののなかにこそ、公的なもの、世界的なものと繋がるための何かが秘められているということであろう。
何か巨大な出来事や危機を前にしたとき、人はつい、自らがそれに対して直接的で即効的な力を持たないことを嘆いたり、そういった大きな問題に取り組むためには私的なものを犠牲にしなければならないと考えたりしがちである。しかし、私たちはいつでも、いま隣にいる人をこそ見つめ、かれを愛することから始めるべきなのではないだろうか。ブラームスたちの次元にまで至ることは難しくとも、ひとりひとりがそれをほんとうに実践しようとし続ければ、世界の呼吸も、保たれるはずだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
