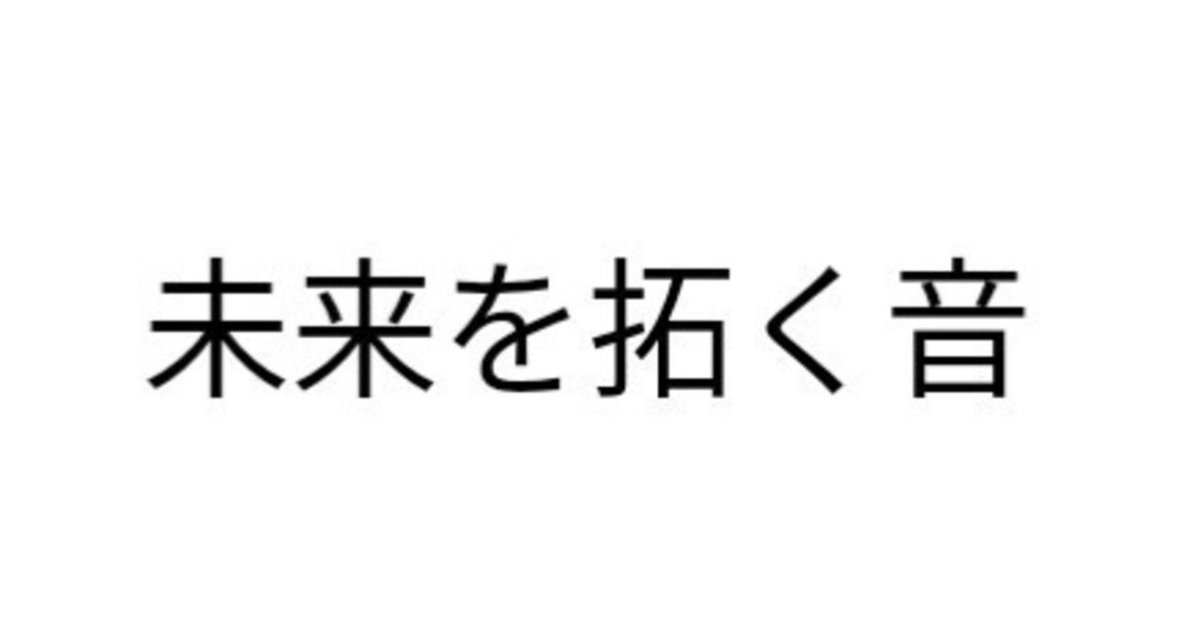
未来を拓く音――寺内詩織のバッハ
ロビーの中央に、誰でもない裸の男が立ち尽くしている。エレベーターホールを挟むかたちで、反対側のロビーにも、直線上に逆を向いた同じ男が立ち尽くしている。そこで、彼だけが時間を止めてしまったかのように。
多くの人は、彼の存在をほとんど気にも留めずに、あるいは一瞥をくれるだけで通り過ぎてゆく。中には立ち止まって彼を眺める人もいるが、ものの数秒である。気にはしているが、避けたという人もいるかもしれない。少なくとも、私がいるこのときは、彼を見つめている人は私の他にいないように思う。
東京オペラシティ2階のオフィスロビーにある、アントニー・ゴームリーの人体の彫刻『トゥー・タイムズ Ⅱ』。設置場所が、人通りのあるロビーであることによって、観る者は、誰もが他者と関わることができないという存在の孤独に、向き合わされる。
しばらく眺めていると、自分自身の姿を見ているような気がしてきた。それは、彼が誰でもないからだろう。誰でもないという空白に、観る者の内面が投影される。
その無名の男が、そこで「立ち尽くしている」と感じるのは、私自身がそうであるからなのだろう。未来の不透明性が語られて久しい今、進む道を見失い孤独に立ち尽くしているなかで、無情にも、世の中は移ろい、時間は過ぎてゆく。
同じオペラシティにある近江楽堂で開かれた、寺内詩織さんのJ.S.バッハの無伴奏ヴァイオリンソナタ&パルティータ全曲演奏会を聴いた(12月21日)。
1曲目のソナタ第1番の冒頭から、彼女の音自体に惹き込まれた。楽器が鳴りきっていることの快感も勿論あるが、それ以上に、その音に表れている、まっすぐな純真さに打たれた。
ゆるやかな楽章では、徒に沈潜せず、シンプルにしなやかに歌を歌う。一方で、疾走する楽章では、息もつかせぬ鮮やかさで駆け抜ける。とりわけ、パルティータ第1番のクーラントのドゥーブルは、何かに追い立てられているかのような、ただならぬ緊迫感だった。
全体に、息の長さと快活なテンポ感が印象的で、パルティータ第2番のシャコンヌのような壮大な楽章も、細やかでありながら、音楽に区切りをつけすぎず、流麗に聴かせる。また、6曲すべての演奏に、即興性や遊び心が溢れ、その表現の抽斗の多さも特筆に値するだろう。
バロックの様式への深い理解を感じる演奏だが、聴いていて、特段ピリオド的な指向性を感じるわけではない。情感に満ちているが、ロマン的に吐露するというわけでもない。彼女自身のまっさらな心に映し出されたものを、迷いなく表出している。バッハのあまりに巨大な世界に、畏敬の念を抱きながらも、まったく構えずに向かい合う。その、彼女という人間の衒いのない大きさに触れて、こちらの心も晴れてゆく。
後半のソナタ第3番に入って、寺内さんの音はさらに精彩を放ち始めた。まばゆいほどの輝きが漲っている。ただ輝かしいだけではない、悲しみや運命を受け入れている人だけがもつ、深い、強い輝き。……
寺内さんのヴァイオリンの音が、暗い未来に向けて光を広げてゆく。その光に導かれ、進む道を見失い立ち尽くしていた私も、歩き始める。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
