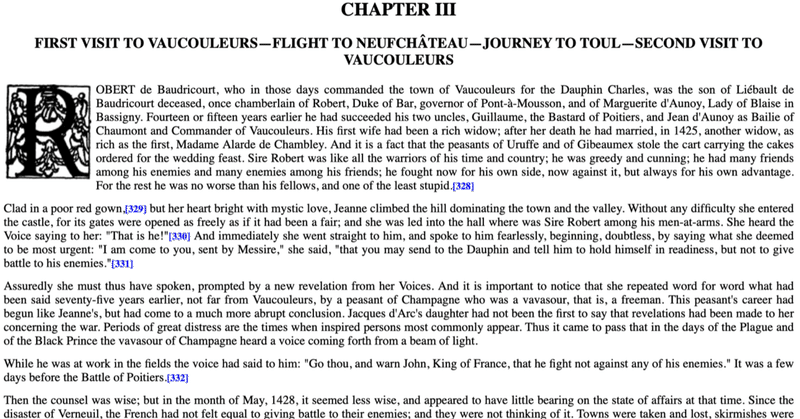
【教皇庁†禁書ジャンヌ・ダルク伝】上巻③ヴォークルール初訪問〜ヌフシャトーとトゥールへの旅~ヴォークルール再訪
アナトール・フランス著「ジャンヌ・ダルクの生涯(Vie de Jeanne d'Arc)」全文翻訳を目指しています。原著は1908年発行。
1920年、ジャンヌ・ダルク列聖。
1921年、A・フランスはノーベル文学賞を受賞しますが、1922年にローマ教皇庁の禁書目録に登録。現在、禁書制度は廃止されていますが、教皇庁は「カトリック教義を脅かす恐れがある禁書だった本を推奨することはできない」という立場を表明しています。
目次一覧とリンク集↓↓
Chapter III.
First Visit to Vaucouleurs. Flight to Neufchâteau. Journey to Toul. Second Visit to Vaucouleurs
(ヴォークルール初訪問〜ヌフシャトーとトゥールへの旅~ヴォークルール再訪)
字数が多い(約1万6000字)ため、訳者の裁量で「小見出し」をつけています。
3.1 ヴォークルール初訪問
当時、王太子(シャルル七世)のためにヴォークルールの町を指揮していた司令官ロベール・ド・ボードリクールは、かつてのバル公ロベールとポンタ=ムーソン知事とブレーズ公女マルグリット・ドーノワの侍従であったリエボー・ド・ボードリクールの息子であった。
14~15年前、ロベール卿は叔父(ポワティエの庶子ギヨームと、ショーモンの地方役人と、ヴォークルールの司令官ジャン・ドノワ)から役目を引き継いだ。最初の妻は裕福な未亡人であり、彼女の死後、1425年には最初の妻と同じく裕福な未亡人、アラルド・ド・シャンブルイと再婚した。
ロベール卿は、かの時代とかの国のすべての戦士のように、貪欲で狡猾で、敵の中に多くの友人がいて、友人の中に多くの敵がいた。それ以外の者にとっては、彼は仲間よりも悪くなく、もっとも愚かな者の一人であった。
ジャンヌはみすぼらしい赤いガウンを身にまとい、それでも心の中は神秘的な愛で輝いていた。ジャンヌは町と谷を見下ろす丘を登っていった。城門は祭日のように自由に開放されていたので、ジャンヌは難なく城に入ることができた。
ジャンヌは声を聞くと「あの人だ!」と、すぐにロベール卿のところへ行き、恐る恐る話しかけた。
「私はメシアの使いとしてあなたのところに来ました」
ジャンヌは続けた。
「王太子に使者を送って『準備をしておくように』と言ってください。だけど、『敵に戦いを挑まない』ように」
このようにして、ジャンヌは「声」からの新たな啓示に促されて話した。
ここで注目すべきは、ジャンヌはこの時、75年前にヴォークルールからほど近いシャンパーニュ地方のある農民が言ったことと「一言一句」同じ内容を繰り返していたという事実である。
この農民が受けた啓示はジャンヌと同じように始まったが、短期間で結末を迎えた。
ジャンヌ・ダルクは、この戦争(※百年戦争)に関する啓示を受けた最初の人ではなかった。
大きな苦難の時代は、神がかりな人物がよく現れる。百年戦争初期、黒死病(ペスト)と黒太子の時代に、シャンパーニュ地方のある農民は光の束から「声」を聞いた。
彼が畑で働いているとき、ふいに声が聞こえた。
「フランス王ヨハネ(※ジャン二世・シャルル七世の曽祖父)に警告しなさい。敵と戦うなと」
ポワティエの戦いの数日前のことである。
この戦いで、ジャン二世はイングランド軍に捕らわれて捕虜となり、フランスは莫大な身代金を払わされた。
しかし、1428年5月のジャンヌの「声」は、当時の戦況とはほとんど関係ないように思われた。ヴェルヌイユの戦いでフランスが大敗して以来、フランス人の心は折れてしまい、敵に戦いを挑もうとは考えなくなっていた。いくつもの町が奪われ、消滅し、小競り合いが起き、同盟が試みられたが、激しい戦闘にはならなかった。
このころのフランスは運の巡り合わせが悪く、シャルル王太子は引きこもりがちで、わざわざ「敵に戦いを挑むな」と警告する必要はなかった。
3.2 ジャンヌの予言
ジャンヌがロベール・ド・ボードリクール卿に話をしていた頃、フランスを占領しているイングランド軍は遠征の準備をしており、アンジェに進軍するかオルレアンに進軍するかを決めかねていた。
ジャンヌは大天使と聖女の勧めにしたがって言葉を発したが、戦争と王国の状況は、ジャンヌが知っている以上でも以下でもなかった。
しかし、自分自身が神に遣わされたと信じる者が、待っていてほしいと願うのは当然のことである。フランスの騎士が再び誇りを取り戻して戦いを挑むのではないかと、ジャンヌは不安を感じていたし、民衆の良識がそう思わせていた。騎士の戦いをよく知っていたからだ。
ジャンヌは、「四旬節(レント)の半ばまでに、主は王太子に援助を与えるでしょう」と王太子に関する予言を口にした。
「ですが、実際には、王国の領地は王太子のものではありません。メシアの意志によって、王太子は王となり、王国を『信託(アン・コンマン)』されるのです。王太子は敵がいようとも王となります。そして、王太子をその塗油式に導くのは私です」
メシアという言葉は、曖昧で奇妙な響きだった。
ロベール卿は理解できずに「メシアとは誰のことだ」と尋ねた。
ジャンヌは「天界の王です」と答えた。
このとき、ジャンヌはもうひとつ、奇妙な言葉を使った。
ロベール卿は何も言わなかったらしいが、示唆に富む言葉だった。
王位継承に関して使用された「アン・コンマン(en command)」という言葉は、「信託で与えられるもの」を意味する。もし、王が王国を「信託」で譲り受けるというならば、王国は王のものではなく、単に神の信頼によって王国を預かっているにすぎない。ジャンヌの発言は「王国の支配者は神である」という信心深い宗教家の解釈と一致していた。
ロレーヌの予言を通じて、ジャンヌは教会の誰かに影響され指導を受けていたことは明白だが、現在まで、黒幕の痕跡は完全に消えてしまっている。
ジャンヌは何人かの司祭に相談していた。ゴンドクール・ル・シャトーのアルノラン司祭やムティエ・シュル・ソール司祭やドミニク・ヤコブ司祭はジャンヌの懺悔聴聞僧であった。
この聖職者たちが、イングランドの飽くなき残酷さやブルゴーニュ公の高慢さや王太子シャルルの不幸についてどう考えていたのか、わからないのが残念である。いつの日か、庶民の祈りのもとに我らが主イエス・キリストが、シャルル六世の息子シャルルに王国を与えてくれることを願っていたのだろうか。
ジャンヌは、この中の誰かから神権主義的な思想を吹き込まれたのかもしれない。
ジャンヌがロベール・ド・ボードリクール卿に話をしている間、ロレーヌの騎士ベルトラン・ド・プーレンギーが同席していた。彼はゴンドクールの近くに領地を所有し、ヴォークルールの司教職に就いていた。当時36歳くらいであった。
ベルトランは教会の人たちと付き合っていたが、少なくとも信心深い人たちの話題に詳しかった。この国の状況をよく知っていたし、女神の木の下に座ったこともあり、ジャック・ダルクとロメ夫婦の家にも何度か行ったことがあるので、彼らは善良な農民であると知っていた。
ベルトラン・ド・プーレンギーは、ジャンヌの言動に心を打たれたかもしれないが、それ以前に、私たちの知らない「ジャンヌを導いた聖職者」と接触していた可能性が高い。
どちらにしても、ベルトランはジャンヌの強い支えとなる友人になった。
情報が正しければ、この時のベルトラン・ド・プーレンギーは何もせず、何も話さなかった。おそらく彼は、町の司令官であるロベール卿がジャンヌの話を好意的に聞くことができるようになるまで待った方がいいと判断したのだろう。ただ一つだけ、ジャンヌは立派な従軍者となり、軍人たちから気に入られるだろうと確信した。
ロベール卿は、ジャンヌを追い返すとき、当時よくありがちなしつけに従って「この娘を父親のところに連れて帰り、耳に蓋をしろ」と忠告した。
ロベール卿は、子供を懲らしめる体罰は正しいと信じていたので、ラッソワ叔父さんに何度も「ジャンヌを鞭打って、家に連れて帰るように」と勧めた。
3.3 家族と故郷の人たちの反応
一週間後、ジャンヌは村に戻った。司令官の屈辱も守備隊の侮辱も、ジャンヌを落胆させたりすることはなかった。彼女は「声」がそれらを予言していたのだと考え、自分の使命が真実であることを証明するものだと思った。
夢遊病者のように、ジャンヌは壁にぶつかっても落ち着いていて、静かに粘り強くその時を待った。家の中でも、庭でも、草原でも、ジャンヌは夢を見続けた。
次第にジャンヌは黙っていることができなくなり、しょっちゅう予言を話したが誰にも信じてもらえなかった。
帰宅して約1ヶ月後、洗礼者ヨハネの祝日前夜に、ジャンヌはビュレイの主人であるミシェル・ルヴァンに向かって、少年のような口調で「クシーとヴォークルールの間に少女がいる。今から1年も経たないうちに王太子はフランス王に叙任されるだろう」と言った。
ある日、ドンレミで王太子の支持者ではないジェラルダン・デピナルに会った。ジャンヌは彼の首を切り落としてやりたいと思っていたが、そんな相手にも黙っていられなかった。
「もし、あなたがブルゴーニュ派でなければ、教えてあげたいことがあるの」
この男は、ジャック・ダルクの娘はもうすぐ結婚するのではないかと考えた。女神の木の下で一緒にパンを食べたり、グーズベリーの泉の水を一緒に飲んでいた若者の誰かと結婚するのではないかと。
気の毒だが、父親のジャック・ダルクは「そのような秘密だったらどんなに良かったか」と望んでいただろう。彼は子供たちの行動に気を配っていたが、ジャンヌの行動は父を不安にさせていた。彼はジャンヌが声を聞いたことを知らなかった。ジャックは彼の庭にしょっちゅう楽園が降りてきて、天界から彼の家にはしごが降りてきて、天使や聖女が現れては行き交っていたとは考えもしなかった。信じられないような奇跡や驚異について考えるには程遠かった。
父ジャックが見たものは、娘が正気を失い、心が迷い、乱暴な言葉を口にしていることだけだった。ジャックは、娘が騎士と戦争のことしか考えていないことを知っていた。ヴォークルールで何かしたことを知っていたに違いない。ジャックは、この不幸な子がいつの日か放浪の旅に出てしまうのではないかと、ひどく恐れていた。
この不安は寝ている間も彼を悩ませた。ある夜、ジャックはジャンヌが武装した男たちと村から逃げていく夢を見た。それから数日間、ジャックは息子のジャンとピエールに何度も何度も言った。
「あの夢が実現するくらいなら、その前におまえたちの手でジャンヌを川に沈めて溺死させる方がマシだ。おまえたちが嫌なら、俺自身の手でやる」
母親のイザベルは、父の言葉を何度もジャンヌに言い聞かせた。娘の目を覚まして、道を正すように願っていた。敬虔なジャンヌの母親は、父親の不安を共有していた。娘が道を外れて危険にさらされるのではないかという考えは、善良な人々にとってつらいことであった。
困難な時代には、武装した男たちと連れ立っている野蛮な女たちが大勢いた。兵士たちはそれぞれ自分の女を確保していた。
若き日の聖人が、常人には理解できない奇妙な言動をして、家族に不安と疑念を抱かせることは珍しくない。ジャンヌはそのような聖人の兆候を示していた。
彼女は村で話題になっていた。村人たちはジャンヌをあざ笑い、指を差しながら「フランスと王家を再建する女が現れた」とからかった。
近所の人々は、ジャンヌに取り憑いている狂気の片鱗を見つけるのに苦労しなかった。
以前、女神の木の下で花輪を飾っているのが目撃されていたから、魔法の呪文のせいだと言われた。古いブナの木は近くの泉と同様に、妖精に取り憑かれていることで知られていた。妖精たちが呪文を使うことも知られていた。「ジャンヌは悪い妖精に会ったのだ」と言った人もいた。「ジャンヌは女神の木の下で『運命(フェイト)』に出会った」と言われた。農民以外の誰もがその話を信じていなかっただろう。
【※誤字脱字・誤訳を修正していない一次翻訳はこちら→教皇庁†禁書指定「ジャンヌ・ダルク伝」】
ここから先は
¥ 100
最後までお読みいただきありがとうございます。「価値がある」「応援したい」「育てたい」と感じた場合はサポート(チップ)をお願いします。
