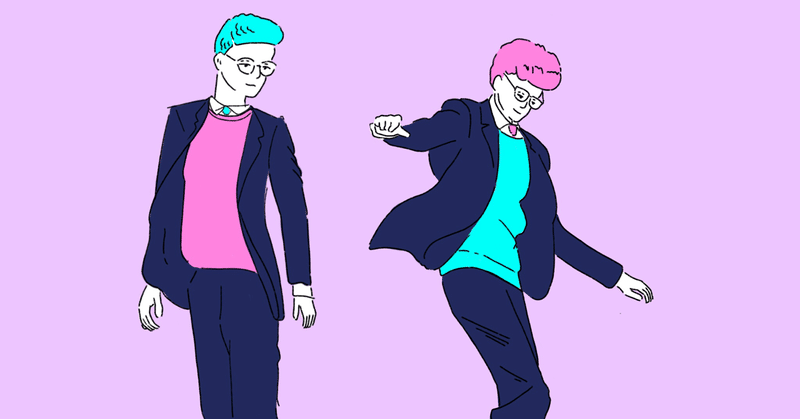
美術館に行くのが趣味だけど、部屋はとっ散らかってるし美意識なんて生まれた時から冬眠してるし。
偉そうに大言壮語を羅列したが、
これから書く内容は、全て私がコンサルのインターンをしているときに「美術館巡りが趣味なんすよ〜!山口周とか読んで好きでw」と表参道のランチで口走ったことがきっかけで上席に「お前のスライドには美意識が微塵も感じられないのに、美術館なんて行ったことがあったのか」とボコボコに20分間ほど詰められたトラウマを言語化するために書いた、文章療法のようなものである。
さて、はじめよう。
***
美術館に行くのが趣味のくせに、部屋はとっ散らかって汚い人は嘘だ。
美術館は絵の隣にある説明文を、したり顔で読む場所ではない。
美術館に来る前の電車で、美術展について調べて、駅中の書店で関連する新書を一冊読んで、楽しみに胸をいっぱいにして向かうのが礼儀ではありませんか。
感性を全開にして芸術の息吹を全身に浴びる場所だ。
満員電車で体をこわばらせて、おじさんの体臭をできるだけ鼻から吸わないようにしている日常に流されて、感性は放っておくと鈍くなる。
摩耗して弱った感性を瑞々しく蘇らせるのが、美術館だ。森林浴と似ている。
蘇生した感性で、自分の部屋を見る。
自分のファッションを眺める。
あまりのダサさに絶望する。
日々食べたもので、体は作られる。
感性も、日々見ているものでスタンダードが作られる。
ギリシア神殿でも、西洋の宗教画も、全ての絵画は当時最先端のオシャレな装飾を凝らした建物の中に、飾られた。
美しい家具が美しい家に飾られるように、美しい絵は美しい建物とセットで眺められてきた。
そして絵を鑑賞する貴族は、幼少期からそんな最先端のデザインの建物で生まれて、絵や彫刻に囲まれて育ち、目を養った。
民主主義の浸透で貴族階級の力が弱まり、現在の絵画はそのような絵の描かれて飾られた背景とは切り離されて、美術館にぽんと放り出されている。
例えば、365日ゴミだらけの家に住み、体のサイズに合わない服をきて探していても、1日思い立っただけで、美術館に行って絵を眺めることは出来る。
そして「ゴッホ見たけど大したことなかった」とか好き勝手な感想を呟く自由に開かれている。
しかし、絵と対峙するなら、日々に淡々と磨き続けた感性で向き合いたい。
全く勉強をしたことがないのに、入試の日だけふらっと試験に行っても試験問題の意味がちんぷんかんぷんだ。
小学校から高校、浪人までの学びの蓄積を叩きつけるのが大学受験だし、それゆえに学歴は尊い。
あらゆる勝負は、試合が始まる前に99%決まっていて、当日はその結果を確認しに行くようなものだ。
絵も同様だ。
美術館に行く前に前提知識を学び、日々の部屋やファッションや付き合う人との会話でも感性を研ぎ澄まし続ける。
研ぎ澄ました牙を突き立てにいくのが、美術館に行く当日だ。
「今日の絵なんだっけ〜」
「なんか分からないけど凄かった〜」
なんてもののために行くのではない。
そんな鑑賞の仕方で「美術館に行ったから感性研ぎ澄まされるっしょw」みたいなことは、一才ない。
「21世紀はしなやかな感性でビジネスをする時代だ。だから美術館に行こう」と主張した山口周も、「美術館にただトコトコと無目的に行くだけで美的感覚なんて良くならない。日々の生活がほとんどを決める。」とあるインタビューで断言していた。
美術館に「行くか」「行かないか」というディベートのテーマにすらならないような、レベルの低すぎる二項対立はさっさと捨てたい。
本を「読むか」、「読まないか」とも似ている気がするが、本はそもそも読むのが前提なのだ。その上で、限られた時間と気力を注ぎ込むなら、何をどのように読むか、という次元まで話を繰り上げて、ようやく議論の対象となる。
美術館に行っても、なんだか「え、美術館巡りが趣味っていうけど、話しててもそんな雰囲気が微塵も感じない」
「失礼だけど、マックでハンバーガー食べてる姿しか想像できない」という人はいくらでもいる。
まず自分がそうかも、と自覚する。
そして、そうならないためには「センスがいい」ひとは何を意識しているのか、と考え始めるようになったところが一流の階段のスタート地点だ。
ところで、上席が私を詰めた理由が「月に一回も美術館に行くなら、そんな美意識が反映されていないパワポになるはずがない。時間とお金を掛けただけのアウトプットになっていないから、どこか考え方か行動に致命的なものがあるはずだ、というコンサル的な視点で私に話を聞き始めたことが、怒られながら面白いと思ったものだ。
話が変わるが、私は弱いながらも合気道の有段者なのだが、師範が「合気道で段を持つということは、24時間合気道の視線で生活を送れるようになることだ。ただ、小手先のテクニックのように知っている技の数を覚えていることではない」と告げていた。
ふとその師範を思い出した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
