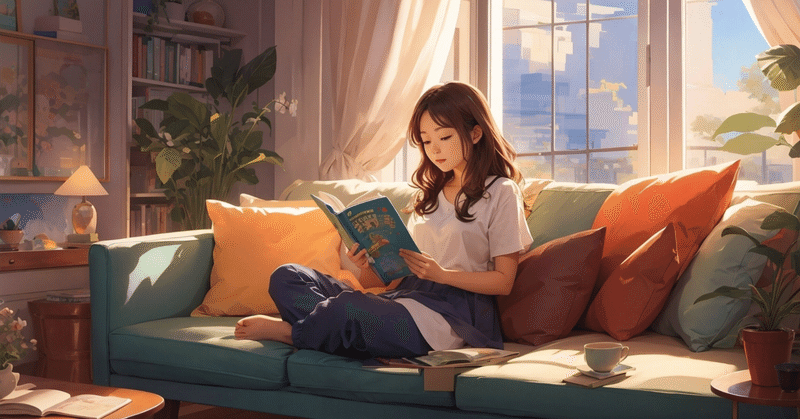
芸術をテーマにした読書
昨日は「線と僕を描く」について書いていきました。
芸術をテーマにしている小説は、なかなかそれを文字だけで連ねていくのは難しいと思います。
でも、すごくわかりやすい。
特に「水墨画」は全く日常の世界とはかけ離れていくのでイメージがしずらかったものの、その世界をきちんと伝えつつ、
主人公の内面にも迫ってくれました。
映画化もされているんですね。
かなり設定は違うようですが、観てみたいと思います。
人間の内面を突き詰める小説は面白い
やはり秀逸だと思ったのは、
主人公の内面の葛藤を、これでもかとあらゆる言葉を使って表現してくれていたところ。
作品と向き合うということは、自分と向き合うということ。
何を描きたいのか。
賞賛されること、承認されることを超えたところにある、
自分自身をただ、表現するという作業。
技術を追い求めた方がもはや楽なのではないか、
しかし技術だけを追い求めると、
それがまた作品に残酷なほど表されてしまう。
読み手にとっては知らない世界、わからない世界なのにも関わらず、
読んでいると「水墨画」の世界に惹きつけられてしまう。
こういう小説は面白いですね。
さて、感動したからこそ、前置きが長くなってしまった。。。
せっかくなので今日は「蜜蜂と遠雷」についても。
昨日のブログでも「蜜蜂と遠雷」についてはちらっと触れました。
改めてこちらもみんなに読んでほしい作品です。
「音楽」を「小説」にするということ
こちらは同じ芸術でも音楽の話。
世界的に有名となった芳ヶ谷国際コンクール。
このコンクールで大賞を獲るのは誰なのか。
これだけ紹介するとすごくサラッとありそうな小説なんですが、
まずは「音楽」を「小説」にする挑戦。
これが物凄いことだと思うんです。
音楽は、耳から感じる芸術。
小説は、目から感じる芸術。
それなのに、音楽を目から感じさせようと挑んでいるところに、
そもそも著者である恩田陸さんの覚悟を感じます。
文庫版のあとがきには編集者の方の記載がありましたが、
(私が)著者の最高傑作なのではないかと思う一方で)編集者の方から見ているとこの小説はやはり、途方もないほどの「産みの苦しみ」があったようです。
読むのは簡単だけど、やっぱり書くのって本当に大変なんだよな。
当たり前だけど。
音を文字で「聞かせる」にはまず語彙が必要。
「線は僕を描く」でも思ったけれど、
専門用語を使いすぎても読者にはわからないし、
かといって使わなければ、リアリティに欠ける。
だからこそ、読者にわかるように説明しながら、
その世界に没入させていく。
芸術をテーマにしながら「売れる」小説は、
やはりその辺りの塩梅が非常に上手です。
「蜜蜂と遠雷」もピアノを題材にしながら、
やっぱり技術を超越した世界を描いてくれています。
また、この小説の面白いところは、
コンテスタント(出場者」だけでなく審査員(評価者)の方からの視点も描いているところ。
結局のところ芸術とはいっても、
人間が作り出したものであり、
審査の中で審査員も試される。といった視点が、
読み手に緊張感すら抱かせてくれていました。
ここに毎日つらつらと、思うことを書いていても、
やっぱり語彙があるといいよなぁと思います。
今日の2作品に共通しているところは、
使われている日本語が非常に美しい、というところ。
美しい日本語を使いながら、
日常を過ごしていきたいものです。
ここまで読んでいただいてありがとうございます!
Instagramでは、最近読んだ本の紹介をしています。
興味がある方は是非覗いてみてくださいね↓↓
https://www.instagram.com/enjoy.reading._/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
