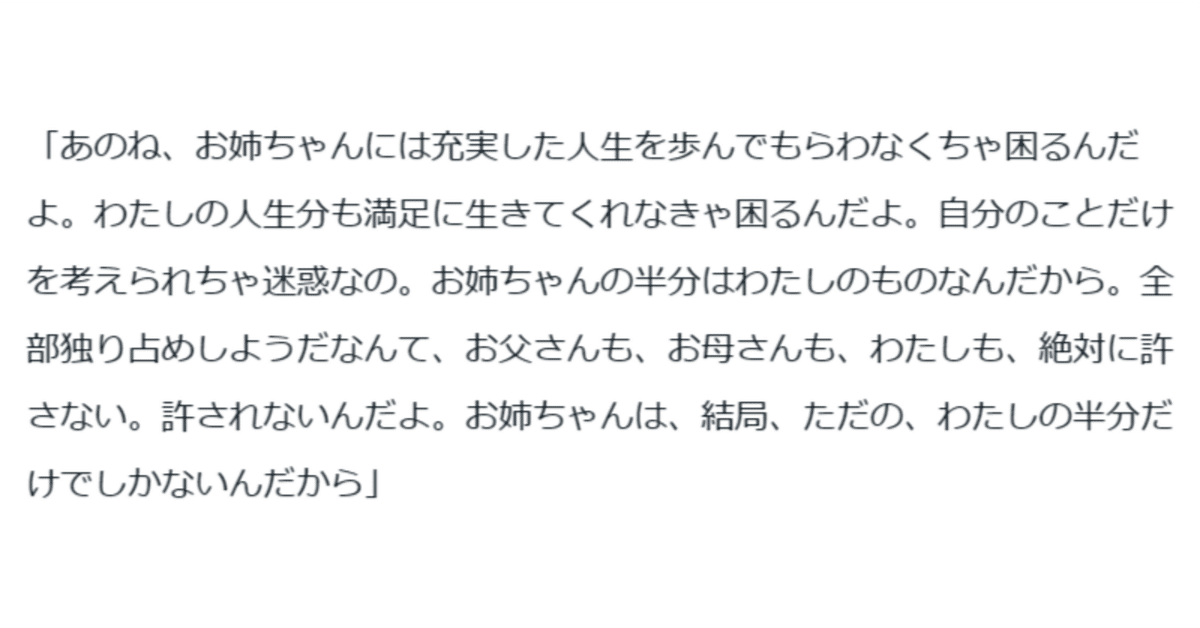
I don't know(小説)
妹は死産だった。
それがひどく悲しいことであることは、八歳の私にも充分に理解できていたはずで、だからこそ私は母や父と等しく、病院でぼろぼろと大粒の涙を流しことを今になっても鮮明に覚えている。
ゆえに、私が二人と同じように狂えなかった理由は、未だにわからない。
両親は、お姉ちゃんは妹の分まで生きてね、と、ことあるごとに言った。 しかし本来、それはあくまでもそういう“類い”の言葉であるはずであって、本当にそうさせるものではないはずなのだ。
両親は妹の命日になると、
「きょうは、誕生日だからね」
と言って、私に綺麗にラッピングされたプレゼントを渡した。
妹が生きていたら、と仮定した年齢に合わせた玩具は、八つも年上の私には何の面白みもない。
妹の三回目の命日、両親は私に子犬の玩具を渡した。プッシュボタンを押すと、わんわん、わんわんと鳴く、短いコード付きの犬。鳴き声よりもモーター音のほうがずっと力強く響く。他に機能はない。
その頃の私は、クラスで流行っていたゲームと、それに使うゲーム機がほしかった。その年の誕生日、私は図書券をもらった。
家族の祝い事のたび、私だけ二人分の食事と、二人分のケーキを食べさせられる。私は祝い膳もケーキも大嫌いになった。
いつだって家族写真には真ん中に私、片隣に父、その反対に母。母と私の間には子ども一人分の透き間が空いている。まるで、見えない妹を母が守っているみたいに。その一人分の空白は、母と私の隔たりを如実に表しているようにすら思えた。
きっと、鏡の中に妹が見えるようになったのは必然だったのだろう。
鏡の中の妹はいつも私に、
「生きててずるいね」
とか、
「生きてるんだからそのくらい我慢したらいいじゃない」
と吐き捨てる。
鏡の中の妹は、私が一人分だけの命を全うしようとすることを徹底的に阻止した。その様子はまるで「妹の分まで生きなさい」と強制する両親とよく似ていて、だから私は鏡の中の妹がただの幻影であることも理解しているつもりだった。
幻影は言う。
「あのね、お姉ちゃんには充実した人生を歩んでもらわなくちゃ困るんだよ。わたしの人生分も満足に生きてくれなきゃ困るんだよ。自分のことだけを考えられちゃ迷惑なの。お姉ちゃんの半分はわたしのものなんだから。全部独り占めしようだなんて、お父さんも、お母さんも、わたしも、絶対に許さない。許されないんだよ。お姉ちゃんは、結局、ただの、わたしの半分だけでしかないんだから」
妹が生きていたら中学に入学するだろう少し前、両親は私を連れて地元の中学の制服を買いに行った。私は二十歳になっていた。
煌びやかに振袖で着飾るはずの年齢の私が、小学校を卒業したばかりの子どもたちと並んで地元のデパートで制服に袖を通すのは、旗目に見てもひどく滑稽で、ひどく歪で、恐ろしいほどに異常だっただろう。
でも、私の家はずっとそうだったのだ。そして、これからもずっとそうなのだろう。
妹が高校に進学する時期になれば、私はまた両親からの呼び出しを受け、一人暮らしのアパートから二人と“妹”の暮らす自宅へ出向き、二人が望む高校の制服を着させられるはずだ。
試着室、個室の鏡に向き合うと、制服に袖を通した妹が私を見て笑っている。
私を見て、嘲笑っている。
「お姉ちゃんがわたしに全部をくれてたら、そんな恥なんてかかなくて済んだのにねえ」
そう言って、嗤っている。
そんな気がしている。ここに私はいない。
私はどこにもいないのだ。
(「I don't know」24.1.10)
ここから先は
¥ 110
頂戴したお金は本やCD、食べ物など、私の心に優しいものを購入する資金にさせていただいています。皆さんありがとうございます。
