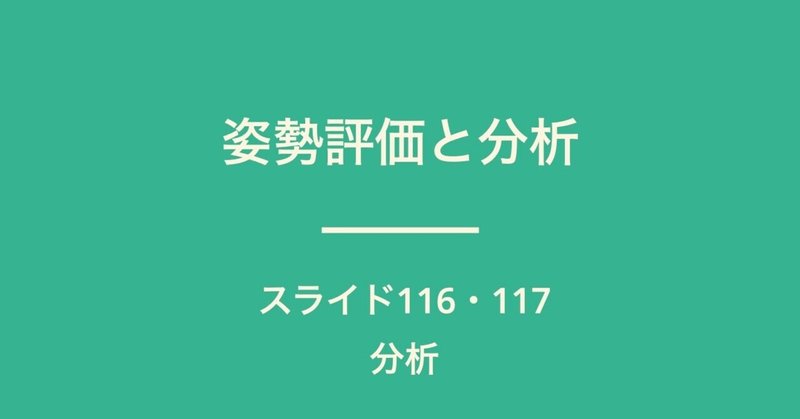
【姿勢評価と分析〜なぜ姿勢は乱れるのか?〜スライド116・117 分析】
Shape-labで開催している「姿勢評価と分析〜なぜ姿勢は乱れるのか?」セミナーのスライドに解説文を加え、ご紹介しています。
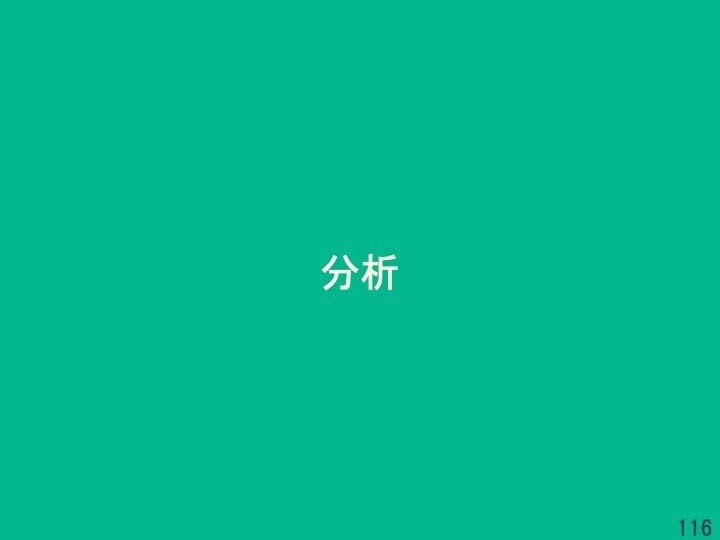
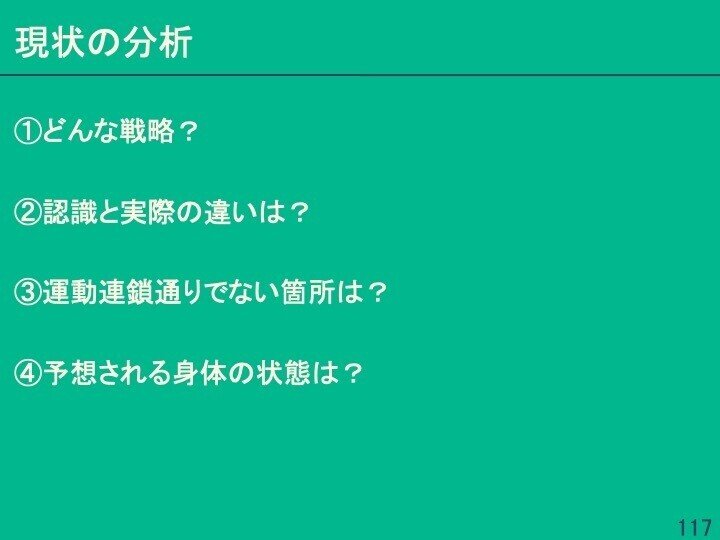
□スライド116・117
全身の姿勢を評価しました。姿勢評価だけでは、クライアントのすべてを知ることはできませんが、姿勢評価の結果をもとにクライアントの状態を、以下4つの質問を参考にして予測してみましょう。
①どんな戦略?
②認識と実際の違いは?
③運動連鎖通りでない箇所は?
④予想される身体の状態は?
①どんな戦略?
評価したクライアントは、どんな戦略を用いて姿勢をとっているのか?やじろべえの解説を参考に考察をしましょう。
例1のやじろべえ 前後左右が均等に近い姿勢
例2のやじろべえ 前後左右偏っている姿勢
・代償していない姿勢
・一部の筋肉で支えているため負担がかかっていえる
例3のやじろべえ 前後左右で偏っていて、身体の一部を用いてバランスをとっている姿勢
・代償している姿勢
・例2の姿勢よりは、負担を分散させている
②認識と実際の違いは?
評価を行い、クライアントが感じていた姿勢(認識)トレーナーが見た姿勢(実際)と、違いがあった部位はどこか?考察をしましょう。
例:
・肩の高さが同じだったとおもっていたが、実際は違った。
・そもそも、基準を知らなかったから、身体の状態に問題があると思っていなかった。 など
③運動連鎖通りでない箇所は?
全ての部位が基準と同じ姿勢だった場合をのぞき、基準からズレている部位が必ずある姿勢となります。
ズレている部位と周辺の部位が、運動連鎖通りなのか?運動連鎖通りでないのか?を考察し、運動通りでない箇所を探します。
例:
胸郭が後弯している
↓
1)肩甲骨が外転している
→運動連鎖通り
2)肩甲骨が基準通りもしくは内転している
→運動連鎖通りでない
運動連鎖通りでない場合、筋肉の長さ・筋出力や他の組織に問題がでる
○補足
基準が外れた部位と隣り合う部位が運動連鎖通りでない場合と、基準から外れた部位から離れた部位が運動連鎖通りでない場合、後者の方がより組織に負担がかかる。
例:
1)胸郭後弯→肩甲骨は基準→上腕骨外旋
2)胸郭後弯→肩甲骨外転→上腕骨外旋
この場合、2の上腕骨外旋筋の負担が大きい
④予想される身体の状態は?
評価したクライアントの姿勢で、予測される身体の状態もしくはやりやすい運動・やりづらい運動は何か?考察をしましょう。
(①〜③結果を整理し、動作を行なった場合やりやすい動作、やりにくい動作などを予測する)
【以下のSNSで公開されている記事を閲覧することで、すべてのスライドを閲覧することができます】
▶︎Shape-lab Instagram
https://www.instagram.com/taisei_okamura
▶︎Shape-lab Facebookページ
https://www.facebook.com/shape.lab.net
▶︎Shape-lab blog
https://ameblo.jp/1980sc
▶︎Shape-lab主催セミナー参加者限定のFacebookグループ
→Shape-labのセミナーに参加した方のみご参加可能のグループ
□スライドの購入↓
□セミナーのご参加↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
