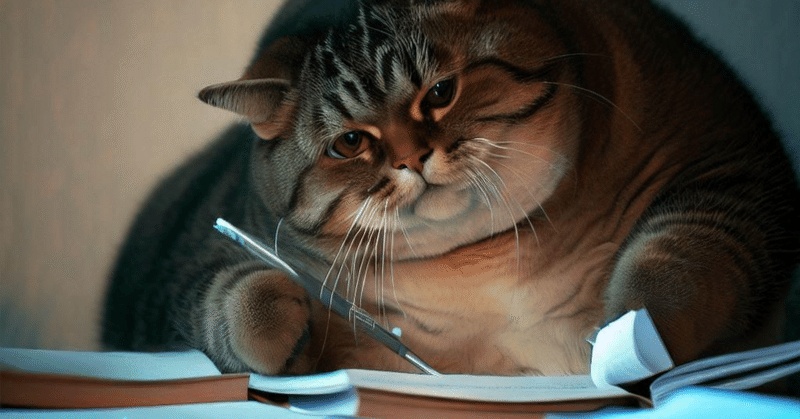
インプットによる研鑽を継続する弁護士の学習方法
法律学の基礎
法律の勉強は、弁護士を目指す者にとっては勿論のこと、弁護士になった後も非常に重要である。法律学の基礎を固めることにより、将来のクライアントが直面するであろう法律問題の解決に向けた土台を築くことができる。教科書や専門書を活用し、法律の基本概念や原則を理解することが重要である。
専門誌の利用
法律雑誌と呼ばれるジャンルが存在し、そのジャンルに分類される専門誌は意外と多い。法律的議論は社会の変化とともに常に流動するものであり、一度何かを勉強すれば足りるといった性質のものではない。
とはいえ、結局は「基礎中の基礎」を習得しておけば後はその応用で何とかするほかない。基礎中の基礎を知らない人が最新の法律情報や判例を学んだところで理解できない。基礎中の基礎に触れるための雑誌としては「法学教室」がベスト。法学部生向けの内容であるということはまさに法律学の基礎中の基礎が示されているわけで、舐めることなくこの雑誌の内容を常に理解しておくことが必要である。
その上で、最新の法律知識を持ち続けるために「ジュリスト」あたりを確認するという流れが理想である。優先順位として「法学教室→ジュリスト」であることを強く意識しておきたい。
オンラインリソースの活用
インターネットの発展により、オンラインで様々な法律リソースにアクセスできるようになった。ウェブサイト、ポッドキャスト、ウェビナー等、多様な学習媒体を利用し、随時、新しい知識や情報を取得することができる。これらの媒体は、時間や場所の制約を受けずに学習できる利点を持つ。気軽に隙間時間を活用してこれらの媒体に触れることによって弁護士としての意識を常に高めておくといった啓発的な効果も期待できる。
実践経験の積み重ね
インプット媒体について述べるとのテーマにおいてこのようなことを言い出すのは恐縮だが、結局は実際の法律問題に取り組むことで理論を実践レベルrに落とし込むことが可能となる。法学教室に連載されている演習などのケーススタディも理論の実践化との位置付けであるものの実際の生の事件には前提情報の質量で適うことはあり得ない。実務に取り組む中で試行錯誤するほかない。研究者ではなく実務家として食べていく以上は実践経験を捨てるわけにはいかない。まあその実践があまりにも体力的にも精神的にも厳しいものとなってしまうがゆえに「専業研究者に転身したいと願う実務化」がどの専門分野にも一定数存在するとの現象は避けられなさそうではある。実務は(も)厳しい。
まとめ
弁護士のインプット、すなわち、知識習得の媒体は多岐にわたる。基礎知識の習得から実務経験の積み重ねまで、様々な学習方法と媒体を組み合わせることで、より効果的な学習が可能となる。法律のプロフェッショナルとして、持続可能な学習方法を見つけ、日々の業務に生かしていくことが求められている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
