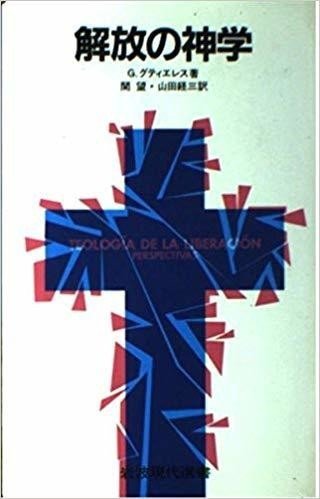感想文:政治神学(1)
1922年に当時34歳のカール・シュミットによって書かれた本である。本文は以下のようにはじまる。
主権者とは、例外状況にかんして決定をくだす者をいう。
その後も、極限領域の概念を意味する限界概念。例外状況、国家論の一般概念として理解すべきものなど、聞きなれい単語や初見で理解するのが困難な文章が1Pには散りばめられている。彼は何に危惧し、何を希求したのか?
一般的規範では、絶対的例外を把握できない
様々な法学者、法律家が想定外の状況のないように、法律は国家運営、詩人関係を網のように張り巡らせていった。しかし、あくまで秩序だった社会の中で出来たものであり、状況に適用されている法でしかないのだ。
私はこの箇所に神学における論理展開を見いだせる気がした。私の高校時代はグスタボ・グティエレスの「解放の神学」が救いの鍵であり、言い換えれば信仰と思想、そして行動への落とし所であった。カール・マルクスによる「宗教はアヘン」と批判したことは、当時の構造的に全くもってその通りであり、そして、ラテンアメリカどころか日本でも、宗教団体が弱者への搾取を構造的に肯定してしまう点が見受けられた。クリスチャンであり社会主義者だった自分は、信仰するということが社会主義を否定するのか?と頭を抱えていた。そして、能動的な信仰活動が資本主義へ争い打ち倒す手段に繋がっていくと「解放の神学」から読み取った。
20歳になり、信仰と思想運動、人生にあぐねいて再度手にした「解放の神学」は、ある側面でカルヴァンの予定説への回答ではないか?と考え始めた。そして、それがこの政治神学にも同様に感じる。
先に出したカルヴァンの予定説とは、 マックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」での解説が最も分かりやすいかと思う。資本主義は宗教がもたらす禁欲的な信仰活動が転換し余暇を削り賃金労働に従事したことで発達した。噛み砕いて述べれば、禁欲的になり天命に務めることで来世での救済を約束されるという一連の流れが、資本主義における余暇を削り職務に勤しむことで成功にたどり着けるという流れに言い換えられた。この変換があの街並み、目の前の製品の山を作り上げたのである。
来世への救済は、全知全能の神が知っている。フランス生まれの神学者ジャン・カルヴァンは神の全知全能と大衆の人生と行動への回答を探した。どうやって生きても、救済にあずかれるかどうか全く不明である。私は僕は、生きている間の善行は意味がないのかもしれない。そこで再度、自己を中心に神を見つめてみると、「私は神の意思を知ることはないだろう。そして、善行を積まないことにもならないだろう。」となっていくのだ。この部分は、アラブにおけるイスラーム社会での神の導きと自己決定の関係性に大いに類似ている。ピンとこない人はアラブに行ってみよう!
現世での善行も意味を持たないことから、人々が虚無的な思想に陥ったり、現世での救済されると予め決まっているというのであるなら、ドラマチックに生きるといった博打的思考も、ある側面で発達した。後者と暫定的に善行を積んでいくことの合いの子は「解放の神学」と呼ばれるものになったと私は解釈している。
本書での秩序の枠外に存在する例外的状況という設定は、まさに不可知的考えそのものでないだろうか?また、例外的状況において国家の主権者が姿を現す。神への不可知論を、国家という枠を演繹して表現しているのではないか?
つまり、人間は不完全であり、人間の思考には必ず例外が生まれる。そして、そこに全知全能の神が存在する。
あらゆる法律的概念のうちで、もっとも強く現実的関心によって支配されるのが、主権概念である。
テーマは主権概念に移動する。主権概念は政治闘争に画されるのであり、ドイツでは国家概念と主権概念の区別も発見された。筆者はルソーの「社会契約論」にはじまり、ケルゼンの「主権の問題と国際法理論」、「社会学的国家概念と法学的国家概念」で締めくくる問いは、こうである。
国家とは、純法律学的存在すなわち規範的に有効な存在であらねばならない。したがって、法秩序とは別の、それと並ぶなんらかの実在ないしは構想物ではなく、まさに、この法秩序そのものーもとより統一体としてのーにほかならない。国家はそれゆえ、法秩序の作成者でなく、源泉でもない。こういった表象はすべて、ケルゼンによれば、擬人化であり実体化である。
国家・法秩序は、究極的帰属点かつ究極的規範に対する、帰属の体系である。この「最高位の演繹できない秩序」といった論理的展開に対して、著者であるカール・シュミットは反論している。
さまざまな帰属点への、さまざまな帰属の、思考上の必然性および客観性は、もしもそれが実定的な規定すなわちひとつの命令にもとづくのでないとしたら、なんにもとづくのであるかと
この箇所はISILのような過激派からムスリム同胞団のような穏健派含めて、法律の源泉を経典であるクルアーン(コーラン)やハディース(ムハンマドの言行録)に求めて、法律や社会体系を構築するイスラーム教がケルゼンの「最高位の演繹できない秩序」への最大アンチテーゼになりうるだろう。人間的権力(国王とか統治権者とか)に代わって、例外なき完全無欠の法体系へと変容した。仮にカール・シュミットが「ありえないなんてことはありえない」という姿勢であるならば(全知全能の神への肯定としての現世への不完全さを認識すること)、例外なき完全無欠の法体系として不完全な政治機構であり、その例外から主権者が現れると推論していると考えられる。前述した論理を前提とすれば、源泉(神)を持つイスラーム教は強大である。理性的な法秩序ではなく、全知全能のアッラーの存在が基準となるので、例外はない。そして、仮に例外があるのであれば、人間の認識能力および思考力が低いからであり、それは究極的に言えば基準に例外があるわけでない。
国家の任務はただ、法を「作る」こと、すなわち諸利益の法的価値を確定するにすぎないのである。
オランダ出身のヒューゴ・クラッベを引用し、そして解釈した一文が上記のものである。法的秩序を嚆矢としてはじめ、焦点を国家に移行しようとしていく。続けて、クラッベの主張には国家には二重の制約があると言う。第一に利益と公共の対立するものとしての法への限定、第二に決して構成的でない法そのものの確定への限定である。この文面だけでは、把握しきれない。カール・シュミットが理解した様々な主張や理論は、とても高度であり、また、批判対象であるヒューゴ・クラッベは困難である。ただ、ここでクラッベ自身が中央集権的官憲国家に対し批判的であるという前提は、本書でも明らかにされている。権利と公益の間で幾度となく最高裁が揺れた。そして、立法というものは大衆の違和感なく、言い換えれば大衆の法意識を満足させる程度に行われる。
「国家とは法を確定させる容器でしかないのか」という問いに言えるのではないだろうか?。その根拠として、団体理論の法哲学者オットー・フォン・ギールケを用いて述べた部分を抜粋する。
国家による立法とはただ、国家が法に対して押印する「究極的形式的印象」すぎず、この「国家による刻印」は、たんに「外的形式的価値」をもつにすぎない。
先の形式的価値における形式とは、法の形式的概念であり、技術的形式、また先験的哲学における形式概念と美学的形式とは本質的に異なるものである。ウェーバーは法的内容の概念的確定がその法的形式だと言う。形式的に発達した法とは、訓練された法律専門家、法の行使者である役人などの協力のもとに、自覚された決定準則(のっとるべき規則)の複合体であるとより明確化していく。そうして、官僚などと利害を調整し円滑な機能発揮という理念に支配されていった。
イギリス経験論の父・ロックはこういった、「法は権威を付与する」。まさに近代化の生みの親であるロックの発言を、カール・シュミットは2章最後に皮肉っているように思える。合理的で円滑な機能発揮された理性的で形式な法は一体、誰に権威を付与しようとするのか。「決定」があるから「主権者」がいるのだというシュミットの疑問と形式への破裂が、詰め込まれていると感じた。いかに決定されるかというシステム的な主張は、いくらでもされたが決定については誰もしていない。王様vs大衆ではなく、権威vs真理なのだと。
民主主義的決定は、非営利の組織に所属した人間であれば誰もが、その民主主義的運営と民主主義的決定に差異があり、また決定が民主化されることのないことに気付くだろう。ひとえに「空気」と呼べるものであり、他方で権威と呼べるものが、その運営の最高位に存在している。
今回はここまでにして、次回は政治神学⑵
一応、参考文献にCiNiiで検索した際に登場した論文を掲載します。
近世・近代ドイツ国法学における国家目的「自由」「安全」「生命」(1)環境国家論への予備的覚書 藤井康博
カール・シュミットにおける民主主義論の成立過程 (3) : 第二帝政末期からヴァイマル共和政中期まで 松本彩花
カール・シュミットと政治的ロマン主義 : モデルネ批判の視点から 竹島博之
この記事が参加している募集
数年前にトルコに渡航していました。現在はオルタナティブ系スペースを運営しています。夢はお腹いっぱいになることです。