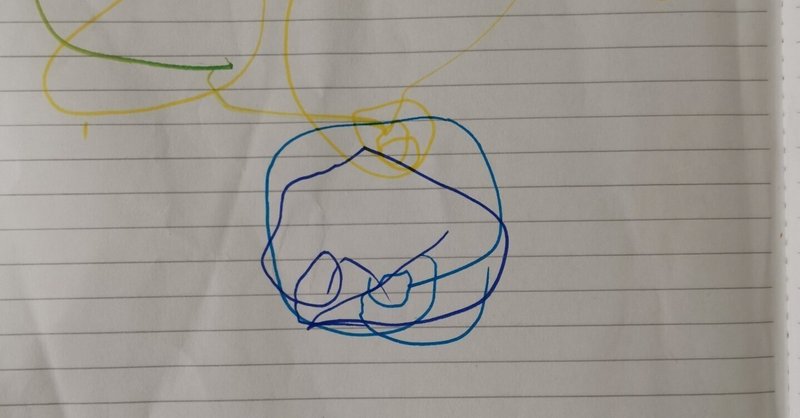
#6 就学相談に迷ったなら
保育園や公民館の掲示板等に貼られている「就学相談の案内」
これは平たく言うと、
「学校生活を送っていく上で心配な点がある場合に相談するところ」
といったものです。
多くの場合、何かしらの病気や障害がある、またはその可能性がある事から相談に行く、それか子供を近くで見ている人からの勧めで行くといったパターンなのかなと思われます。
就学相談に関して思うのは、
相談した方が良いか迷うなら行くべき
相談した上で支援が不要との判断ならそれはそれで良いし、
早くから支援を受ける事で、その子の心身の発達を促進させる事が期待できます。
私も子供の親なので、というか過保護気味なのかもしれませんが、乳幼児健診前(1歳半検診や3歳検診)には、心の隅で期待と不安というのか、複雑な思いがあったことを覚えています。
時には、日本版デンバー式発達スクリーニング検査から発達状況を照らし合わせることもありました。

検診で特に問題なしと言われると、あぁ乳幼児はこんなものなのかと思うものです。
しかし仕事柄、ここで気をつけなければならないと感じている点があります。
1つは、近年は「発達障害」といった形で発信される情報量は膨大な数に登り、極めて複雑化しており、様々な判断が難しくなっていること。
何が正しいか、何をやれば良いか、本当にその方法が子供に適したものであるのか、すべてを適切に処理する事は不可能に近いです。
子育てとして大切だと思われるもの、発達障害支援として大切だと考えられるもの、非常に多くあると思います。
しかし最も大切なのは、難しいんですが、教育の立場としては、少なくとも本人の自信や自発性を失わせないようにすることに尽きると思います。
自信や自発性は、あらゆる物事に通ずる部分で、また積み上げる事は本当に容易なことではないです。
しかし、これだけ守れたなら、その子は立派に育っていくものだと確信しています。
様々な情報がある中で、軸がブレていないことを常に忘れてはならないのだと思います。
2つ目は、乳幼児健診で特に問題なしだったから就学相談を受ける必要はない、と判断するのは必ずしも正しくないということ。
検診は一定の信頼性と妥当性をもつものですが、あくまでもその子の一瞬を見ているだけに過ぎず、親をはじめ、やはり様々な人の目から見ること、特に子供に触れている機会の多い人が継続的に見てどうか、といった視点は非常に重要だと思っています。
乳幼児であれば、具体的には保育士や幼稚園教諭(または自分の親族や友人に同様の人がいれば)、児童生徒であれば小学校、中学校教諭などの人が見てどう思うかといったもの。
子供を何百、何千人と見ている人であれば、その子に対してハッキリと感じるものから、なんとなく感じるものまで気づく事があるはずです。
乳幼児健診では特に何も言われなかったが、保育園では、小学校に上がってから面談では学校生活上の不安について報告を受ける場合もあります。
何より、相談すべきか迷うならすべきと考える最大の理由は、支援は遅くなればなるほど厳しさが増すのが常だからです。
例えが正しいか分かりませんが、大災害が起きて住むところも食べるものもなくて困っている状態だとして、初日から物的支援を受けられる場合と10日経ってから受ける場合では、自分にとってどちらが助かると言えるか。
仮に10日も飲まず食わずでいたら、いざ救援物資を貰っても、むしろ深刻な脱水症状で命の危険に晒されている状態かもしれません。また、初日に受ける支援より、より緊急かつ高度な支援が必要である事は自明です。
早期から支援を受けた生徒の発達は、その障害種に依らず、受けなかった場合と比較して有意な差が見られます。
適切な支援を受けることで、劇的に改善されるケースは実体験としても感じているところです。
さらに初期の段階から適切な支援を受けることで、それだけ適切な教育の機会が長く与えられるものであります。
表面的な話題に終始してしまいましたが、今後同様の話題を取り上げる際には、もう少し深く述べたいと反省しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
