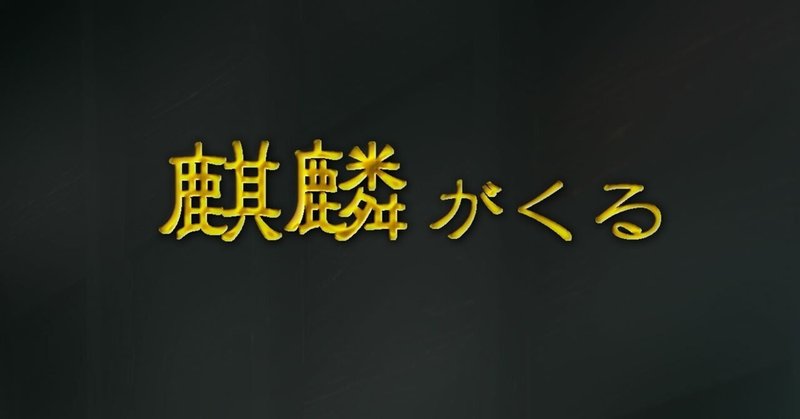
視聴記録『麒麟がくる』第26回「三淵の奸計」2020.10.4放送
義昭(滝藤賢一)を奉じ、信長(染谷将太)と共に上洛を決めた義景(ユースケ・サンタマリア)だったが、その気まぐれな言動から、光秀(長谷川博己)や三淵(谷原章介)らはその真意に次第に不安を感じるようになる。家臣や一族も決して一枚岩ではない様子を見るにつけ、このままでは上洛をしても三好勢と十分に戦えないと判断した光秀は、信長を訪ね、単独で上洛をするように訴える。
<トリセツ>
足利義昭の「元服」と、朝倉義景が務めた「烏帽子親」
劇中では、足利義昭の「元服の儀」が行われました。元服の儀とは、成人を示すための儀式です。義昭が武家として元服したということは、ついに「武士として生きる宣言」をしたこととなり、将軍になるための資格を得たということになります。武家の男子の元服は、当時5〜20歳ごろの間に行われることが通例でしたが、義昭の場合は、足利将軍家の習わしから「跡目争いを避けるため」に幼い頃に仏門に入りました。ところが、実兄・義輝の死により、正統な次期将軍の候補に浮上し、「僧」から「俗人」に戻る還俗(げんぞく)を済ませた後、元服の儀を執り行いました。この儀式の中で、烏帽子(えぼし)を被せる者を「烏帽子親(えぼしおや)」と呼び、今回、この烏帽子親を務めたのは朝倉義景でした。これにより、次期将軍にもなりえる義昭の後ろ盾は『朝倉義景である』ということを、広く諸国に知らしめることができたのです。
「将軍」の上洛と朝倉家
朝倉義景は、病気療養中の将軍・義栄に代わる次期将軍最有力候補・足利義昭の後ろ盾となり上洛することを公言、世間にアピールしました。しかし、朝倉家内の反対勢力をまとめきれず一向に上洛できないまま、義昭は織田信長を伴い上洛することを決意。後ろ盾だった義景は完全に除外され、大大名としての面目を潰されました。
★戦国・小和田チャンネル
https://www.youtube.com/watch?v=YvrI5jxA4Qs
1.予習
足利義秋は、一乗谷の朝倉義景を頼るが、安養寺に新築中の御所の建設工事が遅れているのか、朝倉義景によって敦賀に足止めされた。(一説に足利義秋は、自主的に一乗谷には入らず、敦賀で上杉輝虎や毛利元就を待ったという。『朝倉始末記』によれば、冬は降雪で一乗谷へは行かれず(荒血山、木ノ目峠を越えられず)、雪が溶けて春になった3月には、堀江氏謀叛と、それに同調した加賀一向一揆衆の越前国侵攻により、一乗谷への動座が遅れた(10月21日になった)とする。)
※荒血山:あらちやま。「愛発山」とも。福井県敦賀市の南方一帯の山。奈良時代には、「古代三関(さんげん)」(東海道の伊勢国鈴鹿関、東山道の美濃国不破関、北陸道の越前国愛発関)の1つである「愛発関 (あらちのせき)」 が置かれていた。
※木ノ目峠:きのめとうげ。「木ノ芽峠」「木辺峠」「木部山」「木嶺(もくれい)」とも。福井県の天気予報を聞いていると、「嶺南は・・・。嶺北は・・・」と言うが、嶺北(越前地方)と嶺南(若狭地方)を隔てる峠が木ノ芽峠である。
※『朝倉始末記』(巻第4)「義昭公、越前へ下向の事」
斯くて一乗へ御座を移され度思し召されけれども、例年よりも寒気甚だしく、荒血山木ノ目峠、莫大の深雪にて、人馬の通路絶へければ、九郎左衛門、申しけるは、「今冬は、是非、当地にて御越年成され、来春、雪、消えて後、御遷座宜しかるべし」と頻りに留め奉るに依て、義昭公、其の意に任せ給ふ処に、永禄10年の3月、又、不慮に加州の一揆等、堀江中務丞景忠を語ひ蜂起する由にて、国中、騒動斜めならぬ間、「事、静まりて後、一乗ノ谷へ入御あるべし」とて、同年10月まで、其の儘、敦賀の城にぞましましける。
※同「義昭公、敦賀より一乗へ移る、付けたり密かに義景屋形で遊ぶ事」
斯くて国中騒動で、漸く静まりたる程に、義昭公、一乗ノ谷へ入御成さるべしとて、永禄10年10月21日、敦賀を御出あり。府中龍門寺へ入給ひ、暫く御休息ましまして、其の日の亥の刻、一乗安養寺に着御なり。朝倉中務丞景恒、路次まで御迎へに出づ。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3431173/180
朝倉義景も上杉謙信も動かないので、足利義秋は、一乗谷・安養寺御所へ動座した。すると、足利義栄が先に将軍に就任してしまった。失意の足利義秋は、元服して、名を足利義昭と改め、織田信長を頼って岐阜へ動座する。
(1)義昭動座
覚慶→足利義秋→義昭は、
興福寺→甲賀和田城→矢島御所→小浜→敦賀→一乗安養寺→美濃立政寺
と「動座」しました。「動座」とは、貴人が座所を他に移すことです。
※『福井県史』「義昭の越前逗留と上洛」
足利義昭は義輝暗殺当時、大和興福寺の一乗院門跡で覚慶といった。覚慶は将軍位の後継者とみなされ、母方の叔父大覚寺義俊の補佐により、朝倉義景と連絡して三好三人衆の手の及ぶ大和を脱出し近江に向かった(『上杉家文書』)。朝倉義景は義俊や覚慶の縁者にもあたり、特にたびたび越前に下向した義俊は深く義景を信頼していた。覚慶は還俗して義秋と名乗り、近江から若狭を経て永禄九年九月敦賀に入った(同前)。義俊と義秋は早くから義景のほか若狭の武田義統や尾張の織田信長にも協力を要請しているが、遠く越後の上杉輝虎に期待するところが大きかったといわれる。義秋は輝虎の上洛を促進するために相模北条・甲斐武田との三者和睦を命じ、加賀一向一揆と越前の和睦を本願寺顕如に命じた。だが朝倉氏の内部では、同十年三月に坂井郡の有力国人堀江氏が加賀一向一揆と結んで義景に謀叛をおこすなど安定を欠いていた。しかし同年冬ようやく加賀一向衆と朝倉氏の和睦が実現する運びとなり、十一月二十一日義秋は敦賀から一乗谷へ移った(「越州軍記」)。
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-4-01-04-04-01.htm
(2)義昭動座関連年表 永禄11年(1568年)
2月8日 足利義栄、摂津国で将軍宣下を受け、第14代将軍に就任。
3月6日 上杉輝虎、武田信玄、北条氏康、和睦
3月8日 足利義秋の吹挙に依り、朝倉義景の母を従二位に叙す。
春 足利義秋、一乗谷南陽寺で花見(糸桜観賞)
4月15日 足利義秋、元服。「義昭」に改名
4月日 織田信長の妹・市姫、浅井長政と結婚(諸説あり)
5月17日 足利義昭、朝倉館に御成(『朝倉義景亭御成記』)
6月日 織田信長、足利義昭に上洛の助力を申し出る。
6月25日 阿君丸、病死。
7月16日 足利義昭、織田信長を頼り、美濃国岐阜立政寺へ動座
8月7日 織田信長、六角氏の説得のために佐和山城へ
8月14日 織田信長、六角氏の説得を断念して帰国
9月7日 織田信長、出陣
9月12日 織田信長、観音寺城を攻略。六角氏、甲賀郡へ逃亡。
9月26日 足利義昭、織田軍に警護されて上洛開始
9月28日 織田信長、東福寺へ
9月30日 第14代将軍・足利義栄、富田で病死(『公卿補任』)
10月8日 第14代将軍・足利義栄、撫養で病死(『平嶋記』)
10月14日 足利義昭、京都六条本国寺(現・本圀寺)へ動座
10月18日 足利義昭、第15代将軍に就任
1)足利義昭の元服
4月15日、足利義秋は元服し(『言継卿記』(3月24日条)の書状に「来月15日、御元服」とあるが、実際には遅れたようで、元服式の日を『朝倉義景亭御成記』では4月21日、『朝倉始末記』では4月23日とする)、名を「足利義昭」と改めた。
元服式(奉行は摂津晴門)では、京都から二条晴良を越前に招き(山科言継は、費用の関係で欠席)、加冠役は朝倉義景が務めた。
足利義栄&関白・近衛前久 vs 足利義昭&前関白・二条晴良
https://clioimg.hi.u-tokyo.ac.jp/viewer/view/idata/T38/1568/13-7-3/4/0019?m=all&s=0019
※『福井県史』「義昭の越前逗留と上洛」
義景は義秋を盛り立て、翌十一年四月に朝倉館において元服の儀を挙行した(「越州軍記」、「朝倉義景亭御成記」など)。このとき義秋は義昭と改名した。五月十七日には義景は朝倉館に義昭の御成り(訪問)を迎ぎ、義昭を将軍になぞらえて盛大な宴を催した(同前)。義景の歓待により義昭は越前滞在を続けたが、越後の上杉輝虎は武田信玄との対立によりいまだ越中を攻めあぐんでいる状態であった。義昭はこうした北国の状況に見切りをつけて一乗谷を去り、翌十一年七月美濃へ向かった。織田信長はこの前年に美濃を攻略し、小牧山から井口に移ってこれを岐阜と改称した。義昭は信長が上洛に最短距離にあると判断したのである。信長はただちに江南の六角氏を制圧して義昭を上洛させ、畿内の三好三人衆方の諸勢力を平定して、同年十月義昭は晴れて征夷大将軍になった。
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-4-01-04-04-01.htm
※比較資料
『鹿苑院殿御元服記』(足利義満の元服式の記録と年代記)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2559221/48
『普広院殿御元服記』(足利義教の元服式の記録)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2559221/55
『光源院殿御元服記』(足利義輝の元服式の記録)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2559221/69
2)足利義昭の御成
足利義昭の御成については『朝倉義景亭御成記』が詳しい。この本には、出迎えた朝倉家臣の名があるが、家臣ではない食客の真柄の名まで載っているのに、明智の名は載っていないので、学者は、「明智光秀は、『明智軍記』には朝倉家家臣とあるが、名が載っていないので、朝倉家家臣とはいえない」とする。名が載っていない理由は、越前国にはいたが、牢人であって朝倉家家臣ではなかったからか、他の人(足利義昭、細川藤孝、織田信長の内の誰か)の家臣だったからか。
・説①:明智光秀は、すでに織田家家臣となっていた。(『明智軍記』)
・設②:明智光秀は、奉公衆になっていた。(『永禄六年諸役人附』)
・学説:明智光秀は、朝倉家家臣ではない。(『麒麟がくる』では牢人)
5月17日 、足利義昭、朝倉屋形(朝倉館)に御成。
御成道中では、朝倉家臣によって厳重に「辻固め」が行われ、その役は主に朝倉家の内衆が務めたが、食客の真柄なども勤めている。
足利義昭が朝倉屋形に到着すると、寝殿(主殿)でまず「式三献」(初献、二献、三献と膳を替えて3回繰り返すこと)が供せられ、朝倉義景が御礼に参上した。その後、会所(常の御殿)に足利義昭、二条晴良、仁木義政、朝倉義景の4人が入り、饗応が始まった。酒肴は初献より17献まで続けられ、献を重ねるたびごとに、様々な進物が献ぜられた。
※『朝倉始末記』(巻第4)「義昭公、朝倉屋形に成られたる次第。付けたり、御能の事」
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3431173/185
※「「朝倉館」で元服、改名した足利義昭」(サライ)
https://news.yahoo.co.jp/articles/dbcbc341317cee84ab1f7bd208bdf4dbb4ccf1c1?page=2
https://clioimg.hi.u-tokyo.ac.jp/viewer/view/idata/T38/1568/13-7-3/5/0009?m=all&s=0009
※『福井県史』「贈答と酒宴」
朝倉館で行なわれた酒宴のなかで最も著名なものは、永禄十一年五月の足利義昭の「御成り」のさいの酒宴である。朝倉義景は義昭を次期将軍としてもてなす大宴会を催した。五月十七日の午の刻、足利義昭は朝倉館を訪問し、まず前述のように主殿で式三献という献盃の儀が行なわれた。そして義景は当時の慣習にのっとって白太刀と馬・弓・矢・鎧を進上した。そののち義昭らは常御殿へ座を移し、盛大な宴会が始まった。盃が重ねられ、進物が献上された。進上物の種類は太刀・馬・唐物の香合・盆など故実に従ったものだったが、一三献目には金銀一〇〇両を盆にすえて進上し、一五献目には三尺余の沈香の榾を二人で持って進上したという。三献ののち朝倉景鏡以下の同名衆たちが義昭に太刀・馬を進上して礼を述べ、四献ののちには能が始められた。一〇献目が済むと義昭は別室で休息し、その間に義昭の臣である御供衆・御部屋衆・御走衆・詰衆らに食事が振舞われた。一一献と一三献のあとには義昭の臣に対して、一人一人が盃を主人から戴いて飲んでは引き下がるという飲み方である「御通り」がなされ、一五献ののちには朝倉氏の同名衆にも「御通り」がなされ、最後の一七献のあとには前波景当・魚住景固以下の朝倉氏の年寄衆が義昭に太刀・馬を進上して礼を述べた。また宴たけなわとなったころ舞となり、義景も所望されたという。そして義景は義昭の盃を受け、最後に仁木義将の「御通り」がすぎて「御銚子アガリ」となり、すべての酒宴が終了した(「越州軍記」、「朝倉義景亭御成記」)。
https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T2/T2-5-01-03-04-03.htm
(3)上洛
「足利義昭を擁しての上洛」とは、言い換えれば、
①上洛ルートの確保
②上洛後、足利義栄を擁する三好勢との戦い
のことである。
■尾張国主・織田信長の上洛準備
東(三河国):徳川家康との同盟強化(長女・徳姫と長男・信康の結婚)
西(近江国):浅井長政との同盟強化(妹・市との結婚)
南(伊勢国):北勢(伊勢国北部地方)平定→東海道の確保
北(美濃国):美濃国平定→東山道の確保
朝倉義景の場合、足利義秋の仲介で加賀国の一向宗門徒と和議を結んではいるものの、上洛して越前国を空けたら、後方の一向宗門徒が和議を破って越前国に侵攻しそうで不安だ。織田信長の場合は、後方には徳川家康がいるので安心である。
6月になって、織田信長が、再び上洛の助力を申し出たので、足利義昭は美濃国への動座を決めた。朝倉義景にしたら、匿ってあげたし、元服もさせてあげたのに、「上洛」という1番美味しい所だけ織田信長に取られるのは気分が良くない。(朝倉義景が餅をこね、食べるのは織田信長。)
さらに言えば、足利義昭が将軍になったら、「上洛の助力をしなかった罪」を押し付けられるかもしれない。そう危惧する朝倉義景に対し、足利義昭は、6月24日に「あなたの忠義を神妙に思い、今後もあなたを見放さない。なお、詳しくは(この手紙を持っていく使者の)大蔵卿局(足利義昭の側室)が述べる」という手紙を出した。
※永禄11年6月24日付、朝倉義景宛、足利義昭書状
就今度、当国退座、忠義神妙思食候、向後、身上不可見放候。猶、大蔵卿局可述候也。
六月廿四日 (御判)
朝倉左衛門督殿へ
下に載せた永禄11年7月8日付鯵坂長実&河田長親宛「新保秀種&智光院順慶連署状」(『伊佐早文書』)には、「織尾」(尾張国主・織田信長)が、「善きにつけ、悪しきにつけ、濃州へ御移りになられ、御座あらば、御入洛の御供、早速申すべき候由」(「是非もなく、美濃国に御動座あれば、すぐに入洛のお供をする」と)、「堅く墨付け、切々なる言上に付きて」(堅く約束し、切に願ったので)、「義景も納得の分、相極まり候て」(朝倉義景も納得して動座が決まり)、「今日、16日に濃州へ御動座に義定候」(本日(7月8日)、7月16日に美濃国への動座が義定(議定。合議)で決定した)とある。
※永禄11年7月8日付、鯵清(鯵坂清介長実)&河豊(河田豊前守長親)宛「新保秀種&智光院順慶連署状」(『伊佐早文書』)
於爰元様子為可申上、態飛脚差下申候、然者、路次申無事、御鷹・御馬も当日二日ニ参着申候、二、三日程相伏、則 上意様へ懸御目候、一段入御意御感之旨被仰出候、御鷹も朝倉殿各殊之外大慶此事候、於様躰者、可御心易候、前波・山崎方先以馳走之様候、織尾善悪濃州へ御被移御座者、御入洛之御供早速可申候由、堅墨付切々言上付而、義景も納得之分相極候而、今日十六日ニ濃州へ御動座ニ義定候、随而加州之儀も、去年以来無事之様候ヘ共、于今互一札不相澄候、御成以前ニ如何共相調度由候得共、今之分者、相極間敷由候、左様候者、彼無事も笑止之由此淵各申候、然者、被仰付候御条書覚、上様へも朝倉殿も具申上候、猶可然様御披露所仰候、恐々謹言、
返々、其方へも相聞可申候へ共、能州より加州杉浦方へ以前仕合付而、面々より差越候書状、則上意さまへ参候、移候て差越申候、
七月八日 智光院順慶
新清右秀種
鯵清
河豊
参御宿所
『多聞院日記』によれば、7月16日(『明智軍記』では7月18日)に一乗谷安養寺を出て、浅井館(小谷城)に寄り、美濃国立政寺(りゅうしょうじ)の正法軒(しょうぼうけん)に着いたのは7月22日(『明智軍記』では7月25日)だったようだ。
※『明智軍記』「義昭公濃州御移事」
義昭公、斜めならず御感有りて、永禄十一年七月十八日、一乗谷を御出駕(しゅっか)也。義景より路次の警固として、前波藤右衛門尉景定、五百騎にて御供仕り、敦賀津に御著あり。是より朝倉中務大輔景恒、五百余騎、前波に加へて御送りを勤む。然る処に、浅井下野守方より、御迎へとして、従弟(いとこ)の浅井玄蕃、同・雅楽助兄弟を刀禰坂(とうねさか)迄指越れ、北近江余古の庄に致る。備前守長政も木本の宿迄罷り出で、小谷城へ入れ奉りける処に、岐阜の信長より、案内者と為して、不破河内守、村井民部少輔を指し越さられければ、朝倉家の両使は、小谷よりぞ帰へりける。浅井備前守関箇原ノ宿迄御送りを申されけり。同二十五日、義昭公、濃州岐阜の旅館(きょかん)にぞ入らせ給ひける。
(【現代語訳】足利義昭は、大変感心して、永禄11年(1568年)7月18日、一乗谷を出られた。朝倉義景から道中の警護として、前波景定が率いる500人が付けられ、敦賀港に到着すると、朝倉景恒が率いる500余人が加わって1000余人となって警護した。こうしたところ、浅井久政(浅井長政の父)が御迎えとして、従弟(いとこ)の浅井政澄&浅井雅楽助兄弟を越前国と近江国の国境の刀根坂(福井県敦賀市刀根~滋賀県余呉町の峠)に向けて迎えに出し、(迎えの一行は)近江国側の北近江余古庄(滋賀県余呉町)まで来た。浅井長政自身も、北国街道の木之本宿(滋賀県長浜市木之本町木之本)まで迎えに出て、小谷城(滋賀県長浜市湖北町伊部)へ(足利義昭一行を)入れたところ、岐阜の織田信長から案内者として、不破光治、村井貞勝が来たので、朝倉家の2人の使者(前波景定、朝倉景恒)は帰った。浅井長政は、中山道の関ケ原宿(岐阜県不破郡関ケ原町)まで見送りした。こうして、永禄11年(1568年)7月25日、足利義昭は、美濃国岐阜の立政寺(岐阜県岐阜市西荘三丁目)に入った。)
※『多聞院日記』(永禄11年7月27日条)
公方様、去る16日に越前より江州浅井館へ御座を移され、同22日に濃州へ御座を移され了。尾張上総守御入洛御伴申すべしの由、云々。
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1207457/47
https://clioimg.hi.u-tokyo.ac.jp/viewer/view/idata/T38/1568/13-7-3/6/0051?m=all&s=0051
2.今回のストーリー
光秀の野望は、一つである。
「幕府を中興せねばならぬ」
ということのみであった。京で虚位を擁するにすぎぬ足利将軍家に天下の権をとりもどさせ、むかしどおりの武家の頭領としての威信を回復し、諸国の兵馬を統一し、それによって戦乱をおのが手におさめてみたい。
そういうことである。
(司馬遼太郎『国盗り物語』)
明智光秀にとって、足利義輝が最高の人物であった。その足利義輝が討たれ、共に世を平らげる夢が絶たれた。こういう時に足利義昭に限らず、どんな将軍候補に会っても、足利義輝よりは劣って見えるものである。それは、オーラで光輝く大人気の芸能人と、上京したばかりでデビュー前の芸能人を見比べるようなものである。「石原さとみロス」の男性に、素敵な女性を紹介しても、「さとみさんの方がいい」「さとみさんでなくちゃ嫌だ」と駄々をこねられるようなものである。
失意は時が解決する。いつまでも将軍不在ではまずい。嘆く暇はない。
(このドラマが不思議なのは、明智光秀が足利義昭にしか会っていないことである。足利義栄になぜ会わないのだろう?)
足利義昭に幸いしたのは、足利義栄が重病で上洛できなかったことである。そして、二条晴良が「足利義栄が上洛しないのは、足利義栄を推薦した近衛前久の責任問題だ」と近衛前久を責めてきた。さらに足利義昭を推す二条晴良が、足利義昭の元服要請を取り次いでしまった。関白・近衛前久は、「元服しても良い」という天皇の許可を伝えるために一乗谷へ下向しなければいけなくなったが、伊呂波太夫に名代を頼んだ。関白の名代が旅芸人? 旅芸人が、帝(みかど)の御下命(ごかめい)を伝える? ありえない!
(近衛前久は、一乗谷へは行きたがらない。近衛前久の姉は、朝倉義景と結婚したが「子供を産めない」として、一方的に離婚され、京都に追い返された。これは、名門・近衛家にとってこの上ない屈辱であったろう。もちろん、その事は伊呂波太夫も知っている。)
この時、伊呂波太夫は、御所の崩れた築地塀を気にしていたが、この時の御所の塀は、高価な築地塀ではなく、粗末な竹垣だったという。
また、『信長公記』の永禄12年の記事に、「抑(そもそも)禁中御廢壊正躰なきの間、是れ又、御修理なさるべきの旨、御奉行、日乗上人、村井民部少輔、仰せ付けられ候ひき」(織田信長は、新たに将軍の御所「二条御所」を建てたが、天皇の御所も傷んでいるとして、日乗上人と村井貞勝を作事奉行とし、修理を命じた)とある。
足利義秋を奉じ、織田信長と共に上洛をすると決めた朝倉義景は、足利義秋を本拠地・一乗谷に呼び、永禄10年11月21日、足利義秋は安養寺御所に入った。永禄11年4月15日には、朝倉義景が烏帽子親、京都から来た二条晴良が見届け人となって足利義秋は元服し、「義昭」に改名した。
4月24日、朝倉館で、内々での元服の祝賀会(朝倉義景的には「上洛の前祝い」でもある)があり、近衛前久の名代として来ていた伊呂波太夫が舞を披露した。
※『朝倉始末記』(巻第4)「義昭公、朝倉屋形に成られたる次第。付けたり、御能の事」
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3431173/185
<紀行> 福井県福井市。足利義昭は、越前の朝倉氏を頼り、この地を訪れました。義昭は敦賀から朝倉街道を使い、一乗谷へ入ったと考えられています。安養寺(あんようじ)は、一乗谷の中でも規模が大きく、格式が高い寺院でした。義昭はこの寺に迎え入れられ、敷地には御所も設けられました。次期将軍候補として歓待を受け、朝倉氏の屋敷や寺では、たびたび供宴が催されたといいます。南陽寺では花見が行われ、庭の糸桜を題材に、歌を贈り合ったと伝えられています。しかし、上洛に応じない朝倉氏を見限った義昭は、一乗谷を離れ、美濃へと向かったのです。
https://www.nhk.or.jp/kirin/journey/26.html

足利義昭「もろ共に月も忘るな糸ざくら 年の緒ながき契と思はば」
朝倉義景「君が代の時にあひあふ糸桜 いともかしこきけふのことの葉」
※『朝倉始末記』(巻第4)「義景母儀を二位尼に任ず。付けたり、義昭公、南陽寺の糸桜を見る事」
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3431173/184
元服祝の宴(うたげ)で、朝倉義景は、「阿君丸が後押してくれるので、上洛することに決めた」と言った。ところが、朝倉景鏡は、「元服と上洛は別」だと言う。朝倉義景は「元服と上洛は同義」だと言い、明智光秀に「意見を言え」と振られた。下戸で知られる明智光秀であるが、このドラマでは、酒を飲んでは失敗する。「無礼講」と言われ、酔った勢いで本音を吐いてしまった。
──上洛して戦をするなど論外
(無礼講でなかったら、その場で手討ちであろう。)
上洛反対派の朝倉同名衆(御一門衆)・朝倉景鏡や重臣筆頭・山崎吉家は、「明智光秀を呼んで良かった」と思ったに違いない。困った三淵藤英が助け船を出すと、朝倉義景は、「誰の手も借りず、朝倉家だけで上洛させる」と言い放った。上掲の公式サイトのあらすじには「その気まぐれな言動から」とあるが、今回のドラマの朝倉義景は、「上洛する」の一点張りで、ぶれていないように思われる。(このドラマでは、「朝倉義景が上洛の決心をしたのに上洛できなかったのは、家臣の中に上洛に反対する者がいたためだ」という解釈なのであろう。)
伊呂波太夫が明智光秀に近づいてきて言った。
「そろそろ船出の潮時ではありませんか?」
「生憎、船出の船が見つかりません」
と明智光秀が返すと、伊呂波太夫は、
「その船の名は既にお分かりのはず──織田信長。帰蝶様が仰せでしたよ。『十兵衛が考え、信長様が動けば、敵(かな)う者無し』と。お二人で上洛されればいいのです。上杉様も、朝倉様も不要ではありませんか?」
(朝倉丸はダメだね。忠太郎が逃げた。「ネズミは沈む船から事前に逃げ出す」と言われているからね。そして、今の織田丸は、最初会った時の小さな漁舟ではない! ドラマでは「尾張勢+美濃勢で六角勢に勝てる」と言っていたけど、実際の織田信長の上洛軍は、尾張+美濃+三河+江北+北勢勢で、その数は5万人とも、6万人とも言われている。)
マムシイズムを継承した二人──知の明智光秀と剛の織田信長は、二人で足利義昭を上洛させることに決め、岐阜城へ向かった。
「何? わしひとりで義昭様を京へお連れするのか?」
織田信長は驚くが、「大きな世」構想を受け入れる。
足利義昭も、
「私は美濃へ行く。そなたを信じよう」
と言った。
妻の煕子も、
「いつかこのような日が来るものと信じておりました」
と喜んだ。実は「子供たちに父親の故郷を見せたかった」とも。
※「大きな世」構想の説明が無かった。(以下の説明は想像)
・「大きな国」構想:周辺諸国を併合して「大きな国」を作れば、誰も手出しできなくなり、戦がなくなるという斉藤道三の構想。(ただし、平和なのは「大きな国」の国内だけであり、小さな国は、小さな国と戦い続け、戦国時代は終わらない。)
・「大きな世」構想:将軍が諸国をまとめて、平和な世を作るという明智光秀&織田信長の構想。(将軍が統治する「天下」の範囲を、京都、畿内、全国と広げていき、最終的には将軍が惣無事令を出して、戦国時代を終わらせる。)
明智光秀&織田信長は「天下布武」(武家、公家、寺社の3大勢力の内の武家が天下を統治するという考え)、将軍中心国家の再興が目的であって、「建武の新政」のような天皇(公家)中心国家については考えていないようである。
──三淵藤英の奸計(かんけい。悪だくみ)
三淵藤英は忠義の人である。主君・足利義昭が「朝倉義景と共に上洛したい」と言えば、そうなるよう努力するし、「朝倉義景を見限って織田信長と共に上洛したい」と言えば、そうなるよう努力する人である。
★参考記事:『麒麟がくる』に登場する三淵藤英は忠義の人だった。
https://note.com/senmi/n/n63984fa31ee7
織田信長の助力で上洛する場合の問題は、朝倉義景の説得である。
「織田信長と共に上洛したい」という足利義昭直筆の手紙を読んだ朝倉義景は、
「わしは悪い夢でも見ておるのか?」
「これは何かの間違いではないか?」
と困惑し、怒りを顕にした。
困った三淵藤英は、上洛反対派の山崎吉家&朝倉景鏡と密談した。
朝倉義景に上洛を断念させる方法は無いものか──。
下した結論は、上洛を後押しする阿君丸の毒殺──。
阿君丸は、病死とされるが、『朝倉始末記』(巻第4)「義景嫡子、逝去。付けたり、義昭公、美濃へ移る事」によれば、御サシという女房が阿君の乳母を妬んで毒殺し、その乳母の毒を含む乳を飲んだ阿君丸も死んだという。とはいえ、7歳の阿君丸が乳母の乳を飲むはずはない。乳母にしても、7年間も乳が出続けないであろう。ということは、毒殺?(史実は「絶妙なタイミングで病死」だと思うけど、足利義昭の御供衆に、密かに京都から毒薬が伝えられたという噂もあり、三淵藤英が朝倉家臣と手を組んで、毒殺したのかなぁ。それにしても、侍女(嘉門洋子さん)は、手際がよかった。くノ一なんだろうか?)病死にせよ、毒殺にせよ、阿君丸が死んだことには変わりなく、朝倉義景は、「阿君丸ロス」により、放心状態になり、政務を放棄したという。当然、上洛の意欲も薄れ、織田信長の足利義昭を擁しての上洛も認め、
「織田信長ごときが、ひとりで上洛させられる? 見ものだな」
と嫌味を言うのが精一杯であった。
「史実」をもとに話をすれば、織田信長は、足利義秋が矢島御所に居る時、単独で上洛させようとして失敗しているので、それを知っていれば、
「わしひとりで義昭様を京へお連れするのか?」(by 織田信長)
「織田信長ごときがひとりで上洛させられる?」(by 朝倉義景)
という言葉の重みが変わってくる。
※『朝倉始末記』(巻第4)「義景嫡子、逝去。付けたり、義昭公、美濃へ移る事」
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3431173/187
それはそうと、時代考証の先生、見逃しちゃいましたね。小宰相が出てるじゃありませんか! 小宰相は、阿君丸を産んですぐに病死(子を産めずに離婚させられた近衛前久の姉が呪い殺したとも)してますよ。7年前に。
あなたのサポートがあれば、未来は頑張れる!
