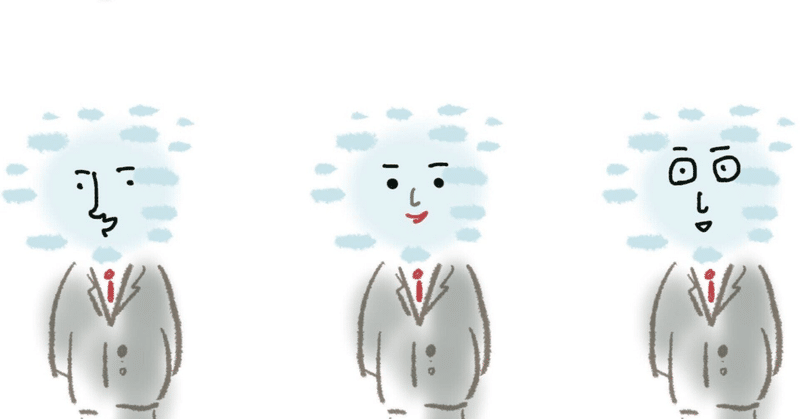
職場のニートに感謝するぅ!? 私の知る公務員ニートへ
主夫の薄衣です。
今回は、
以前私が勤めていた市役所で
一大勢力を築いていた人種
「公務員ニート」についてです。
「ニートに感謝する」
これは養老孟司さんの著書『超バカの壁』の一節です。この中では、主に当時(2006年刊)の若者のニート問題に触れる中で、「社内ニート」についてこんな既述がありました。
江戸時代には5人組という制度がありました。 ・・・どうしようもない人はその村でローカルに面倒を見ていた。ともかく生きる権利ぐらいは確保してやると言うことにしていました。日本人は基本的にはそういう慣習を持っていたのです。…
今でも、日本の会社というのは、そういう人を必ずある程度抱えています。給料を貰っているけれど、実際はニートみたいな社員です。勤めているふりをしているだけ、というような人です。
それは、養老さんの勤務先であった東大医学部にもいたんだとか。ホントか!?と思いますが、ともかくいたんだそうです。
これについて養老さんは
社内ニートに腹をたてたり彼らを放り出したりするよりは、そういう人が働かないから自分がちょっと働くだけで重宝されると思っておいたほうがいいのです。(中略)まさに努力さえすれば、出世できるという社会になっている。
その点においてニートに感謝すればいい。彼らは初めから脱落してくれている。自分の価値を上げてくれているということです。それを働いている方が怒ってはいけない。
正直、あと100年かかってもこの域には届かないと思いました。働かない人が自分のとこにいたら、やっぱり腹立ちますもの。
それならと、これを私に都合よく考えてみることにしました。
私のモデルとなる職場は、かつて勤めていた市役所です。
役所内ニート
私の元職場にもニートはいました。
でも、彼らはある意味堂々としていたように思います。
自分はこれでいいのだ、とか、ちゃんと仕事をしているふりができている、と、少なくとも堂々とサボっていました。
こういう人たちをそもそもニートと呼んでいいのかは分かりません。ただうちの役所では、仕事をしていないことを自覚し、組織の中で目立たないようにこっそりと潜んでいるタイプのニートは、あまり記憶にないですね。
かたや、組織はニートを黙認し、そうじゃない人々のところに仕事が回ってくるシステムでした。仕事の引き継ぎや業務分担が、はじめからニート達に仕事をさせないようになっていたのです。
「あの人には無理だよ。」
で済まされていました。
そうすると、
ニートじゃない人々も知恵がついてきます。
「あれでいいんだ」
と思う人も出てくるわけです。
能ある鷹が爪を隠し始めます。
すると、爪を出しっぱなしの人がどんどん消耗し、1人、また1人と倒れたり、爪を隠し始めたりしていきました。
公務員だって、仕事が原因でクビとか、処分されるシステムはちゃんとあります。でも、その実例が我が職場は全くありませんでした。
問題が起きると、せいぜい【他課へ異動】で済ませていました。それだと当人も、上司も痛くもかゆくもありません。そのせいか、誰も責任感や危機感を持たない、緊張感のない組織でした。
それでも、組織がニートを許容して、それを包み込んでなお前進する力を持っていればよかったのですが、うちの場合はその力も無かった。
また養老さんが言うように、ニートのお陰で仕事をした人が認められるという点も・・・う~ん?です。
非ニート、つまり使える人材はメチャメチャ使い倒されていましたが、その先にいいことがあったのだろうか?
なにせ給料はほとんど変わりませんから。働いても、働かなくても。
出世も年功序列が基本ですから、これまたほとんど変わりません。
そうして、
組織全体がニートになっていった・・・
そんな印象です。
ここまで私なりに整理してみて
思うことは、やっぱり
「辞めてよかった」です。
心からそう思いました。
かつて在職中、友人にこの話をした時、
「そんなところにいたら人間ダメになるぞ」
と言われたものです。
一方で、
生活にはお金がかかります。
皆そのために職場に留まり、
我慢したり、
自分の世界に入ったり、
爪を隠したり、
見て見ぬふりをしたり・・・
ついにはみんなと一緒にサボる人もいたわけですが、私はその世界から解放されました。
改めて、家族に感謝せずにはいられませんでした。
養老孟司さんの著作のホンの一節から、自分に都合よく考えを巡らせてみました。最後は、著者の考えるところとは全く違う場所に、不時着したかもしれません。
なんか、完全に独り言になったような・・・
でも、私はスッキリしました。
改めて、やっぱり社内ニートには感謝できんなぁと思いました。
自分の器を知りました。
まだまだ私は修行が足りないようです。
今回も最後までお読みくださり、
ありがとうございました。
タイトル画像は霞いちかさんから。
霞ヶ関勤務、大変大変お疲れさまです。
ありがとうございました。
サポートに心から感謝です。主夫、これからも書き続けます。
