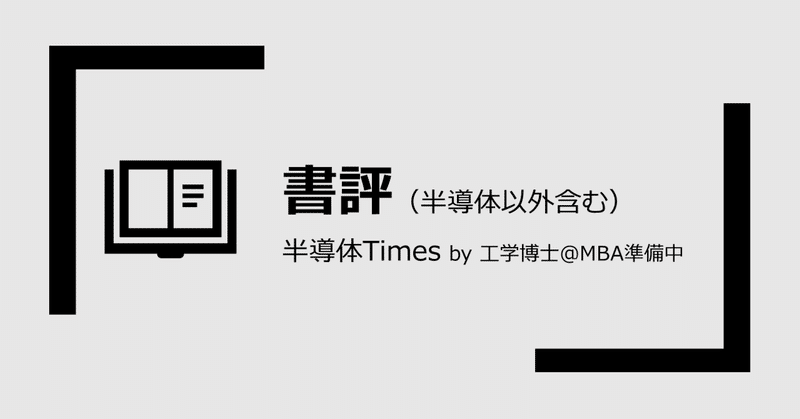
【書評】書評の仕事
「読み書きのスキルを高めたい」
そんなモチベーションでnoteを書かれているという方もいらっしゃると思います。
なにか文章を書こうと思うと,読み方,書き方,選び方,接し方など複数の能力が必要になります.
それらに得るためのコツについて本書では丁寧に述べられています.
書評なんて書かないよ...
という方もいらっしゃるでしょう.しかし,上述した能力を必要としないという仕事は非常に稀でしょう.本書は文章を書く全ての人に役立つ本です.
また,なかなか明かされる機会のない「書評家」という仕事について,
・苦労
・喜び
・プライベート
について述べられているという意味でも非常に貴重な一冊かと思います.
本書は以下のような人にオススメです.
・書評そのものに興味がある方
・ビジネスでの読み書きのスキルを高めたい方
・業界事情を覗いてみたい方
00.著者紹介
・印南敦史(いんなみ あつし)
・1962年生まれ
・東京都出身
氏はウェブメディアを中心に複数のメディアで執筆する書評家/作家として活躍していらっしゃいます.
なんと書評だけでも月に40本は書きながら,コラムやエッセイも執筆しているそうです.
面白いのは,氏は以前は音楽ライターとしてその経歴をスタートし一般雑誌へと移行していらっしゃいます。リーマン・ショック後に書評の依頼が届いたのをきっかけに活動開始したとのことです.
それまでは書評を全く書いたこともなかったというから驚きです.
書評とは何なのか?
そもそも書評とは何なのでしょう?
辞書では以下のように述べられています.
書評ー
「(読者のために)新歓の書物の内容を紹介・批判した文章」
三省堂『新明解国語辞典』第7版
氏は,この意見に対して賛成であるが伝統的な紙媒体の書評(=トラッド辞書)と情報としての書評(=ネオ書評)を比較すると前者はその目的に沿っていないことが多いという問題について指摘しています.
つまり,お偉い学者が新聞に載せている書評は表現も難解で読みにくく”読者のため” になっていないことが多いとのことでした.
氏の言葉を引用すると,
あたかも相応の知識や情報量を持っている人たち
のためだけにあるような(もちろんそんなことは
ないのですけれど),それらを持たない人には
近づきがたい読む気にならないものだったのです
確かにそうかも知れません.新聞の表紙に掲載されているような紙媒体の書評(=トラッド書評)とネットで読むような情報としての書評(=ネオ書評)を読みやすさで比較すると,
トラッド書評 > ネオ書評
と感じる人は多いでしょう.
事実,自分もトラッド書評を読んで本の購入に至ったことは数えるほどしかありませんが,ネオ書評を読んで ”ポチった” 経験は数え切れません.
また,ネオ書評(特に情報提供を主とする)を書く側に対する注意点として自分を出しすぎない重要性が述べられています.
(前略)情報メディアに対して読者が求めているのは「情報」であり,「個人」の考えではありません.わかりやすくいえば,情報発信者の「顔」はどうでもいいのです.
つまり,情報発信を目的としたネオ書評を執筆する場合は「書き手が出すぎないようにする」ことが重要であると述べられていました.
確かに発信する個人の顔が見えないほうが,何となく安心感を抱きやすい傾向はあるかもしれませんね.
最後に,氏は書評家のあるべき姿について以下の点が重視されるべきであると述べています.
1.伝える=わかりやすい書き方を考え,実行する
2.共感をつかむ=読者の目線に立つ努力をする
相手が求めているのは,情報か意見か.書評だけでなくビジネス文章を書く方もぜひ意識してみると良いかもしれません。
プロフェッショナルな書評とそうでない書評

新聞や雑誌,各種サイトに掲載されている書評はプロが書いていますが,そこには必ず編集者がいて原稿をチェックしています.
仮に差別的な表現,過激な表現などがあれば指摘が入り修正等を加える必要があります.
だからこそ掲載された書評にはプロフェッショナルとしての信頼性が担保されています.
しかし,現在はインターネットが発達しているため誰でも簡単に情報発信できます.もちろんそれ自体は,実績がなくとも才能さえあれば有名になれる
という意味で非常に良いことです.
しかし氏は注意すべき点もあると指摘しています.
それは編集・校閲機能が欠如していること.
個人が掲載している文章には編集者のチェックが入らないのです.
氏はこの点について非常に危険であると述べています.
私達は自分たちが書いた文章が他人を不快な気持ちにさせたり,悲しい気持ちにさせたりしないよう細心の注意を払う必要があるでしょう.
書評を通じて得られること

友達と話していて,自分の意見を述べた時に初めて自分の意見が分かった
ということを経験された方は多いと思います.
書評を書くことは文字で自分の意見を述べることに他なりません.
書評を書くことで,自分が何を考え,なにに関心を持ち,なにに興味がないかを改めて認識することが出来るのです.
つまり(書評に限らず)文章を書いて自分の意見を述べることは自己分析につながるのです.
氏はこう述べています.
従って僕は,自分の選んだ本を眺めたとき,
その本について書いたとき,
知人の意見を聞いた時などに
自分を再確認できるのです.
自分が何をやりたいか分からないという人は自己分析方法の1つとして
文章を書いてみてはいかがでしょう.
見えてくるものもあるかもしれません.
文筆業は儲かるのか?

程度の差はあれど,他人がどれほどの収入なのかは気になるものでしょう.
特に何をやっているかよくわからない人は尚更気になるものですね.それでいえば文筆業(書評家も含む)はよくわからない世界かもしれません.
本を出せば多額の印税が入る
というイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょう.
しかし氏はそれを ”ありえない” とまで言い切っています.
(人気作家や芸能人の場合を除く)
多くの場合,著者に入る印税は
印税=定価×部数×0.1
で計算されるそうです.(0.1より低くなる場合あり)
つまり1300円の本が、100万部売れれば1.3億円です.
しかし実際は,初版5000部~6000部程度なので一冊の印税は65万円程度です。つまり普通の文筆家は ”そんなに儲からない” ということでした.
ただしこれはあくまで文筆業における一般論.
実は本書では,書評家としての原稿料についても触れられています.
ここでは具体的な数字は割愛しますので気になる方は是非本書を手に取ってみてください。
書評の文字数について

書評において適切な文字数とは一体どれくらいなのでしょう.
本書で紹介されている例を取り上げるなら,
朝日新聞:800文字
週間文春:1000文字
Web:いくらでも
なのだそうです.
確かに紙ベースの書評であれば紙面が限られていますのでそれほど多くの情報を載せることは出来ないでしょう.
一方でWEBは無制限に書くことが出来ます.現に書評を含むこれまでのWEB記事は長ければ長いほど良いという傾向がありました.
なぜその様な傾向が生まれたのでしょうか?
答えはSEO(Search Engine Optimization)対策のためです.
SEOとは...
優良な被リンクを集めたり(外部施策)ユーザーに価値あるコンテンツを提供し適正に検索エンジンにページ内容を理解・評価されるようWebページを最適化することです.
一言で言えば,GoogleやYahoo!などの検索エンジンでキーワードが検索された場合に自サイトが上位に表示されるようにします.
実はSEO的には長ければ長いほど良質な記事を提供しているという判定になります.その結果として中身のない長いWEB記事が多数執筆されています。
しかし著者は長い文章を書くことに対して違和感を持っていると述べています.
大切なのは中身であって,長さではない.
そう確信している著者は「3で済むものを10に引き伸ばすことは決してしない」ように心がけているそうです.
なお現在は長ければ良いわけではないと読者の傾向が変化しつつあるようです.
そして適切な文字数として3000文字くらいという数字が出ていました.
もちろんケースバイケースですが,書評を執筆する方は3000文字を1つの基準としてみてはいかがでしょうか.
最後に
いかがでしたでしょうか?今回は,印南敦史氏の「書評の仕事」の書評を執筆しました.
最後まで読んでいただき,ありがとうございました.
本書へのAmazonリンクはコチラ↓
Kindle版はこちらです。
その他のおすすめ記事はこちら↓
よろしければサポートもよろしくお願いいたします.頂いたサポートは主に今後の書評執筆用のために使わせていただきます!
