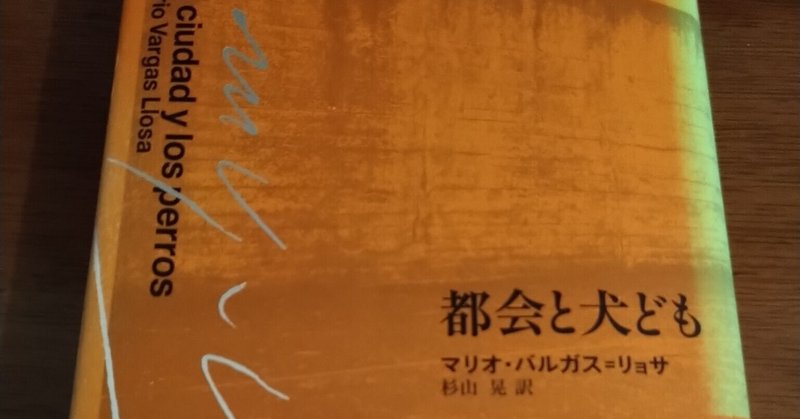
マリオ・バルガス=リョサ『都会と犬ども』
今回はマリオ・バルガス=リョサの『都会と犬ども』を紹介する。これはリョサが27歳(!!!!)で書いた初長編で、リョサ自身が2年半過ごしたレオンシオ・プラド士官学校(この小説の舞台にもなっている)での生活がベースとなっている青春小説。
まず初めに宣誓しておくと、ここではネタバレ的なものは極力さける。だからジャガーのあのこととかは書かない。それだけでなく、ストーリーを進めながら、リョサが読者にどの情報を隠し、だからここではこういう人物の視点を採用しているのだとか、最初あんまり効いていないようにみえたあの人の視点が、こういう事態に至って、こう効いてくるというような話は一切しない。これは正直厳しい。小説の書き方と内容は密接に関わっているから。しかし、まあしょうがない、頑張ります。
最初に感想を述べると、僕はこの小説がめちゃくちゃ好きだ。ここ最近なかったくらい夢中になった。最初はとっつきにくく感じたが、ものの50ページも読んだ頃には、先の物語が気になってしょうがなかったし、それ以上に(これは僕が小説を書いているから余計にそうなのだけど)それをどう表現するのかとわくわくが止まらなかった。最初のページから最後のページまでそれは変わらなかった。こんなことはめったに起こらない。紛れもない傑作。ただの傑作ではなくて、歴代の小説でベスト100とかやったら、絶対に入れなければいけないほど、それほどのレベルの傑作だと言い切れる。
この小説は81の断片から成っている。どういうことかというと、まあそのままなのだけど、あるエピソードがある人物の視点で、時には一人称、時には三人称で語られ始めて、それが短い時は2ページくらい、長い時は15ページとか語られ(いくつかの断片では三人称多視点を採用しているので、断片内でも視点の入れ替えがある)、エピソードが終わると、三行空けて別の断片が別の人物の視点(視点人物が変わらないで、場面転換だけが行われる場合がある)から別のエピソードが一から語られるという案配だ。まずこれだけでもこの小説の凄まじさの一端がうかがえると思う。リョサは最初時系列で一度この小説をまるまる書いたらしい。それから断片に分解していったという(おそらく足りない断片があって新たに書いたり、断片の初めや終わりを滑らかにするために書き直したりしたことだろう)。しかし、できあがった断片を読むと、それが元々一つであったとは到底思えない。それくらいバラバラ。士官学校に入る後と入る前のエピソードが並んでいたり、三人称、それもかなり引いた視点から語られる断片の後に、近視眼的な一人称がきたり、最初はその雑多さに面食らう。だがそれがだんだん癖になる。前の断片と全くちがう内容なのにすっと次の断片に入っていけるのは、その都度小説を立ち上げるのだというリョサの執念によるものだろう。それをリョサは81回もやった。とんでもない男だ。
あんまり概要ばかり書き連ねてもわからないと思うので、ちょいちょい引用する。といって、この描写だらけの小説のどこを引用すればよいのか迷う。迷うけれど、まずは冒頭をちょっとだけ。『都会と犬ども』杉山晃訳、新潮社、p5
「四だ」とジャガーは言った。
若者たちはほっと胸をなでおろした。うす汚れた電球からもれる明かりは、かすかにまたたいている。危険が過ぎさったのである。もっともポルフィリオ・カーバひとりにとってはそうではなかった。サイコロが振られ、三と一の目が出たのであった。うす汚れた床の上でサイコロがまばゆく映えている。
「四だ」とジャガーは繰り返した。「誰だ?」
「おれ」とカーバはつぶやいた。「四はおれだ」
「急いでやるんだ、左から二つ目だ、いいな」
カーバは寒気をおぼえた。便所は寮舎の奥にあった。寝室とはドア一つでへだてられ、窓がなかった。冬が訪れると冷たい風が、割れた窓ガラスや壁の隙間から寝室に吹きこんだ。今年の冬は特にきびしく、寝室のみならず、士官学校のどんな奥まった所でも、寒風が生徒たちの肌を刺した。夜になると、便所にまで風が入りこんで昼間からの悪臭やよどんだ空気を追い散らした。しかしカーバは山育ちだった。寒さには慣れているはずであった。だから肌があわだつとすれば、それは寒さのせいではない、こわいのだ。
男四人が士官学校の寮舎の奥にある便所の床に座り込んでサイコロを振り、出た目によって、その目を割り振られていた者に、なにかの役割をあたえている場面。これは三人称でカーバの視点が語られる断片だ。続いてこの小説の中心人物の一人、アルベルトのパート。『都会と犬ども』杉山晃訳、新潮社、p11
《親父のところへ行って、二十ソルくださいとねだったらどうだろう? きっとよろこんで、目をうるませて、四十か五十ソルくれるだろうよ。だけど、それじゃまるで親父に、母さんを苦しめたことは忘れることにします、こづかいさえたっぷりもらえれば、ぼくにはなんの文句もありません、どうぞ思う存分女遊びを楽しんでください、と言ってやるようなものだ。》母親がプレゼントしてくれた毛糸のマフラーの下で、アルベルトの唇はかすかに動いている。上衣とまぶかにかぶった軍帽は、寒さから身を守ってくれる。すでにライフル銃の重みに馴れ、肩にかけているあいだもほとんどその重みを意識することがない。《母さんのところへ行って、こう言ったらどうだろう? 父さんからびた一文受けとらないと言ったって、なんの得にもならないじゃないか。自分のやってることを反省して家に帰ってくるまで、毎月生活費を送ってもらおうよ。だけど、母さんがどういう反応を示すか、目に見えるようだな。泣きだして、イエス・キリスト様のようにじっと耐え忍びましょう、十字架を背負いましょう、とかなんとか言いだすにきまってるさ。それにたとえ小切手を送ってもらうことになったとしても、話し合いやら手続きには何日もかかる。おれはそんなに待てやしない。二十ソルが要るのはあしたなんだからな。》規則によれば、歩哨は、所属学年の中庭と閲兵場を見回ることになっている。しかしアルベルトは、寮舎の裏手を歩いていた。目の前に士官学校の色あせた塀がそびえている。外側を走る道路は、塀にはまった鉄格子の列に寸断されて、縞馬の背のように見える。蛇行する道路の向こう側は断崖になっており、打ち寄せる波の音はアルベルトの耳にもとどいた。霧が濃くなれば沖のほうに、あたかもきらめく槍のような形をしてラ・プンタの海岸線が見えた。それは海のなかへ長く突きでた防波堤のようでもあった。そしてそれと向かい合うような恰好で、まっ暗な湾のちょうど反対側に扇状の街の灯が夜空に浮かんだ。それはアルベルトが住む町、ミラフローレスの街灯かりであった。当直将校は二時間おきに歩哨の点呼をとることになっていた。アルベルトは、一時までに持ち場へもどればよかった。彼はいま、土曜日の外出のことで頭がいっぱいなのだ。
長くなった。この断片も三人称。アルベルトを視点人物にしているが、前の断片とはまるで違う。ほとんど一人称みたいな三人称。《》内でアルベルトの内面が長々とつづられる。三人称の意識の流れだ(前に紹介した『ダロウェイ夫人』でも似たような書き方がされている)。
最後にもう一つだけ断片を紹介しよう。『都会と犬ども』杉山晃訳、新潮社、p29
カーバがおれたちに言った。兵舎の裏手にめんどりがいるんだぜ。うそを言うな、この田舎っぺ、いるわけねえだろ。いやちゃんとこの目で見たんだ、うそじゃねえって。そんなわけで、おれたちは、晩めしのあと行ってみることにした。寮舎を避けて迂回し、戦闘訓練のときみたいに、腹這いになって進んだ。ほら、見ろよ、いただろ? な、おまえたち? 野郎は得意げだった。どうだい? 白い囲いに、色とりどりのめんどりときてる、どうだいおまえたち、ええ? どうなんだ? 黒いのを犯っちまおうか? それともあの赤いのにするか? 赤いのが太っててよさそうだぜ。おい、なにをぼやぼやしてんだよ。おれがこいつを押さえて、羽んとこを食っちまうぜ。ボア、くちばしを押さえろよ、とやつは簡単そうに言ってたけど、なかなかむずかしいことだった。こいつ逃げるなよ、おいで、こっちへおいでったら。おい見ろよ、ボアの野郎がこわいんだってさ、この男なんかいやだって顔をしてるぜ、尻をむけちまったよ。まったく、あいつめ、やけにはしゃぎやがってよ。だけど、おれはにわとりに指を突っつかれて、ほんとに往生してんだ、おい、はやいとこくちばしを押さえて、グラウンドへ連れて行こうぜ。巻き毛があの坊やを犯っちまったらどうだろう? 脚とくちばしをひもでしばりゃいいんだからな、とジャガーは言った。羽はどうすんだ、ええ?羽でちんぽこをちょん切られちまったらどうするんだよ、ええ? このめんどりはおまえが嫌いなんだよ、ボア。おい、田舎っぺ、たしかなんだろうな。さあ、だけどこの目でちゃんと見たんだぜ。どうやってしばるんだ? 馬鹿だな、きさまらはそろって馬鹿ばかりだ、にわとりは小せえからままごとみてえだけど、あそこんとこは熱いんだぜ! 巻き毛のやつがあの坊やを犯っちまったらどうだろう?
ここは一人称の断片。語り手の思考の垂れ流し、一人称の意識の流れ。「」なしで他の生徒の声も混じり合い、いったい誰がなにをしゃべっているのか、なにが起こっているのか、完璧に理解するのは不可能に近い。フォークナーは『響きと怒り』でこういう語り(もっとわかりにくいけど)で小説をはじめた。そのことであの小説は多くの挫折者を生んだわけだけど、『都会と犬ども』ではそんなことはない。リョサは三人称の語りを基調とする。時たま上の引用のような意識の流れによる語りが混ざる感じなので、小説がまるでわからなくなることはない。この辺りに人をこの小説に引き込むための、リョサのしたたかな戦略がみるのは僕だけだろうか?
目についた3つの断片を紹介した。この他にもリョサはいろいろなテクニックを駆使している(フローベール『素朴なひと』の感想でもとりあげた通底器も使われている。フローベールとフォークナーがリョサに与えた影響の大きさをこの小説読んで実感した。というか、この小説はフォークナーmeetsフローベールともいえるかも)。しかし、ここだけでも凄さの一端はわかってもらえると思う。これらの断片にはいくつもの声が飛び交っているが、他の断片にはもっと多くの声が響き合っている。それらは小説を外へ外へと押し広げる。その拡散する力は小説という定められた器を壊さんばかりだ。にも拘らず、この小説は全体としてとてもバランスがいい。こじまんまりとせず、どこまで読んでも得たい知れなさを感じるのに、小説としてまとまっている。凄まじい偉業としかいいようがない。なんというか、いつかこんなの書けたらいいなあと見上げるような小説だと思う。
ということで、今回はマリオ・バルガス=リョサの『都会と犬ども』を紹介した。上手く紹介できたかどうか心もとないけど、あとは実際に読んでみてください。定価で3000円くらい(中古で2000円くらい)で、ちょっと勇気がいる価格ではあるけれど、詰まらない小説をいくつか買うよりも、この真の傑作を一冊買ってじっくり読んだ方がいいと、僕は断言します。
ではまた!
よかったらサポートお願いしやす!
