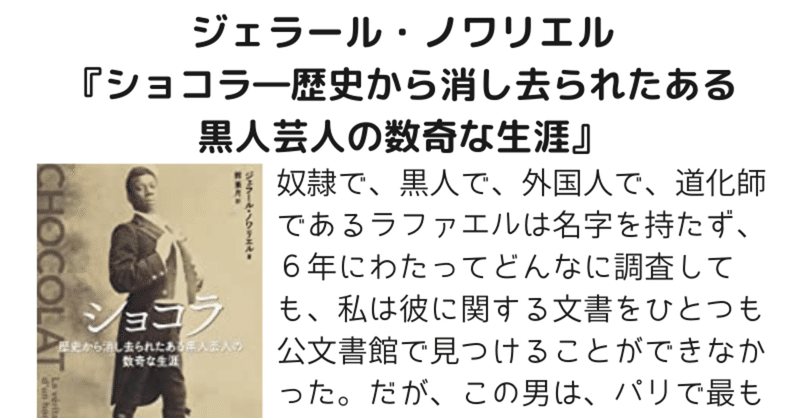
歴史のことば No.10 『ショコラ―歴史から消し去られたある黒人芸人の数奇な生涯』 (ジェラール・ノワリエル)
”ショコラ”――この男性には身元登録すら存在しない。リュミエール兄弟の映画に出演し、ロートレックの絵の題材となるなど、同時代のパリで彼の名はひろく轟いていたにもかかわらずである。
奴隷で、黒人で、外国人で、道化師であるラファエル[注:のちに”ショコラ”という芸名になる]は名字を持たず、6年にわたってどんなに調査しても、私は彼に関する文書をひとつも公文書館で見つけることができなかった。だが、この男は、パリで最も有名なアーティストのひとりだったのだ。そして当時のパリは世界の文化的首都と見なされていた。
黒人ラファエル(”ショコラ”)が連れてこられた19世紀末のパリでは、各地に回遊式の商店街(パサージュ)が建設され、消費文化やショービジネスが花開いていた。
すでに同じカリブ海に浮かぶハイチでは1804年に黒人共和国が建国され、フランスでは1833年に奴隷制が廃止されていたはずだ。
にもかかわらず、なぜ黒人奴隷はなおもパリにいたのだろうか?
実は、砂糖プランテーションが最盛期を迎えていたキューバでは、19世紀末にいたって、なおも奴隷を使いまくっていたのだ。
しかも19世紀末といえば、ナイジェリアのオヨ王国が植民地化によって衰退していった時期とも重なる。
多くのヨルバ人がカリブ海へと運ばれ、砂糖資本を潤した。ハバナの旧市街と新市街を分かつパセオ・ディ・マルティ大通りは、アメリカのクラシックカーの並ぶ観光スポットだが、この通りこそが、かつてのキューバの上流階級が飲み歩く繁華街でもあった。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oldtimers_on_Paseo_de_Marti,_Havana,_Cuba_(41807460714).jpg
キューバでは1868年以降に生まれた子供とすべての高齢者が解放されたが、ラファエルが生まれたのは、その少し前のことだった(最終的に奴隷制が廃止されるのは1880年代のことである)。
こうした時代背景のもと、ラファエルはハバナから強制的に出向させられ、パリに売られた…と思いきや、ノワリエルは、彼がスペインのバスク地方・ビルバオに移送され、農場で苦しい仕打ちにあい、鉱山に逃げ出していた経緯を現地にも足を運び紐解いていく。特に58-69頁あたりから第3章にかけての展開は、実におもしろい。いかにしてラファエルは”ショコラ”となり、パリにたどり着くことになったのか。数奇な運命が描かれる。
パリ随一のサーカス座ヌーヴォー・シルク(パリ1区、現在はマンダリン・オリエンタル・パリになっている)に雇われることとなり、相方の白人芸人フティットとのコンビで、”ショコラ”と名付けられる。由来はもちろん、肌の色からである。
リュミエール兄弟の映画におけるショコラ
当時はまだパリにおける黒人の人口は、そこまで多くなかった。通りでは人々に指さされ、侮蔑的な言葉が投げかけられたようだ。ステージ上では上流階級に拍手喝采を浴び人気を博したラファエルだったが、あくまで”元奴隷の黒人芸人”として消費され続けたことに彼の苦悩があった(のだろう)。
著者ジェラール・ノワリエルはフランスの歴史学者で、移民に関する研究で知られる。本書は分厚く(571頁)、上下巻に分かれた長編小説でもある。ラファエルの実像に迫ろうとすればするほど、史料の壁はとてつもなく高い。
さきほどわたしは彼の心中について「のだろう」を添えた。人間ラファエルの存在が声なき者として葬り去られることに、ノワリエルは強い問題意識を感じていた。
彼を持ち上げ、そして忘却したのも、そしてショコラと名づけたのも、当時のフランス人全体ではなかったか。今なお巣食う人種主義も、それと連続しているのではないか。そのような意識がノワリエルにはある。
しかし、公文書館になんの史料も残されていないがために君の真の人生が闇に包まれたままなのを見て、このままでは、君が記憶に拒否されている現状を、私自身も容認することになってしまうのではないかと感じ始めた。この罠から逃れるために、鏡の向こう側に行くことを私はついに決意した。(本書57頁)
鏡の向こう側とは、たとえば「文学」である。作家の生み出した物語の想像力を狩りながら、ラファエルの実像に肉付けしていく。文学と歴史を架橋する。そんな歴史学者としての自問自答が随所にナレーション挿入され、ドキュメンタリー映画のようでもある。ショコラを題材とした映画もつくられた。こちらから入ったほうがイメージがつきやすいかもしれない。
歴史書を読むように、文学作品や映画作品を読む。もちろんそのなかには、構築されたイメージも多分に含まれているだろう。だが、そもそもイメージに囚われていない人間などいない。特定の作品を「厳密に言えば違う」と指摘しても、まずは土台となるイメージがなければ、歴史的な現実はやせ細り、具体性のないものになってしまう。本書が教えてくれるのは、そうした「文学的肉付け」のなんたるかだ。
このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊
