
歴史のことばNo.3 「黒人労働者たちは「民族自決」に触発され、黒人解放運動を展開し、暴動を起こした」(北村厚『20世紀のグローバル・ヒストリー』)
タイトルにもあるように、本書は一般向けの、グローバル・ヒストリーの現代史編だ(この姉妹編に、近代までを描いた『教養のグローバル・ヒストリー』がある)。
本書は一見、堅めの教科書のようにみえるかもしれない。
だが、北村氏の提供する視点に、うまく気づくことができるか、そこが重要だ。
冒頭で筆者は、「人類共通の問題群を主軸にすえる」と宣言している。
たとえば、これである。
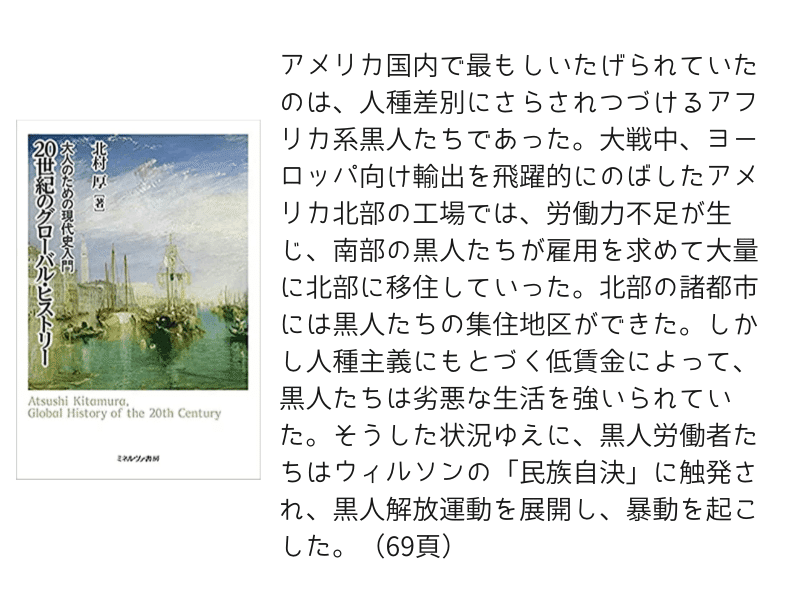
第一次世界大戦中の、アメリカ合衆国内の事情を記した箇所である。
通常の教科書であれば、こんなことは書かれず、閑却されてきた。
「民族自決」という国際政治上の大問題は、各地の民族運動を触発した。
これでおしまいである。
だが、ここに、アメリカ合衆国国内の「人種」、そして労働者という「階級」の問題が交錯する。
昨今、インターセクショナリティへの関心が高まっているが、「ジェンダー」「民族」「イデオロギー」といった大文字のカテゴリーは、たしかに互いに重なり合い、ときに対立し合うことで、社会のなかに周縁を生み出してきた。たとえば黒人参政権に対する運動に対し、白人の主導する女性参政権運動は冷淡であった。
複数のカテゴリーがどのように交錯し、いかなる「しくじり」を生み出してきたのか、そして、それがグローバルな規模でどのように連関し、変容してきたのかを問うことは、現在のわれわれの社会のしわよせに「気づく」力を提供する。
現代史をひとまとめにし、バランスよく一人の著者が概説する一般書は、意外にも少ない。
筆者はそれを、「人類共通の問題群を主軸にすえる」ことで実現した。
かねてからの私の関心とも、ここ数年書き継いでいる私の書き物にも、合致する考え方だ。
ところで表紙は画家ターナーの作品(「ヴェニス」)だ。ナポレオン戦争後の、平和なヨーロッパでは、蒸気船の普及とともに観光旅行が流行した。近世以来のグランド・ツアーの伝統を引き継ぎ、ターナーもローマに憧れた。ターナーといえば「雨、蒸気、速度」(1844)で、新時代の蒸気機関車を描いたことが有名だが、積荷を満載した帆船の浮かぶ「ヴェニス」(1835)は、その数年前、まさに蒸気機関車の草創期に描かれた。
ヴェニスは、16世紀以降、大西洋・太平洋にネットワークの中心がうつることで、そのプレゼンスを低下させたとよく説明される。だが「中心主義を排する」(羽田正2018)グローバル・ヒストリーの立場から歴史を再構成するならば、「中心が移動した」のではなく、「関係性が変化した」といったほうがよいのだろう。北村氏は前著でネットワークに着目したグローバル・ヒストリーを展開されているが、本書を読み、そのうえで装幀をみて、近代までの世界史を引き継ぎながらも、20世紀に向けたグローバルな変容を予感させるような印象をいだいた。
話が横道にそれたが、本書に施されているさまざまな仕掛けを丁寧に読み解くことで、現在の世界にもひきつがれる問題群に「気づく」力を養うことができるはずだ。
このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊
