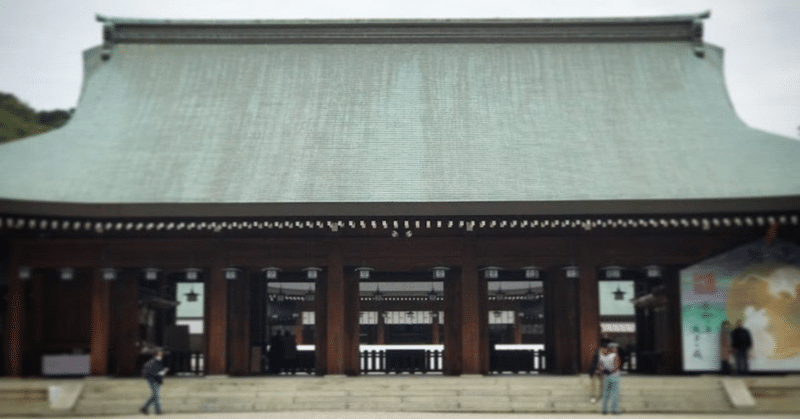
一からわかる歴代天皇 初代~第9代 神武・綏靖・安寧・懿徳・孝昭・孝安・孝霊・孝元・開化
皆さんこんにちは。今日から一からわかる歴代天皇として、初代神武天皇から現在の第126代の今上陛下までの歴代天皇について解説をします。
第1回目のこの記事では、初代天皇の神武天皇から第9代開化天皇までを解説します。
初代 神武天皇
神武天皇は紀元前660年に橿原宮(現在の奈良県橿原市)で即位したとされています。
神武天皇について書かれているのは古事記と日本書紀です。ただ神武天皇についての情報は神話要素が含まれており、実在したか否かについては議論がされています。この記事では実在したか否かについては述べないこととします。
日本神話に登場する太陽の神でもある女神天照大神はイザナギノミコトとイザナミノミコトを父母にもちます。
古事記によると、天照大神の孫、瓊瓊杵尊のひ孫にあたるのが神武天皇です。
古事記では神武天皇が即位するまでのことが書かれています。神武天皇は日向の国(今の宮崎県)で生まれたされ、東征を行い大和(今の奈良県)を目指すことにしました。
古事記などによると、ナガスネヒコが大和を支配しており、神武天皇らは大和へ入ろうとした際にナガスネヒコと戦い、その際、兄のイツセノミコトは流れ矢があたりなくなってしまいます。
船に乗り神武天皇ら兵は撤退し熊野(紀伊半島南端)へ行きます。熊野に上陸すると、土地の神の毒気にやられて全員気絶してしまいます。
絶体絶命のピンチに、タケミカヅチオの布都御魂を持った高倉下命が現れます。この布都御魂の霊力により毒気をはらったのです。
しかしその後も山の中で迷子になるというトラブルが起きます。その時、天照大神の遣いで足が3本あるカラス、八咫烏(ヤタガラス)が現れ神武天皇を案内しました。
その後、神武天皇らは連戦連勝を繰り返しついに最終決戦、因縁のナガスネヒコとの戦いになります。
日本書紀によると、またしても負けるかに思われたその時、金色のヤタガラスが現れ、神武天皇の弓にとまったのです。そのまぶしさにナガスネヒコの兵は目を開けることができず降参をしました。
その後、梶原宮で紀元前660年2月11日に即位を宣言しました。現在の建国記念日はこれが由来です。
この即位した日から1年をカウントするのを皇紀といい、西暦2023年は皇紀2683年です。
即位から76年後、神武天皇は梶原宮で崩御しました。古事記などよると、神武天皇は127歳で崩御したとなっています。
この年齢は当時の平均寿命が40歳前後だったことを考えると不自然です。ただ、古代日本では春分の日と秋分の日を1年とする春秋二倍暦というのが使われていた可能性があるのです。つまり現代の1年が古代の2年ということです。
その場合、神武天皇は63.5歳で崩御したとなります。しかしこれについても議論が交わされています。
第2代 綏靖天皇
日本書紀によると、神武天皇が即位してから42年後の、神武天皇42年1月3日に綏靖天皇は立太子となりました。
名前は「神渟名川耳尊(かんぬかわみみのみこと)」と言います。
神武天皇76年、初代天皇である神武天皇が崩御しました。
日本書紀などによると、神武天皇は2人の女性との間に子がいました。そして綏靖天皇の異母兄弟で神武天皇の第一皇子、手研耳命(タギシミミノミコト)は自らが天皇になるために綏靖天皇と第二皇子の神八井耳命(カンヤイミミノミコト)を殺害しようとします。
この計画を知った2人は弓で手研耳命を射て殺します。この時、神八井耳命は手足が震え矢を射れなかったと書かれています。
その後、綏靖天皇第2代天皇として即位します。
日本書紀・古事記には綏靖天皇ついてこれ以上書かれていることはなく、情報が少ないことから第2代天皇~第9代天皇は欠史八代と言われています。
綏靖天皇33年、84歳で崩御しました。
綏靖天皇は第三皇子であり、日本の古来に末弟相続の考え方があった可能性があります。
第3代 安寧天皇
綏靖天皇5年、綏靖天皇の長男として安寧天皇が誕生しました。記紀(日本書紀・古事記)などには兄弟姉妹についての記載はありません。
綏靖天皇25年に立太子になり、綏靖天皇33年に父の綏靖天皇がが崩御したのち即位しました。
古事記によると49歳で崩御しました。
綏靖天皇と同様に、記紀に情報がほとんどないことから欠史八代と呼ばれています。
第4代 懿徳天皇
綏靖天皇29年、安寧天皇の第二皇子として懿徳天皇は誕生しました。
16歳の時に立太子になり、安寧天皇38年に安寧天皇が崩御すると即位しました。
懿徳天皇元年に即位し、懿徳天皇34年に、古事記によると45歳で崩御しました。
懿徳天皇も情報が少ないことから欠史八代の1人です。
第5代 孝昭天皇
懿徳天皇5年、懿徳天皇の子として孝昭天皇は誕生しました。
古事記によると、兄弟にタギシヒコノミコトがいます。
懿徳天皇22年に立太子になりました。
懿徳天皇が崩御した2年後に即位し、83年間在位したのち113歳で崩御しました。
春秋二倍歴として考えると、56.5歳で崩御したことになり、当時の平均寿命が40歳前後だと考えると、不自然な数字ではなくなります。
ただ記紀に載っている情報が少ないため、欠史八代の1人です。
第6代 孝安天皇
孝安天皇は記紀の中で最も情報が乏しい天皇です。
兄弟にアメオシタラシビコノミコトがいます。
孝昭天皇68年正月に立太子しました。
孝安天皇の名は、日本足彦国押人尊です。
記述していなかっただけで、初代天皇の神武天皇から孝昭天皇も名前が存在します。
足彦とは美称なので特に意味はありません。また、秋津島に都があったと記紀に記載されていますが、秋津島は特定の地域ではなく、日本全体をあらわしていると研究されています。
在位期間は102年間でした。
前途の通り、欠史八代の1人です。
第7代 孝霊天皇
孝霊天皇も神話の要素が多い天皇です。
孝安天皇51年に誕生しました。
名は、大日本根子彦太瓊尊と言います。
根子はその土地の人という意味や、魏志倭人伝にある地方の豪族を表す「爾支」にあたるといった研究もあります。
皇后との間に大日本根子彦国牽天皇(後の孝元天皇)が生まれました。
また、 倭国香媛との間には、倭迹迹日百襲姫命・吉備津彦命・倭迹迹稚屋姫命が生まれました。
この倭迹迹日百襲姫命が中国の魏志倭人伝に登場する邪馬台国の女王卑弥呼なのではないかという研究もされています。詳しくは、第十代崇神天皇の際に説明します。
また、吉備津彦尊も崇神天皇の時代に登場します。多くの研究では、第十代崇神天皇から実在したとする説が有力となっています。なので、その崇神天皇時代に登場する人が孝霊天皇の子として記紀に記録されていることから、神話から実在したとする時代への転換のあたりではないかとも言われています。
孝安天皇76年に立太子し、孝安天皇102年孝安天皇が崩御した翌年に即位しました。
在位76年で、106歳で崩御しました。欠史八代の1人です。
第8代 孝元天皇
孝元天皇の名は大日本根子彦国牽尊です。
この国牽を国引きととらえて、他国を併合した天皇であるとする説もあります。
孝霊天皇18年に誕生し、孝霊天皇36年に立太子したとされています。
皇后との間に、大彦尊・稚日本根子彦大日日尊(後の開化天皇)・倭迹迹姫命が生まれました。
倭迹迹姫命は孝霊天皇の子である倭迹迹日百襲姫命と同一人物であるのではという見方もあります。
大彦尊も崇神天皇時代に登場します。また、安倍氏の始祖ともされています。
即位57年に崩御しました。欠史八代の1人です。
第9代 開化天皇
孝元天皇の第二皇子です。
開化天皇の時代、都が北のほうへ移動しています(現在の奈良市のあたり)。
このことから、開化天皇が勢力を大和の北部へ拡大させたという見方もあります。
歴史学者で東京教育大学名誉教授であった肥後和男氏は著書の歴代天皇紀の中で、こう述べています。
『魏志』の記載によると二世紀の中頃、日本は大きな政治的混乱の状態にあったことになる。それはいわば日本の統一に当る前段階としての騒乱であったと思われるが、その具体的な状況は全く不明である。
つまり、開化天皇時代に日本の統一の前段階としての戦いがあり、それが魏志倭人伝に記録されいている騒乱のことであるということです。
開化天皇は、孝元天皇22年立太子し、孝元天皇57年、孝元天皇の崩御に伴い即位しました。
皇后との間に、御間城入彦五十瓊殖尊(後の崇神天皇)が生まれました。
古事記によると、63歳で崩御しました。欠史八代の1人です。
あとがき
今回解説したのは
初代 神武天皇
第2代 綏靖天皇
第3代 安寧天皇
第4代 懿徳天皇
第5代 孝昭天皇
第6代 孝安天皇
第7代 孝霊天皇
第8代 孝元天皇
第9代 開化天皇
です。
第2代綏靖天皇から第9代開化天皇は系譜以外の情報が乏しいため、欠史八代と呼ばれています。
参考文献
このnoteは以下のものを参考にしました。
肥後和男 (1975). 歴代天皇図巻 秋田書店
肥後和男 水戸部正男 福地重孝 赤木志津子 (1972). 歴代天皇紀 秋田書店
笠原英彦 (2001). 歴代天皇総覧 中央公論新社
所功 (2006). 歴代天皇知れば知るほど 実業之日本社
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
