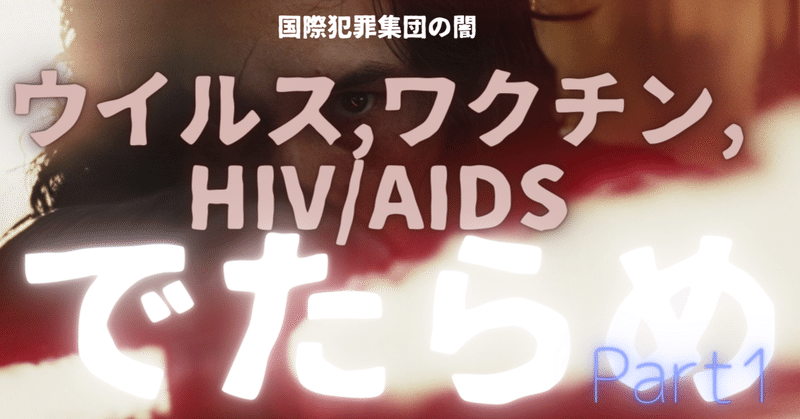
ウイルス、ワクチン、そして HIV/AIDS仮説についての再考 - Part 1 / Dr. Robert O Young
本記事は下記URLをDeepL機械翻訳したものです。
ところどころ、機械翻訳が誤訳をするように原文を改竄工作された箇所がありましたので手直しを掛けていますが、お気づきの点がございましたらご連絡下さると幸甚です。
国際的に罪を犯しているものが、まだ現役で人の上に立っていますからね。
医療利権が国際犯罪を犯し続けていることが信じられない人は、下の動画をちょっとご覧になっていただくと冷静に判断できるかもしれません。
以下、3部作中の1作目となっております。
Robert O Young博士に敬意を表して
International Journal of Vaccines & Vaccination
eISSN: 2470-9980
ウイルス、ワクチン、そして
HIV/AIDS仮説についての再考 - Part 1
Robert O Young
Universal Medical Imaging Group, USA
Correspondence: Robert O Young, pH Miracle Inc., 16390 Dia del Sol, Valley Center, California, 92082, USA, Tel 760 751 8321
Received: January 01, 2016 | Published: June 20, 2016
Citation: Young RO (2016) ウイルス、ワクチン、HIV/AIDS仮説についての再考 - Part 1。 国際ワクチン学会誌「ワクチン2」(3): 00032.
DOI: 10.15406/ijvv.2016.02.00032
ウイルス
「科学の世界では、大学やアカデミーで学んだことや受け継がれてきたことを、すぐに自分の所有物と考えるようになる。しかし、(何年も唱えてきた)信条に反するような新しい考えを持った人が現れ、それを覆そうとすると、その脅威に対してあらゆる情熱が高まり、それを抑えるためにあらゆる方法が試されることになる。知らないふりをしたり、調べる価値もないかのように悪く言ったり、あらゆる方法で抵抗します。そうして、新しい真実は、長い時間をかけてようやく受け入れられるのである」(ゲーテ)
はじめに
ウイルスを初めて分離したのは1892年、ロシアのバクテリアハンター、ディミトリ・イワノフスキ/ Dimitri Iwanowskiである。イワノフスキは病気にかかったタバコから液体を採取した。イワノフスキは、病気にかかったタバコから液体を採取し、細菌が付着しないように目の細かいフィルターに通したが、驚いたことに、細菌が付着していない濾液は簡単に健康な植物を病気にしてしまった。1898年、オランダの植物学者マルティナス・ウィレム・バイヤリンク/ Martinus Willem Beijerinckがこの実験を繰り返し、目に見えない原因があることを認識し、その感染源を「タバコモザイクウイルス」と名付けた。バイヤリンクの報告と同じ年に、ドイツの2人の科学者が、牛の口蹄疫の原因となるろ過可能なウイルスを含む液体を精製した(かつてウイルスは「ろ過可能なウイルス/ filterable viruses」と呼ばれていたが、やがて「ろ過可能な」という言葉はウイルスにのみ適用されるようになり、使われなくなった)。1901年にウォルター・リード/ Walter Reedが黄熱病の原因となる濾液を発表したのに続き、すぐに数十種類の病気の原因となるウイルスが発見された。
1935年、もう一人のアメリカ人ウェンデル・M・スタンリー/ Wendell M. Stanleyは、初心に戻って、タバコモザイクウイルスの純粋な結晶をろ過液から作り出した。スタンリーは、この結晶が植物に容易に感染することを確認し、ウイルスは塩のように結晶化しても感染力を失わないことから、生物ではないと結論づけた。その後、世界中の細菌学者がウイルスをろ過するようになり、生物学の新しい分野である「ウイルス学」が誕生しました。
ウィルスが生きているかどうかは、歴史的に見ても医学的には曖昧であった。当初は非生物とされていたが、現在では極めて複雑な分子、あるいは極めて単純な微生物とされており、通常は生命サイクルを持つ寄生虫と呼ばれている。(ウィルスワクチンの一部には「殺した」という言葉が使われており、ウィルスは生きているという公式見解が示されている)。ウイルスは、DNAまたはRNAを核として、それをタンパク質で覆っているのが一般的であり、固有の生殖能力を持たないため、複製は宿主に依存する。ウイルスは、感染した細胞の核酸を利用してタンパク質を複製し(つまり、宿主を騙してタンパク質を作らせ)、そのタンパク質を自動車の組み立てラインのように新しいウイルスに組み立てるのである。理論的には、これがウイルスが生き残り、新しい細胞や宿主に感染するための唯一の手段である。
ウイルス学の誕生と誤算?
すなわち、すべての微生物(ここではマイクロフォームと呼ぶ)は固定種であり、不変であること、各病型は(通常は)1つの特定の病気を引き起こすだけであること、ミクロフォームは決して内因的に発生しないこと、すなわち宿主の中で絶対的な起源を持つこと、そして血液や組織は健康な状態では無菌であること、などである。この最後の点については、すぐにコメントする必要がある。理論的には、理想的な健康状態であれば、血液は無菌であるかもしれないが、本書の本文で述べたように、病的なマイクロフォームが発生する可能性を内在しているのである。しかし、生きた血液を位相差暗視野顕微鏡で長時間繰り返し観察してみると、無症状の宿主であっても、あるいは正統的な用語で正常または健康と定義される状態であっても、血液には様々なマイクロフォームが含まれていることがわかる。その形態は、他の身体的症状が出る前に容易に見ることができる。(長い間、繰り返し観察されてきた結果、マイクロフォームの存在は他の病気の症状と関連し、マイクロフォームの消滅は健康の回復と関連しているため、マイクロフォームは差し迫った病気の外見上の兆候を示す指標となるのである。)
単形性は20世紀の医学研究と治療の発展の礎となった。ウイルスやバクテリア(酵母や真菌も)はミクロの細胞から進化したものであること、ミクロの細胞は生体内で急速に形を変え(進化し、「消滅」する)、内側の地形(環境)の条件に応じて別の細胞になること、血液や組織は必ずしも無菌ではないこと、特定の病気は存在せず、特定の病状だけが存在することなど、多形性の実証された事実を、主流派は公平に検討することを拒み、ましてや受け入れようとしなかったことが、後世の「ガリレオ論争」の基礎となった。ガリレオ論争とは、科学的権威の「衣」をまとった人々が、天文学者の真理を罰した宗教的狂信者と同じように、反証を提示されても愚行から逃れられないことからそう呼ばれている。これらの証明は、前世紀のアントワーヌ・ベシャン/ Antoine Bechampから本格的に始まった(彼もまた、狂信的な聖職者の憤りに耐えた)。
20世紀初頭には、濾過できる細菌と濾過できない細菌の激しい論争が行われた。これは、後述する微小形態学に関わる大きな戦いであった。細菌の形態は通過するほど小さくない、あるいはもっと小さい初期段階がなかった、という正統派の見解が優勢であった。バクテリアを通さないフィルターを通過するのは、別のもの、つまりウイルスである。標準的な医学の教科書では、このように細菌とウイルスが区別されていた。しかし、その後、マイコプラズマ、リケッチア、その他の様々なグループのように、元々ウイルスと考えられていた多くのろ過可能な形態の細胞性が確立された。筆者の考えでは、単形論の勝利により、感染症の「病」に対する深い理解が失われ、癌や変性症状、エイズの原因となった。
1μm(マイクロメートル)=1μ(ミクロン)=1000ミリミクロン
1ミリミクロン=1nm(ナノメートル)=10Å(オングストローム)
参照:https://www.convertworld.com/ja/length/micrometre.html
何が見える?
典型的な細菌の大きさは約1μm(1マイクロメートル=1000ミリミクロン=1000ナノメートル)である。現在、ウイルスと呼ばれているろ過可能な形態のほとんどは、0.3ミクロン(300ミリミクロン)から0.01ミクロン(10ミリミクロン)の大きさで、一部はコロイド領域(0.1~0.001ミクロン)である。大規模なウイルスのほとんどは、平均的な細菌の3分の1から4分の1の大きさである。なぜなら、0.3ミクロンというサイズは、現代の光学顕微鏡の解像度の限界だからである(カナダの顕微鏡学者、ガストン・ネサン/ Gaston Naessenの「ソマトスコープ/ Somatoscope」の解像度が0.015ミクロンであることを除いて)。このように、ウイルスが発見されると(おたふくかぜのような非常に大きなものを除いて)、電子顕微鏡でなければ見ることができなかった。特に、ロイヤル・ライフ/ Royal Rifeの顕微鏡技術とキャリアが既得権益者によって破壊されてしまったことを考えると、電子顕微鏡が必要であった。残念ながら、電子顕微鏡と化学的染色法は、すべての試料を無秩序にしてしまうが、ライフの技術は、そのレンズの下で生命を進行させ、進化させることができたのである。ウイルスが技術の進歩によって見えるようになると、その技術は、モノマネに感染した心に、体にとって異物とみなされるタンパク質構造を明らかにしたのである。
新しい理論
19世紀にベシャンが提唱した「マイクロザイムの原理/ microzymian principle」は、「ウイルス」に関する新しい理論の基礎となっている。この原理を簡単に説明すると、すべての生物の中には生物学的に破壊できない解剖学的要素があり、それをベシャンは「マイクロザイム」と呼んだ。それらは独立して生きている組織化された発酵体であり、酵素を生産することができ、バクテリアのようなより複雑なミクロ形態に進化することができる。ベシャンの論文は、病気は自分の内部環境(地形)の状態であること、病気(とその症状)は「私たちから生まれ、私たちの中にある」ものであること、病気は微小実体の攻撃によって生じるのではなく、微小実体の内発的な進化を呼び起こすものであること、である。(この共通の生物学的根拠については後述します)。
私の研究と調査によると、科学がウイルスやレトロウイルスと呼ぶ複合体は、マイクロザイムの原理が示すように、細胞内で発生する。しかし、それらは、遺伝子の修復を目的として、憂慮すべき状況(病気の状態)に対応して作られる。それらは、解剖学的要素(マイクロザイム)から進化した修復タンパク質であり、病原体ではない。
正常な細胞活動には、遺伝子修復が含まれていることが知られている。酵素もタンパク質も関与しているはずです。どのようなメカニズムなのでしょうか?ウイルスは、DNAかRNAのどちらかで構成されていますが、両方ではありません。したがって、おそらく、遺伝子分子などの構造を修復することが目的であり、体がそれを必要としているからこそ、病気の症状が現れるのだと思います。ウイルスが繁殖するためには、生きた細胞や宿主が必要なので、侵入された結果ではなく、細胞(つまりマイクロザイム)が目的のためにシナリオを動かしているとは限らないのではないでしょうか?病気(生体内のバランスの乱れ)は非常に多く、特に一般的な症状が出ていないものは、修復タンパク質が頻繁に、あるいは常に存在している可能性があります。毒素を受けた細胞は、簡単にゲノムに局所的な損傷を受けます。ほとんどの観察者はマイクロザイムの原理を知らないし、ましてや理解も検討もしていません。また、単形性は侵略を強調するので、これらのタンパク質複合体は異物とみなされ、病気はそれらに起因するとされています。
もう一つの興味深い点は、マイクロザイムと比較したウイルスの大きさです。ウイルスは生物学的に最も小さい粒子の一つと考えられており、コロイドサイズであることが多い:例.例えば、A型肝炎27ナノメートル(0.027ミクロン)、B型肝炎(0.042ミクロン)、ポリオウイルス(0.030ミクロン)、EBV(0.042ミクロン)、インフルエンザ(0.080~0.120ミクロン)、おたふくかぜ(0.150~0.300ミクロン)、天然痘(0.300×0.240ミクロン)、そしてベシャンによれば、マイクロザイム(0.0005ミクロン)である。これは、ガストン・ネサンがソマチッドの大きさについて、「数オングストロームから10分の1ミクロン」と言っていることと一致する[1]。
ベシャンはその著書『血液とその第三の解剖学的要素/ The Blood and Its Third Anatomical Element』の中で、次のように述べている。「微小血管はすべての組織の始まりであり、終わりでもある。細胞、組織、器官、生物の全体が生きている状態を構成する基本的な解剖学的要素である。... 健康な状態では、マイクロザイムは調和的に作用し、私たちの生命は、あらゆる意味で規則的な発酵である。病気の状態では、マイクロザイムは調和的に作用せず、発酵は妨げられ、マイクロザイムはその機能を変えているか、媒体の何らかの変更によって異常な状況に置かれている」[2]。ウイルスは、自己秩序化したマイクロザイムの重合体か、(可能性は低いが)マイクロザイムによって作られた構造体である。ウイルスは、同じくマイクロザイムからなるタンパク質に包まれており、自律的な分子ツールボックスと考えることができる。
グレン・デットマン/ Glen Dettman博士やアーチー・カロケリノス/ Archie Kalokerinos博士とともに、私は「ベシャンの文章は、RNAやDNAの発見をある面で先取りしていたのではないか」と考えています。遺伝子構造は、マイクロザイムの構造物、つまり道具なのではないか?彼らは、ソビエト連邦科学アカデミーのベイエフ/ Bayev教授の私信(1974年)を引用し、ビール酵母からの純粋な転移RNAのパーツからの分子の自己修復が可能であることを示す研究について述べている[3]。
私自身の研究では、ベイエフが述べたのと同様の分子修復を発見しました。私の実験では、癌の女性から採取した5年前の凝固した毛細血管の血液を使用しました。その血液に0.9%の塩化ナトリウムを1滴垂らすと、採血したばかりの時のような外観と活動レベルに回復したのです。つまり、乾燥した血液の解剖学的なマイクロザイムが活性化したのである。白い球体も活性化した。凝固時に作られたポリマーが逆転することの説明を求めたいところである。この逆転現象がどのようにして起こるのか、現時点では不明であるが、進化できるものは進化できる可能性があるということだけは言える。しかし、それは観察可能です。例えば、私は、棒状のマイクロフォームが10ミクロンの長さから0.1ミクロンの近さまで、目に見える分解を伴わずに逆戻りするのを見て、ビデオに記録したことがあります。
この研究は、「細胞は、従来の医学で言われているような最小の生物学的単位ではない」という非常に重要な仮説を裏付けるものです。ベシャンは、少なくとも1100万年前の白亜の堆積物の中に、今にも活動を始めそうなマイクロザイムを発見している[4]。
昴のサイクル
私は、生体内での発生サイクルを3つの大段階からなるものと考えている。(1)修復タンパク質複合体からなる原始的な段階、(2)リダ・マットマン(Lida Mattman)博士(『細胞壁の欠損した形態、ステルス病原体/ Cell Wall Deficient Forms, Stealth Pathogens』)が記述した細胞壁欠損型のような濾過可能な形態を含む中間的な、あるいは細菌的な段階、(3)酵母と真菌の段階、そして最終段階であるカビからなる集大成的な段階である。通常の発生過程では、マイクロザイムから修復タンパク質、そしてバクテリアなどへと変化していきます。しかし、例えば外傷などの特定の条件下では、マイクロザイムが原始的な段階を飛び越えて、そのまま細菌になる可能性が高い。これらの変化は、幼虫が蝶になるような驚異的なものですが、観察していて感心するのは、数分、時には数秒という速さで行われることです。同じように、条件によって誘発され、酵母、真菌、そしてカビへとサイクルが進むとき、それはあまりにも急速に起こるので、細菌の段階が起こったとしても、重要な意味を持つ時間はありません。
このように、症状を呈するマイクロフォームは、状況がそのような変化を必要とするときに、内在性のマイクロザイムの順列を介して、侵略されることなく高等生物内で発生することがある。その状況とは、ベシャンが "媒体の改変 "と呼んだ不均衡である。内在性の進化は、最初は正常に見える赤血球からバクテリア、酵母、真菌の形態が出てくるのを顕微鏡で見ると明らかである。
多型性サイクルの生物学的根拠
本文と第1節で述べたように、多型性サイクルとその組織の複雑化には共通の生物学的基盤がある: 生物の死後、その解剖学的および化学的構造を炭素サイクルに再利用するために、より複雑な形態が本質的に進化する。急速な進化の過程(可逆的)は、修理段階を超えて、死んだ生物を地球に戻すために必要な必須の生命過程である。第2段階と第3段階のミクロフォームは、腐敗(バクテリア)と発酵(酵母とカビ)を介して身体の重要な物質と組織を退化させる。発酵は、酸の老廃物を発生させ、組織をさらに分解する。病気の症状、特に変性タイプの症状は、ウイルスによるものではなく、化学的な分解、あるいは発酵や酸の毒素を介したリサイクルの試みとして現れますが、「宿主」の生存プロセスはまだ機能しています。もちろん、重金属の毒性や精神状態など、他の要因が症状の発生に重要な役割を果たすこともあります。また、体の生存プロセスの中には、一般的に病気と呼ばれる症状を引き起こすものもあります。例えば、酸の毒素が皮膚から緊急に排出されてできる湿疹などです。
前述の原因(警鐘)となる状況、つまり媒体の修正とは、酸性を呈する食品、不利な生活習慣、感情的ストレス、環境ストレスなどによる血液や組織の慢性的な酸性化(pHの不均衡)と酸素不足である。これは決して単純化しすぎではありません。酸性化/低酸素状態は、生化学的にはマイクロザイムに死んだ宿主を知らせる一方、細胞間液中のコロイドシステムの崩壊領域(デッドゾーン)を作り、一般に特定疾患と呼ばれる症状が発生する主要な生理的疾患状態である。
したがって、この病状とそれに伴う症状は、病的に進化したマイクロザイムと、一般に特定疾患と考えられている生理的徴候の両方を含むものとして区別される。微生物(細菌、酵母、真菌、カビ)は、その発生過程において、実際にはマイクロザイムの除去形態であり、細胞生活における病気によって組織を破壊する必要が生じたときに発生する。これらの上位発生型は、身体的な症状が出る前に血液中で容易に確認できるものである。リサイクルの作業が完了すると消滅(デボルブ)し、再び大地や空気のマイクロザイムになります。
ウイルスか毒素か?
ウイルスが分離された初期の頃、ろ過された液体中に分離された目に見えない実体には、酵母や真菌がDNAなどの細胞要素を発酵させた廃棄物(マイコトキシン)が伴っていたのではないかという疑問があります。ウイルスの病原性を証明するために、ウイルスの濾液を宿主に注入する場合、容易に濾過できる分子性毒素も混入することはほぼ確実である。スタンレー博士の「タバコ・モザイク・ウイルスの純粋な結晶」は、結晶化した毒素だったのだろうか?もしそうであれば、サイクルの中間段階の外毒素などと同様に、確かに高い症状を示すだろう。しかし、毒物を注射して病気を作ることができるというのは、その同語反復的な事実の証明以外の何ものでもありません。
私は暗視野顕微鏡や位相差顕微鏡を駆使した研究を行っていますが、血液中に結晶化が見られることがよくあります。体内のタンパク質、脂肪、糖分の病的な発酵による老廃物をキレートするために、カルシウムなどのミネラル塩や脂肪を使うのは普通のことである。このような結晶は、がん組織にも見られる。私の研究対象者の乳房から摘出した悪性腫瘍には、多数のカルシウムが付着していました。これは、私たちの体内の流れを汚し、細胞を毒し、血液や細胞間液のコロイド系を凝固させる物質を不活性化させようとするものである。
「ウイルス」という言葉はラテン語で「毒」を意味し、病気の症状の直接的な原因である毒物、すなわちマイコトキシン、エンドトキシン、エキソトキシン、環境由来の毒素(その多くは一次または二次マイコトキシン)について洞察することができる。正統派の医学では、感染症と呼ばれる症状を引き起こすのは、細菌そのものではなく、細菌の毒素であることをよく知っています。しかし、この微妙で重要な違いはほとんど強調されていない。常に、細菌が強調されています。また、多形サイクルの頂点に位置するマイクロフォームの毒素が同じ役割を果たしていることも、ほとんど認識されていない。毒素の作用やそれに対する身体の反応は、毒素を作らず、他の様々な手段で破壊をもたらすとされるウイルスに起因すると考えられがちである。しかし、もしウイルスが宿主の症状発生に関与しているとすれば、それはウイルスが刺激されて、より複雑な毒素を持つ形態に進化しているからである。また、ミネラルの欠乏による酵素の欠乏など、何らかの理由で構造や機能に誤りが生じた結果、障害を引き起こすという可能性もあります。
誤解が軽蔑を生む
しかし、化学的毒性に加えて、「ウイルス」という言葉がもたらす恐怖心(感情的毒性)はどのような影響を及ぼすのでしょうか。恐怖心は病状の中で最も致命的であると言われています。「病気」が1人を殺すなら、「恐怖」は20人を殺すかもしれない。ウイルスの危険性に対する一般的な偏見は、ルイ・パスツール/ Louis Pasteurの細菌説に基づく根本的な生物学的エラーであり、それ自体が自己暗示的な病気の加害者である。例えば、アフリカでは、エイズの病気の一部を医師が「ブードゥー・デス」症候群(心理的に引き起こされる病気)としている。ある看護師によれば、「症状としてはエイズ患者だった人たちがいました。彼らはエイズで死にかけていたが、検査を受けて陰性であることがわかると、急に立ち直り、今では完全に健康になっている」と述べている[5]。皮肉なことに、もし細菌説が事実に基づいているならば、ウイルスを恐れることは正しいでしょう。これらの病原体と呼ばれるものは、研究者、医療従事者、マスコミにとっては、刑事にとっての犯罪者のようなものであり、彼らの存在の焦点であり正当性の根拠である。
ブリタニカ百科事典には、細菌について次のような記述がある
多くの人がバクテリアに対して抱いているイメージは、人類を待ち伏せている隠れた不吉な存在というものである。この一般的なイメージは、約70年前にバクテリアと人間の病気との関係が発見されたことにより、初めてバクテリアに注目が集まり、その初期には細菌学が医学の一分野であったという事実から生まれたものである。なぜなら、今日知られているバクテリアの中で、人間の体内で生活できるように発達したものはごくわずかであり、この種のバクテリア1つに対して、まったく無害で、人間の敵とは考えられず、むしろ親友に数えられるべき数多くのバクテリアが存在するからである。
実際、バクテリアの活動に人間の存在が依存していると言っても過言ではない。実際、バクテリアなしには、世界の他の生物は存在し得ないのである。この記事の主な目的の1つは、この記述がいかに正しいかを示すことである。この記事の中では、人間や動物に病気をもたらす生物については、ほんの少ししか触れられていない-これらに関する情報は、病理学と免疫を参照のこと。
前述の記事の一般的なメッセージは、ウイルスの周りで多くの恐怖心が育まれてきたという意味で、ウイルスにはより適切に当てはまる。前述の筆者は、細菌について、人間や動物に存在する症候性細菌は病気を起こさない(二次的な症状が出るだけ)という例外を除いて、その前駆体は高等生物に内在するものであり、"人間の体内で生きられるように発達したものではない "と理解している。むしろその逆である。微生物学の一説によれば、マイクロフォームは長い年月をかけてコロニー化し、高等生物になったという。ある意味では、人体は微生物のための特別な環境として発展してきたとも言えます。
高等生物の細菌依存性の重要な側面として、人間の消化管内の花粉症患者が挙げられる。文字通り、これらの「外来種」が私たちを生かしてくれているのです。
ほとんどのバクテリアは、土壌、下水、人間の消化管、その他の自然界に存在するものにかかわらず、根本的な機能は同じで、高等生物の生命活動に不可欠な存在である。健康な細胞や組織を攻撃することはないし、できないが、ある種の細菌は、害虫が弱った植物に引き寄せられるのと同じように、病気や死んだ組織を再利用する。ベシャンが言ったように、"何も死の餌食にはならない、すべてのものは生の餌食である"。
病気の細菌説という生物学の基本的な誤りから生じた誤解に続いて、病気の組織の濾液を新たに発見された感染性のマイクロフォームと定義することは、バイオサイエンスの大きな副次的な誤りを生むことになった。
ウィルスの行動を再考する
正統派の医学や細菌説では、ウイルスが宿主の細胞を破壊するとされているが、以下のようになっている。Ⅲ.,Ⅺ.b).の太字で書かれているのは、マイクロザイムの原理に基づく別の解釈です:
Ⅰ.
ウイルスのタンパク質が宿主細胞の細胞膜に挿入され、その完全性を直接傷つけて細胞融合を促進する(HIV、麻疹、ヘルペスウイルス)。
タンパク質は、膜の損傷を修復しようとしたり、他の修復を行うために細胞内に入ったりする。細胞壁に付着したウイルスは、来るのか、去るのかという疑問があります。どちらの場合も、過剰な発酵や酸によって細胞が乱されているかどうかが問題になる。しかし、前者の場合は、付着する前に細胞が機能不全に陥っているため、修復複合体が必要となる。もう1つの可能性は、おそらく遠い話だが、細胞上の機能不全に陥った受容体が修復を必要としているか、機能不全に陥った細胞を不活性化するためにこれらの複合体で覆われているということだ。危うい地形にある正の電荷は、主に発酵による酸の分子に乗って、細胞膜を放電させ、細胞をくっつけるモルタルのような働きをする。
Ⅱ.
ウイルスは宿主細胞のDNA、RNA、タンパク質の合成を阻害する。例えば、ポリオウイルスは、キャップされた宿主細胞のmRNAが指示するタンパク質合成に不可欠なキャップ結合タンパク質を不活性化し、キャップされていないポリオウイルスのmRNAからのタンパク質合成を可能にする。
タンパク質の不活性化は、おそらく発酵や発酵による酸性の毒素によって行われており、「ポリオウイルス」はそのダメージを回復するために細胞内で生産される。
Ⅲ.
ウイルスは効率的に複製し、宿主の細胞を溶解する。例えば、黄熱病では肝細胞、ポリオウイルスでは神経細胞が溶解される。
可能性は低い。溶解は、酸によるマイコトキシコーシス、マイコトキシコーシスのストレスに反応して放出されるフリーラジカル(ROTS)、あるいは他の原因(電離放射線など)によって引き起こされる可能性が高い。修復粒子は細胞壁が破壊された後に残留する。
Ⅳ.
遅発性ウイルス感染症(例:麻疹ウイルスによる亜急性硬化性全脳炎)は、長い潜伏期間を経て重篤な進行性疾患に至る。
これはどのように証明されるのでしょうか?おそらく「潜伏期間」とは、修復に成功したり、修復を試みたりしても、結局はうまくいかない期間のことだと思います。症状は当然、体の弱い部分に現れる。過剰な酸は常に局所的な全身の問題であり、癌が症状の影響が後に広がるにもかかわらず局所的な全身状態であるのと同様である。
Ⅴ.
宿主細胞の表面にあるウイルス抗原タンパク質が免疫系によって認識され、宿主のリンパ球がウイルスに感染した細胞を攻撃する(例:B型肝炎に感染した肝細胞)。
肝細胞はカビ毒によって修復不可能なダメージを受けていますが、精巧な掃除屋である免疫系がゴミを掃除してくれています。おそらく、修復タンパク質抗原は、(細胞が修復不能であるため)免疫反応を知らせるために発現しているのではないかと思われます。これが、これらのタンパク質に対する抗体が存在する理由の一つの説明です。
Ⅵ.
ウイルスは宿主の抗菌防御に関わる細胞を傷つけ、二次感染を引き起こす。
免疫細胞の機能が、真菌の侵入や毒物の過剰摂取により損傷を受け、不調和な症状を引き起こす要素の適切な浄化と除去ができない。
Ⅶ.
例えば、ポリオウイルスが運動ニューロンを攻撃することで、筋肉細胞が変性してしまう。
もう一度言いますが、神経細胞にダメージを与えるのはウイルスのマイクロフォームではないという誤った解釈と理解の欠如です。バクテリア、酵母、カビなどの毒素や、ブドウ糖、タンパク質、ホルモン、脂肪などの発酵物が、病気の症状を引き起こしたり、体に影響を与えたりするのである。観察者は「ウイルス」が何であるかを認識していないので、それを病気としてしまうのである。
Ⅷ.
ウィルスに対する宿主細胞の反応には、代謝異常や腫瘍化をもたらす変化がある。
代謝異常は、修復タンパク質が出現する前に、細胞内の毒性過剰のために起こりました。むしろ、タンパク質が細胞の変形を防ごうとしている可能性の方が高く、癌の発生は、カビや菌が媒介する、主に酸化的な代謝から完全に発酵的な代謝への細胞の転換であると考えられます。
以下は、ウイルスの複製などに関するさらに正統的な見解で、斜体で別の解釈を示しています。
Ⅸ.
正統派の理論では、ウイルスは宿主細胞に侵入し、宿主の犠牲の上に複製を行う。複製は、ウイルスファミリーごとに異なる酵素を使って行われる。例えば、負鎖のRNAウイルスはRNAポリメラーゼを使って正鎖のmRNAを生成し、レトロウイルスは逆転写酵素を使ってRNAを鋳型にしてDNAを生成し、そのDNAを宿主のゲノムに組み込むことができる。
修復タンパク質は、その働きをするための酵素を生成するのが普通である
Ⅹ.
ウイルスのトロピズム(ある細胞には感染するが、他の細胞には感染しない傾向)の理由の一つとして、ウイルスが付着するための宿主細胞の受容体の有無が挙げられる。例えば、HIVはヘルパーTリンパ球の抗原提示に関わるタンパク質(CD4)に、エプスタインバーウイルスはマクロファージの補体受容体(CD2)に、狂犬病ウイルスは神経細胞のアセチルコリン受容体に、ライノウイルスは粘膜細胞の接着タンパク質(ICAM-1)に、それぞれ結合すると言われている。
理論的には、いったん付着すると、ビリオン全体、またはゲノムと必須ポリメラーゼを含む部分が、次の3つの方法のいずれかで細胞質内に侵入する。(1)ウイルス全体が細胞膜を越えて移動する、(2)受容体を介したウイルスのエンドサイトーシスとエンドソーム膜との融合、(3)ウイルスエンベロープと細胞膜との融合である。理論的には、細胞内でウイルスはコートを脱ぎ、ゲノムを構造成分から分離し、複製の前に感染力を失うと考えられている。核や細胞質では、新たに合成されたウイルスゲノムとカプシドタンパク質が子孫のウイルスに組み合わされ、細胞膜を通って芽生えてくる。また、カプセル化されていないウイルスは、膜を介して直接放出されることもある。
しかし、興味深いことに、ウイルスは何らかの方法で「感染」を中断、潜伏、持続のいずれかにすることができます。(1)複製サイクルが不完全なウイルス感染、(2)後根神経節内の帯状疱疹が突然活動を開始して帯状疱疹を引き起こすように、隠蔽状態で持続する、(3)細胞機能の変化を伴うか否かにかかわらず、継続的にウイルスを合成する(例:B型肝炎)。これらの3つの考え方、特に潜伏期間は、手に負えないウイルス説の弱々しい言い訳として生まれました。
Ⅺ.
ウイルスが繁殖するためには、以下の4つのステップを経る必要がある。
a).
細胞への吸着と侵入。ウィルス粒子は宿主細胞の膜に結合する。これは通常、カプシド上のウイルスコード化されたタンパク質や、ウイルスのエンベロープに埋め込まれた糖タンパク質が、宿主細胞膜の受容体に結合し、その後、内在化されるという特異的な相互作用である。この内在化は、エンドサイトーシスによって、あるいはビリオン(=ウイルス粒子)のエンベロープが宿主細胞の膜と融合することによって起こる。
b).
これは、ウイルス粒子が損傷したDNAまたはRNAの修復を行う目的で細胞内に入るメカニズムである。
c).
核酸がカプシドから核や細胞質に放出されるように、ウイルスのアンコート(=脱外被)を行う。修復作業にはアンコートが必要な場合がある。細胞質内のコートされていない「ウイルス」は、med scienceによるとB型肝炎の場合のように、核から来てまだコートを持っていない場合がある。そして、核酸を保護したり、伝達性や応答性のあるタンパク質複合体を作ったり、遠隔機能や免疫系による中和やリサイクルのために細胞外に出られるようにするために、コートが作られる。
d).
ウィルス製品の合成と組み立て、および宿主細胞自身のDNA、RNA、タンパク質合成の阻害を行う。憂慮すべき状況-発酵ストレスやマイコトキシックストレスに反応して生成されたタンパク質複合体は、自己秩序的な複製を行うことができる。ベシャンが示唆したように、マイクロザイムは各器官に固有のものであり、したがって、障害を受けている特定の器官を構成する特定の細胞には、特定の修復タンパク質が必要となる。なぜ大量に発生するのかという疑問があります。一つの可能性は、単に過剰反応です。
e).
そして最後に、出芽または溶解によって、宿主細胞からビリオン(=ウイルス粒子)が放出されます。
A. 複合体が細胞から離れ、遠隔地で機能したり、中和されたりする。
B. 修復がうまくいかず、酸の毒素や免疫系による細胞の破壊に先立って、あるいはその間に複合体が放出される。
さらなる考察
ウイルス学者は、ある種のマイクロフォームを「パッセンジャー(旅客)・ウイルス」と呼んでいるが、これは無症状の状態で存在し、宿主の遺伝子分子に乗客のように乗っているものである。新しい病気を探したり、原因不明の病気のウイルス的な原因を探したりする従来の考え方からすると、パッセンジャー・ウイルスは非常に興味深いものです。なぜなら、科学界におけるウイルス学者の地位は、彼らが研究するウイルスの病原性に依存しているからである。このコロイド状のパッセンジャーは、遺伝子修復に不可欠な動物や人間の核内タンパク質のサイレントマジョリティーである。
カロケリノス/ Kalokerinosとデットマン/ Dettmanは、ウイルスの変化しやすさについて、フレッド・クレナー/ Fred Klenner博士の言葉を引用しています。「私は、ウイルスユニットは、そのタンパク質コートを変更することによって、あるタイプから別のタイプへと変化する可能性を持っていると考えています。感謝祭には水ぼうそう、クリスマスにはおたふくかぜ、春には赤かぜ、夏にはポリオやコクサッキーが流行します」[6]。季節ごとに異なる病原体が現れるのは、祝祭日や季節に伴って糖分や動物性タンパク質などの過剰な食事が発酵することで、生物学的な地形や栄養媒体のバランスが崩れ、異なる修復タンパク質が必要になることが原因と考えられます。
例えば、ポリオの発生は、夏場の砂糖摂取と関連しています。また、様々な精神的ストレスもこれらの季節に対応しています。
このような食の責任に関する一般的な考え方を裏付けるものとして、英国の偉大な医師であるロバート・マカリソン卿/ Sir Robert McCarrisonが1936年に発表した声明があります。「目に見えない微生物、ウイルス、原生動物が病気の重要な原因であることにとらわれ、実験室での診断方法に従順で、命名法のシステムに縛られている私たちは、医師にとって最も基本的なルールである、適切な種類の食べ物(栄養)が健康を促進する最も重要な単一の要因であり、誤った種類の食べ物が病気を促進する最も重要な単一の要因であるということをしばしば忘れてしまう」[7]のです。
ベシャン/ Bechampが小球菌を発酵体と見なし、献身的な同僚であるエストール/ Estor教授とともにその性質について13年にわたる研究の旅を始める6年前、フローレンス・ナイチンゲール/ Florence Nightingaleは細菌説についての声明を発表した。ナイチンゲールは、1860年に出版された『看護学ノート』の中で、感染症について次のように述べている。
「病気は、猫や犬のようにクラス分けされた個体ではなく、互いに成長し合う状態である。
現在のように、病気を猫や犬のように存在しなければならない個別の存在として見るのではなく、汚れた状態ときれいな状態のように、同じように私たち自身のコントロール下にある状態として見るのではなく、むしろ、私たちが置かれた状態に対する親切な自然の反応として見るのは、常に間違いを犯していることになるのではないでしょうか?
私は...はっきりと、例えば天然痘は、かつて世界に最初の標本があり、最初の犬(あるいは最初のペアの犬)がいたのと同じように、永久的な子孫の連鎖の中で自己増殖していくものであり、親犬がいなければ新しい犬が始まらないのと同じように、天然痘が自ら始まることはないと信じて育った。
それ以来、私は自分の目で見て、自分の鼻で嗅いで、天然痘が最初の検体の中で成長していくのを見たのである。いや、それ以上に、私は病気が始まり、成長し、互いに移り変わるのを見てきた。... 例えば、ちょっとした過密状態で発熱が続き、もう少しすると腸チフスになり、もう少しすると発疹チフスになるのを、同じ病棟や小屋で見たことがある。
このような観点から病気を見れば、はるかに良く、真実で、より実用的ではないだろうか。なぜなら、すべての経験が示すように、病気は形容詞であり、名詞の実体ではないからである。
つまり、症状(病気と呼ばれる)は、状況を説明するものなのである。」
私は、空気中の細菌と呼ばれるものは、基本的にはリサイクルプロセスによって消費されている生物のマイクロザイムであるというベシャンの結論に正当性を見出している。つまり、ある種の植物性消化-腐敗または発酵である。要するに、既存の病菌種は存在しないのである。微生物医学の原則は、生物学的に根本的な誤りを犯しています。ベシャンが言ったように、「ミクロビアン(微生物)の教義は、この時代の最大の科学的な愚かさである」。これは、感染がないと言っているのではなく、侵入は症状発生に必要ではなく、病気の主要なメカニズムでもないということです。つまり、感染が起こるためには、受け手の中に、損なわれた地形という形で感受性があらかじめ存在していなければならず、受け手はいずれにしても病気になる可能性があるということである。粘膜バリアの免疫成分を除いて、一次宿主の「抵抗性」は、それ自体が免疫ではなく、地形の状態の機能である。
幻のウイルス 肝炎/ Hepatitis
肝炎はつらい症状ですが、近年はウイルス探しの対象としても注目されています。この病気にはいくつかの種類がありますが、「急性ウイルス性肝炎」と呼ばれるものは大きく分けて3種類あります。A型(旧・感染性肝炎)、B型(旧・血清肝炎)、C型(旧・非A・非B型)です。対応するウイルスは、HAV、HBV、そして現在Cと呼ばれている非A, 非Bの「グループ」です。A型はRNAウイルスが原因と言われ、主に水や食べ物の糞便汚染によって広がり、血液や分泌物も感染する可能性があります(ただし、不衛生な環境に伴う毒素が原因です)。60年代に発見されたB型肝炎は、肝細胞の核で複製し、細胞質で表面のコートを受けるDNAウイルスが原因と言われています。輸血された血液や血液製剤、あるいは静脈内麻薬使用者の注射針の使いまわしによって感染すると言われている(ただし、主に麻薬、特にヘロインによる過酸化が原因である。滅菌されていない注射針や乱暴な性行為などによる体液の血液への交換も、異質なタンパク質による繰り返しの免疫ストレスのために、時間の経過とともに役割を果たすことになります。出産前後に栄養状態が悪く、不衛生な環境に置かれた第三世界の赤ちゃんも影響を受けやすいと言われています。
70年代に発見された第3の肝炎は、薬物使用者やアルコール依存症患者に見られ、輸血による肝炎の8〜9割を占めている。このタイプはB型に似ているため、当初はB型肝炎と考えられていたが、被験者を徹底的に調べた結果、B型ウイルスもA型ウイルスも存在しないことが判明した。しかし、被験者を徹底的に検査したところ、B型ウイルスもA型ウイルスも見つからなかったため、「非A非B型肝炎」と呼ばれ、少なくとも2種類以上のウイルスが存在すると考えられていた。
1987年、科学者たちは、3つ目のタイプであるC型肝炎を引き起こす単一のウイルスを発見したと考えた。しかし、実際に発見されたのは、ウイルスと関連する抗体でした。これで、HIVと同じように、目に見えないウイルスに対する抗体を患者に調べることができるようになった。しかし、この新しい観察結果は、ウイルス仮説に新たなパラドックスを突きつけました。幻のC型ウイルスに陽性であっても、何の症状も出ない人が大勢いるのだ。肝炎はまさに、乳酸、酢酸、エタノールなどの物質によって、人体最大のフィルターが過酸化、毒素化された結果であり、病的なウイルスの病気ではないのである。興味深いことに、これらの肝炎ウイルスはいずれも潜伏期間が2〜25週間あり、ファーの法則(後述)に違反しているにもかかわらず、遅発性ウイルスに分類されていません。また、高度に人工的な注射による侵入ではなく、「自然な侵入」がどの時点で起こるのか、したがって、真の潜伏期間はどのように決定されるのか、という点も興味深い問題です。
ハンタウイルス/ Hantavirus
アメリカの生物医学界が不当にパニックに陥った最近の例として、1994年に発生したハンタウイルスが挙げられます。おそらくこのウイルスは、ネズミから人間(アメリカのナバホ・インディアン/ Navaho Indians)へと種を飛び越えたのでしょう。しかし、この幻のウイルスは、多くの人を殺した後、インディアンと和解し、マウスの貯蔵庫に戻ったようです。ウイルスは実体化しなかった[8]。サンフランシスコ・クロニクルの一面記事では、CDCが "全米の疫学者がシロアシネズミの個体数とその中のウイルスのレベルを注意深く監視している "と報じられている。しかし、CDCの疫学者たち(宇宙服を着ている姿)がかつての「ナバホ・インフルエンザ」を発見したのは、山の中の健康なマウスだけだった[9]。ナバホ・インフルエンザはネイティブ・アメリカンにとっては目新しいものではなく、衛生状態、栄養状態、ライフスタイルと結びついている可能性が高い。
エボラ出血熱/ Ebola
1995年5月、CDCは新たな脅威であるエボラウイルスを発表した。この致死性の殺人ウイルスは、アフリカの熱帯雨林に隠された貯蔵庫を出て、ヨーロッパやアメリカを襲うと予想された。タイム誌に掲載された記事には、宇宙服を着た男性が登場し、ウイルスのカラー電子顕微鏡写真が掲載された(電子顕微鏡ではカラー写真は撮れないのだが)。CDCのウイルス学者は、"人間にとって致命的で、かつ空気中で感染するウイルスを手に入れれば、ウイルスは熱帯雨林を離れることができる "と示唆した。このように、ウイルスが宿主から放出されて空中に舞い上がり、殺人的な風に乗って他の土地へと流れていくというイメージを、私たちは恐れなければならない。もっと想像力のあるシナリオを提案したのは、国連のエイズプログラムを率いるヨーロッパの疫学者である。クウェートからキンシャサに行った感染者が、ニューヨーク行きの飛行機に乗って発病し、現地で感染の危険にさらされることは理論的には可能である」と、CDCの警告と同じことを述べている。しかし、1カ月も経たないうちにアフリカではウイルスが消滅し、アメリカやヨーロッパではエボラ出血熱の患者は1人も報告されなかった[10]。
世界保健機関は当初、1995年12月19日に、西アフリカで245人の死者を出したエボラウイルスの流行が終わったことを発表していた。(この発表は2014年に再び行われた)残っている疑いのある症例の検査はすべて陰性だった。いささか不安な事実は、アフリカで発生したすべてのエボラ出血熱は「公立病院を介して広がったと関連している」というものだった[11]。結局のところ、これらの病院で再使用された皮下注射針に関連していたのです。ハンタウイルスのように、エボラ出血熱は消えてしまい、二度と聞かれることはありませんでした。最も興味深いのは、この伝染病が、ワクチンや他の薬剤を使わずに止まったことである。しかし、このような話が私たちの心に影響を与え、細菌に対する見方や理解を深めたことを考えてみてほしい。アンドロメダ菌というウイルスドラマの次の展開は?
一つだけ、陰湿な可能性について触れておく必要がある。過去に発生した謎の大流行は、数年後に人為的なものであることが判明している。政府機関が一般市民を使って、放出された生物や弱い生化学的毒素をテストし、医学的な報告書を通じて、生物兵器の活動に対する期待を検証したケースもある。このような事件や行動の全体像は、ロバート・ハリス/ Robert Harrisとジェレミー・パックスマン/ Jeremy Paxmanの著書『より高度な殺しの形/ A Higher Form of Killing』によく記されている。このシナリオでは、真実から目をそらすために、このような事件の原因は公式に構築されるか、または謎のままにされるだろう。
追記:上でご紹介の書籍『A Higher Form of Killing: The Secret History of Chemical and Biological Warfare』には第二次世界大戦時の大日本帝国軍が行ったとされる化学実験やもろもろの作戦についての記述があります。しかし、これらは戦勝国によって敗戦国を裁くという本来あってはならない違法な裁判を通して集められた情報に基づいて著されています。いわゆる「戦犯」裁判となりますが、戦犯裁判では戦勝国によるでっち上げや横暴が当たり前にまかり通っていたことが歴史的事実として記録されています。戦後に戦勝国のソビエトで行われた戦犯裁判であるハバロフスク戦犯裁判などが代表例となります。
本書籍の内容を読めば読むほど、分かってくることですが、大日本帝国軍が行ったとされる化学兵器戦の数々は国際コミンテルンが非常に好む残虐なやり口で行われており、かつ、日本人として考えられない行為に及んでいるということが分かってきます。
731部隊が行ったとされている数々の行為のうち、どれほどが戦勝国の共産国ソビエトや中国共産党によって歪められている情報であるか分かったものではありません。
本書籍の記載内容で大日本帝国軍に関しての記載は真に受けてはいけないように思えます。
参考文献
1. Gaston Naessens (1991) L'Orthobiologie Somatidienne.
2. Bechamp, Montague R Leverson (1912) Pierre Jacques Antoine. The Blood and Its Third Anatomical Element. John Ouseley Ltd., London, pp. 205-229.
3. Kalokerinos A, Dettman G (1977) Second Thoughts About Disease: A Controversy and Bechamp Revisited. Biological Research Institute, Warburton, Victoria, Australia, 4(1): p. 9.
4. Hume E Douglas (1923) Bechamp or Pasteur? The CW Daniel Co. Ltd., Ashingdon, Rochford, Essex, England, pp. 109.
5. Farber C (1993) Out of Africa, Part I. Spin Magazine, p. 61-63, 86-87.
6. Kalokerinos and Dettman, op. cit., p. 12.
7. 同上
8. Denetclaw TH, Denetclaw WFJ (1994) "アメリカ南西部の謎の病気 "はハンタウイルスが原因か?Lancet 343: 53-54.
9. Russel S (1995) On the Trail of Hantavirus. San Francisco Chronicle, USA.
10. Russel S (1995) Signs that Ebola virus Is Fading Away. San Francisco Chronicle, USA.
11. Kaiser R (1995) Africa State Hospitals Make Viruses, Not Patients, Feel at Home. Washington Post.
©2016 Young. これは、無制限の使用、配布、および非商業的に作品を構築することを許可する、の条件の下で配布されるオープンアクセスの記事です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
