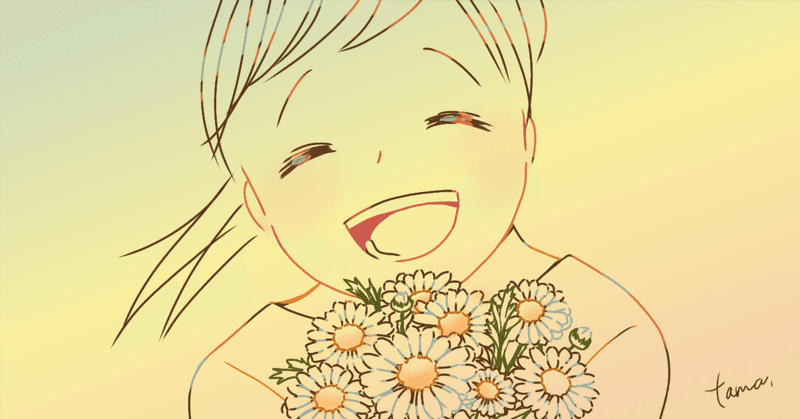
[短編小説] 放浪の精霊使い
会社で魔法ファンタジーと頼まれたので、義理と人情で執筆。すいません、書いたら推敲はおろか誤字脱字チェックさえやっていません。
-----
たまたま知り合いと出会うことは珍しい。約束も待ち合わせもなく、それが旅先での出来事となれば尚更だ。ましてそれが異国での遭遇ともなれば、まずありえないと言っても過言ではないだろう。
その上、その知り合いが、自分の友だちや両親を抹殺した魔法使いとなると、これはもう人違いに違いないということを願ってしまうのが、人間というものである。
「紹介しましょう。魔法使いのアイリーンです」
「……」
私はいろいろな思いが頭の中を駆け巡り、まったく口を動かすことができなかった。
棒立ちになって、倒れないでいるのが精一杯だ。
両親や友だちを亡き者にし、私の人生を根本から変えてしまった存在。
圧倒的な暴力の化身。
そんな恐ろしい存在が、無造作に私の目の前に立っている。
静かな表情をしており、その胸中を推し量ることはできない。
女性としては平均的な身長であって、スラリとした美しい顔立ちであるゆえの繊細さが逆に、いっそう恐く子供心に感じられてくる。
「アイリーン、こちらに立っている女の子はユリーアと言います。こちらへ来なさい、ユリーア。アイリーンに挨拶して頂けますでしょうか」
そんな私の様子を察したのか、ヘンタル様が助け舟を出してくださった。さすがは聖都の司教だけのことはある。
「……」
私はかろうじて立ちすくんだまま、黙って頭を下げた。
「さすがに十歳にもなっていない子供には、まだ急なお客様をお迎えすることは難しいかもしれませんね」
そんな私を見て、ヘンタル様は苦笑した。そして彼は、ドアの入口近くに立っていたアイリーンと呼ばれた女性の方へと向き直った。
「アイリーン、この子はユリーアと言います。パルメザン共和国の首都に住んでいた子です」
それを聞くと、彼女の肩がピクリと動いた。そしてこの家のドアを開いて入って来た時から表情に乏しかったけれども、完全に無表情となってしまった。
「パルメザン共和国……」
「ええ。あなたが魔力を暴走させて、都市を一つ壊滅させてしまった場所です」
ゆっくりと、ヘンタル様は頷いた。
ヘンタル様の言葉を聞いて、悪夢のような光景を思い出す。あらゆる場所が業火につつまれた街並みと、ピクリとも動かくなったお母さん……
その悪夢を実現してしまった存在が、目の前に立っている。
もちろん悪意はなかったと、ヘンタル様から聞かされている。彼女は勇者パーティーのメンバーで、勇者を愛していた。その彼が不意打ちを受け、絶命してしまった。その場面を目の当たりにした彼女は魔法を暴走させてしまい、炎の嵐が都市を襲った。
彼女はただの魔法使いではなく、精霊使いだったのだ。
*
それから数分後、私たちはテーブルに座っていた。
ここはヘンタル様の邸宅であり、お手伝いさんが紅茶を入れてくれた。
その香りのおかげで、少しだけ気分が落ち着いた。
「わざわざ呼び出してしまって申し訳ありません」
「気にする必要はないよ。それよりも、どうして急に私を呼び出したの?」
それを聞くと、彼は少しだけ困ったような表情になった。そして……
「実はあなたへお願いしたいことが生じました」
ヘンタル様は、向かいに座ったアイリーン様に向かって、ぐいと身を乗り出した。そんな彼を、彼女は冷静な視線で観察していた。
「少し落ち着こうよ、ヘンタル。そんなに変な顔をしていると、それこそ変た……いや、変なおじさんに見えてしまうよ」
いくら大変に偉い司教の邸宅とはいえ、書斎におかれたテーブルである。一般家庭の台所にあるテーブルサイズなので、両者を隔てる距離は殆どなかった。
「ははは、あいかわらず率直ですね」
ヘンタル様は楽しそうに笑った。そして乗り出していた身を、元に戻した。
それにしてもアイリーン様って、ヘンタル様に遠慮なく話せるのだなあ……
なぜか「ユリーアも同席してください」と言われて、ヘンタル様の隣に座っていた私は、あらためてアイリーン様の率直さに驚かされた。
おまけに向かいに座った彼女を改めて見ると、無表情というよりも仏頂面とも言えそうな雰囲気を醸し出している。
美人のお姉さんなのに、もったいないなあ、と私は思った。
ヘンタル様は紅茶を一口だけすすった。そしてアイリーン様に視線を戻した。
「実はお願いしたいのは、この子をあなたの弟子にして頂くことなのです」
「!」
思いがけない『お願い』に、私は驚いた。え、何?
「どうして私が、その子を弟子にする必要があるの?」
当たり前だろう。私だって尋ねたい。
ちらりと私の方に視線を移して、彼はやさしく私の頭をなでた。国によって風習に違いはあるけれども、教会では聖職者が他人の頭に手を置くことは、祝福を与えることを意味している。
素直に驚いた。
そんな私の感情に、一体どこまで気付いているのか分からないけれども、ヘンタル様は口を開いた。
「アイリーン、おそらくあなたには分かっているでしょう……。この子は精霊使いです」
「うん、わかっていたよ」
「さすがは精霊使いですね」
精霊使い?
「その女の子……、まだ十歳にもなっていないのかな。精霊使いのことを知らないみたいだね」
「ええ、その通りです。つい最近わかったばかりで、それで一時的に私がこの子の身柄を預かっています。いつまでも手元に置いておくことはできないので、それでまずはあなたに相談してみようと考えたのです」
さすがにヘンタル様は司教をなさっているだけあって、言葉によどみがない。そんな私たちを眺めるように見ながら、アイリーン様はつぶやくように言った。
「私の弟子になるかどうかは、彼女が決める話だと思うよ。まずは精霊使いのことを説明するのが良いかな」
「そうですか……。ではまず私が説明してみることにしますか。アイリーンは昔から、人に説明するのを面倒くさがりますからね」
「そこは『寡黙』と言ってほしいな。そもそも私は人に説明するのが苦手なんだよ」
「本当はあなたに語って頂けると嬉しいのですが……、仕方ないですね」
笑いながら首を振った後、ヘンタル様は説明を始めた。
「ユリーアは、この世界の魔法が空気のように存在している魔法分子によって構成されていることは知っていますね」
「そうなんですか」
「まだ小学校に入ったばかりの子供には難しかったかもしれませんね」
ヘンタル様は苦笑した。
「小麦粉の袋を開けると、小麦粉の粉が飛び散って、白い煙のようなものが立ち込めることがありますね」
「はい」
ヘンタル様は頷いた。
「あれは小麦粉の中でも本当に小さな粉たちが、軽くて小さいので、いったん吹き上げられるとゆっくりと落ちてくるから立ち込めてしまうのです。世の中にはそれよりも、さらに小さい粉……分子と呼ばれるものがあります。それが空気なのです」
「はい」
よく分からないけれども、私は頷いた。空気が粉?
「小さくなるほど、大きさに比べて動きが活発になります……。このあたりは『そういうものだ』と覚えておくだけで良いでしょう。さてその空気ですけれども、主に酸素という粉と、窒素という二種類の粉で成り立っています」
「酸素の粉と、窒素の粉……」
「正確には粉ではなくて、分子と呼ばれています」
「はぁ……」
良く分からないけれども、ともかく私は行儀を良くして聞いていた。
「火が燃えるのは、空気に酸素分子の集団が存在するからです」
黙って頷く。はあ、そうなんですか。
「そして空気とは別に、魔法の源となるものの存在も確認されています。これは酸素や窒素といった空気を構成する分子とは異なった存在であり、魔素と呼ばれています」
「……」
なんだか難しそうな話だ。
どうして私が、こんな話を聞かなければならないのだろうか。
それでもヘンタル様に嫌われたらば孤児院へ逆戻りすることになりかねない。あそこで再びいじめられることになるのはイヤなので、私は黙って話を聞き続けた。
「つまり魔法とは、火を操るようなものなのです。特別な道具などがあれば、自分の周囲に漂っている魔素を利用して、魔法を使うことができます。稀に魔素を道具を使わずに操れる存在もいて、吸血鬼や狼男が存在する訳です。本当にごく稀にしか存在しないので、伝説で語られているくらいですけれども」
「へえー、絵本で読んだ吸血鬼や狼男は魔法使いだったのですか」
ヘンタル様は頷いた。
「魔法使いの場合は、魔法の杖を用いて魔法を使います。私のように神に仕える者は、祈ることによって少しだけ周囲の魔素に影響を与えることができるようです」
「そうなんですか」
ちっともわからないけれども、とりあえず分かったようなフリをする。
「そして話は本題である、精霊使いになります」
話について行けていない私が、果たして『本題』とやらを、少しでもわかることがあるだろうか。
ともかく話を聞いていますということを示すため、とりあえず私はヘンタル様へ頷いた。
「精霊使いというのは、基本的には魔法使いだと説明して良いでしょう」
今度はアイリーン様が頷いた。
「ただし魔法使いと違うのは、魔素のように空気中に漂っている精霊に対して、魔法の実現を依頼することができるのです。これは精霊魔法とも呼ばれています」
「精霊魔法?」
聞いたことにない魔法に、思わず反応してしまう。
そんな私に対して、ヘンタル様が頷いた。
「私も感じとることはできませんけど、精霊というのはどこにでもいるという訳ではないようです。ただし先ほどの小麦粉の例え話のように、魔法を実行することが出来るだけあって、魔素よりも遥かに大きいのかもしれません。ともかく精霊の力を借りることにより、精霊使いは普通の魔法使いよりも強力な魔法を使うことができるのです。……簡単に喩えてしまうと、小麦粉の粉塵爆発のようなものでしょうか。空気中に漂っている魔素を一気に『燃やす』ことができるので。その効果は絶大で、室内で発生した場合には死者が生じるほどです」
さすがに粉塵爆発という言葉が理解できなかったので、聞き直してしまった。
「あの……、すいません。粉塵爆発とは何でしょうか」
ヘンタル様は、しばらく何かに戸惑っているように見えた。そしてやがて、重そうに口を開いた。
「そうですね、小麦粉だと少し分かりにくいかもしれません。昔は石炭を採掘する時に生じたことがあり、千名以上もの方々が亡くなったこともあります。燃えやすい粉が空気中を舞い上がっていて、それに火がつくと大変に激しい爆発となるのです」
「大変に激しい爆発……」
「私があなたの住んでいたパルメザン王国を爆発させたのも、精霊魔法を暴走させて、粉塵爆発のようなことを起こしてしまったからだよ」
「アイリーン、先回りは……」
ヘンタル様は、困ったような表情になった。私の初めて見る顔だ。
「いずれ彼女は知らなければならないことだよ」
えっ?
私は彼女の言ったことを理解できなかった。『知らなければいけない』って、どういうこと?
「その通りですけど……」
「そのために私を呼んだのでしょ?」
「そうですけど……」
「大丈夫。今この周囲の精霊たちは、私の味方になってくれているよ」
「精霊使いには、そんなことまで分かるのですか」
「なんとなくだけれどもね……」
「あなたがそう言うのであれば、間違いないのでしょうね」
ヘンタル様はため息をついた。これも私が初めて見る表情だ。
そしてアイリーン様は、ヘンタル様から私に視線を移した。
「ユリーア……、君にはちっともうれしくないことだと思うけれども、君は私と同じように精霊使いだ。君はたった一人でも都市を一撃で壊滅させることが可能な、『戦略級魔法使い』なんだよ」
「えっ?」
思いがけない知らせに、私はしばらくの間、何を言われたのか理解することができなかった。
*
「ヘンタル、面倒ごとを避けようとして、今まで黙っていたんだね?」
「いやあ、面目ないです」
聖都の司教に説教する若い女性というのも不思議な構図だ。しかし魔法使いは自らの体をコントロールする術に長けているので、一般人よりも歳を取りにくい。まだ二十歳後半くらいにしか見えないけれども、アイリーン様もヘンタル様と同じく、五十歳前後にはなっているだろう。
それはともかくとして、ヘンタル様のノリが妙に軽くなっている気がする。もしかしたら、彼女たちと勇者パーティーを組んでいた頃の気持ちに戻っているのかもしれない。
「それにアイリーン、万一ということがありますから。ここは聖都の中心からは離れていますけど、それでも何かあったら大惨事になりかねませんから」
それを聞くとアイリーン様は、あきらめたように溜息をついた。
「まあ、いまさら何を言っても仕方ないけどね……。ともかくヘンタルたちの鑑定結果の通りで、ユリーアが精霊使いであることは間違いないよ」
それを聞いて、思わず体がビクっとしてしまった。
「あの……、すいません。私が精霊使いだと、何か問題があるのでしょうか?」
おそるおそる、勇気を振り絞って尋ねてみた。
「あ、今のところは問題ないよ。それよりも、今までよく頑張ったね」
「よく頑張った?」
私の言葉を聞いて、アイリーン様は再び溜息をついた。
「今まで徹底して、彼女に精霊使いであることを隠していたのか」
「私が仕組んだ訳ではありませんけど、どうやらそうなっていたようです。
「ま、仕方ないか」
アイリーン様は、ヘンタル様の隣に座っている私の方へ、少しだけ身を乗り出してきた。しげしげと私のことを観察するような目で、じっと顔を見つめられる。
この涼し気な雰囲気の美人さんが、私の住んでいた街を破壊し、両親さえも……。
私の隠された感情の動きなど気付かないように、彼女は話しかけてきた。
「精霊使いはね、見つかったら殺されてしまうこともあるんだよ」
「えっ?」
「ユリーアは幸運だったね」
それを聞いたヘンタル様が、口を差し挟んできた。
「彼女の存在を知ってからは、できるだけ早く手を打ちました」
「さすがはヘンタルだ」
「あなたの存在も助けになりましたよ、アイリーン」
彼女は私から目をそらさず、ヘンタル様へ返事をした。
「そうかもしれないね……。魔法使いは精鋭部隊の兵士みたいに役立つけれども、頑張っても一軒家を焼けるかどうかといった程度だ。他人の精神を操作する力だって、大したことはない。国家を代表するような政治や軍人だったら、そう簡単には影響を及ぼせない。しかし精霊使いは次元が違う。その時に関わる精霊の数や魔素によりけりだけれども、連邦議会の議事堂にいる全員を精神コントールするだって可能だ」
分かっています。実際、あなたは私の人生を破滅へと追い込んだ……
「大き過ぎる力は災いの元。だから子供の頃に始末されてしまう精霊使いは多い。残念なことだけれども、国家レベルで見たら、私だって同意せざるを得ない」
私はヘンタル様に引き取れるまでのことを思い出していた。
同い年の子供たちには何も知らされていなかったらしい。
私は戦災孤児として引き取られて、永長失調ではなかったものの、やせ細った体つきだった。だから運動は得意ではなかった。もちろん勉強も遅れていた。
何より友だちまで失って心が傷ついており、誰とも話をする気になれなかった。そんな私と仲良くしようとする者など、誰もいなかった。
おまけに私は奇跡的に生き残った例外で、街中で他に生き残った者は誰もいなかった。だから苦しみを分かち合えるような者もいなかった。
「ユリーアには私はもちろん、精霊使いという存在自体を恨む資格がある」
「資格?……、ですか?」
いったい何のことだろうか。ともかく彼女は頷いた。
「もちろん暴走して街を破壊してしまった私のことを恨んでいるだろう」
「それは……、それは……」
言いよどむ私に対して、さらに彼女は話を続けた。
「それに私がキッカケとならなくてもいずれ判明したかもしれないけれども、ユリーアは精霊使いであることが判明してしまった。これからは精霊使いであるからという理由で、命を狙われることになる」
「そんなひどい……」
「ヘンタルと私が話し合っていたように、大き過ぎる力は邪魔だとか、恐怖の源だとして排除しようとする者も出て来る。実際、私は精霊使いだというだけで、何度も命を狙われたことがあるよ」
「……」
私は憎しみを超えて、呆然自失となってしまった。
そんな私に、彼女は容赦なく説明を続けた。
「それと……実は魔王も精霊使いだったんだ」
「魔王が精霊使い?」
隣に座っているヘンタル様が、私の方へ向き直る気配が感じられた。
「アイリーンの言う通りで、魔王は精霊使いでした。先ほどの説明にあったように、精霊使いは魔法使いとは比べものにならない魔法を使うことが可能です。それによって魔力で人々の心を操り、さらに魔法力を与えて魔物化していたのです」
アイリーン様は黙って頷いた。
「それからアイリーンにしても、別にあなたが住んでいた街を壊したくて壊したという訳ではありません。勇者が刺されてしまい、そのことに衝撃を受けて、精霊を暴走させてしまったのです……。つまり、そもそも魔王が存在していなければ、アイリーンが暴走するようなことも起こらなかったのです。魔王は精霊使いであることを除いても恐るべき存在でしたが、人類にとっての脅威となるほどの存在となった原因として、間違いなく精霊使いであることを上げることができるでしょう。そして私たちも、アイリーンの精霊使いとしての能力のおかげで、なんとか魔王を討ち取ることができたのです」
「……」
私は何も言うことができなかった。魔王討伐に隠された秘密……
目の前にいる女性が、恐ろしい化け物のようにも見えてきた。
そして彼女は、ヘンタル様の後を継いで、話を続けた。
「いずれにせよ私が自分の未熟さゆえに、精霊を暴走させて街一つ壊滅させてしまったことに変わりはないよ。先ほどヘンタルからは、ユリーアのご両親も巻き添えになって亡くなられたことは聞かされた。私としては誤って済む問題ではないけれども、ともかく街に住んでいた方々にお詫びするしか、自分にできることは無いんだ」
そういうと彼女は、まだ子供に過ぎない私に向かって、深々とお辞儀をした。そのおかげか、少しだけ恐さが和らいだような気がした。
「さてそして、ここで大きな問題が残っています」
ヘンタル様が、再びアイリーン様の説明を引き継いだ。
「大きな問題って、何でしょうか?」
どうしてなのか分からないけれども、私はヘンタル様に質問してしまった。
今にして思えば、子供ながらに薄々と察していたのかもしれない。
「ユリーア、これからあなたがどのように生きていくのかという問題が残っているのです」
「私のことですか?」
ヘンタル様は、黙って頷いた。
*
「実は、ユリーアは今のところ私の住まいに住んでいますが、これは一時的な措置なのです」
「措置?」
「子供には少し難しかったですかね。私は孤児院や国のお役人さんたちと相談して、しばらくの間だけ一緒に住むことを許されただけなのです」
「しばらくの間だけ……」
子供心に、足元が崩れ去っていくような感覚に襲われる。
イスに座っていたので、倒れずに済んでいる。しかし世界がグルグル回っているような感覚から、逃げることはできなかった。
今までどうして孤児院から脱出することができたのかを気にしなかったけれども、どうやらヘンタル様が頑張ってくださったということらしい。
一瞬だけ泣きたい気持ちになった。
しかしアイリーンが冷静なまなざしで自分を見つめているので、我に返った。
そうだ。今は泣いている場合ではない。
「ずっとヘンタル様と暮らすことはできないのですね」
静かにヘンタル様が、首を横に振った。
「ユリーアはしっかり屋さんなので正直に言ってしまうと、あと長くても半年くらいでしょうか」
「半年……」
「実は国だけではなく、教会の中でも『ユリーアには田舎に引っ越して貰うのが良い』という意見も出ているのです。今のところ、誰も引き取りを希望していませんけど」
アイリーン様は、静かな表情を崩すことなく反応した。
「無理もないよ。誰だって暴走するかもしれない精霊使い……、それもまだ情緒が安定ししていない子供を、進んで受け入れようとする人がいたら聖人だよ。ヘンタルがユリーアと一緒に田舎へ引っ越せば問題解決するかもしれないけど、そうすると今度は聖都の司教をどうするかという問題が生じてしまう」
ヘンタルは静かに頷いた。
「私も老い先の長い身ではありませんので、思い切って司教を引退して田舎へ引っ越すことも考えています。ただしそうすると、誰が私の後を引き継いで、ユリーアが一人前になるまで見守ってくれるかという問題が生じて来ます。それに私は僧侶です。宗教に関することを教えることは出来ますけど、彼女を精霊使いとして育て上げることはできません」
そう言うとヘンタル様は、アイリーン様の顔をチラリとのぞき込むように見た。
気のせいかもしれないけれども、今までポーカーフェイスを保っていたアイリーン様が、一瞬だけ表情を曇らせたような気がした。
「もしかして私にユリーアを引き取らせようと考えている?」
ヘンタル様は、晴れやかな笑顔になった。
「おや、すばらしい。あなたも他人の心が読めるようになりましたか」
「激しく誤解していると思うけれども……、私と一緒にいると、命を狙われる危険が高くなりそうだよ」
「精霊使いである限り、大なり小なり命の危険はつきものでしょう」
「私は弟子を取らない主義なんだ」
「では今から、その主義を見直してください。ユリーアには魔法使いの先生が必要です」
「私は田舎に住んでいたから魔法使いの先生に師事することができたけれども、ロクな先生じゃなかったから、我流に近いよ」
「この子が一人で独習するのに比べれば、遙かに良いでしょう」
「聖都でユリーアが精霊使いとして暴走したら、大惨事になるよ」
「その時はアイリーン、あなたが精霊を鎮めてくださるでしょう」
「私が聖都に長期滞在していることがバレたら、問題になるよ」
「そこはこの生臭坊主が、政治力で何とかしますよ」
「……」
ヘンタル様が、片っ端からアイリーン様の言うことを切り捨てているように見える。さすがは聖都の司教をなさっているだけあって、議論ではアイリーン様には勝ち目がなさそうに見える。
「どうやらヘンタルを説得することはむずかしそうだね」
「アイリーンがユリーアの師となってくれることが理想解ですから」
アイリーン様が、はじめてため息をついた。
「仕方がないな……、ただしヘンタルのいう通りに理想解だとしても一つだけ大きな問題が残っている」
「そうですね」
「仕方ないな……。すべてお見通しか」
そういうとアイリーン様は、私の方に視線を移した。
「私はユリーアのご両親を亡き者にした魔法使いにして精霊使いだけれども、私に師事するつもりはあるかな?」
「……」
残念なことに、私は即答することができなかった。
もちろん師事した方が私の人生にとってプラスになることは明らかだ。それに何より、私を孤児院から連れ出して、無理してまで引き取ってくださったヘンタル様が希望なさっている。
しかし……、たしかに燃えさかっている街を思い出すと、身がすくんでくる。たとえ精霊を暴走させたとはいえ、その後で平然としているような人物だ。今はヘンタル様がいるから大丈夫だけれども、果たして二人きりになっても大丈夫だろうか。
「ヘンタル、残念だけれども私がユリーアを教えるのは難しいと思うよ」
「そうですか……」
しばらくの間、ヘンタル様は何かを思案なさっているようだった。そして三分くらいが経過した後、ようやく口を開いた。
「私も老い先が短くなったせいか、少し性急すぎたようです。せっかく来て頂いたのだから、アイリーンには今日は泊まって頂いて、明日にでもユリーアに結論を出して貰うことにしましょう」
とりあえず即答せずに済んだことに、私はほっとした。
そして晩ご飯のお手伝いに、邸宅の調理室へと向かったのだった。
*
アイリーンという来客のために、夕飯はごちそうだった。普段は貧相とは言わないまでも、さすがに司教という立場だと、つつましやかな食事になることが多い。
ヘンタル様は一人で饒舌だった。
日頃から信者に講話をすることが多いし、会食も多い。話題が豊富だった。
ただしアイリーン様にしても表情に出ないだけで、食事を楽しんでいるようだった。服装で分からないけれども、長旅に耐えられるように日頃から鍛えているらしい。食欲も旺盛だった。
そして私はと言えば……、せっかく同席を許されたものの、食事を食べるだけで精一杯だった。なにしろ自分がかつて経験したことがあるように、都市を丸ごと破壊しかねない精霊使いだと知ってしまったのだから。
だからヘンタル様が何を語られたのかは、全くといって構わないほど覚えていない。
「ヘンタルは酒を飲むのを止めたの?」
「健康第一に生きることにしたので」
「へえー、あんなに大酒飲みだったのに。聖都の司教らしくなって来たね」
そういう会話を覚えている程度だ。
それに食事の後でヘンタル様と会話をして、そちらの方が重要だった。
片付けを手伝った後で夜空を見て落ち着こうとバルコニーへと出た私に、ヘンタル様が語りかけて来たのだ。
「今まで隠していて申し訳ありませんでした」
ヘンタル様の最初の一言は、謝罪だった。
驚いたのは、私の方だ。
「いえ、私こそ申し訳ありませんでした。今までヘンタル様のご厚情に甘えて、何も考えていませんでした」
「ユリーアはしっかり者ですね。まだ小学校の低学年生だというのに、そのような気配りまでするようになりましたか。大したものです」
ヘンタル様に自分の成長を驚いて頂くのは、うれしいことだった。魔法使いとしての素質を測定する際に知能テストも受けたけれども、このまま育てば国立第一大学へも入学できそうな知能指数だったらしい。
魔法使いとしては大した測定結果ではなかったので、私はヘンタル様のように聖職者になる道を考え始めていた。
その矢先に、今日の出来事である。
いくらしっかり者であっても、あまりのことに受け止めきれない。
いくら私の思考力が高くても、社会経験は圧倒的に不足している。今にして思えば、どうして後継者の素質があるかもしれないけれども、孤児院では問題児と化してしまっていたけれども、わざわざヘンタル様のような方が一緒に住まわせて下さるのか不思議だと気づくべきだった。
たとえヘンタル様のお役に立てる資質を持っていても、私が本当に精霊使いなのだとしたら、都会暮らしは避けないと人々の迷惑になる……。たとえ本当に迷惑をかけることがなくても、恐怖心を煽るには十分な存在だという事実が、今の自分には大変重いことだった。
自分も両親を殺した原因となった、暴走した時に大惨事を巻き起こす精霊使い……か。である
たしかに冷静に考えれば、アイリーン様の弟子となって、少しでも人々に迷惑をかけない存在になることが理想的な人生だ。誰かの役に立とうと頑張るよりも、死にたくなければ、人々の迷惑にならないように努力する必要がある。
そういえば孤児院で読んだマンガというものには、自らの能力が暴走した超能力者が辺境の惑星に一人だけで暮らしているという設定があった。まさか自分も、似たようなことで悩むとは思わなかった。
どうやら私が今までホタルのように綺麗だと感じていた存在が、どうやら精霊だったらしい。どうやらたしかに、私は精霊使いなのかもしれない。
そう考えてみると、思い当たる節もある。
そもそも魔法の基礎も習っていないし、子供に過ぎないのに、希に自分でもあっけに取られることが出来ることもあった。たとえば自動車に轢かれそうになった子供を見て、自動車を中に浮かせてしまったり……。
精霊使いは本当に希な存在である上に、都市を壊滅させるような絶大な力を発揮できるので伝説的な存在らしい。喜ぶ人も多いかもしれないけれども、私はそのような素質を持って生まれてしまった自分がイヤになってきた。
「今まで気付いていた能力だけで十分だったのですけども……」
思わずため息をついてしまう。
「人生とは、なかなか思い通りに行かないものですね」
ヘンタル様は苦笑した。もしかしたらヘンタル様のような立場の御方でさえ、いろいろと苦労なさったのかもしれない。
それはさておき、こんな自信過剰な私だから、孤児院でも大人たちに好かれなかったのだろう。小学校に入学する頃には、既に口げんかで私に勝てる大人は存在しなかった。
そんな私にイヤな顔ひとつせず、子供ではなくて一人の人間として接して下さる人がヘンタル様なのである。
もしかしてヘンタル様って、かなりの変わり者?
そもそも魔王を倒すためとはいえ、勇者パーティーに加わっている。
アイリーン様とも平気でやりとりしている。
悪い人ではないとは、頭では分かっている。ただし表情が読みにくい。
私の街を破壊した時、一体どんな表情をしていたのだろうか。
「頭ではヘンタル様のご配慮に感謝して、アイリーン様に師事するのが理想的だということは分かっています。しかし今一つ気持ちが……」
「おや、流れ星です」
そんな私に対して、彼はバルコニーの壁に両肘をついて、右手の人差し指で正面の方を示した。たしかに星空の右上から左下に向けて、斜めにゆっくりと流れ星が落ちていく……
「……」
「ユリーアは今の流れ星に、何か願い事をしましたか?」
「えっ?」
私は驚いた。神に仕える聖職者なのに、流れ星に願い事をしても良いのだろうか?
「どうしました?」
「いえ……、司教の職にあるヘンタル様が、流れ星に願い事などしても構わないのでしょうか?」
「ははは、ユリーアは聡明ですね。……たしかに人々の前で公式に『流れ星に願い事をしましょう』と言ったら、それは問題となるかもしれませんね……。しかしたとえそうであったとしても、子供を持つ親御さんたちは、願い事をするかもしれません」
「何をお願いするのでしょうか?」
「子供の幸福ですよ」
「あっ……」
たしかに私の両親が生きていたら、間違いなく私の幸福を願ってくれたことだろう。そのことを思い出すと、ずきりと胸が痛んだ。
「私もあなたの幸福を願いましたよ」
「!」
ヘンタル様が私のことを心配してくださる……
「不思議に思いますか?」
「はい」
実のところ、どうしてヘンタル様に引き取られているのか、私には理解できなかった。もちろんヘンタル様は立派な方で、大変に尊敬している。子供が大好きで、お茶目な部分もある。
しかし同時にヘンタル様は聖都の司教であり、大変にお忙しい方なのだ。わざわざ自ら私を引き取らなくても、他の聖職者に私を引き取って貰うとか、親戚の誰かに私を引き取って貰うという方法もあるだろう。
「やはりユリーアには感心させられますね」
「どうして……、どうしてヘンタル様は、私のような者を引き取って下さったのでしょうか。たとえば最初から辺境の田舎の司祭に引き取らせれば、何の問題もなかったハズです」
相手の立場に立ってものごとを考えてみる……、私が両親を失って孤児院に引き取られてから、身に付けた習慣だ。これは魔法とも精霊とも関係ないけれども、大人には超能力のような特別な異能だと感じられたらしい。
しかしヘンタル様は、今までの大人とは全く違っていた。
「そうですね……。人数は少なくとも悲劇は悲劇ですが、たしかに精霊使いが聖都に存在するというのは、望ましい状況ではないです。ただし……」
「ただし?」
そこでヘンタル様は、にっこりと微笑んだ。
「あなたと一緒に暮らすことは、私にとって大変に貴重で楽しいことです」
「貴重?」
「ええ……。実は私は若い頃の無理によって、余命わずかと医師から宣告されました」
「ヘンタル様は、年齢の割にはお若く、お元気そうに見えますけど?」
「肺に異常な細胞が見つかったとのことです。それも小細胞と呼ばれるものが」
「医師や魔法使いにも治せないのですか?」
「無理だそうです。あと長くて一年くらいとのことです」
「!」
だったら自分の病気のことを願い事にすれば良いのに……、と、私は呆然となった。
「それにね、義理と人情というものがあります」
「義理と人情?」
ヘンタル様は小学校の低学年に過ぎない私にも、大人に接するように説明して下さる。しかしさすがに『義理と人情』というのは、子供の私の手には余った。
「ええ、まず義理ついて説明しましょう。……私は仮にも勇者パーティーの一員でした。そしてアイリーンも一員でした。彼女が暴走してあなたの街を破壊した時、私たちもその場に居合わせました」
「!」
たしかに言われてみれば、ヘンタル様も存在していて当然だった。
「……しかし彼女の暴走を止められなかった。あの時の私の力では、自分を守るだけで精一杯でした。しかし今にして思えば、力に頼らずとも彼女の暴走を抑える方法もあったのではないかと思うのですよ。今さら反省しても、あの時に生じた結果を変えることはできませんけれども」
「……」
私には急に生じた爆発のような大災害としか記憶に残っていなかったけれども、ヘンタル様の目には別なように映っていたらしい。同じ物事でも見る人によって見え方が全くことなることもあると本で読んで知ってはいたけれども、まさかその事例に出くわすとは思っていなかった。
ヘンタル様は、子供にも分かるように説明しようと頑張って下さっている。私は次の言葉を辛抱強く待った。
待っている間に、木の葉が一枚だけ飛んで、地面まで到着してしまった。
「そして……、そして人情に関していうと、アイリーンはああ見えて、深く傷ついています」
「そうなんですか?」
「そうなんです」
どうしてなのか分からないけれども、ヘンタル様は笑顔になった。
「ユリーアに説明した通り、いくら修行を積んで腕を磨いた精霊使いでも、自分の感情が乱れると精霊を暴走させてしまうことがあります。そのような時には、どうやって精霊の暴走を止めるのが良いと思いますか?」
「術者が亡くなっても、精霊の暴走は止まらない気がします……」
その通りだというように、ヘンタル様は頷いた。
「そうすると精霊が集めた魔素を放出し終わらないと、暴走が終わることは無さそうですね……」
「そうです。残念ながら私たちには、どうしようもありませんでした。少しでも早く、アイリーンを落ち着かせることしか出来なかったのです」
ヘンタル様も街の惨状を思い出したのか、悲しそうな表情になった。
「あの時はどうしようもありませんでした。しかし希望は残りました」
「希望?」
私はなぜか、イヤな予感がした。
「精霊の暴走を鎮める方法、わかりましたか?」
その言葉を聞いた瞬間、いきなりパズルの全てのピースが一枚の絵を描いた……、少なくともそのように、私には感じられた。
「わかった……、と思います。つまり私は、偶然生き残ったのではなかったのですね」
「どうやら、そういうことのようです」
再び星空を見上げながら、ヘンタル様は返事をした。
私も一緒に並んで、星空を見上げた。
「私は未熟だったけれども、精霊使いだったから周囲の精霊の暴走を鎮めることができた。つまり私が一人前の精霊使いだったら、アイリーン様が暴走させてしまった精霊たちを鎮めることができた。だから精霊使いは一人ではなくて、二人存在していた方が望ましい。だからヘンタル様は、私がアイリーン様の弟子になることを希望なさっている」
ヘンタル様は、再び笑顔に戻った。
「そういうことです。あと半年のうちにあなたが一人前の精霊使いに育ってくれれば、あなたにとってもアイリーンは暴走時の安全装置をなってくれる。だからあなたにとっても、精霊使いのアイリーンは重要な存在なのです」
それを聞いて、ようやく私はヘンタル様の意図を理解することができた。
「でも精霊使いが二人揃って暴走したら、災害規模が二倍になることはありませんか?」
「それは大丈夫」
返事をしたのは、ヘンタル様ではなかった。
いつの間にか、アイリーン様もバルコニーへ出て、こちらへ歩いてくるところだった。
「私たちは暴走する時、周囲に存在する全ての精霊に影響を与えて巻き込んでしまう。しかしその影響範囲は限定されているから、二人揃って暴走してしまっても、一人の精霊使いが暴走した時と災害の内容は変わらないんだ」
「それでは私は、アイリーン様の弟子になるしか、人生の選択肢は無さそうですね」
「そういうことなんだ。ちなみにヘンタルが君と一緒に暮らすことができるのも、すぐに私がやって来るということで教会から了解を取り付けたんだと思うよ。違うかい、ヘンタル?」
ヘンタル様は苦笑しながら返事をした。
「その通りです、アイリーン。ユリーアは納得したので、アイリーンにも部屋を用意しますので、あと半年ほどで一人前の精霊使いに育て上げることは可能そうでしょうか」
やれやれ……、といった風情で、アイリーン様はかぶりを振った。
「可能か、不可能か……じゃなくて、『どこまで行けるか』だね。明日からさっそく修行を始めることにするよ。ところで……」
「ところで?」
オウム返しにヘンタル様が尋ねた。
「私は今やって来たばかりで良く分からないのだけれども、どうして聖徒に留まるの? 私がここに長期滞在すると騒ぎになるんじゃないのかな?」
彼は驚いたような表情になった。
アイリーン様と違って、ヘンタル様は本当に表情豊かな御方だ。
「素晴らしい! あなたも『気配り』というものを覚えたようですね。そうですね……、どうして聖徒で修行するかというと、あなたにしごかれて泣きべそをかいているユリーアを見れそうなのが楽しみだからです。本気で指導するあなたは、本当にスパルタ式ですからねえ……、アイリーン」
「ヘンタルこそ本当に変……、ロリ……、変わり者の坊主だなあ」
「ともかく、よろしくお願いします。アイリーン」
「よろしくお願い致します。アイリーン様」
「では明日の朝ご飯が終わったら、さっそくこの場所に来てもらえるかな、ユリーア」
「はい!」
そうして私は、精霊使いの弟子になったのである。
*
そしてヘンタル様が無事に倒れることなく半年くらいが経過した。たしかにアイリーン様の修行は大変だった。別に指導された通りにできないと体罰があるとか、魔法で攻撃されるといったようなことは全くない。
大変に整然としてわかりやすかったけれども、それを実践するのが大変だったのだ。たとえば予め紙片に一連の呪文を書き込み、からくり人形(なんでも大人は自動人形というらしい)として動かすようなことを教わった。
おわかりになって頂けるだろうか。
私は大人の真似をして、大人のように考えたり話したりすることは得意だった。しかし残念ながら、読みやすい文字を書くことは年齢相応だった。これは私だけではなく、孤児院では同じような仲間がいた。
体を動かすこと……、特に指先を思い通りに動かすというのは、子供には大変に難しいことなのだ。それを私は、半年で特訓しなければならなかった。
私のことを心配してくださるヘンタル様がいなければ、すぐに心が折れてしまっただろうと思う。聖徒は豊かな都なので、同世代の子供たちは楽しく遊ぶ光景をみかけたことがある。しかし私は文字通り命がけで修行に励む必要があった。
実際、「かわいそうだけれども、精霊使いの子供は見つけたらば即座に追放」という国もあるくらいだ。
しかし本気というのは恐いもので、半年くらいで形になって来た。
「ユリーア、最近はアイリーンに雰囲気が似て来ましたね」
と、ヘンタル様に驚かれることもあった。
精霊使いであるからには、どんな時でも感情をコントロールできる必要がある。気がつくと最初から暴走するまでの距離を大きくしようと、私はできるだけ感情を動かさないように振る舞う習慣が身についていた。
別にアイリーン様に憧れている訳ではなかったけれども、『小型アイリーン』となることは避けられなかった。
そしていつものように修行を続けていたある日、事件は起こった。
*
砂塵と一緒に、西の大陸からイナゴの大群が聖都へ迫ってきた。
そして東の大陸は、数十年に一度というレベルの干ばつに襲われた。我が中央大陸は穀物の備蓄もできている程に豊かだったけれども、さすがに両大国へ支援をするとギリギリの状況となってしまう。
つまりイナゴが聖都へ到来してしまうと、大量の餓死者が生じてしまうことを意味していた。なぜなら中央大陸の穀物生産は、聖都に頼っているのだ。聖都は気候もさることながら、ピリル山脈水源とするベリーサ川を利用できる上に、土地も肥沃だった。もちろん信仰深く働き者の農夫たちや技師も多く、豊富な労働力がある上に機械化も進んでいた。
裏を返せば、イナゴにとっては天国のように魅力的な土地なのだ。豊かに育った栄養価の高い食物が豊富に存在する。油断すれば、あっという間に大増殖してしまう。
それを未然に防いでいたのが穀物生産と同じく、労働力と機械化だ。
農薬という便利なものも存在はしていたけれども、首都を聖都呼ぶだけであって宗教国家だったのだ。無益な殺生は教義によって禁じられていた。許されていたのは、自分たちが食事するのに必要となる生き物を殺めることだったのだ。
農薬を使わずイナゴの大群の侵攻を防ぐには、労働力と機械化以外の手段も必要とされた。
多くの者が絶望に捕らわれた時、ヘンタル様は落ち着いて方策を説いた。
「皆さん、慌てることはありません。私たちには精霊使いがついています。国全体とは行きませんが、聖都の周囲には十分な防壁を魔法で張ることができます。何の不自由もない程という訳にはいきませんが、少なくとも空腹に悩まずには済むでしょう」
彼の後でミニッツ行政官が、具体的な予想内容や対応計画を説明した。少しお腹まわりが貫録のある、やさしそうな笑顔を絶やさないおじさんだった。アイリーン様と私は、彼の指揮下で働くことになった。
そこまでは事件は事件であるけれども、私にとっては奉仕活動のようなつもりだった。しかし本当の事件は、いよいよ精霊使いの出番だという時に起こった。
「さてミニッツ行政官からの指示が出たので、いよいよ魔法で防壁を張るよ。頼んだよ、ユリーア」
アイリーン様は私の方に振り返って、そう言ったのだ。
えっ?
「あの、アイリーン様。よく理解しきれなかったのですが、私が最初に防壁を張るのでしょうか?」
彼女は表情を変えず、私の質問に淡々と返事をした。
「いや、『最初』にではなくて、ユリーアが一人で防壁を張るんだ。この半年で、聖都の周囲の精霊たちにお願いごとができるようになったでしょ」
「はい、練習ではできるようになりましけど……。多くの人々の命がかかった仕事です。最初からアイリーン様がなさった方が確実で宜しいのでは?」
精霊たちの力も無限ではない。それにアイリーン様にしても、どのくらいの速さで防壁を展開できるか分からない。
不安のあまり、思わず尻込みしてしまう。
「大丈夫、ユリーアだったら出来るよ。それに今は説明できないけど、理由もある。長話をしている余裕もなさそうだから、お願いできるかな」
「でも……」
「私からもお願いして構いませんか。ユリーア」
「!」
驚いて後ろを振り返ると、ヘンタル様が立っていた。公務で忙しいはずなので、普段はあり得ないことだ。今は普段ではないけれども、それでも予想外だった。
「ユリーア、驚いて感情を乱してはいけないよ」
相変わらず抑揚のない声で、アイリーン様の注意指導が入る。
「ははは、相変わらず厳しい指導ですね……。それはともかく、ぜひユリーアにお願いしたいのです。理由はアイリーンと一緒に、後で説明しましょう」
「……わかりました」
心の中では全く納得できていない。
けれども最初から、アイリーン様の指示に逆らうことはできない相談だった。それに何より、ヘンタル様からの強いお願いだ。
「私の心の声が届くところにいる全ての精霊に対して、お願いをするものです。どうぞイナゴの大群を通さぬよう、できるだけ広い範囲で防壁を構築して頂けますでしょうか……」」
それと同時に、あらかじめ用意しておいた御札を空へと投げる。知らない者が見れば不思議なことに、御札は意思を持っているかのように、静かに各々の方向へ飛び去って行く。
そうしてそれから日が暮れるまで、私は防壁を張り続けたのだった。そして防壁にぶつかって地面へ落ちるイナゴたちを、ミニッツ行政官の手配した人々が一匹残らず回収したのだった。
*
「よくやったね、ユリーア。これだけのイナゴが取れれば、各戸に佃煮のビンを配れるかもしれない」
心なしか上機嫌のように見えなくもないアイリーン様が、冗談とも本気ともつかないことを口にした。私としては、そうですね――と返事をするしかなかった。
「本当によくやりましたよ、見事でした」
ヘンタル様が、私の頭をなでてくださった。西の大陸ではそういう習慣はないとのことだったが、ここでは子供への親愛の情を示すことを意味している。
「ありがとうございます」
私はヘンタル様の願いを叶えることができて嬉しかった。
思わず半年前のように星空を見ながら、帰宅してから食べる夕飯のことを想像してしまう。
と、その時だ。
「さてそろそろ限界のようです。術を解いて頂いて構いません」
ハイター様がアイリーン様に向き直って言った。左手で心臓のあたりを押さえている。
「私はまだ余裕あるけど……、せめてユリーアに説明したらどうかな」
「そうですね、数分ならば余裕がありそうです」
ヘンタル様は、地面に横になった。
いつの間にかミニッツ行政官が手配して下さったのか、地面には薄い布団のようなものが敷かれていた。
「すいません、家まで保たなくて」
「えっ?」
「そろそろ体が限界のようです」
思いがけないヘンタル様の言葉に、私は呆然となった。
覚悟はしていたけれども、あまりに突然過ぎた。
「どうして急に……」
「実はすでに限界が来ていたのです。動けていたのは、アイリーンが魔法で私の動きを支えてくれていたからなのです」
「そんな……」
「今まで楽しかったですよ。ありがとうございました。ユリーア」
「ヘンタル様、急すぎます!」
「感情を乱すのは、精霊使いとして望ましいことではありませんよ」
その通りだねという声が後ろでしたような気もするけど、頭には何も入って来なかった。ヘンタル様が苦しそうな表情になって来たからだ。
「どうしてそんなに無理をなさったのですか!」
「あなたが心配だったからですよ。ともかく一人前の精霊使いになれたようで良かったです。もうあなたは、自分の力で生きていけるでしょう」
気がつくと、私は涙を流していた。
「……」
「……あなたのおかげで、心残りなく神様のところへ行けます。ありがとうございました」
「……」
何も言えない私の頭に、ヘンタル様は再び手を置いた。今度は右手だ。
「あとはアイリーンが、必要に応じて面倒をみてくれます。私も少しは役に立てたようで良かった。聖都で修行して貰った甲斐があったというものです」
「私のことを心配して、修行場所を聖都になさったのですね」
「ははは、ばれてしまっては仕方ありませんね」
「ヘンタル様は無理をし過ぎです。それに私に甘すぎます」
「我が子のように愛している子に対して甘くなるのは、親バカだから仕方ないですね」
とうとう感情を抑えきれなくなってしまった。涙がこぼれて止まらない。
私が聖都で修行をする了解を各所から得るため、ヘンタル様はどれだけ苦労なさったのだろうか。そのために寿命を削ってしまったのかもしれない。
「繰り返しますけど、無理をし過ぎです!」
「そうですか……。それで私の分も、元気に楽しく生きてください。」
「……」
ヘンタル様は、静かに目を閉じた。
「アイリーン、ありがとうございました。彼女に言いたいことは言えました。もう術を解いて頂いて大丈夫です」
「……わかった」
そう言うと、アイリーンは静かに歩みよってきた。
「それじゃユリーア、私は動きを支える術を解いて、痛みを感じなくする術をかける。ユリーアは深く眠りに落ちる術をかけて」
「……はい」
ヘンタル様の方を見続けたまま、私は返事をした。そしてそのまま、眠りを誘う術を発動した。精霊たちのおかげで、本当に深い眠りへといざなったことが感じられた。
アイリーン様も精霊たちと一緒になって、ヘンタル様に痛み止めの術をかけることが感じられた。それは痛みを止めると同時に麻痺も誘うようで、程なく左手で胸を押さえていたヘンタル様は静かになった。
そして呼吸は次第にゆっくりと深くなり、やがて止まった。
彼は私に言ったように、神様のところへ向かったのだった。
*
その晩の私たちは、ヘンタル様の邸宅へと帰宅して夕飯を頂いた。こんな時でも食べることのできる自分が不思議だった。アイリーン様からヘンタル様のことを知らされた執事さんは、心なしか元気がなさそうに見えた。
ミニッツ行政官が手配して下さったスタッフの方々が、ヘンタル様の亡骸を運んでくださった。執事さんやスタッフに任せて、私たちは寝させて頂いた。ほとんど一日に渡って精霊とやりとりした疲労で、夢も見ずに泥のように眠った。
しかし翌朝目が覚めると、アイリーン様と私は朝食を済ませてから屋敷の方々に御礼を言ってから、早々に邸宅を去った。
「アイリーン様、ここまで急いで出発しなくても良かったのではないですか?」
彼女は歩きながら、チラリと私の方を見て言った。
「いやヘンタルが亡くなった今、私たちに聖都にいて欲しいと願う人は誰もいないからねえ」
「追放されるのと同じようなものですか」
「いや……、そこまでじゃない。私は勇者パーティーのメンバーだったし、ユリーアは聖都の周囲に防壁を張ったという実績を作ったからね」
そう言われて、私はようやく自分に全てを任された理由を理解した。
「私が聖都に貢献したという実績を作らせて人々の感情を穏やかにするため、敢えて私に全てをやらせたのですか」
「そーゆーこと」
その時の私は、仏頂面になっていたと思う。
「アイリーン様、お気持ちは嬉しいですけれどもスパルタ過ぎます」
私の文句を聞いた彼女は立ち止まって、ゆっくりと私の方へ向き直った。
「言っておくけど、これはヘンタルの案だよ」
「えっ?」
「うまく行ったから『結果オーライ』だけれども、ヘンタルは本当に親バカだね。実は私もヒヤヒヤものだったよ」
「そうだったんですか……」
つぶやいている最中に、ピンと来るものがあった。
アイリーン様の目を覗き込む。
「もしかして私にワザと悲しい別れを経験させるように仕向けませんでしたか?」
彼女にしては珍しく、アイリーン様は渋い表情になった。
「よく気がついたね……。その通りだよ。でも、それを考えたのもヘンタルだからね」
「えっ?」
「最もツライ時でも精霊を暴走を抑えることができれば、それがユリーアの自信と精霊使いとしての成長につながるだろうって」
「……」
最も愛する人を失う……。再び経験することはあるかもしれないけれども、たしかにこれ以上に感情を揺さぶるようなことは存在しないだろう。
「私たちは、二人ともあの古だぬき坊主に手玉に取られたっていう訳さ」
そういうことだったのか……。
しばらく二人で向き合っていたけれども、やがてどちらかともなく再び歩き始めた。
そして三分くらい歩いてから、私は口を開いた。
「手玉に取られたのはアイリーン様だけだと思いますよ」
再び珍しく、少し驚いたような表情をして、彼女はチラリと視線を向けて来た。
「そうなの?」
「そうです。だって私は今でもヘンタル様に感謝していますから」
アイリーン様の足どりが、一瞬だけ止まった。
「そっか。つまり手玉に取られたのは私だけ?」
「そうです」
数秒ほど過ぎてから、彼女は私の方へ振り向いた。
驚いたことに、少し笑顔になっている。初めてみる表情だ。
「それは良かった」
私の気のせいかもしれないけれども、どこかが誰かの笑い声が聞こえたような気がした。
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
