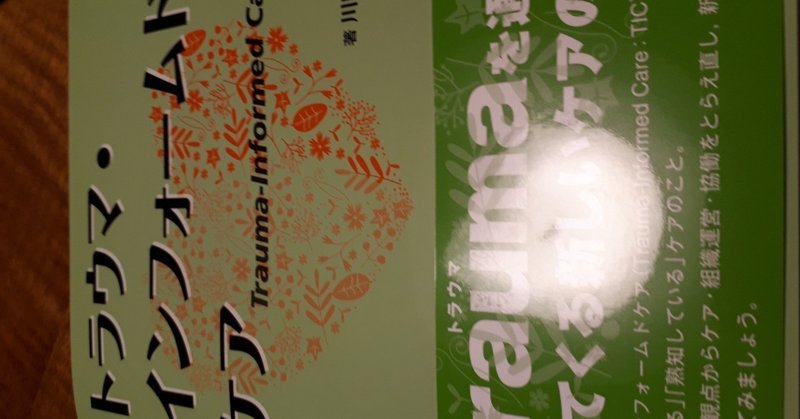
トラウマ・インフォームドケアからの学び、その2
前回のおさらい
「なにが起こったのかをお話ししてください」=状況、事実を共有
「何がそのような気持ちにさせていますか」=その状況から本人が主観的に感じたこと。本来の目指している姿との差異が見える。
「いま、何が必要ですか」=それに対して本人のこれまでの経験から何が必要かという主観にアクセス
「あなたが選べる事として」=本人が主導権をもって選択できる感覚(やらない選択も自分が選択しているという認識があれば主体に戻れる)
「どのようにする事で楽になれますか」=これまでの楽になったコーピングを想起。または、今後やれそうなコーピングを発見、強化
具体的な実践として
何が起こったのか?
よくある例として
・よくあるのは気分のスイッチのオン、オフがわからない。オンになった状態では何を自分が言っているのかさえわからない。
・例えばそれがフラッシュバックすることもある。
何がそのような気持ちにさせたのかを聞くことにより、先行刺激を同定することができる。また、そのような気持ちになりたくない自分という逆説的な視点で話ができる。
よくある例として
・体重が減るとみんなより痩せているので自分で自分を認められる。
・生活面が充実している人を見ると自分は充実してないと思い人から認められていないと孤独感を感じる。
この二つを丁寧に整理していくことにより引き金であるトリガー、スタックポイントが共有できるのでは。
例えば
・気分のスイッチが常にオンになっているわけではないので、オンになっていない時の生活から共有(オンになると記憶がないため)。そこから外れていく生活(セルフケア)は、どうなれば良くなって、どうなれば悪くなるのか。
・もしオンになった状態があったとして、覚えている範囲で言語化。オフの状態との異なる箇所をみる。
今、何が必要か?
・オンになる引き金。例えばトリガーが人であれば、その人を避けることもできるだろうし、見ないように目をつぶることもできるだろう。その場で立ち止まり後ろを向くこともできる。どのように対処するのかは考えることはできる。今、ここで何が必要かを考える。
あなたが選べることとして
・トラウマがあったとしてもより良い人生は選択できる。トラウマとの付き合い方を学ぶことを選択することもできるし、向き合うことを先延ばしにすることもできる。ここで対処を考えながら実践することは、いつでも選択できる。
どのようにすることで楽になれるか
・楽になりたい自分と楽になることに不安を感じる自分。楽になることで現実的な課題に向き合う必要が出てくる可能性も考えておく。
今後の課題として、実践としての記述として必要なところ
・患者と共同
・症状管理ではなく技能習得→病状は適応への試み
例として
薬の飲み忘れでパニックになる。なぜパニックになるのかというと、以前に薬を長期間自己調整をしていた時に調子が悪化した経験(トラウマ的経験による影響)。それが蘇る。薬を飲み忘れないように時計のアラームをセット。しかし、服用の時間は毎日同じではない。食事をする時間や外出によっても変わる。
ここで考えないといけないのは、パニックになった時に冷静になれる対処。そのためにはまずは何が課題になっているのかを明らかにする。
例えば、飲み忘れ記録をつけてもらうと昼が忘れやすいことに気づくことがある。昼は主剤は入っていないとするのなら、昼を飲み忘れたらスキップして次回の診察時に主治医へ持っていく。
昼に主剤が入っていたら半減期を一緒に調べて前後の時間はどの程度ならズレても大丈夫かを検討。または、薬を朝や夕にまとめてもらい飲む回数を減らすなど。
次回の診察時に主治医とその情報をもって話し合ってもらえるようにサポートする。
医療者主体にならないことが、もしかするとTICの実践ではKeyになるのではないか。
そのためには
・その患者に何が生じたのかに関心を向ける
・トラウマを避けるのではなく、接近する
この二つを意識すれば小手先の対処ではなくトラウマ的体験とお付き合いをする方法が見えやすくなる。
ここに記した例としては実在する方ではなく、よくある共通項を組み合わせた架空のケースです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
