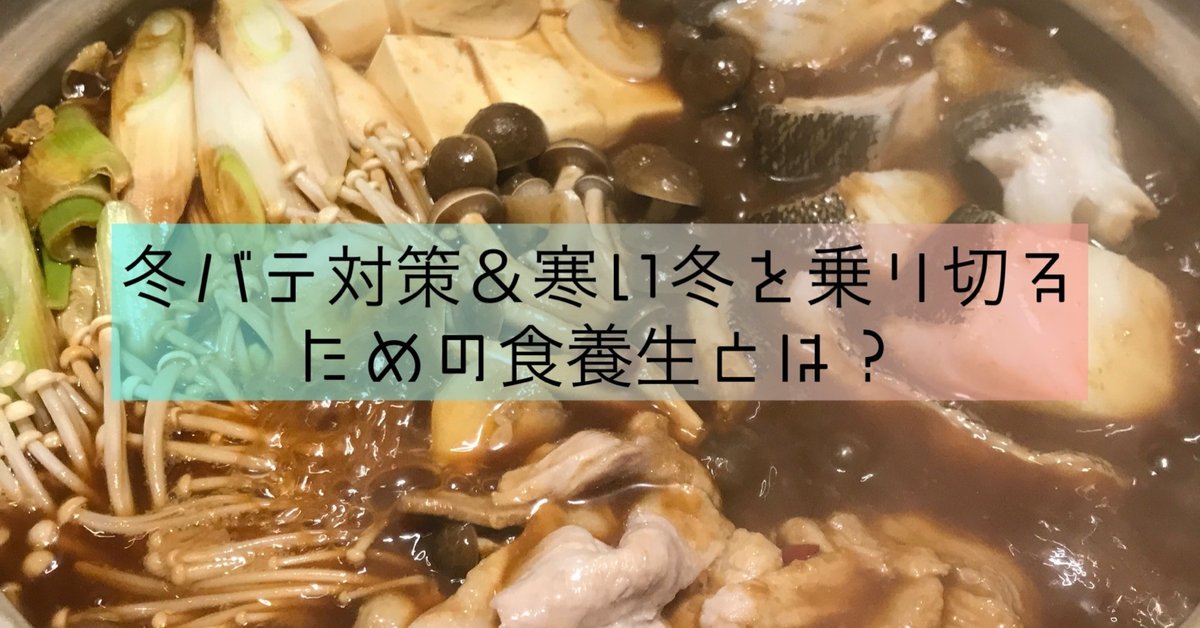
冬季うつ〜冬バテ対策&寒い冬を乗り切るための食養生とは?
どうも!
両国でたべるちゃんこ鍋ってどうしてあんなに美味しいのでしょうか?
ちなみに寒い冬に両国でちゃんこ鍋を食べたら美味しいと思うのですが、両国でちゃんこ鍋を食べた時期は見事に全部『真夏』です。
さわたや薬房の早川です。
#なぜ真夏なのかは新日本プロレス真夏の祭典とわんぱく相撲があるからです
ちゃんこ鍋って『お相撲さんが食べるから』ちゃんこ鍋であって『ちゃんこ』とは本来『お相撲さんの食事』を指すそうです。
そこで食べるから『ちゃんこ鍋』と言うそうです。
また、昔は『手をつく』=『負ける』と縁起が悪かったので4本足であるく豚や牛の肉は使わなかったそうですが現在では普通に食べられているそうです。
またヤセ型の力士を『ソップ』と言う風に呼ぶのですが、その語源は
ちゃんこ鍋の出汁を昔から痩せこけている『ソップ』と呼ばれる鶏ガラを使って取っていたことが由来だということです。
さて、そんな鍋料理が美味しい季節になってきましたが、今回は前回テーマとして取り上げた『冬バテ』の食養生をご紹介したいと思います。
詳しくは前回のnoteを御覧いただきたいのですが『冬バテ』とは季節の変化によって起こる心身の不調「季節性感情障害」一つですが
そんな季節性感情障害の中でも、最近注目されているの
「冬季うつ」
別名「冬バテ」
などと言われる症状です。
「冬バテ・冬季うつ」とは名前の通り、冬になると調子が崩れてきて、春になると回復するという特徴があります。
前回のnoteでは冬バテの症状、原因、おすすめの予防法などをお伝えしました。
今回は冬バテ対策の中でも食養生を取り上げて、寒い冬を乗り切るための食養生も含めてお届けいしたいと思います。
冬バテ対策&の寒い冬を乗り切るための食養生とは?
というテーマでお届け致します。
☆冬だからこそ食養生
冬バテ対策は食養生も大きなポイントです。
冬は食べ物がなにかと美味しい季節です。
今年は新型コロナの影響もあり例年のような大規模な忘年会や新年会、クリスマスパーティーは開催されないかもしれませんが、家族単位や少人数で楽しむ方は大勢いると思います。
外食の機会が減っているだけに自宅での食を楽しむ方も増えています。
そんな時期だからこそ、皆さんの健康のお役に立つような食養生を今回はお伝えしたいと思います。
まずは食養生の基本的なところですが、バランスに気をつけながら
『食事を楽しむこと』を意識しましょう。
『あれ食べなくちゃ!』
『これ食べなくちゃ!』
と意識するあまり食事がストレスになっては本末転倒です。どんなカラダに良い食事も『しかめっ面』で食べていては効果半減どころかマイナスにすらなってしまいます。
まずは笑顔で食事を摂ることで心の健康に繋がります。
☆冬バテ対策の食養生とは?
冬バテは日照時間が短いこと、寒さで交感神経が優位になるなどで、自律神経のバランスが乱れてカラダをコントロールしてくれる、メラトニン、セロトニンバランスが崩れることが主な原因です。
そのため、まずはセロトニンの原料となるトリプトファンを多く含む食品がおすすめです。
・セロトニンの原料となるトリプトファンが豊富な食品・・・バナナ、アボカド、かつお節、大豆類、ゴマ、ナッツなど
トリプトファンばかり取っていても実は体内でセロトニンは出来ません。それと一緒に体内でセロトニンを合成するのに必要な栄養素『ビタミンB6』も取りましょう。
・セロトニンの合成に必要なビタミンB6・・・かつお節、バナナ、玄米、魚類、にんにく、しょうがなど
最後は脳でセロトニン神経のエネルギー源となるものもとらないと宝の持ち腐れです。その栄養素は『炭水化物』です。
・ セロトニンのエネルギーとなる炭水化物が豊富な食べ物・・・米、麺類、イモ類、アボガド、各種果物
こうやって見るとバランスよく食べることが大切なのがよく分かると思いますが注意が必要な点もあります。
それはセロトニンの原料トリプトファンは動物性たんぱく質に多く含まれていることがわかっていますが、肉類、魚類に多く含まれる動物性たんぱく質は過度に取りすぎるとトリプトファンを脳に取り込みにくくすることがわかっています。
何事もバランスが大切、ということです。
☆冬バテ&寒さに負けないための中医学的冬の食養生とは?
冬バテ対策はセロトニンの活性化につながる食養生だけをすればよいというわけではありません。
冬の寒さに負けないカラダをしっかり作っておくことは当然、冬という寒さが不調の原因である『冬バテ』対策には欠かせません。
また、例年『冬は冷えが酷くて・・・』という方にも今からご消化する中医学的冬の食養生は非常におすすめです。
中医学では冬は五臓の『腎』が弱る季節と考えます。
この『腎』は生命力を蓄える場所で、成長、発育、生殖をつかさどる場所なのです。髪の毛、骨、歯などはもちろん、泌尿器系の弱りや腰痛など加齢とも繋がり深いところなので、腎を養うことは加齢を予防することにも繋がります。
基本は体全体を温めること、特に腰回りを冷やさないことが大切です。
『腎』を養うのは『黒い食材』なので黒い食材や季節の食材を上手に活用しましょう。
◆黒い食材・・・黒豆 黒ごま ゴボウ 黒キクラゲ 昆布やわかめなどの海藻類 牡蠣など
◆旬の食材・・・大根 人参 蓮根 白菜 ほうれん草 水菜 ブリ 鮭 りんご ゆずなど
旬の食材でおすすめが『鮭』と『ブリ』
ブリは出世魚としても有名で関西ではお正月に食べる魚としても有名です。
僕が住む山梨県ではお正月が『新巻鮭』をたべるのが風習なのですが、むかし広島県に住んでいた時、鮭がまったくなくて、豪華なお刺身、とくにブリがたくさん売っていて
正月休み明けに広島が地元の先輩に『鮭ってないんですね』と聞いたら
『塩鮭なんて保存食を正月から食わんやろ』と言われたのを今でも覚えています。
でも鮭もブリも冬が旬なので積極的に食べておきたいですよね。
鮭は元気不足の気虚、血液不足の血虚、ストレス疲労が強い気滞タイプにおすすめの万能選手。
カラダを温める温性で胃腸の働きも整えてくれます。
ブリは気虚と血虚を養うのは鮭と一緒ですがカラダの潤い不足の陰虚を補ってくれる働きがあります。乾燥してカラダの潤い不足になりやすい方にもオススメの食材です。
ブリも鮭も脂肪分が多く、カラダの冷えにもつながるためお刺身よりは焼いたり、鍋に入れたり、煮付けにしたりして冬はできるだけ食べたいですよね。
☆朝一番最初に口にするものが大切
冬バテについてお届けしてきましたが、冬独特の気候が不調の原因の冬バテです。最後はカラダを冷やさない養生も中でもとっても大切な『朝の習慣』について。
みなさん、朝起きて一番最初にカラダに入れるもの、気をつけていますか?
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
