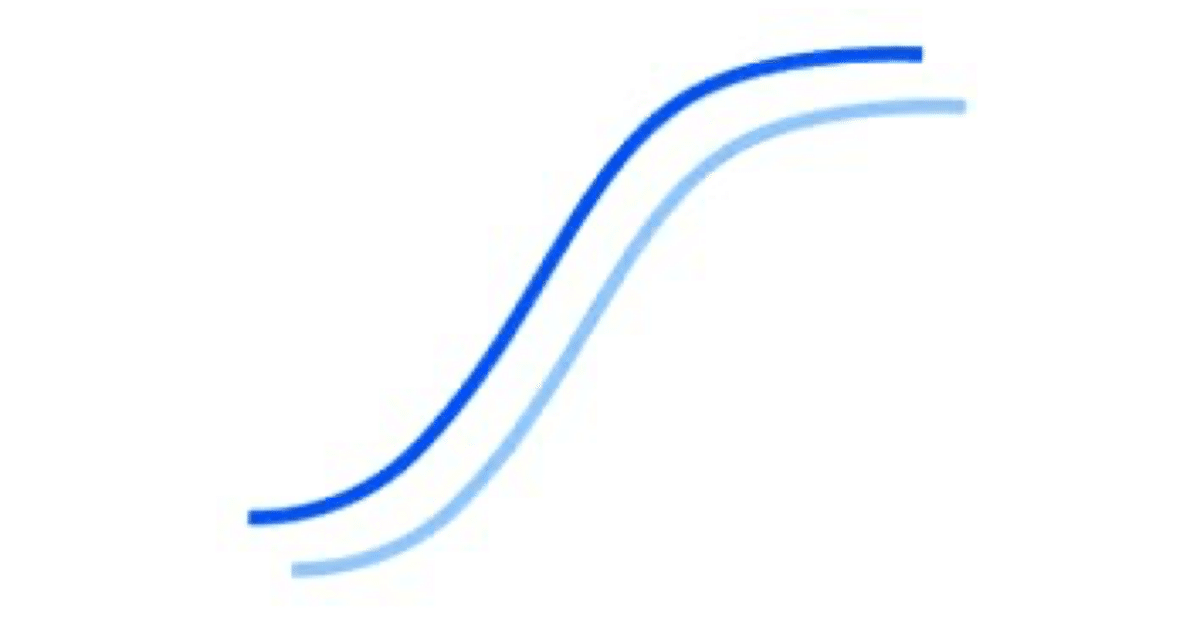
リテラシーとコンピテンシー(2010)
リテラシーとコンピテンシー
Saven Satow
Jul. 04, 2010
「他国の言葉を知らないものは、自国の言葉も知らない」。
ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ
東京都品川区は、2010年4月から、「一日保育士」をスタートしている。これは、39の区立保育園に通う約3700人の園児の保護者が少なくとも1人ずつ一日保育士を体験する取り組みである。この全国初の挑戦は好評で、新聞やテレビでも取り上げられている。
区の狙いは大きく二つある。
一つは、集団内で生活する子どもを朝から夕方まで共にすごせば、その姿を知り、接し方を学ぶことが期待できる点である。保護者は、一般的に、家庭でのわが子しか見ていない。しかし、集団の一人として相対化して観察すると、今まで気がつかなかった諸々のことを発見できる。
もう一つは保護者と保育士の信頼関係の構築である。保護者と保育士の間の不信感は、最近の保育をめぐる大きな問題の一つである。女性の社会進出に伴い、夜間保育や病児保育、乳児保育など保育の拡充が自治体に求められている。品川区は積極的に取り組んでいる。けれども、保育士との間の意思疎通が十分にとれないため、その対応に疑いを持ったり、文句ばかり口にしたり、見下したりする保護者も少なくない。
保護者の側にも考慮すべき事情がある。「時間地理学(Time Geography)」を提唱したスウェーデンのトルステン・ヘーゲルストランドは、現代空間では人は三つの制約の中でスケジュール調整を苦心しながら行動の軌跡、すなわち「パス(Path)」を辿らざるを得ないと指摘している。1日は24時間しかなく、休み時間や移動手段も限られているなど「能力の制約(Capability constraints)」がある。また、職場や保育所、駅など施設の空間的な位置関係が行動を制限する「結合の制約Coupling Constraints」」もある。その上、職務規定によってある時間帯はその場にいなければならないなど「ドメイン(Domain)」と呼ばれる管理領域への出入り、すなわち「アクセス(access)」=「イグレス(Egress)」が自由にできるわけではない「権威の制約(Authority Constraints)」も影響を与えている。現代人の行動は時間に支配され、被害者意識が過剰になり、疑心暗鬼や敵意にとらわれることも珍しいことではない。保護者はこうした精神状態で、なおかつ数分足らずの会話しか保育士と交わすことができなければ、信頼感を持つのも難しい。
「一日保育士」は保育のリテラシーの体験である。「リテラシー(Literacy)」は、ある領域における通時的・教示的な固有の知識・技能の言語化された共通理解を意味する。これは明治地で、日常的な繰り返しから地域を体得する暗黙知と異なる。コミュニケーションには共通基盤が欠かせない。しかし、専門知識はその内部において暗黙知として共有されている場合も少なくない。「一日保育士」は素人なので、専門家がそれを明示化してサポートしないと、仕事ができない。他者に対して説明するにはその言語化が必須である。「一日保育士」は暗黙知のみならず、リテラシーの体験うぃする。
言うまでもなく、一日の保育士で得られる知識や技能は限られている。しかし、保護者に保育にはリテラシーがあることを認知してもらうのが重要である。それを共通基盤にしてコミュニケーションを行い、双方の間で信頼関係を築くことができる。
保育士はリテラシーを習得した上で、保育のコンピテンシーを日々拡充している。「コンピテンシー(Competency)」は、リテラシーを習得した後、高度な専門的知識・技能を特定の文脈の中で複雑な課題に活用する能力である。これは、もともと、組織体において高度な専門的人材の活用に用いられる手法を指していたが、現在、教育などの方面で拡張して定義されている。OECDは、「コンピテンシー(能力)」を「単なる知識や技能だけではなく、技能や態度を含む様々な心理的・社会的なリソースを活用して、特定の文脈の中で複雑な要求(課題)に対応することができる力」と定義している。この場合、リテラシーはキー・コンピテンシーの一つに位置づけられている。保育のコンピテンシーは、実践するわけでもないのだから、保護者には、必ずしも要らない。その目的から言って、キーの一つであるリテラシーの認知だけで十分だ。批評にはリテラシーが必須である。
保育に限らず、従来、多くの分野でコンピテンシーを持つものと持たぬものの間で情報の非対称性が生じ、不振感や無責任、軽蔑に両者共にとらわれることがしばしば見受けられる。テレビ番組のやらせや事業仕分けにおけるスーパーコンピュータの問題がその一例であろう。こうした事態を払拭して信頼関係を構築するにはコミュニケーションが欠かせないが、情報の非対称性を改善するために、リテラシーの共有が必要である。
先に述べた通り、専門知識は明示知化されないまま、暗黙知としてその領域の内部で共有されている場合も少なくない。「習うより慣れろ」や「仕事は教わるものではなく盗むもの」といった経験や勘、見立てへの依存はその領域を停滞させる危険性がある。頭の中を整理しようと、人はそれを書き記しているうちに、さらに発見することもある。同様に、暗黙知を明示知にしてそれを理解するとき、内部も成長する。コンピテンシーもリテラシーと相互作用している。コンピテンシーを向上させたければ、リテラシーを認識するべきである。
〈了〉
参考文献
小林茂他、『人文地理学』、放送大学教育振興会、2004年
品川区、「公立保育園、幼稚園に通うお子さんの保護者を対象とした一日保育士体験」
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000011100/hpg000011037.htm
文部科学省、「中央教育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会(第27回(第3期第13回))議事録・配付資料 [資料4-1]」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/05111603/004.htm
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
