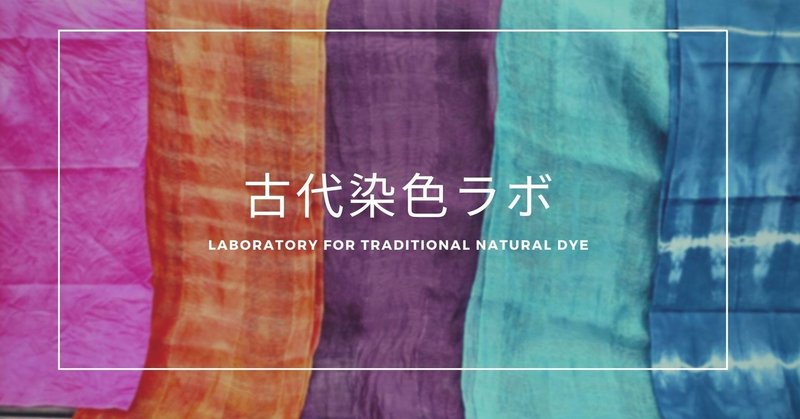
発酵と植物と色の研究室「古代染色ラボ」全5回の記録ノート
古代染色ラボの最終回でした。
乳酸発酵の媒染剤、お歯黒を作るところから始まり、型染めの型作りと、小紋糠から糊づくり、そして、灰汁づくりと、色と植物を追求する実験室。ラストは生薬をテーマに、麦灰と稲灰の色のサンプルをとりました。
第1回 「お歯黒」
昭和初期まで使われていたというお歯黒は、1ヶ月の乳酸発酵で鉄を溶かして作る媒染剤。歯を染めるだけでなくいい天然の媒染剤。2ヶ月間乳酸発酵させたお歯黒を持ち寄り、お茶とクロモジのお歯黒媒染をしました。

第2回 「灰汁」
こんにゃく作りや染色、発酵にも活かせる灰は、アルカリに持っていくことで酵素や菌の力を活用する昔ながらの知恵。灰屋という職業もいまや消えてしまいました。麦藁と稲藁から灰汁を作り、紅花で比較しました。
第3回 「ねば糊」
染色の型抜きにつかわれるねば糊をもち米や糠、石灰を使って作ります。古代の和文様をもとに、型染めの型も一緒に掘りました。

第4回 「柿渋」
奈良は渋柿の一大産地(全国3位)ですが、柿渋はほとんど利用されていません。一閑張りや自然塗料としても使える柿渋アートを研究します。前回掘った型とネバ糊を使って引き染めをしました。

第5回「生薬」
奈良は生薬に加工される薬草の産地。生薬には抗菌作用があったり、防虫効果があるものもの。紅花、黄檗、地黄を使って色のサンプルをとりました。

黄檗の森から樹皮を採集するところからの染色体験
あまり知られてませんが、奈良は古くからの薬草の産地で、トウキ、黄檗、芍薬、地黄など、現役でいろんな薬草が生産されています。役場で苗を配っているので、けっこう、一般家庭のお庭にもうわってたりしますよ。
紅花染めの紅をいっそう赤くする烏梅も奈良の月ヶ瀬が類を見ない生産地。
さらに、柿も全国3位の生産地で柿渋づくりの原料も身近に手に入るのでネタにつきません。
次回はまた、来年6月ごろ、キハダと柿渋づくりの参加者を募集します。
よろしければサポートお願いします。いただいた費用は、出版準備費用として使わせていただきます。
