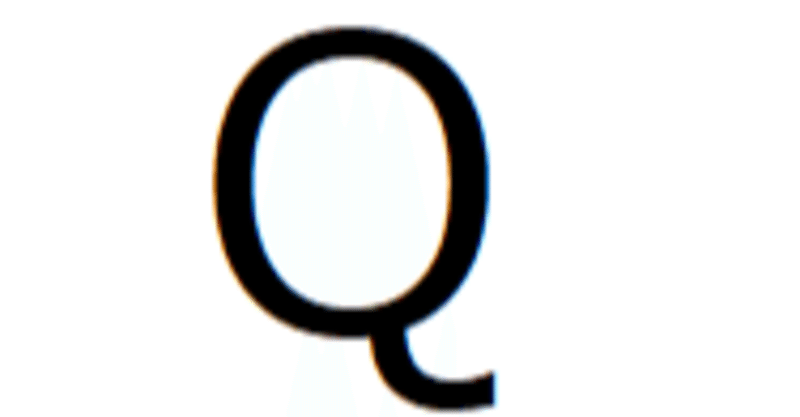
第Q回六枚道場感想
グループX
「ハゲの歌を聴け」 佐藤波平さん
これまでに数多く書かれてきた「風の歌を聴け」のパロディー小説。これは作者自身の若ハゲをネタにしたものらしい。「完璧な発毛方法などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね」や「放って置いても人は死ぬし、女と寝る。そして髪は抜ける。そういうものだ」といった文章はなかなか良かったが、全体としては竜頭蛇尾という印象。作者の頭皮状況には共感したが、ネタを最後まで読ませるのに必要な技術と勢いが足りなかったように感じる。
「第Q期どうぶつ将棋名人戦第Q戦感想」 佐藤将棋平さん
将棋の観戦記のパロディー小説。藤井ゾウ太二冠がハブ善治名人に挑む。杉本昌タカ八段はいいが、タイガー浩司九段は少し強引だった。
鷹が藤井二冠に運んできた扇子が実は師匠の託したものだったり、ハブ名人がおやつのバナナを藤井二冠の猿に与え、餌付けしておいたことが最後の逆転につながったりするなど、小説としてはしっかりと構成されている。
将棋好きな私としては楽しめた作品。続編への期待も込めてこの作品に投票した。
「旅する手紙」 佐藤純文平さん
これまで六枚道場でなかったのが意外な書簡体小説。コロナウイルスの流行により二つの国に引き裂かれた男女の手紙による交流を、作者らしい端正な文章で描く。
言葉遣いが不必要に古臭い点が気になったが、現代における書簡体小説の可能性は示してくれたと思う。
グループY
「廃墟の再生」 佐藤本文平さん
いわゆる本文消失系の作品。一九九二年のサラエヴォ包囲で焼失したボスニア・ヘルツェゴビナの国立図書館の蔵書を、教養ある大学教授であったにもかかわらずセルビアの民族主義者に加担し、図書館への爆撃を指示したニコラ・コリェヴィッチ(Nikola Koljević)の著作から蘇らせるアイロニーの切れ味は見事である。
未邦訳文献を駆使して難題に取り組んだ作者の静かな熱意に感動し、この作品に投票した。
「Q望」 佐藤杜甫平さん
六枚道場史上初の漢詩作品。作者はこれまでも唐代の伝奇小説などを題材にした作品を発表してきたが、まさか漢詩もかけるとは驚きだ。
作者の教養の幅広さはよく分かったが、肝心の詩の内容はほとんど理解できなかったというのが正直な感想。せめて書き下し文くらいは用意してほしかった。
「回文 六枚の宮の姫君」 佐藤回文平さん
これまた六枚道場初の回文作品。しかも、ただの回文ではなく、芥川の「六の宮の姫君」を題材にした野心作である。回文としてはやや強引な部分もある気がするが、作者の知的努力は賞賛に値する。
「嫌い」 佐藤杉平さん
「花粉」という文字が六ページすべてを覆いつくした作品。これは詩という分類でいいのだろうか。作者が酷い花粉症で悩んでいることはよく伝わってきたが、読んでいる私まで鼻がムズムズしてきた。勘弁してほしいというのが正直な感想。
グループZ
「QとR」 佐藤QR平さん
今回の六枚道場で一番の問題作。作品自体がQRコードになっていて、それを読み取ると作者のホームページで小説を読むことができる。小説や六枚という枠組みに対する固定観念に挑戦した作品、なのかもしれない。
QRの読み取り先で読める小説自体は、ありきたりな青春恋愛小説だったことが残念。できれば動画を流したり、さらに別サイトへのリンクを張り付けたりして、徹底的に小説の常識を破壊してほしかった。
「走れメロスと三匹の子豚」 佐藤豚平さん
「メロスと三匹の子豚は激怒した」というインパクトのある一文ではじまる作品。三匹の子豚がメロスと行動を共にしている理由は説明されないし、その後の展開にも強引さが目立つ。
長男の子豚が一匹で山賊に立ち向かう場面や、次男の子豚が丸太を背負い城壁に突撃する場面には読んでいる私も熱くなった。それだけに、王の回心後におこなわれた宴会で、三男の子豚をレンガの窯で丸焼きにして食べてしまったことには唖然とした。メロスにとって、三匹の子豚たちとの友情はその程度のものだったのだろうか。
「第Q回六枚道場感想」 佐藤相平さん
六枚道場の感想を題材にした作品。アイディアは悪くないが、内輪ネタでしかない気もする。安易なパロディーネタが並んでいることは残念だし、作者の詩に対する知識の無さも明らかだ。もう少し用意をしてから挑むべき題材だったのではないかと思う。
英語を教えながら小説を書いています/第二回かめさま文学賞受賞/第5回私立古賀裕人文学賞🐸賞/第3回フルオブブックス文学賞エッセイ部門佳作
