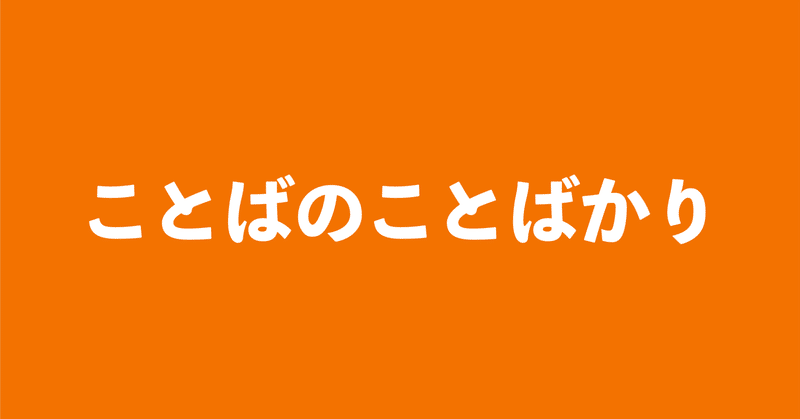
言語化のこの先と問題点について
言語化というものを言語化してみる。:4
しつこく言語化の話です。個人的には仕事してく上で「思ったことや伝えたいことを言葉にする」って当たり前に大事なことだったので気にもしてませんでしたが、言語化って、最近流行ってるんですね。そういう関係の本もいっぱい出てる。
おいおい知らなかったのか、って話ですが、世の中だいたい、ブームになると終わるってのが常識なので、ちょっとヤバいかも、と思いました。
そう思うと、なんかちょっと変な方向にきてるんじゃないか。ってことがいくつか思い当たります。
コンセプトの時代は終了です。という説
ひとつには、みんなが学びたい、と思うようになったってことは、このまあスキルみたいなものが、すごく一般的になってきた、ということです。
あるスキルが一般的になってみんなが使えるようになる、ということは素晴らしいことなんですが、一方でみんなが使うことでそのやり方そのものがコモディティ化する恐れがあります。
僕の身近な例でお話しすると、広告の作り方の変化、みたいなのがあります。CMが世の中に広く出回ってきた頃、高度成長期には、CMはほとんどが機能訴求でした。新しい技術がどんどん生まれて、それをそのまま見せればそれでよかった。
それがだんだん、新しい技術なんて出てこなくなって、ただの機能訴求では売れなくなってきた。そこで作り手はそこに新しい意味を持たせることを考えるようになりました。
コンセプト、ストーリーで差別化する時代になりました。機能そのものではなく、それが生み出す物語に価値があり、それに共感してもらえれば同じ機能でもそっちを選ぶ。今はこのやり方が主流です。そして、このやり方にも限界がちょっとだけ見え出しました。
コンセプトがコモディティ化するって何じゃい、って話ですが、コンセプトを作ることも技なので、やり方があるし、コツもある。それを学べば誰にでもできるようになります。みんながやるようになれば、それ自体が当たり前になり差別化できない。
一つには、質の悪いストーリーが増えてしまう、ということが起きてくる。なんか話の底が見えるというか、いかにも作った裏話、みたいなものが出てきます。そうなるとこのやり方そのものの足を引っ張って全体が「なーんだ」みたいに思われてしまう。
そうなるとどう変わっていくか。今言われ出したのが、もう一度機能に戻る。ということです。ただ、機能そのものはもう新しいものは生まれてこないので、機能の高いものを「妙におすすめしないで、ただそこに置く」というやり方です。
これ、感覚が掴みにくいですが、機能が高いものを見つけた人側が、それを受け取って自分でストーリーを作る。自分が見つけた「いいもの」が自分の生活の中でどう作用するか、を楽しむということです。
なので、あえて送り手は「何もしない」ということになります。かなり無謀ですが。
そういう流れが見えてきている一つの例として、ジブリの宮崎駿監督の新作「君たちはどう生きるか」が、公開までいっさい何も発信しなかったというのがあります。これ、どう見てもわざと何も言っていない。
機能の高いものを、そこに置いて、それを受け取る人が自分でストーリーを作るのが理想。
言ってしまえば自信の現れなんでしょうが、これまで巧みな宣伝戦略でヒットを作ってきたジブリがやるんだから、これも作戦なんじゃないか、と勘繰ってしまいます。
まあそんな戦略的なものじゃなくて、素直に何も先入観を与えないで、それを自由にそれぞれの感性で受け取って欲しい、ということかもしれません。とにかく今は事前情報が過多すぎて、公開時にはほとんどお話がわかってしまってるということも多いので、それに対するカウンターパンチかもしれない。
人が勝手に見つけたものに自分のストーリーを作ってそれを愛すること。宣伝しないで、そのものをポンとそこに置いて判断をゆだねる広告。何もしないをすること。これが新しい流れになる可能性はあると思います。
こういうものが出てくると「コンセプトを作る」という作業そのものがちょっと嘘くさくなる。そう見えてしまうという恐れはあります。
チャットGPTは泳いだことないのに泳ぎ方の話をする。
話が逸れてしまいましたが、こういう「技術そのものが当たり前になってしまうと、全体の質が落ちてそれ自体の信頼度が落ちてしまう」ということが、言語化というものについても起きる可能性がある、と思っています。
じゃあ、言語化の場合、どういうことが起きるのか。
言語化という技術は一言で言うと、共通の感覚を使った言葉による「置き換え」です。非常に便利だけれど、それは本物とは言い切れない。一つの例えにすぎません。つまり、技術さえあれば「うまいこと言えちゃう」ものでもあります。
これにすごく似てるものを最近よく目にします。それはチャットGPTです。
チャットGPTは聞かれたことに対して、言葉で説明してくれます。うやむやな質問をしても何らかの言葉でそれを形にして見せてくれる。これはある意味言語化です。
すごく便利だな、と思う一方でちょっと気に入らない感じもする。なぜそんなに語ることができる?それを語る君は何者だ?と、もちろん機械だと知ってるのにそう思ってしまうときがあります。
たとえば泳ぎ方について質問したとする。AIは懇切丁寧にやり方について説明してくれる。「だけど君、泳いだことないよね」と思ったりします。
自分で経験してないことを我がもの顔で話すガリ勉小僧のよう。接地していないものを、別の接地していないもので言い換える。ぐるぐる地面に降りることなく回り続ける。
認知学者のスティーブン・ハルナッドという人が「感覚と接地しない、身体的な経験を持たないAIは、別の記号で表現することはできても、対象を「理解」できない。」と言っているそうです。
これっていわゆる口先だけってやつで、つまり本当に理解してなくても言い換え、つまり言語化はできるということです。これって言語化の問題点ではないかって気もします。
さっきの話で、広告が商品の機能訴求では売れなくなって、ストーリーで売る時代になっている中で、そのストーリーが、感覚や経験と接地しないものに広がっているということと同じです。
昔見た「奇跡の人」という映画で、ヘレンケラーが初めてWaterというコトバを知るときのエピソード、サリバン先生が井戸の水にヘレンの手を当てながらその手にwaterという文字を書いて、それが同じである、と伝えたシーンがありました。経験があって初めて本当に理解できるってことだと思います。
僕らが使う言語化は言葉によるイメージの置き換えなので、便利だけれどホンモノではない。甘いという味はコトバで表現できて伝わるけれど、経験しないと本当に理解したとは言えない。
なーんてことを最近考えた。というお話でした。
ちなみにオノマトペはすごく感覚的な言語化で、普通の言葉より実感がこもってる気がします。
ということで本日のお話は以上になります。ではでは
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
