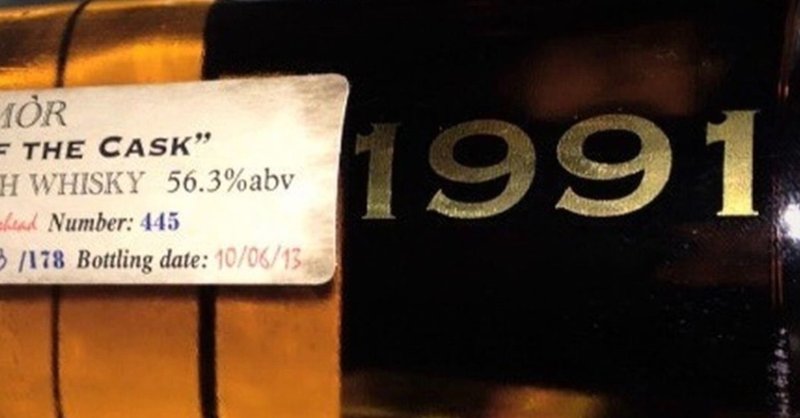
優しさを鍛えるために賢くなる。
最近、ツイッターで科学の中で「車輪の再発明」という言葉があることを知りました。
意味は「既に誰かが発見したことを自分で思いついたと錯覚すること」なんだそうです。
それを踏まえてツイートは以下のように続きます。
過去にいろいろな研究をした人や、データを集めた人がいる。それをまず、心を澄まして学ぶことから始めなければいけない。学ぶ前に自分の頭で考えようとするのは愚かです
自分の頭で考えることは重要だが、その前に先人が残した知恵に心を開いて受け入れ、煩悩を排除して世界を見る
僕は評論を下敷きにしたエッセイを幾つか書いたことがあります。
評論には幾つかの役割があります。
今回は漫画「ヒカルの碁」のラストみたいなことを言いたいと思います。
どうして碁を打つのか。
それは遠い過去と遠い未来を繋ぐ為だ、と「ヒカルの碁」では語られていました。
評論にも似た役割があります。
例えばですが、1000年前のテクストが脈々と論じられてきていたとして、それについて僕らの世代が論じなくなってしまったら、僕らより先の世代は1000年前のテクストを読めなくなってしまいます。
前の世代の方々が論じてくれているものを引き受けて、次に繋ぐ努力は誰かがしないといけません。
その努力は必ずしも、僕がしないといけないことではありません。
つまり、Mr.Childrenの「ヒーロー」の歌詞みたい感情がそこにはあります。
例えば誰か一人の命と
引き換えに世界を救えるとして
僕は誰かが名乗り出るのを待っているだけの男だ(Mr.Children「ヒーロー」より)
ただ、小説でもエッセイでも、何かを書こうとした時、先人が残した知恵から学ぶところから始めなければなりません(学ぶ前に自分の頭で考えようとすることは確かに愚かだと僕は思うので)。
問題はその先人が残した知恵を受け入れる為にも知恵は必要だ、という矛盾でした。
そのような矛盾の為に、先人の知恵を理解する為の試行錯誤が、小説投稿サイトのカクヨムで書いていたエッセイの内容でした。
カクヨムには小説も載せています。
この小説に関して言えば、その先人の知恵を自分の頭で考える為の試行錯誤、ということになります。
エッセイが先人の知恵を理解する為のもの。
小説が先人の知恵を自分で考える為のもの。
そのような訳で、僕が小説を書く時にはモチベーションがどれだけ高くても、自分の頭で考えられるだけの知恵が溜まっていないと、まったく書くことができません。
逆にモチベーションが低くても、知恵が溜まっていれば小説は書けると思っています。
いや、ちょっと格好をつけたかも知れません。
モチベーションを維持しなければ死活問題!
ってなるのは、むしろ先人が残した知恵を学ぶ時なのかも知れません。
知恵は自分から、「俺、こういうヤツなんだぜ!」とは言ってきてくれないので、自分から「君はこういうヤツなんだな」と迎えに行く必要があります。
そういう時、先人の知恵を学び得た未来の自分を想像します。
「頭がいい人はやっぱり優しい。」
舞城王太郎の小説の一文です。
優しさを鍛える為には、賢くなる必要があります。
さきほど、引用したMr.Children「ヒーロー」の歌詞になぞるなら以下になります。
つまづいたり 転んだりするようなら
そっと手を差し伸べるよ(Mr.Children「ヒーロー」より)
人生において、複雑に絡み合った感情や状況によって、人はつまづいたり、転んだりしてしまう時があります。
そういう時に、そっと手を差し伸べたい。複雑な問題を抱えているなら、一緒に糸口を探すくらいには賢くなりたいと僕は思っています。
サポートいただけたら、夢かな?と思うくらい嬉しいです。
