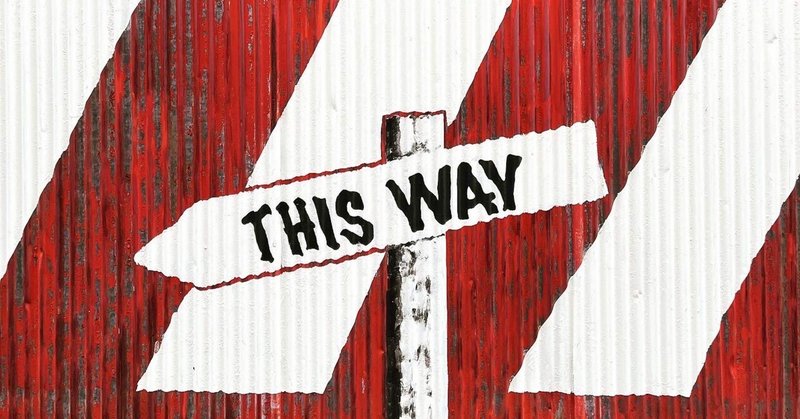
非母国語である英語を話すということ
(見出し写真は、神奈川県二宮町まで見に行ったmural=壁に描かれたアートのひとつ!)
私の母語は日本語で、
第1外国語は英語、
第2外国語はフランス語、
第n外国語は中国語/ドイツ語/etc.である笑
大学へ進学した後、
外国語=非母国語の学習への向き合い方が
180度変わった。
英語に限って言えば、
「ネイティブ」・イングリッシュではなく、
「シンプル」・イングリッシュを目指せ!
ということである。
このことは、大学入学後、
様々な経験や読書を通して学んだ。
大学入学直後の私は、
留学生や帰国生が使うように、
「ネイティブ」・イングリッシュを
話せるようにならなければいかん!
と息巻いていた笑
だが、いかにも「ネイティブ」さながらに
英語を「カッコつけて」話したとしても、
話す内容が支離滅裂/頓珍漢ならば、
ネイティブ・ノンネイティブ話者に関わらず
言いたいことは伝わらないのだ。
そもそも言語は単なる意思疎通の手段であること、英語を話すことはパフォーマンスではないことという当たり前のことを忘れていた。
そんな私はいま、「シンプル」・イングリッシュを目標にしている。
まず、実例として、下記Wikipediaの2記事を比較してもらいたい。
○(Native)English ver.
○Simple English ver.
2つの記事を比較すると、
Simple Englishの記事の方が、
英語が非母国語ではない人にとっては
いささか読みやすいだろう。
書き言葉であれ、話し言葉であれ、誰にとってもすんなり理解できる、Lingua Francaとしての英語が英語の非母国語話者が目指すべき「シンプル」・イングリッシュであると考える。
よって私たち英語の非母語話者が、無理に「ネイティブ」・イングリッシュを目指す必要はなく、「ネイティブ」らしさを追求することでコミュニケーションに支障が出るならば本末転倒である。(「ネイティブ」・イングリッシュは幼少期の一定期間以上に鍛えられないと身につかないそうです。純ジャパの私たちは諦めましょう😊)
また、上記のLingua Francaとしての英語は、文化相対主義Cultural Relatismの面でも重要ではないか、と考える。
私たち(日本語話者)はどうしてもアメリカン/クイーンズイングリッシュを基に、自分の英語や他者の英語に関して比較優劣をしてしまう。
昨年インドに旅行した後も「インド人やっぱ訛ってた?聞き取りづらかった?意味わからなかった?」と予想以上に周囲から聞かれた。
このことはやはり、アメリカン/クイーンズイングリッシュ=「正統」であるという風潮が根強いことを示していると思う。
しかし、悪く言えば「現地訛り」「異端な英語」であるかもしれないが、視点を変えるとそれはその国・地域の特性を反映した多様な英語の一形態と捉えられないだろうか。
日本訛りの英語「Janglish」(もはや英語ではない?)も含めて、現地の言葉に大きな影響を受け多様な相貌を呈する多様な英語を尊重したいものである。他者が話す訛り=アクセントのある英語を文化そのものとして受け止めた上で、自分自身が話す英語を相対化する。そうすることで、自分の話す英語を恥ずかしく未熟だと感じることはなくなると思うし、そこから見えてくる世界線をもっと大事にしていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
