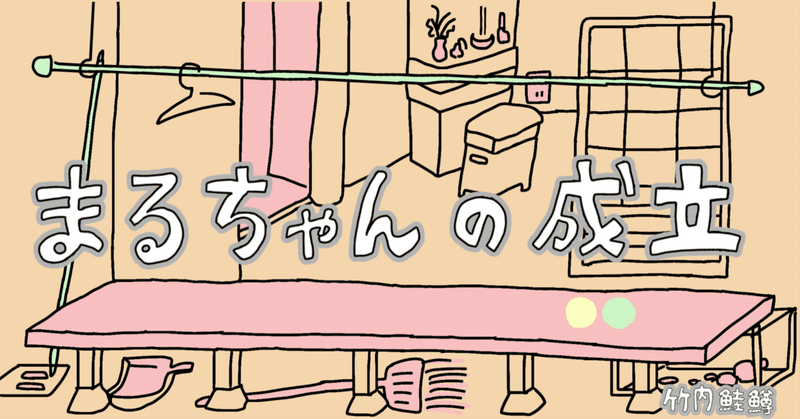
まるちゃんの成立(2/3章)/小説 #創作大賞2024
▼前回のお話
はじめから読む方はこちら
4.
〽︎まるちゃんってなんでできてる
マザーグースの替え歌
まるちゃんってなんでできてる?
まるちゃんってなんでできてる?
アクリルの毛糸、綿、フェルト、ボンド、ゆりちゃんの愛
そんなもんでできてんのよ
〽︎まるちゃんの絵描き歌
作詞・作曲 ゆりちゃん
まるかいて、ちょんちょん
にゅ~っと笑って、わっかをつけたら、ぼく、まるちゃん
単純な素材で構成され、簡単な作法で描けてしまうようなぼくだけれど、ときおり見習い哲学者のようにかんがえてしまう。昔、ゆりちゃんのリュックに入っていっしょに大学の授業を受けていて、そうなった。物の存在について語る講義は、よくわからないということだけがわかったのだが、かんがえることは楽しいと気づいた。
ぼくは、どこからきたのか。どこへいくのか。どうして、ゆりちゃんの声や熱は、ぼくに命を吹きこんでくれるのか。ほかの物もそうなのか。
そもそも、どうしてぼくは、ゆりちゃんのことが、こんなにだいすきなのか。
先生が言っていた。目も耳もつかえずに生まれた人間は、手のひらから物がなくなると、この世から物の存在がなくなったとおもうらしい。だから、ある施設はそうやって生まれた子に、手のひらの物がなくなっても、この世からなくなったわけではないことをおしえこむらしい。まずは触感から存在をおしえることは、愛をおしえることとおなじくらい必需であると、その施設員は語るらしい。
おそらくぼくも、ゆりちゃんにぼくの存在をおしえてもらったことから、すべてをはじめられた。
もし、ぼくが人間の子なら、心臓が波うち、体中が濡れていて、安全だった母のおなかから出てきたときは、風が体をはねかえし、空間を押しのけてそこに存在することができたのだ。けれどぼくはあみぐるみである。あみぐるみはザルや鳥かごと似ている。胸を張って、その場所に存在し、風をはねのけられるものではない。自分の抜け穴すべてから風が入りこんで、さっきゆりちゃんに温められたはずの熱はすぐにどこかへ行ってしまう。ぼくを構成する、毛糸、綿、フェルト、そして、外からの付着物、それから、ゆりちゃんの熱は、ぼくにとっては記憶する脳とおなじだ。脳がないぼくは、彼女の体温やにおいで記憶する。体内の空気が入れかわってしまうと、空に漂うものにすぎなくなる。風がぼくの記憶を逃がしてしまった後は、ぼくと記憶がずいぶん離れてしまったところでお互いを探しているのかもしれない。あの雲も昔はぼくの記憶だったということかもしれない。
5.
ぼくには、中学生のころのゆりちゃんとの記憶がほとんどない。たしか、中学校に入ってすぐ、ゆりちゃんは塾へかようようになって、ぼくとお話する回数が減った。高校生になってからは、おもいだしたかのように、ぼくを愛でてすごすようになった。
あの頃、ぼくは一日中お父さんのちかくにいた。
ゆりちゃんがお父さんの体調を気遣うとき、ぼくも親子の会話が弾む場所にいた。不安だったことばかり覚えているけれど、あの三年間、ぼくはゆりちゃんのお父さんの専属セラピストのようにすごしていた。単身赴任で寂しかったお父さんに貸しだされて、ゆりちゃんの分身として、心の介抱を託されていたし、お父さんの入院した個室へもいっしょに行ってお父さんの役に立っていたようだった。ゆりちゃんがそばにいないとことばがつながらず、記憶はあいまいなままだけど、「お父さん」としきりに話しかけていたゆりちゃんの声をよく覚えている。
そもそも、いつもいっしょにいるからといって、ぼくが彼女のすべてをしった気でいてはならない。彼女が本当は何をかんがえているのか、夢は何なのか、いまいちわからなくても当然だとおもう。そんな簡単にわかるものではないし、わかった気になられてはたまらないはずだ。頑固なゆりちゃんは、夢も弱みもそう簡単に見せてはくれない。ガラパゴス諸島へ行くのが夢だと、小学校の卒業文集に書いてはいたけれど、彼女はいまだ一人きりで国内旅行にさえいったことがないのである。
だから、三十歳目前の彼女が、転職して東京へいくと決めたとき、ぼくはおどろいた。そんな兆しはどこにもなかった。すっかり元気になって定年退職をしたお父さんはさみしそうに応援していて、いまだに仕事で忙しいお母さんは、ゆりちゃんを頼りにしていたから残念がった。ぼくはというと、長く彼女とすごしたこの部屋が、いとおしくなった。この部屋にはたくさんの静止物があって、ゆりちゃんのおもいでを持っていた。
引っ越しは、静止物たちが選抜されるということだった。ぼくはあたりまえのように、ゆりちゃんのハンドバックの中にスペースを用意され、ふわふわの手ぬぐいにつつまれて、新幹線に乗っていく準備をしてもらった。ほかのものは、段ボールにつつまれたり、リサイクルショップに持っていかれたりした。大きな変化は静止物の色彩をまばゆく映しているようで、ゆりちゃんは皆に「ありがとうね」と声をかけながらお別れした。
この部屋にのこるものは、学習机と、六つの引き出しのついたベッドと、水槽になった。六十センチメートルの横幅で、いつも出窓に置かれたままの水槽だった。いつかそこに、逃げた亀が帰ってくるかもしれないからと、ずっとおいてあるもので、透きとおったガラスは自然と部屋と一体化し、オフホワイトの壁紙がいちばんよく似あう静止物だった。
6.
ぼくにはやりのこしたことがあった。
二〇〇〇年に突然亀が逃げ出した。その亀のことである。
それは竹内家にとって事件であり、小学五年生のゆりちゃんは行方のわからない亀をおもって泣きさけんだ。亀はミシシッピーアカミミガメで雑食性であり、すききらいも激しく、食べたくないイトミミズを水槽に入れられ、たいへん不愉快だったようだ。
亀はふしぎなもので、ゆりちゃんに愛されることをよろこばなかった。愛を受信するよりも餌を食うほうが大事だった。だから、ゆりちゃんのおままごとにかまっている暇はないし、もっとうまいものを食いたいと鳴いて、水槽から逃げだした。
くさいから、いなくなってよかったのよと、ゆりちゃんのお母さんは聞こえるようにつぶやいた。ただ、そんな亀がまだ生きていて、ゆりちゃんの寝ているベッドの下にいるなど、だれも想像しなかった。
亀は、部屋中の埃を体にへばりつかせて、たわしみたいな風貌になって、夜になると部屋を闊歩した。まずは、ゆりちゃんが持ってきた、飲みかけのマグカップに顔をつっこみ、水を一飲みした。また一飲み一飲み、ドリンクした。通称「バー・マグカップ」。ゆりちゃんのちょっと汚い習慣に命が助けられている亀だった。隅を歩く虫、水気をすった埃、食べかす。そんなものを食べていた。
ことばが通じるならこんなふうに話したかった。
「いちど食べた小松菜やにぼしが忘れられないからといって、こんな生活を続けてはいけないよ。たしかに気まぐれなゆりちゃんのおもりをするのは疲れるね。だけど、だからって逃げるのはちがうとおもう。君は亀なんだから、水辺がなくちゃ生きられないでしょう」
けれど、この亀は勇敢にらくらくとぬけでてしまった。
ぼくは、のほほんとすごすあみぐるみだからわからないのだ。亀は腹が減り、静止物は腹が減らない。生きることは腹が減るから、できることなら、すきなものをすきなだけ食べて、悠々とくらしたかったのだろう。
ぼくは亀に毛玉を食べられてもいたくないし、ゆりちゃんのような愛にあふれている人のもとにいる幸せなあみぐるみで、物体的にちがうのだ。しょせん、ぼくは世界の外側をしらない毛糸や綿の集合体にすぎない。世間しらずのことを「井の中のかわず」というらしいし、ぼくはかわずと似た大きさでもある。
何もしらないぼくだけれど、ぼくとゆりちゃんがいなくなったら、この部屋はだれもつかわなくなることはしっている。何年か前の新神戸での一人暮らしとはわけがちがう。ゆりちゃんはもうここに戻る気はないのだ。おそらくだけれど、彼女は冒険すると決心したのだ。だからほとんどの静止物に別れを告げたのだ、きっと。
ぼくは亀の弔いをやりのこした。墓を作って、にぼしを供えて御祈りをしたかったのにできなかった。ぼくは亀のことがすきだった。寝返りをうったゆりちゃんが、ぼくを放りなげて床に落下させたとき、亀はいつもちかづいてきてくれた。ぼくの体の中から風が飛びだし、埃が宙を舞ってしまったのを、口をあけて浴びていたのは、ぼくをもっと食べたかったからなのかもしれない。
まるちゃんデリシャスおにぎりの作りかた
〈レシピ考案者〉ゆりちゃん
◆材料
・ごはん二〇〇グラム
・卵(Mサイズ)二個
・のり
◆道具
・フライパン
・はさみ
・ラップ
◆手順
1 おにぎりを作ります
2 薄焼き卵を作ります
3 薄焼き卵が冷めたら、おにぎりをつつみます
4 のりを目と口とわっかにきります
5 ごはんつぶをつぶしたもので、かわいく貼りつけましょう
6 ラップでくるんだ後、おしりをプリッとつきだしましょう
◆ワンポイントアドバイス
しあげに「かわいいね」と呼びかけましょう
ぼくはときどき亀に食べられてしまったけれど、自分のことを語るのに、この生き物の存在はきってもきりはなせない。亀がいたからこそ、ぼくは生き物になりたいと真にねがうことをあきらめたのだ。
ずっと、生き物になりたかった。生命のバトンをつなぐことに、心底あこがれていた。
本当は、亀となかよしになっておなじエサも食べてみたかった。排泄にだって興味があった。
そうなることはゆりちゃんもねがっていた。亀を買ってほしいとお母さんにせがんだ十歳のゆりちゃんは、ぼくに足りないものを亀に求めたにちがいなかった。
逃げられてしまった今は、生き物は逃げるものだというおもいこみを植えつけられてしまって後悔しているだろう。大昔、どこかの国の富豪が、おきにいりの踊り子の足をきって逃げられないようにしたという逸話に、ちょっと共感するくらいに。
ぼくなら逃げない。逃げるために動く体は持っていないし、その欲望さえない。
彼女はそれをしっていて、おもう存分にぼくを愛してもうらぎられないと再認識したのだ。
お父さんに貸しだされていた三年間、ぼくは意識が戻るたびに、このまま捨てられるのではないかと不安だった。
ゆりちゃんは病室でお父さんに話しかけながら、ぼくの頭もなでてくれていた。
けれど、あのお母さんが、中学生になってもあみぐるみで遊ぶ彼女を平然と見ていたとはおもえない。きっとどこかへ捨ててもらう気で、入院しているお父さんに貸しださせたのではないか、ともかんぐってしまう。お父さんはゆりちゃんに甘かったし、ぼくを守ってくれたのかもしれない。
ぼくは亀に生きることをおそわり、病院で死ぬことを学んだ。
いつか人が死ぬことや死を恐れる人が大半であることをしり、ゆりちゃんもいつか死ぬものとわかった。ぼくも死ぬものになってしまったら、彼女のかなしみが増えてしまうような気がした。
だから、ぼくは静止物として彼女が逝くまでそばにいることにした。
ゆりちゃんの夢をぼくはしらない。けれど、その魂胆は見えている。
彼女は、今まで神戸で家族以外と会話らしい会話をせず、静かにすごしていた自分を何かべつのものに変える気なのだ。恋人もいない、友達もいない彼女には、地方出身者も外国人も多い東京は、最良の場所なのだ。
彼女が失敗して財産を売りはらうようなことになっても、ぼくは唯一の持ち物になって彼女の役に立とうと決めた。
+++
◆続きはこちら
・第3章
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

