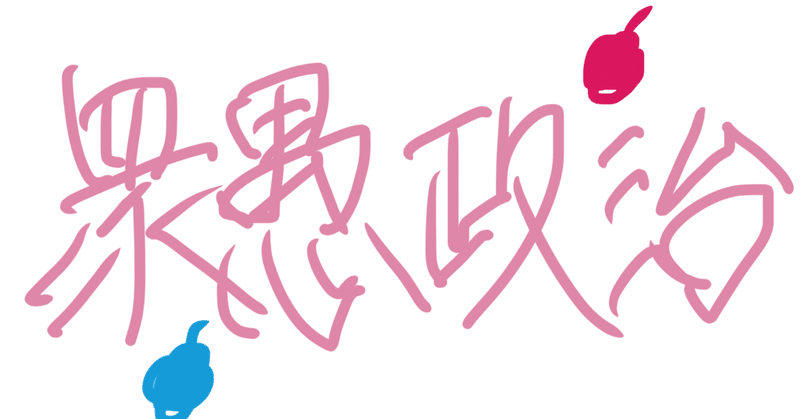
デデデーデマ・デマゴーゴス
公共の利益という言葉を聞いて思い出すのは、シャーロック・ホームズである。君を確実に破滅させることが出来るならば、公共の利益の為に僕は喜んで死を受け入れよう。そう言って彼は、最大のライバルかつ悪党一味の統領であるモリアーティ教授と共に無理心中のような形で滝壺に落ちるのだが、のちにホームズだけ助かったという。名言として名高いこのセリフはあまりにもかっこよく、その後の行動も華麗でドラマチックである。一度知れば忘れられないシーンであろう。自分も死に際にはライヘンバッハの滝へと赴きたいものである。
とは言っても自分は、コナン・ドイルのシリーズを読んだことは一度もない。しかし名探偵コナンの映画シリーズの中のひとつ「ベイカー街の亡霊」は何回も観たことがある。ホームズとモリアーティの最後については、この映画の中で工藤新一が教えてくれた。私はこの作品が大好きだ。かつて美容院で担当の人と「名探偵コナンの映画で名作といえば?」という話題になり、「ベイカー街の亡霊」で一致したことがある。その時の高揚感と言ったらなかったし、何回でも観たくなる名作であることを強く実感した瞬間でもあった。
「正統性原理は、政治体制の根幹に関わる理念や公共の利益に関する判断や対立の問題として考える必要がある」。まったくわからん。まったくわからん。怖い怖い怖い。前者の文は、私が最近受けている政治学の授業での「政治変動について」の一文であり、後者の文は、その一文を読んだ時の私の感想である。ここまで意味がわからないと人は恐怖を覚えるのだということは、少なくともこの授業から学べたと思う。再びここで「公共の利益」に注目してワンクッション置いてもいいのだが、ここで私が注目したいのは、この文よりも少し前に記述されていた「正統性と正当性は違う」というような事柄についてである。
省き倒して伝えるとするならば、正統性は主観で、正当性は客観だ(絶対違うけど死ぬほどわかりやすく言うとこうなる)。正「統」性は、理念ではなく、あくまでも「支持」。他方から見てそれがいくら愚かなシステム・制度であっても、当人たちの経験上それがある程度支持できるものであり、続投を望むなら、そこに正統性が生まれる。そしてその「正統性」は、それが「正当」であることを根拠づけるものにはなり得ない。戦時中に敵国者を殺す行為や、独裁政治体制などが例に上がると思う。違ったらほんまにごめん。
私は、簡単に「それは違う」とか「あなたは間違ってる」とか言えてしまう人のことをある意味尊敬すると同時に、何のつもりでそんなこと言うんだろう? と思う。あくまでもそれはその人がその人なりに情報収集して得た結果をその人なりにまとめただけの「解釈」に過ぎないのに、そんなホロホロの解釈を矛として他の人の解釈を否定することはこの上もなく愚かしい。正直、「りんごは青い」という主張に対しても、私は何らかの反論に際し、二の足を踏むだろう。まずりんごとは何か、青いとは何かから考えなくてはならないし。私がこれはりんごだ、これは青だと言って指差すものが、他人からどう見えているかもわからないのに。
あくまでも授業の中で先生は正統性と正当性を政治用語として用いていたが、私は、日々の生活の中にも昇華、スピンオフできる言葉たちであると思った。りんごは赤い。りんごは赤い。正統性を根拠にして、明らかに正当なことであると、どこかで思いこんでないか。りんごは赤い。りんごは赤い。自分が支持、また承認できることが、世界の全てのように思わないことだ。りんごは赤い? それが概して悪いことであるとは思わない。しかし、時に極めて常識的に感じるイデオロギーやパラダイムのような存在を、疑ってみることも必要だと思う。りんごは赤い。りんごは赤い。りんごは…。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
