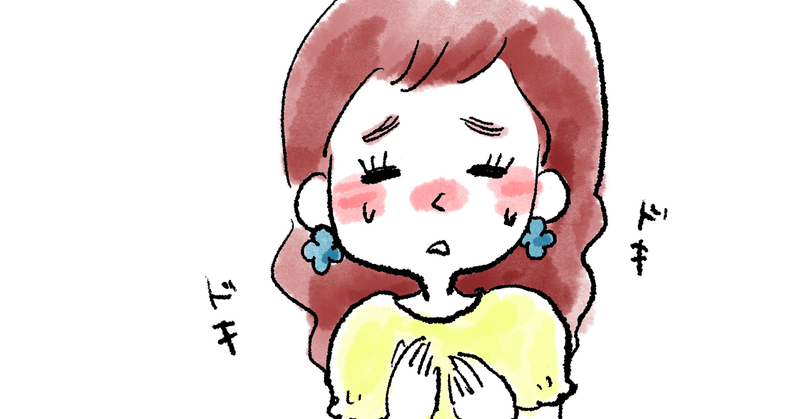
アニメオタク女子、一目惚れした苦しい恋の行方は?
毎日、同じ電車の同じ車両に、とても気になっている人が乗っている。
彼は、私の大好きなアニメに登場するあこがれの登場人物にとってもよく似ているのだ。
初めて彼を見かけたときは衝撃が走り、心の中で叫んだほどだ。
私立に通う小学生が電車の中で降りられないで困っているときに、彼が助けてあげているところを目撃したときには二度目の衝撃が走った。
以前は、朝起きるのが苦手だったが、彼にめぐり逢ってからは少し早めに起きて髪の毛を整え簡単なメークをするようになったが誰も私の変化に気づかなかった。
なんてったって私は流行には無頓着、地味な服装が好みだしコンタクトなんていまさら恥ずかしいし、分厚いメガネがトレードマークみたいになってるさえない女なのだから。
そんな私が、恋をしてしまった。
一日、たった30分足らずのしあわせなひととき。
その30分の間は、胸の鼓動は、ドキドキ、ハラハラ。
こんな感情は、初めてなのだ。
今まで、男性から相手にされたことはなく、恋愛はあきらめていた。
でも、片思いするのは勝手だからと自分に言い聞かせている。
彼が乗っていない日がたまにある。
そのときの私の一日のテンションは急降下。
今日も、乗っていますようにと祈りながら電車に乗り込む。
いた!!
後頭部の寝ぐせを見つける。そこがまたいいのだ。
あっという間の30分が過ぎて彼の降りる駅がきてしまった。
あれっ、今日はここで降りないの?
でも、少しでも一緒にいる時間が伸びてうれしい!!
私の降りる駅がきた。
あ~あ、束の間のしあわせだった。
ホームに降りて、電車の中の彼をもう一度見ようと後ろを振り返ると彼も電車を降りた。
もう心臓が飛び出るほどドキッとしてしまった。
何度も後ろを見たら、おかしいと思われるかな?
あ~、自意識過剰。
彼は私のことなんて眼中にないんだから、見たって大丈夫!!
どーしよう!えーい!もう一回振り返ってみた、、、。
ギェッ!なんと、すぐ後ろにいるではないか!!
そして、目がばっちり合ってしまった!!
そのとき、彼が、ニコッと笑った??
な、な、何が起こった!!
あせった私は、ニコリともせず、すぐに前を向いてしまった。
ドキドキしながら改札を出てもう一度振り向いたときには、もう彼の姿はなかった。
それからの私は、もう仕事どころではなかった。
気がつけば、朝のことを考えミスを連発。
上司に怒られても上の空。
熱でもあるのかって、今度は心配されて調子が悪いなら無理するなと言われる始末。
退社時間になって、皆に早く帰って休んだほうがいいと言われひとり退社した。
ぼ~っと、駅まで歩いていたら、な、なんと、彼が前を歩いているではないか。
こんな偶然は、テレビドラマにしかないと思っていた。
天にも昇る気持ちになって、彼の後ろ姿を眺めながら歩いた。
幸せな瞬間。
突然、彼が後ろを振り返った。
え~~~。
予想外の出来事に私は、びっくりしてしまった。
そして、私の顔をみて、「よく会いますね」と話しかけてきた。
どひゃ~!
緊急事態発生!
男性とまともに話したことがない私にとって今の状況は、
ど、ど、どピンチ!
「そ、そうですね」
それだけ言うのが精一杯。
「いつも、同じ電車に乗っていますよね?」
「そうですね」
ぶっきらぼうにそれしか言えない。
あ~笑顔になれない。顔がひきつる。
「まっすぐ帰るんですか?」
「はい」
ますますひきつるわたしの顔。絶望的。
「あの、お時間ないですか?いっしょにお茶でもどうですか?」
「えっ?」
今なんて言った?
もしかして、お茶に誘われたの?
いやいや、そんなことがあるわけない!
「お急ぎですか?」
「いえいえ、お急ぎではありません!」
どひゃ~!夢じゃない!奇跡が起きた!
あこがれの彼と一緒に並んで歩いてる。
しかし、何を話していいのかわからない。
心臓の鼓動が、彼に聞こえるんじゃないかと焦ってしまう。
カフェは、どこも席がいっぱいで、カウンターしか空いていなかった。
私にとっては好都合、向かい合わせは恥ずかし過ぎる。
彼がコーヒーを買って手渡してくれた。
お金を払おうとしたら、いいですって受け取ってくれなかった。
生まれて初めて、男性にごちそうしてもらった。
なんだか、涙が出そうなくらい嬉しい。
彼は、語学の教材を売る営業マンということだ。
今日は、顧客のところに行った帰りらしい。
行きも帰りも会うのは、すごい偶然で運命を感じたらしい。
そんなこと言われた私は天国にも昇る気分。
「今度、会社でセミナーがあるんですけど良かったらきませんか?
キャリアアップしたいと思っている前向きな人に是非来てもらいたいんです」
「私が行ってもいいんですか」
「もちろんですよ」
そして、お互いの連絡先を教えあった。
それからの私は毎日が夢の中で、その日が来るのを待ち遠しいと思う反面、来ないでほしいという怖い気持ちとが入り乱れていた。
当日、母が、出かけにニヤニヤしながら、頑張ってねと送り出してくれた。
今日のことは一言も言ってないのに母のカンは、するどい!
待ち合わせの場所に行ったら、もう既にそこに彼がいた。
「本当に来てくれたんだねありがとう!」
「いえ、あ、そんな……」
慣れないことを言われて戸惑い、あやふやな返事しか出来ない自分に腹がたつ。もう既に来たことを後悔している。
彼のことばかり考えていたので、セミナーの内容ははっきりいってよくわからなかった。
この教材を使って語学を学べばすごい成果が出るみたいだ。
どうすごいかは説明できない。
セミナーが終わり、ロビーを出たところで彼が数人のスタッフの女性たちとおしゃべりしていた。
みんな、洗練されたきれいなひとたちばかりだ。
その時、ひときわ人目を惹くすらっとした美人が彼に駆け寄り、雑談を始めた。笑い合う二人を見ていると映画のワンシーンのようだ。
あぁー、早くここから姿を消したい!!
自分が急に恥ずかしくなって、そそくさとロビーを出てしまった。
後ろから、私の名前を呼ぶ声がする。
振り向くと、彼が駆け寄って来た。
「今日は、ありがとう。また、連絡してもいいですか?」
「あ、はい…でも… 」
「でも?」
「あ、いえ、ごめんなさい」
そう言うのが、精一杯で顔が強張ったままその場を立ち去った。
毎朝、電車で姿だけ見て片思いしていたほうが良かったのかもしれない。
あんなに素敵な女性たちと、話している彼を見なくてすんだのだ。
彼の目的は、教材を売ることなんだ。
だって、そうじゃなきゃ、私になんか声をかけるわけないんだから。
最初に話したときから、そう感じていたのにその気持ちに気づかないようにしていた。
束の間だけど、ドキドキの気分が味わえてよかった。
あこがれの人とカフェで、お茶ができて嬉しかった。
それだけでよかったじゃないかと自分に言い聞かせる。でも、心が痛くて、こんなにもつらい。
涙があふれそうだったけど、必死でこらえた。
駅に向かって歩いていたら、一軒のカフェの扉が開いた。
中から、ひとの良さそうなおばさんが顔を出し、
「あ~良かった!!間に合った!!今彼から電話があってお店で待っててほしいって連絡があったの」
「え?どうして私ってわかったんですか?」
「服装といいたいところだけど、その悲壮感あふれるあなたの顔ですぐわかったわ。さあさ、中に入って」
促されるままに店に入った。コーヒーの良い香りが鼻をくすぐる。
なんともいえない不思議な雰囲気で、暖かいぬくもりを感じさせてくれる空間。
こころなしか、さっきまでの絶望感が薄らいでいる
注文したコーヒーを一口飲む。
「美味しいでしょう?ちょっと一息つけたかな?」
「はい……あ、あのどーして?」
「彼が慌てて電話してきて、このまま帰ってしまったら終わりになってしまうかもしれないって、必死に止めといてくださいって頼まれたのよ」
「。。。」
「彼は常連さんで、根が優しくて素敵な男性よ」
「それはわかっています。私自身の問題です。自信がなくて、つまらない人間なんです」
「つまらないって誰かに言われたわけではないでしょう?」
「私は、ほんとにさえないブスなんです。今まで、男性に相手にされたこともないんですから」
私は、彼とのことをおばさんに話してみた。
「それは、自分でそう思っているだけなんじゃない?
現に彼、また連絡するっていったんでしょ?
教材を売りたいからに決まってるなんて、自分の憶測だけで決めつけてしまって、もしそうでなかったときは人生すごーく損しちゃうわよ。
あなたは、傷つくのが怖いのね。
傷つくのが怖いから、それが、起こる前に逃げてしまってる。
もし、仮にあなたの想像通りだったとしても、彼は、それだけの人だったって思えばいいんじゃないかしら。
ひとつの苦い経験として、それを人生の糧にしていくの。
それは、あなたにとってけっしてマイナスではないわ。
それを経験したことで、ひとはとても成長できるものなのよ。
あー、でも彼は教材を売りつけるためにあなたに声をかけるような人ではないわよ。念のため言っておくわね」
「私はそれを言い訳にして彼から逃げ出したかったんです。傷つくのが怖いんです」
「勝手に彼を悪者にして逃げてしまったら、あなたは人生のひとつのチャンスを潰すことになるのよ。
まだ、なにも始まっていないのに、自ら幕を下ろすことはないでしょう?
確かに、街でみかける女性たちは、華やかなで美しいひとが多いけれども、それがすべてじゃないから……。
男性も外見ばかりにこだわるひとばかりじゃないのよ。自信を持って自分の良さを認めてあげて」
確かに、おばさんのいうことはわかるけど、彼に嫌われてしまったことを想像するだけでとても怖い。
それなら、最初から何もないほうが苦しい思いをしなくてすむ。
突然、おばさんが席を立って、扉のほうへ向い外へ出た。
おばさんといっしょに入ってきたのは、彼!
私の向かい側に座る彼。
「実は、さっき、君の様子をみて絶望的だと思ってたんだ。
連絡するとは言ったものの、君が僕のことを拒否しているようにみえたからもうダメだと思っていたんだ」
「…うそ…そんなことあるわけない…」
「最初に電車で君に気付いたのは、実は僕の方が先だよ。
おばあさんに席を譲っていたのを見て優しい人だなって思ったんだ。
しばらくして、突然君は僕に気づいたんだ。
なんとなく、僕を気にしていてくれるのがわかったので、この前話しかけたんだけど、君にとっては迷惑だったのかなと思っていたんだ」
「ね~わかったでしょう?自分勝手に判断して人生のチャンスを逃すところだったんだから」
こんなことがあるなんて夢にも思わなかった。
男性は、みんなセンスのよい見た目がステキな女性がいいと思っていた。
私は、恥ずかしくて下を向いてしまった。
私と彼は、よろしくお願いしますとお互いに頭を下げた。
おばさんはいつの間にか席をはずして、他のお客さんと談笑している。
私と彼は、いろいろな話をした。
あんなに緊張して話せなかったのに、今は素直に話せる自分が不思議だ。
コーヒーを飲み終え、おばさんにお礼を言って二人でカフェをあとにした。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
