
自分への質問 Q13.縁がないと思っていることは?
自分への質問の全体像が知りたい方は、こちらへどうぞ ↓
縁がないと思っていること どんなことでしょう?
私の答えは、こちらです!
1.バッチリおしゃれ
2.はなやかなパーティ
3.意識の高い暮らし
4.お手伝いさんのいる暮らし
5.ストイック
6.一生友だち
7.まるごと理解されること
8.子どもに手が離れること
9.議員になる
10.災害ボランティア
11.山登り
12.スポーツの集まり
13.上流の付き合い(そんなものがある?)
14.経団連
15.宗教
縁がないと思っていること? 桜会 2024.04
権力とか、集団で熱意をもってやるようなものに、どうも縁がないように感じる。
一生友だちに縁がないって、さみしい奴かも。
バッチリおしゃれは、しようと思うこともあるが、私がするとどこか抜けてしまう。完璧って縁がない。
縁がないと思っていること?を書くヒント
この設問、ちょっと「Q11.うらやましいこと」に似てますね。イメージとしては、うらやましいより、遠いですが…
自分の地図の中に、なさそうなこと
自分の人生には、おきそうにないこと
なんだか馴染みそうにないこと
身近でない感じが、ポイントでしょうか?設問を作ったときは、縁があることを書くと膨大になるので、縁がないことを書こうと思った記憶があります。
理屈ではなく、感覚で書くことが大切な設問です。
振り返りのヒント
では、自分の答えを振り返り、反芻するためのヒントをお知らせします。
縁があるという感覚は?
縁があると、直感的に感じるときありませんか?
スピリチュアルなことが影響しているのかどうか、私にはわかりませんが
なんとなく馴染む
そこにいる自分が想像できる
だれも勧めていないのに、なぜか惹かれる
というものに対しては、きっと縁があるんです。
縁があるものとは、いったん遠く離れたとしても、結局人生のどこかで、つながる瞬間があるように思います。(これは50年以上生きてきたからこそ、わかることかも…)
縁がないという感覚
例えば、周囲がうらやましがる物事であったとしても
なんだか乗らない
手にしてもうれしくない
ワクワクしない
義務感しかない
ような気がするのなら、縁がないのかもしれません。縁がないという感覚は、なんとなくのもの。
理屈ではありませんが、本人にはわかることです。
自分への質問は、その時の自分の感覚を客観視するものです。今後、縁がないと思っていたものが、どんどん身近になって、運命だと感じることもあるかもしれません。
でも、いまのあなたにとって縁がない感覚のものは、あまり大切にする必要がないものなのでしょう。一度断捨離してしまっても、きっと縁があるなら戻ってきます。

縁のありなし感覚を磨いておく
今回の質問は、答えの内容より考えること自体が大切な設問です。
普段、自分にとって縁があるかどうかなんて考えてはいる人は少ないでしょうから。
でも、自分の感覚を使わずに、得か損か、周囲からの評判が上がるか下がるかで、道を選んでいくと迷ってしまいます。
自分らしく生きていくには、自分の中で縁がありそうなほうを選ぶ必要があるわけです。
そして、毎日は選択の連続です。どの人に会うか、どんな体験をするかは選択によって決まります。
でも、その選択はとても小さくて無意識におこなわれることも多いもの。だから、感覚が大切になります。
縁がないもの。あなたは、思いついたでしょうか?
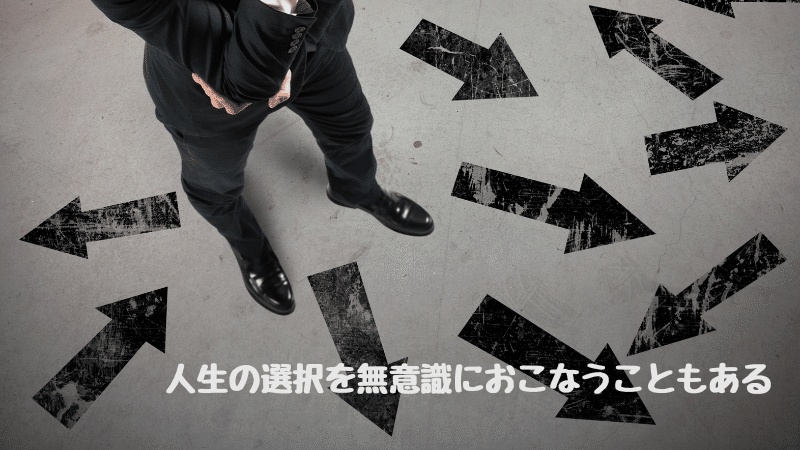
縁がないものは?先人の言葉
縁について名言を集めてきました。縁についての感覚を磨くヒントにしてください。
小さな出会いを大切に育てていくことで、人生の中での大きな出会いになることもあります
苦情を受けたときは「縁が結ばれる好機」と考える。一つの機会として生かしていくことが大事です。
人は、運命を避けようとしてとった道で、しばしば運命に出会う
自分が歩んできた過去を振り返ってみると、何とたくさんのすばらしい、一生に一度の出会いがあることか
みんなのために良かれと思ってやっていることを、冷たい目で見る人たちがいます。そういう人は、”縁なき衆生(しゅじょう)”と思って放っておきましょう。あなたはあなたで正しいことを、自信を持ってすればいいのです。
人生は、縁に始まり縁で終わる
次は自分には無理だと思っていることです。どんなことが書けそうですか?

おことわり
私はヨガ療法士の取得し、その際に心理学を学びました。大学で心理学を専攻した専門家ではありません。この記事に心理学上気になる間違いがあれば一報いただければありがたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
