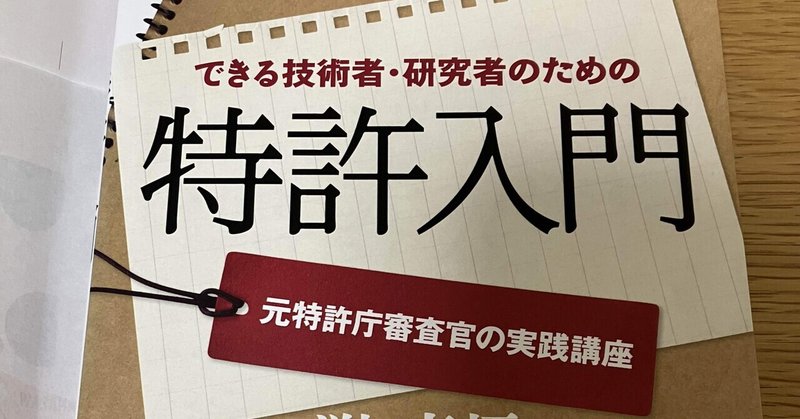
『できる技術者・研究者のための特許入門』は、特許庁の審査官ならではの目線で書かれた読みやすくて参考になる本でした
先日、『できる技術者・研究者のための特許入門 元特許庁審査官の実践講座』を読みました。

本書を購入したきっかけは、本屋さんで様々な本を試し読みした中で、読みやすくて今の自分が気になっていることがわかりやすく書いてありそうだったからです。
本書の筆者がもともと特許庁の審査官だったこともあり、審査官ならではの話がたくさん書いてありました。例えば、特許庁でのFIの付与の仕方、担当審査官の決定方法等です。また、審査官の心証といった観点で様々な話題について語られていたことも、この本ならではであり、参考になったポイントです。
難しかったポイントもあります。個人的に難しかったと感じたポイントは以下です。
・説明をするときの具体例において、化学分野や電気分野の例が多くあまりわからなかった。(※自分が情報系の分野ため)
・p88-p97に記載された「多機能化の検討〜櫛形電極の具体例」はしっくりこなかった。
・p142−p145のに記載された「特許請求の範囲の再設定」の表を用いた説明はよくわからなかった。
逆をいえば、上記に記した難しかったポイント以外の部分は、文章がわかりやすく書かれており、参考になることばかりでした。
特に、p.84の上位概念化・下位概念化の説明は非常にわかりやすかったです。
また、p.58に記載されている審査基準に関する以下の文章は、「まさにそう!」と読んでいて共感しました。
審査基準には、例を挙げながら、進歩性有無の判断について説明されています。しかし、例は理解できるけれども、現実的な案件に対しては、わかったようなわからないよな感覚に陥ることもあると思います。これは、特許庁が……
本書は、非常に読みやすく、ちょうど良い内容感で今の自分と相性が良い本でした。このタイミングで読んでおいて良かったと感じます。
