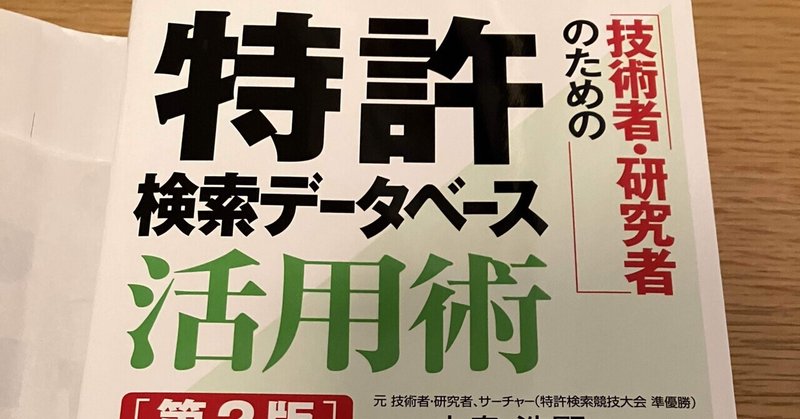
『技術者・研究者のための特許検索データベース活用術』は、J-PlatPatで先行技術調査をしたことがない人にとっては良い本なのかもしれません
今日は、『技術者・研究者のための特許検索データベース活用術 [第2版]』を読みました。

先行技術調査をするにあたり、他の人はJ-PlatPatをどのように使っていたり活用しているのかを知る目的で本書を購入しました。
思わぬ収穫となったのは、 「2-5 特許・実用新案制度の歴史」の章です。おおまかな歴史とともに、以下のようなプチ雑学を知ることができました。(いつ使うんだという話はあります)
特許の現行法が規定されたのは昭和34年で、もう60年以上も前のことであること
実用新案は、最初から無審査なわけではなくて、1993年に無審査登録制度が導入されたこと
特許公報に記載された特許番号がなぜ2,500,001号から始まっているのか
「登録実用新案公報」と「実用新案登録公報」の違い
また、先行技術調査の調査方法においてへぇとなったのは以下の2点です。
適切な特許分類コードを調べるときに発明の名称で検索を絞ること(p.128)
1つ上の階層の分類コードを使用する方法(p.137)
本書は、先行技術調査をしたこともJ-PlatPatも全く触ったことがない人にとっては良い本なのかもしれません。個人的には、少なからず触ったことがあったので物足りなさを感じました。
本書を読んだ後に、先行技術調査に関して違う本も読んでみたくなりました。
