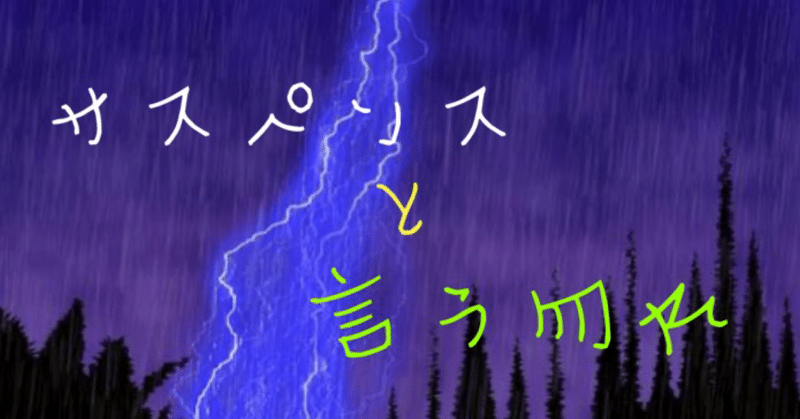
サスペンスと言う勿れ
「いいか、五千万用意しろ、それをカバンに詰めて、N駅から14時発の電車に乗れ、先頭車両だ。そしてカバンを網棚に乗せたまま次のA駅で降りろ。降りたら後は直ぐタクシーに乗って家に帰れ。分かったな。もしこの指令に背いたら家に火をつける。警察や他の人間に連絡した時も同じだ」
少し長いセリフだったが、目の前にカンペを置いて受話器越しに一方的に喋るだけだ。売れない舞台俳優の神田にしてみればゴールデンに放送されるこのドラマ出演に今後の役者人生を賭けていた。ただし、少々意気込み過ぎていたことは否めない。
「じゃ、いいか、先ずはテストだ。良ければ次は本番だからそのつもりで演技しろ、いいな」
ディレクターの野崎は鋭い目付きで神田にそう告げた。
「はいっ」野崎に見詰められ萎縮したように神田は応えた。
「緊張するな。それから電話はこのナンバーをプッシュしろ、スタッフが応対する。相手がいた方がセリフを言いやすいだろ?」
「あ、た、助かります」
神田は野崎から数字の書いたメモを受け取った。クセのある記号のような数字が並んでいる。
はい、テスト始めまーす!
スタジオ内にADの声が響き渡った。
緊張しながら神田は電話の置いてあるデスクの前に座ってスタンバイした。
はい、スタート!
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
はい、カット!
神田は深くため息を吐いた。
野崎がやって来る。
「悪くは無かったが、最初の部分、少し噛んだな。いいか、五千万だ、そこは大事な部分だからしっかり発音しろ。次は本番行くぞ」
「は、はいっ」
そこに携帯を手にしたスタッフが近寄って来た。
「あのぉ、僕、外の廊下で電話がかかって来るのを待ってたんですけど、携帯が鳴らなくて、今のはテストだったからナンバープッシュはしなかったんですか?」
「いや、してたな、なあ」と野崎は神田に訊ねる。
「あ、はぁ」
「ちょっと確認する。さっきのメモあるか」
「あ、はい、デスクの上に」
野崎はデスクまで歩いて行き、ナンバーをプッシュする。するとスタッフの携帯が鳴り出した。
スタッフが出ると野崎の声が聞こえる。
「よし、これでいいな、なんでさっきは繋がらなかったんだ?」
神田がメモを見て首を捻っているのを見て、
「まあいい、どうせナンバープッシュしてる部分は使わないんだ。次はこの再ダイヤルボタンを押せばいい」
「はい、分かりました」
神田は頷いた。
携帯を持ったスタッフはほんの少し何かを言いたそうにしていたが、本番始めまーす!というADの声を聞いて再び廊下に出て行った。
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
「よし、オッケー!」
現場に野崎の声が響いた。
無事にシーンを撮り終え、神田はほっと息を吐いた。
「ご苦労さん、上手く行ったよ。君の出番は今日はこれで終わりだ。もう上がっていいぞ、明日また頼む、お疲れ」
そう言って野崎は役者の肩をポンと叩いた。神田は黙って頭を下げる。額には汗が浮かんでいた。
ふと時計に目をやると時間はお昼を少し過ぎたところだった。
急いで楽屋で私服に着替えると神田は背を丸めてそそくさと撮影所を後にした。
そんな後ろ姿を先ほどの携帯を持ったスタッフが木陰からじっと見詰めていた。
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
翌日、別のシーンの撮影が行われた。神田には昨日のような重要で長いセリフは充てがわれていなかったが、午後まで続いた撮影に幾分疲弊した。
夕方になって漸く身体の空いた神田は休憩室で缶コーヒーを飲みながら昨日のことを思い出して、ため息を吐いた。すると……。
「ここ、良いですか?」
ふいに声を掛けられて神田はギクリとした。顔を上げると昨日携帯を持って廊下で待機していたスタッフがいた。
「あ、あ、どうぞ」神田は席をひとつずらし、スタッフのために席を空けた。
スタッフは、あ、どうもと言って、腰掛けたものの、暫く何も言葉を発さず身動きしない。
何だか妙に息苦しい沈黙が数秒間流れた。
「あのぉ、私に何か御用でしょうか?」
気まずい空気に耐えかねて、神田はそのスタッフに問い掛けた。相手は自分よりいくらか歳下に見えるが、ここはあえて敬語で話しかけた。
「あ、あぁ、ごめんなさい。何から伝えようかと思いを巡らしてしまいまして」
「思いを巡らす……、とは何を?」
「いえね、昨日は随分とガッカリされたのじゃないかなと思いまして」
「な、何をですか? そりゃ、確かにあの長ゼリフにテストの段階では一度噛んでしまいましたが、本番は一発オーケーだったから、別にガッカリなんてしてませんよ」
「いや、演技のことじゃないんです。ここを出たその後のことです」
「ここを出たその後……?」
「はい」
神田は急に驚いた素振りをして、
「あなた、もしや、私の後を尾行していたのですか?」と訊いた。
「いやいや、尾行なんてしませんよ」
「じゃあ、何故?」
「いえ、ちょっと気になったものですから、後から電話してみたんですよ」
「電話? どこへ?」
スタッフはそこで少し照れたような笑顔を浮かべると、ふと思いついたみたいに襷掛けしたポーチから何かを取り出した。
「あ、良かったらこれでも食べながらお話ししませんか? 美味しいですよ。ここのお煎餅」
それを見た瞬間、神田は目を見張り身体を硬直させた。
「あれ、どうしました? 何か見覚えあります? このゴマせん」
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
「あの店に、電話したのか?」
絞り出した神田の声は呻くように震えていた。
「僕は常々思ってました、野崎さんが書く数字の1は随分紛らわしいなと、だって縦棒を少し右に傾けて書くクセがあるし、おまけに上の部分に横線をちょっとつけるんですよ。あれだと1だか7だか、パッと見よく判らないですよね。ま、これは野崎さんがいけないのですけど。そこで僕も自分の携帯番号の最後の1を7に変えて発信してみたのですよ。そしたら繋がりました。乃木坂にあるあのお煎餅屋さんに」
「ふん」
神田は不貞腐れたようにそっぽを向いた。
「だからあなたは野崎さんの書いた数字の最後の1を間違えて7だと思ってしまった。あの時あなたは間違い電話をしたのですよ。そしてそのままあのセリフを口にした」
「どうしてそんなことが判る?」
「テストと言っても一応カメラは回ってますから、確認させて頂きました」
「へぇ、そうかい」
「でも、幸か不幸か、あなたはあの時、大切な箇所を噛んでしまいましたね。噛むと言うよりは、言い間違えてしまったんです。五千万と言うところを『ごまんせん』と言ってしまった。おそらくそれが向こうにはゴマせんと聞こえてしまったのでしょう」
「・・・・」
「とにかく、お煎餅屋さんは慌てたでしょうね。直ぐにカバンいっぱいにあの店の名物『ゴマせん』を詰めて、東京メトロ千代田線の乃木坂駅から電車に乗って次の赤坂まで行くと、カバンを網棚に置いたまま直ぐ家に帰った。もちろん誰にも言ってないですし、警察にも届けていないようです。まあカバンいっぱいと言っても中味は煎餅ですからね、売り値として二千円から三千円程度のものでしょう。家に火をつけられるよりはずっといい」
神田は大きくため息を吐いた。
「あきれたよ。その通りだ。よくそこまで見抜いたものだな」
「いえ、ちょっと気になったものですから」
「それで、俺は罪になるのか?」
「ま、一応このままだと犯罪になるでしょう。煎餅はどうしました?」
「家にあるよ。あんたの言った通り、カバンを開けてガッカリしたよ。中味が煎餅で。噛んだとは思ってたけど、そんな言い間違いをしてたとは思いもしなかった」
神田は脱力して項垂れた。もう敬語を使う必要もない。しかし、悪いことは出来ないものだな。
「あのぉ、ひとつ伺ってもよろしいでしょうか?」
「ああ、構わない」
「本当は五千万円のお金が欲しかったのですか?」
神田は首を傾けて少しだけ笑った。
「いや、そんなつもりはなかったよ。でも言ってしまったものは仕方ない。直接行って確かめようと思ったんだ」
「カバンが残されてるかと?」
「まあそういう事だ。何も知らない他人に持って行かれたら、困るだろ?」
「それは、そうですね」
さて、どうしたものかと思いを巡らしていると、ADが走って来て、次のシーンの撮影に入りますと神田に告げた。
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
その日の終わり、神田は再びさっきのスタッフのところへやって来た。
「これからあの店に謝りに行くよ。カバンと煎餅を持ってな。警察に突き出されても構わない。もう今日で俺はこのドラマ、クランクアップしたんだ」
「そうですか」
「でも、ひとつだけ、俺は今回のことで今まで味わった事のないスリルとサスペンスを味わったよ。こんなに胸がドキドキしたのは初めてかも知れない。勝手な言い草だけど、この経験がこれからの役者人生に活かされればいいなと思う」
「そうだと良いですね」
スタッフの落ち着いた受け答えに神田は妙に感心した。
「あんた、ホントにテレビ局のスタッフかい?」
「いえ、僕はただの大学生で、ちょっとバイトを頼まれて来ただけなんですよ」
「ああやっぱり、そうだろうな。そんな自由で個性的なヘアスタイルのスタッフなんて珍しいと思ったよ」
彼はほんの少し言葉に詰まった。
「あんた、名前はなんて言うんだい?」神田が訊いた。
大学生の男の子はちょっとだけ目を見開いた。
「ぼ、僕ですか? 苦能 漂といいます」
「クノウ タダヨウ くんか、変わった名前だな。覚えとくよ。じゃ、またいつか」
神田はそう言うと背を向け、手を振りながら去って行った。
その後ろ姿を苦能は佇んでじっと見詰めていた。
そして心の内でそっと呟く。
いや、サスペンスとは言えないっしょ。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
