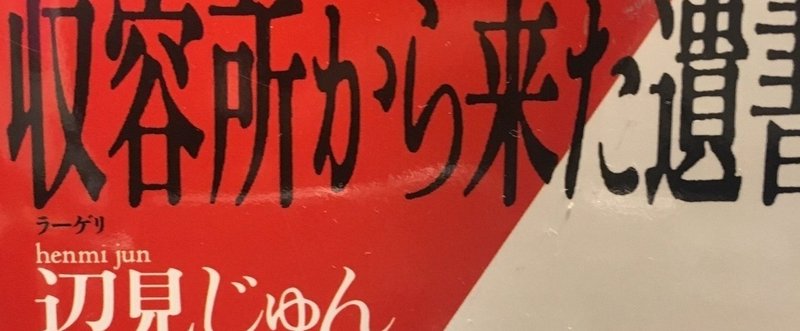
言葉の力に生かされる【辺見じゅん著:収容所から来た遺書】
私は、おなかが空いてひもじい思いをしたり、喉が渇いて脱水になったことがない。たくさん運動をした後とか、残業中に非常食がないとか、あってもそれくらいだ。数時間後には水も飲めるし、ごはんも食べられた。
人の死に遭遇したことも、数える程しかない。いずれも病院や介護施設での死で、血が流れたり身体が損傷したりしたものではない。ケガや病気も、転んで擦りむいたり捻挫したりとか、料理の最中に包丁で切ったとか、それくらいしか経験がない。身近に起こりそうな事故として、交通事故や火事が思いつくが、それらも遭ったことはないし、渦中の現場は見たことがない。
「命の危険」というものからは、程遠い人生を歩んでこれている。ありがたいことだ。
ただ、「自分が死ぬかも」と感じたことはある。精神的にも肉体的にも負担が大きい仕事をしていた時のことだ。ある時期から周りの人が恐ろしくて上手に話すことができなくなり、街はグレーで靄がかかって見え、風や車が通る音におびえ、衣食住への心遣いをする余裕はなくなった。
さらに、本が読めなくなった。
文字を目で追っていても、脳みその表面をつるつる滑って、一向に内容が理解できない。小説もビジネス書も、雑誌の記事でさえ、無理だった。子供の頃から、誰に言われるでもなく常に本を読んでいて、自然な生活の営みのひとつだったことができなくなった。この時、「身体は動いても、中身は死ぬかも」と感じた。
この時期に、唯一読めたのはエッセイだった。石井好子さんの「巴里の空の下オムレツの匂いは流れる」とか、平松洋子さん、高山なおみさんとか、食にまつわるエッセイが多かった。今思い返すと、家族で暮らしていた頃の食卓につながるような作品ばかりだった。帰るべき場所、囲むべきテーブル、いることが許される場所を思うことは心を支える。それが言葉として目の前に示されることが、とても力強い救いだった。
言葉には、人を支え、救い、生き延びさせる力があると信じている。
それはきっと、昔から知られていること。
その証拠に、歴史の中で植民地支配や奪った領土を統治する時には、もともとそこで使われていた言葉も奪う。
ソ連で収容所に送られた方たちは、手紙のやりとりはおろか、日記やメモなども含め、「言葉を書いたもの」の所持を厳しく制限されたらしい。収容所で亡くなった方のほとんどは、だから遺書も遺っていない。そんな中で、最期まで帰国の時を信じ、帰国後に言葉に困ったり頭が鈍らないように、隠れて句会を開催していた山本幡男さんの遺書は、亡くなってから2年後に帰国した人たちの記憶の中に遺され、ご遺族へ届けられた。
俳句を通じて祖国への思いを形にするとともに、出ることのできない収容所からも、ささやかに感じられるソ連の自然に目を向けさせ、圧せられ続ける人たちの心に、自由の風を吹かせ続けた山本さん。病を患い、帰国はかなわなかったが、彼を慕い、敬う人たちは、彼の遺書をご遺族に届けることを使命として、最後まで帰国をあきらめずに生き延びた。
私には、言葉も通じない寒い土地に留め置かれ、いつ帰れるかわからない強制労働の日々の辛さは、精いっぱいの想像力をかき集めても、想像し切れない。しかし、罰せられても隠れて句会を続けた山本さんや、彼の遺書を届けた方々の思いは、実感をもって理解できるような気がするのだ。
===================================
この記事は投げ銭制です。
いただいた投げ銭を元手に本を買い、読書感想文を書いています。
応援していただけたら嬉しいです!
ここから先は
¥ 100
最後まで読んでくださり、ありがとうございます!サポートいただきましたら、別の方をサポートします。
