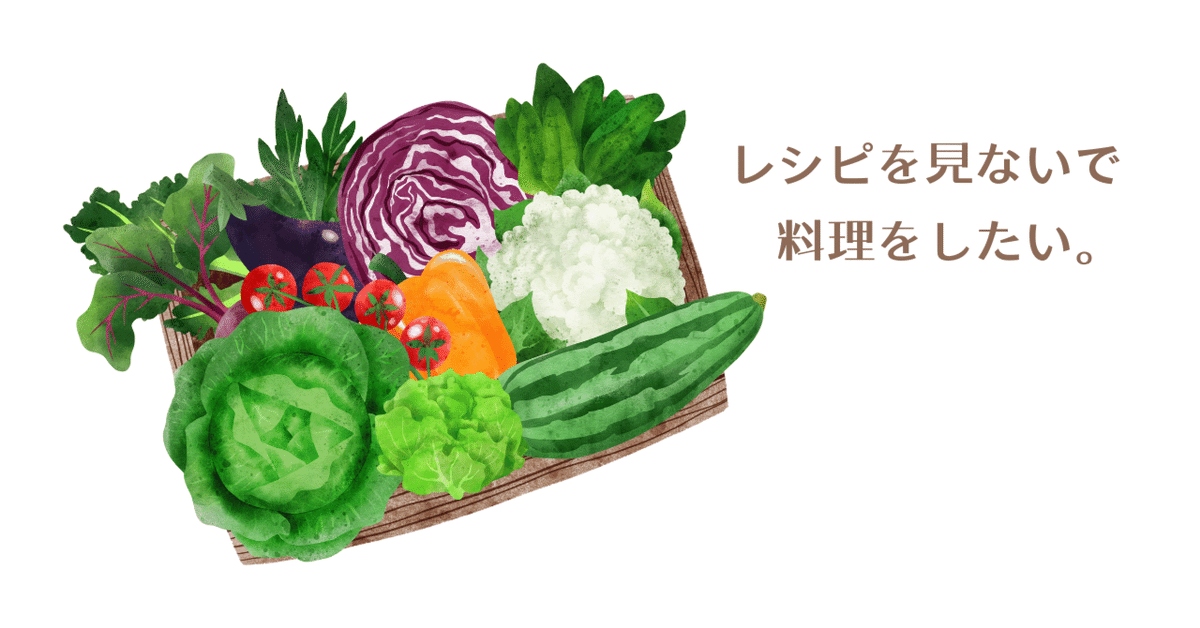
レシピを見ないで料理をしたい。 2024.5.17
『レシピを見ないで作れるようになりましょう。』(有元葉子 著)という本がすごくよかったという話。
私は衣食住で言うと、住→衣→食の順番で関心がある人間で、食の優先順位は最後だ。一般的に日本人は食→衣→住という感じの人が多いような気がするので、(完全な主観です)たぶんそこそこマイナーな方だと思う。
とにかく食については、長年そこまで強い関心がなく、もちろんどうせ食べるなら美味しい方がいいとは思うものの、そのための探究心というのはほぼなかった。ちゃんとしたものを食べないと体調が悪くなってくるので多少の気は使うけど、常にもっと簡単に栄養補給ができればいいのに、と思っている。ゼリーの完全栄養食とかできてほしい。
そんな感じだから、食はできるだけ手間なく、それなりにおいしく、健康に生きていけるだけのものを食べればそれで十分。そこにかける労力は他の部分に向けよう。そう思って35年間生きてきた。(あ、今週35歳になりました。)
料理はまあ下手ではないとは思っているけれど別に上手くはないし、何も見ないで作れるものは焼きそばとかパスタとかカレーとか、そういういわゆる名前のついた「メニュー」になっているものだけだった。あるものでちゃっちゃと手早くいい感じのものを作って組み合わせて出す、というスキルはあまりなかったし、またそれを身につける必要もない、と思っていた。
作りたくない日は買ってくるか外食すればいい。ミールキットだって簡単で美味しいものがたくさんある。出来合いのものでこんなに手軽にそこそこうまいものが食べられるのに、わざわざ自分でスキルを身につけてまで作る必要ある? そう思っていた。いままでは。
問題は、それだと、高いのである。
もちろん、食費が。
もうね、めっちゃ高いのよ、うちの食費! 夫婦2人と幼児食の子1人の家庭としては、たぶんべらぼうに高い。そんなに贅沢なもの食べてるというわけではないのに……。
理由はわかっている。
簡単につくれるものを、と思って宅配でミールキットやら冷凍ものやらの中間調理ものを軽率に買う。そしてそれを上手く使い切れていないのに、組み合わせを考えるのがめんどくさかったりで、すぐ外食とかテイクアウトをする。たまに野菜や肉を買っても定期的に作る習慣がないから余らせて無駄にする。冷蔵庫にあるものを忘れてまた買い、そして廃棄する……。
要するに、「簡単に、手間なく、必要最低限でいいや」をやっていた結果として、いろいろなコストが増しているわけである。本末転倒だね。
しかも、最近は子供がどんどんごはんを食べるようになってきて、レトルトや冷凍の離乳食でごまかせていた乳児期のようにはいかなくなってきた。食べムラもすごいので、外食も連れていくのもかなりハードルが高い。
そして悟りました。
料理の根本的なスキルを学ぶ時が来たのだと………。
ということで読んだのが、図書館でみつけたこちら。
ひっじょーーーーによかったので、あとから紙の本を買い直しました。
タイトルの通り、レシピを見ないで、自分の目と舌を使って、あるものを焼いたり煮たり揚げたり、シンプルに調理して食べるのがいいよね、というコンセプト。
ハンバーグ、オムライス、グラタン、みたいな名前のついた派手な「レシピ」ではなくて、野菜を美味しく焼くにはこうするといい、とか肉をうまく焼くにはこういう手順で、とか、料理の原型のような基本原理を教えてくれる、そういう本です。
こういうことが!!
知りたかったの!!!!
ってなりました。
いわゆるレシピ本ってさ、「なんでそれをするのか」をあんまり書いてくれないじゃないですか。まあそのメニューを美味しくつくる方法を無駄なく解説することがレシピ本の目的なので、仕方がないのかもしれないけど。
たとえば「野菜を切って、水にさらす」みたいに書いてあっても、「なぜその切り方なのか」とか「水にさらすのはなぜなのか」とか、そういう「理由」は教えてくれない。
違う野菜を使う場合も同じなのか、違うのか。調味料の分量はどのくらい調整していいのか。ないものは省いてもいいのか、だめなのか。そういった、何がクリティカルな手順で、それをしないとどうなるのか? というひとつひとつの工程が意味するところは、レシピを見て作っているだけだと理解するのは難しい。
もしかしたら、料理センスがある人はただレシピを見て作っているだけでも学べるのかもしれない。だけど、私には冒頭の通り食への探究心があまりないので、ただでさえ面倒くさい料理をしながら、その料理の工程から帰納的に原理原則を導き出して応用する、という頭の使い方をするなんてことは、やってやれないことはなかったかもしれないけど、負荷が高すぎたのだ。
日頃、インテリアのつくり方だとか、仕事だとかでさんざん抽象化能力を酷使しているので、料理くらいは演繹的にやらせてほしい。応用が効く原理を教えてくれ。完成した料理のレシピじゃなくて、それを構成するためのパーツを解説してほしい。
そんなふうにぼんやり思っていたところに、完全な回答が得られたので、にっこりです。
今週はこの本で仕入れた知識を元に、野菜をいい感じに焼いたり揚げたりしたものと、冷蔵庫に眠っているミールキットや冷凍の肉や魚を合わせてせっせと消費している。
ミールキットや半調理ものは基本的にたんぱく質に偏っているので、副菜がないと単体ではうまく1食になってくれなくて、せっかくあってもなんとなく使いづらくてずっと残ってしまっていた。それがこの本を読んだことで、「適当な野菜の副菜一品」を作ることのハードルがぐっと下がり、冷蔵庫の中身がうまく回せるようになってきた気がしている。
何よりも、「簡単にしたい、考えずにやりたい」と思いながらも毎日ごはんをどうするかに悩まされていたのが、今日はあの野菜を焼けばいいや、とぱっと決められることのストレスのなさといったら! こんなに楽になるならもっと早く学んでおけばよかったと思わなくもない。
35年生きていても、まだまだ新しいことを学ぶといろんな発見があるもんだ。
レシピを見れば作れるには作れるけど、レシピを探したり組み合わせを考えたりすることに疲れている、という方。おすすめです。
ということで、久しぶりの日記でした。
35歳の1年間もぼちぼち書くかもしれないし、書かないかもしれないけど、どうぞよろしくお願いします。
たのしいものを作ります
![早[SAKI]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/13256300/profile_38b09a3c49303381af3d68640c08d16e.png?width=60)