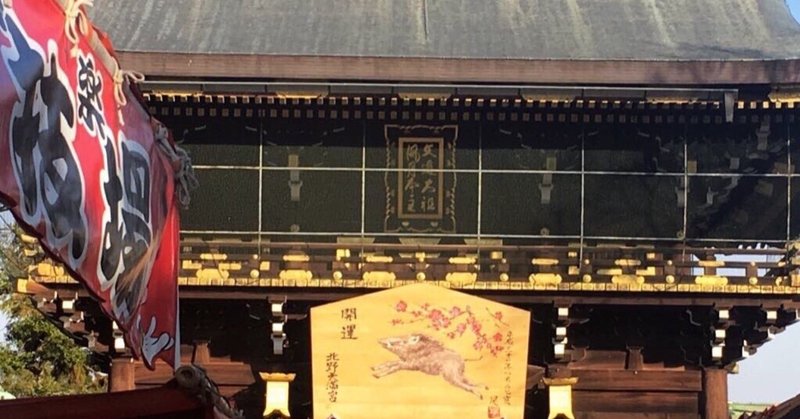
令和からの幼児教育 そして読み聞かせの夢
(この記事は2019年1月に書いたものを4月に修正しています。)
さて、最近は教育についての発信をあまりしてこなかったので、久々に私見を述べたいと思います。
ポスト平成(※執筆時)の幼児教育という題ですが、勉強が進むにつれてなかなかそういった大きな枠組みの話をするのも難しくなってきました。
日本の大きな動きとしては幼児教育の無償化がありますが、その件については多くの方が妥当な論拠を用いてメリット・デメリットを挙げてくださっているので、今後それを背景に妥当な運用がなされていくことでしょう。他にベターな方策はあったかもしれませんが、政権がそれを採用するインセンティブは恐らくなかったので、少なくともこのように予算が増えて注目されるのは肯定的に受け止めたいですね。ちなみに現場で聞いた面白い話としては、無償化に先駆けて料金を上げることで得られる補助金を増やそうとしている園があるとかないとか。賢く経営して、現場の待遇改善がなされればと願います。
幼児教育一般について考えた時、これはなかなか難しく、結論としてはそもそも人間というものの捉え方が今後大きく変わっていって教育は大混乱するだろうと考えています。
ちなみに最近帰省して、灘高校の近くにある本屋さんを覗いたところ、教育関係の陳列はこのようになっていました。

みんな天才を育てたいのだなと感じられます。これは素晴らしいことで、豊かな経験を得られる子どもたちが増えていくのでしょう。でも、それで親や教育者の期待通りになるのは遅くて20歳ごろまでだろうなという気がします。
その頃になると、人間性というものの相対化が今よりも進んでいて、過去を踏襲するようなキャリアや生活の設計はかなり非自明な選択になっているはずです。今でもその気はあるのですが、ポスト平成においてはそもそも人間として生き続けることが相対化できてしまうと予想され、さらにドラスティックな変化になるだろうと思います。肉体を持たず社会と関わる手段は確立していますし、隣国では遺伝子操作ベビーも産まれました。私が私であるとはなんなのか。それを産まれたときから考える世代を、どう教育するかというのがこれからの議論になります。
と小難しいことを言いつつ、日常的にはより豊かな成長環境というものを地道に考えていくことになります。読み聞かせはかなり質の良い経験ですが、そこに成功体験を得られる仕組みがあればより豊かになるかもしれません。
ということで昨年ずっと、みつけた!カードというのを導入していました。これは、読み聞かせ中に面白いポイントを見つけたらみつけた!と挙手してもらって、みんなの前でそれを発表してもらい、できたらカラフルなカードをあげるというものです。外的な動機付けなので一長一短だなと思いつつ、僕としては絵本の細部まで楽しんでほしいと思い、それを続けていました。すると5回目くらいから、こちらがカードを用意していかなくても、自分たちで見つけた!と言ってくれるようになったのです。見つけるポイントもどんどん多様になっていき、効果としては期待以上どころではありませんでした。おそらくこれは、カードを渡す際に逐一大げさに褒めて感情を高め、外的要因にとどまらない成功体験へと昇華できたことが効いています。そしてやはり絵本そのものの魅力も大きいでしょう。
このチャレンジを続ければ、子どもたちが絵本の絵画表現に対してより繊細な感性を持つことができるようになり、ひいては将来の彼らによって面白い表現が世界にたくさん生まれることを、僕は夢見ています。これからも研究を続けていきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
