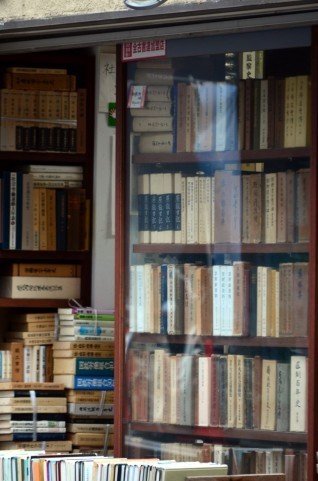
聖書や日本書紀、平家物語などを読みながら、「日本」について外国人に説明するにはどうしたらいいかとか、農村部の論理と都会人の論理がどう違うかと言ったことについてのヒントを考えていま…
- 運営しているクリエイター
2019年8月の記事一覧
古事記の神統譜は日本書紀第二別伝、第四別伝を「合成」した形になっている
古事記本文の書き出しは、日本書紀第四別伝の後段とほぼ同じであると述べました。
この後、古事記本文は以下のように神々の名を記しています。
次に国稚く浮かべる脂の如くしてくらげなすただよへる時、葦牙の如く萌騰る物によりて成れる神の名は宇麻志阿斯訶備比古遅神。次に天之常立神。
次に成れる神の名は国之常立神。次に豊雲神。
この順序は日本書紀第二別伝に似ています。
第ニ別伝はこう記します。
古に
神々の「進化」を記す「平家物語神学」
平家物語巻11第107句「剣の巻」は、以下のような神々の系譜を載せています。
それ神代と言うは、天神のはじめ、国常立尊は色はありて体なし。虚空にあるごとく、煙のごとし。
国狭槌尊より体はありて面目なし。豊斟渟尊より面目ありて陰陽なし。第四より陰陽ありて和合なし。埿土煑尊埿土、沙土煑尊、大戸之道尊、大苫邊尊、面足尊・惶根尊等なり。
この系譜は、日本書紀本文と一致(独り神に関する限り、第一別伝とも
中世における日本神話~平家物語が語る「草薙の剣」
平家物語巻第11第107句「剣の巻」は、壇ノ浦の戦いで海中に没した三種の神器のうち、「草薙の剣」について述べています。
この部分の記述は、当時の人たちに、日本神話がどのように受容されていたかを知る貴重な手がかりのように思われます。
剣の巻は、草薙の剣が登場するまでの経緯についてこのように語り出します。
それ神代と言うは、天神のはじめ、国常立尊は色はありて体なし。虚空にあるごとく、煙のごとし。








