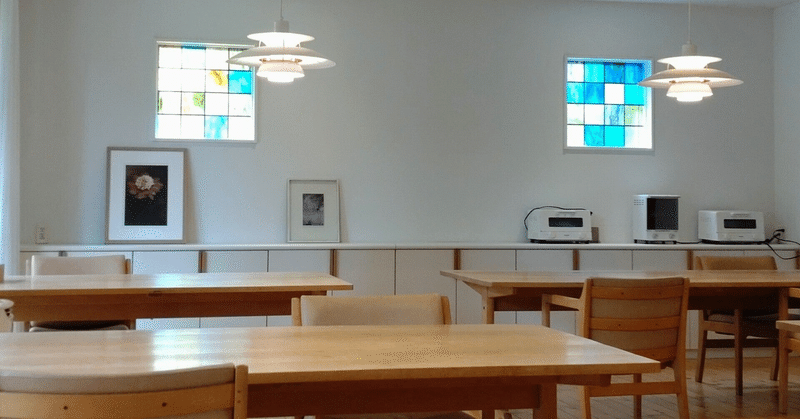
実話怪談 第二十話 「助六寿司」
数年前の4月に羽柴さんの祖母が長い老人ホーム生活の末に誤嚥性肺炎で亡くなった。94歳の大往生だったそうだ。
その頃は既にコロナが流行しており民営の斎場で大勢の人を呼ぶことはできないので、火葬場が併設された市営の葬儀場で家族葬をする事になった。
祖母は生前交流が多く、コロナ禍とはいえもしかしたら近所の人が来るかもしれないという事で、家族分以外に余分に仕出しの助六寿司を用意していた。
しかしやはり厳戒な外出禁止が呼びかけられていたためか誰も参列者が来なかったので助六寿司が余ってしまった。
通夜の晩、遺体への付き添いは父親と叔父夫婦がするというので、羽柴さんはその晩自宅に帰る事にした。その際に「これ余ったから、今日の夜と明日の朝食べなさい」と、父親から助六寿司を2パック渡された。
羽柴さんは火葬場から自宅まで帰る時、来た道と別の道を行かないと死んだ人がついてきてしまうと考えていたため来た道と別ルートで帰ろうとしていたそうだが、その時に限ってナビが上手く作動せずに火葬場周辺の道を何度も行ったり来たりと繰り返してしまう。
火葬場など滅多に来る場所ではなく、来た道以外のルートが分からなかったのでナビに頼る他ないのだが、一向にナビは同じ場所を何度も案内する。
路肩に駐車して考えあぐねいていたが、結果として「途中にあった大型スーパーに寄ってそこでお酒を買おう。そうすれば来た道とは違うはずだし大丈夫だ」と思いたち、近くのスーパーを目的地として登録した。
するとそれまでの挙動が嘘のようにすんなりとナビの案内でスーパーに辿り着くことができ、そこで度数の弱いチューハイを1本買って帰った。
帰宅してから翌朝食べる分の助六寿司を乾燥しないように新聞紙で二重に包みダイニングテーブルの上に置いておいた。まだ涼しい季節で傷む事はなく冷蔵庫に入れて固くなるよりは良いと思ったのだ。
その晩の内に食べた助六寿司は、太巻きのかんぴょうの味もよく染みており玉子も出汁が効いていていた。
稲荷は甘い味が控えめで「葬儀会社もいい仕出し屋と契約しているな」と感激する程美味しい助六寿司だった。
そしてシャワーを浴び、アルコールの入った羽柴さんはゆるりと眠りに就いた。
翌日の朝食ははまた昨夜持ち帰った助六寿司。
2連続だったが嫌な気分はせず、昨日食べた味が忘れられなかった彼女は寧ろ楽しみにしていた。
包んだ新聞紙を外し、太巻きを一切れ口に運んだ。
ところが、何の味もしない。
お寿司自体がパサついていたり傷んで味が変わっているのでもない。
もちろん流行病に罹ったというわけでもなく、味がなくなり食感だけが変わらないのである。
稲荷の方も同じで、全く味がしない。
味が抜け落ちた助六寿司を目の前に羽柴さんはなぜこんなことが起こったのかと首を傾げた。
しかし、すぐに一人の顔が思い浮かんだ。
それは亡くなった祖母の顔だった。
祖母は94歳と大往生だったが、晩年は老人ホームで寝たきりの生活をしていた。
吐き出す力も飲み込む力も弱くなってしまい、何も食べることはできず点滴で栄養を摂り「生かされている」だけの状態であった。
そんな祖母は生前食べることが大好きだった。
とくに寿司が大好きでまだ元気に動けていた頃、家族で外出すると必ず外食に寿司を所望するほどだったのだという。
「おばあちゃん、一緒に帰ってきて食べたのかな……」
昨晩祖母は羽柴さんの運転する車に乗って最後に家に帰ってきたのではないか。
ナビが上手く作動しなかったのもそのせいだったのかもしれない。
そして大好きだった寿司を食べて天国へと旅立ったのではないだろうかと、生前美味しそうに寿司を頬張る元気だった頃の祖母の姿を思い出していた。
羽柴さんはその日も前日と同じルートで火葬場へ向かい、葬儀、火葬、を済ませて、帰りは父親の先導で違う道で帰ってきたそうだ。
以来、羽柴さんの家でおかしな事は何も起こっていないという。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
