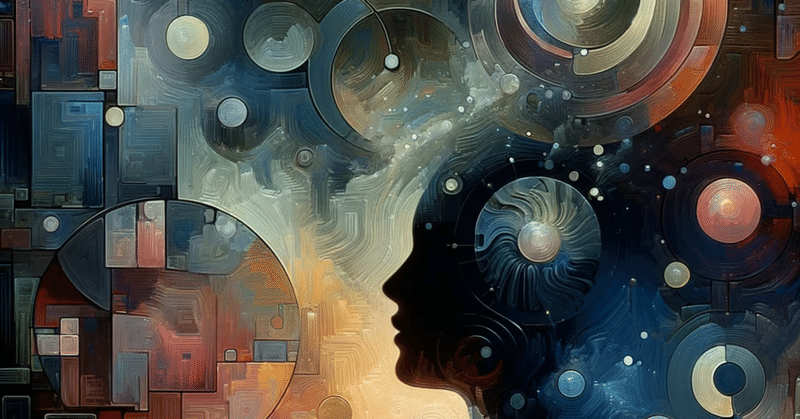
『痛みと悼み』 四十
いつもゆるぎのない自信と温かさと信仰の確信を持って、人を叱り導くのが牧師の仕事で、聡二さんだと思っていた。
「小さい頃から、そうだった。僕にはできない。この家を守ることは、少しではない血が流れるかもしれないと思った。僕には耐えられない。」
「それは、比喩として。」
「そう、資本主義的比喩として。」
めぐむには正確にはその意味は分からなかった。資本主義的に、家産を守るためには、人の血が流れるということ、それはある意味で残酷なことで、その残酷さを冷静に見つめる冷たく凍った心が必要なのだろうか。多恵さんは、それを自分の血で、最後に贖った。
多恵さんが持っていたもので、聡二さんには無かったもの。
聡二さんにはあって、多恵さんにはなかったもの。
聡二さんが黒いシミになることはないのだろうか。人は誰でも黒いシミになる可能性があるんじゃないか。
「僕は、多分、行方の知れない父親に似ているのかもしれない。同じように母から離れたことも皮肉なことだと思う。母には、それが重なって見えたのかもしれない。そして、自分の行く末の形が見えたのかもしれない。具体的じゃないとしても、何かの影絵のように。そんな母を支えてくれていたのが、あの本なのかも。」

自分のある意味の強さ故に、人が離れていく。多恵さんはどう思ったのだろう。強くなければ生きていけないときに、強さ故に否定されるとすれば、多恵さんの心は、その瞬間、深い暗闇に沈んだと思う。そして、その暗闇の中でも、強く光る多恵さんの目をめぐむは想像した。目眩がして、暗い部屋で目だけが光っていた自分の姿が脳裡に浮かぶ。深い沼にはまり込んだ同類の二人。
めぐむの物思いに何かを感じたように、聡二さんが務めて明るく言う。
「兄の方が、その強さを持っていた。双子でも大違いだ。」
「でも、瑛一さんも、お母様から離れていった。」
「それは、兄なりの復讐だったと思う。自分の資本主義的な血に目覚めたことの。」
血を見ることに苦痛を感じない、血を見ることで闘争心を沸き立たせる種類の人たち。それは、ある意味、天性の資質なのかもしれない。資本主義に祝福された人たち。その血で走り出し、止まることを知らない人たちは、脇目も降らず、資本主義的な増殖ゲームに突き進む。口座の、あるいは決算書の資産が増えることに、垂涎の喜悦を覚える。寝ているときすら、頭の中では資本主義のゲームの戦略を考える。遠い遠い所までたどり着いて、振り返ったときに、羨むような資産と誰も後にはついてきていない空白に気づく。瑛一さんの家族を想像して、そこに奥さんらしき女性と小さな男の子がいるのに顔は白くてのっぺらぼうに見える。
「瑛一さんには、ご家族がおられるのですか。」
何かを吐き出すように大きな息を一つして、聡二さんは、顔をしかめる。
「結婚したがね、別れたよ。だって、地球が回り続ける限り、世界中のマーケットとともに24時間戦っているような生活をしているからね。それは、家族もたまったものじゃないだろうなあ。」
あの立派な富永のお家にお邪魔したときの、時間を惜しむように時計に目をやっていた瑛一さんが浮かぶ。そう言われると、他のプレーヤーが走っているときに、それを指を加えて見ている時間の無駄に、悔しさを滲ませていたように思える。
「遅く結婚してまだ小さな男の子が一人いるが、母親が引き取って暮らしている。養育費は十分に渡している−そのくらいしか兄にはお金の使い道がないからね−が、会うこともないそうだ。時々、その子が黙ってこの教会にくるんだ。」
「そのお子さんは、お父さまに会いたがっているのですか。」
「多分、そう思うよ。でも、兄の方がそんな状態だから、それでこの教会にくるのかも知れないね、何か思いたいときに。双子の弟は、そういうときにはありがたい父代わりの存在かも知れない。」
聡二さんは、またため息をついて、次に反動のようにめぐむに微笑む。
