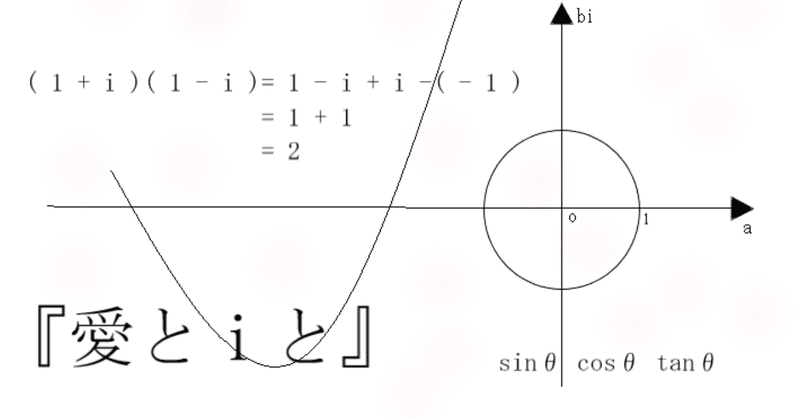
連作短編『愛とiと』3-後編
そして放課後、何故か私は野球部の部室にいた。
「氷山さんって転校生に案内とか買って出るのね」
マネージャーだという斉川が目の前で書類仕事をしている。すなわち、楽の入部届を確認して部員名簿に追記している模様。
「意外と面倒見いいんだ」
「買って出たと言うか、頼まれて断る理由がなかったと言うか……斉川こそよくマネージャーなんてやってるわね」
「やってみると面白いよ。敵も増えるけど」
「敵?」
すると彼女は「敵」のモノマネを始める。
「斉川さんって、いつも男の子にちやほやされてるよね? ねえ、そういうの恥ずかしくないの?」
「……くだらない」
「氷山さんならそう言うと思った。そもそも、ちやほやされる余裕なんかないんだよね」
斉川綾乃の第一印象を「ぶりっ子」と捉えてしまうのは女の性かもしれない。しかし、黙っている時に唇をきゅっと締める癖も鼻に掛かった甘え声も意図的でないことは話していれば分かる。何より彼女はきちんとマネージャー業務をこなしている。
「ねえ、氷山さんと荒木くんってどういう関係?」
「え?」
「初めて会ったわけじゃないでしょう?」
……まあ、見ていれば分かるか。
「中学の同級」
「え、でもあの人大阪から来たんじゃ」
「本人も言ってたでしょう。チャキチャキの江戸っ子だって」
楽が大阪にいた期間は私の知る限り、二年に満たない。二年前は東京に住んでいたのだ。
「それだけ?」
「だけ」
「ふうん。じゃ、枦田くんは?」
「……え?」
「氷山さんと枦田くんはどういう関係なの?」
斉川の意地の悪い笑顔を見て、これが「本題」なのだと分かった。だから仁と楽をさっさとグラウンドに向かわせ、私を引き留めて書類仕事を始めた。
「どういうって、隣の席のよしみで……」
「隣の席に座ったら、もれなく氷山さんのモーニングコールがもらえるの?」
「は?」
「だって、枦田くんの寝坊がなくなったのってそういうことじゃないの?」
「あたしが叩き起こしたのは隣の席で寝てた時だけよ。そんな、朝から電話で起こしてあげてるような言い方しないでくれる。仁に失礼だわ」
あの男は、きちんと自分で遅刻癖を直しに掛かっているのだ。
「でも野球部的には枦田くんの朝寝坊って、何て言うか……必要悪? みたいなところがあったんだよね」
「どういう意味?」
「枦田くんってウチで一番足が速いの。あれだけ毎朝走り込んでれば、そりゃ自然と鍛えられるよねって意味」
夏の大会は一番ショートだと、何故か得意げに斉川が言う。
「一番にしては出塁率が悪いんだけど。あの足を活かすならまずは打って出てくれないと」
「……練習すればいいんじゃない?」
「なるほど。正論だ」
最後に書類をファイリングし直して、ここでの業務は終わったらしい。
「そろそろ帰っていいかしら?」
帰るタイミングを失っていたが私は部外者である。これ以上この場に留まる理由はない。
「待って。じゃあ、最後に一つだけ」
一つと言ってから絞ったのだろう。次の質問までは少し、間が空いた。
「……氷山さんがマネージャーだったら、練習に来ない選手に対してなんて言う?」
最後に捻り出した問いがそれでいいのか。と、思ってから例の優等生もどきの存在を思い出した。
「言葉なんか要らないわ。張り倒してやればいい」
「え、でも」
「あたしだったらそうするって、言ったのよ」
「……そっか」
斉川綾乃は笑った。
ぶりっ子なんてとんでもない。今にも泣き出しそうな痛々しい笑顔だった。
「二つ、聞きたいことがある。」
仁がなかなか生意気な面をして私を見ている。
「前以て質問を整理して置くことは大切ね」
けれど野球部員たちの邪魔が入らないように時間を引き延ばしたのはよろしくない。彼だって部活動が控えている。
「一つ、斉川と何を話したんだ?」
「それは……あなたに関係のないことでしょう?」
「関係ないかもしれないけれど、気になる」
正直な男である。
「そうねえ、遅刻癖は必要悪だって話とか?」
「は?」
間の抜けた表情。私は男のこういう顔が好きなのかもしれない。幸せそうな寝顔とか、起き抜けの虚ろな瞳とか、そういう隙だらけの部分が。
「答えたわよ。二つ目は何?」
「……荒木って氷山にとって何なの?」
私は笑い出したい衝動をこらえるのに必死だった。
「それこそあなたには関係ないでしょう?」
「いや、関係はあるんだ」
「どうして?」
「……俺が、氷山のことが好きだから」
限界だった。
可愛い。可愛すぎる。何なのこの男は?
「どうしよう。最高なんだけど」
「え?」
「その質問、端的に答えるなら楽は中学の同級生よ」
「うそ」
「嘘じゃないわ。転校先に知り合いがいたから気安いってそれだけでしょう」
関西弁で江戸っ子だと言い張った謎の自己紹介のおかげで説明がしやすい。
「で、でも氷山ってさ」
「何よ?」
「なんというか……知り合いだからっていきなり話し掛けられるタイプじゃなくない?」
なるほど。仁の精一杯のオブラートは伝わった。
「中二の時にもあれと隣の席になったことがあるのよね」
当時の楽が置かれていた状況を「いじめ」ととるか「タチの悪いいじり」ととるかは彼自身の認識にもよるだろう。どちらにしてもセンシティブな問題だから、私がペラペラと話すのは気が引けたのである。
「そのセンシティブな問題と氷山がどう関わってくるの?」
「いや、あたしがその……現場を『うるさい』って一蹴しちゃったことがあって。それで懐かれた感じかしら」
クラスの人間関係に興味のなかった私には怖いものがなかった。
「好きなのに入りそびれたっていう野球部に一緒に乗り込んであげたら、あとは勝手に白球を追いかけてたわ」
楽が私よりずっと社交的な人間であることは見れば分かる。というかそもそも、いじめられるタイプの人間は他者と関係を築く意志があるのだ。私みたいに他人に興味がなければ孤立してもダメージを食らわない。
「そんなこと言って、氷山だって他人に興味がないわけじゃないじゃん。そういう風に強がるのはよくないと思う」
「それは……その通りかもしれないわね」
楽に勉強を教えてあげたこともある。彼の目まぐるしい成長はなかなか興味深く、私は自分が思いの外お節介な人間であることを知った。私の世界は単位円ほど狭くない。
仁は腑に落ちたんだか落ちないんだか分からない様子でもう一つだけ、と質問した。
「あいつのこと、楽って呼んでるのは何で?」
結局、噴き出してしまった。
「あなた、あたしの名前知らないの?」
「氷山だろ?」
「そうじゃなくて」
私のことが好きなら名前くらい覚えときなさいよ。
「アラキ」
「え?」
「新たな希望で新希。あたしの名前は氷山新希」
仁がへなへなと笑い出す。
「そりゃ、アラキとは呼べねえわ」
「まったくよ、仁!」
彼のフルネームはもう分かっている。それでも私は、きっと今後も彼のことをジンと呼ぶ。
〈第三話、了〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
