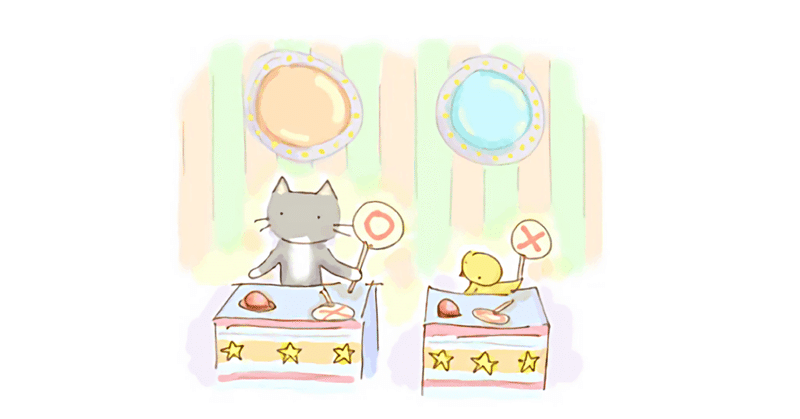
正しいことから少し離れる
*さくらもちさん、ステキな画像をありがとうございます。
問い、「Question」の語源はラテン語のQuest「探し求める」とion「こと、もの」だそうです。
今の時代のリーダーは正しいことを知っている人ではなく、まさに、常に自分や周囲の人に対して、「Question」を投げかけられる人、だと言えます。
不透明な未来に対して、自分たちが新たな行動を起こしていけるよう、効果的な「Question」を投げられる人。
私たちは起きている間中、無意識に自分にたくさんの問いかけをしています。
「大丈夫だろうか?」
「もし失敗したらどうしうよう?」
「みんなに、どう思われるだろうか?」
こんなふうに、受け身の問いを多く自分にしている人がいます。
そして正しい答えを出そうとして動けないでいる人がいます。
受け身の問いはいつも同じパターンで、新たな問いが生まれることは、まずありません。
どうしたら、新しい自分を行動につなぐような「問い」が立てられるのか。
マサチューセッツ工科大学のリーダーシップセンター所長のハル・グレガーセン氏はこんな事を言っています。
どこから見ても「正しい」あるいは「正しい」と見られる人間であろうとすることほど、問いにとって、有害なことはない。私たちは自分が正しいを信じきっていたり、早く決定をくださなければいけないと思い込んでいると、手近になる答えに飛びつき、それ以上、問おうとしない。新しい発見のプロセスを開くことを拒み、周りにもそれを閉ざすよう圧力をかける。
私たちは「一見正しいこと」が好きで、その罠にハマると問いを捨ててしまう、ということです。
特に「自分は正しい」と思っている限り、残念ながら、他者に対しても自分に対しても、新しい「問い」は、いっさい生まれません。
したがって、新しい発見もないのです。
いえいえ、自分は自信などなくて、自分が正しいとは思っていません、という人もいるでしょう。でも「自分には自信がない」ことを1mmも疑わない、つまり自分の考えは「正しい」と思っていないでしょうか?
この本の中では、有名なコダック社の倒産(2012年)についても触れています。
命令はできても、「問い」を立てられなかったことが最も大きな原因だと。
コダック社はカメラとフィルムのぶっちぎりトップだった会社です。130年の歴史を持ちながら、あっけなく倒産したのはなぜか、多くの識者がその理由を論じています。
これも、対立を歓迎しなかった、つまり正しいと思われる一つの答えに執着していたコダックの姿が表されています。
対立を歓迎し受け入れ、当たり前の前提として、その上に新たな「問い」を作ることができたら、もしかしてコダックは倒産しなかったかもしれないのです。
対立を恐れず、自分は間違っているかもしれない、そうやって「正しいこと」から少し距離を置く、
または、正しいか間違っているか、ではなく、
美しいか美しくないか、
心地よいか悪いか、
好きか嫌いか、
と、いろいろな物差しを持ってきていろいろな角度から「問い」を立てる、
そんなことをできる人が現代のリーダーなのかもしれません。
もちろん、自分の人生のリーダーは自分であるはずだから、
自分をどう活かすのか、自分にどういう問いを投げるのか、
「あなたは、どうして自分ができないと思っているの?」
「あなたは本当は何がしたいの?」
「あなたにとって大切なものって何?」
「なぜ、それが大切なの?」
「あなたにとっての価値とは何?」
「なぜ、それに価値をおくの?」
「いつからその価値観を持つようになったの?」
「その価値観は今のあなたにとって、どんな役目を持っている?」
そんなたった一つの質問から人は考え始め、つまり求めはじめ、そうして「新しい答え」を生み出し行動してゆくのです。
探し求めることがQuestionの語源、
自分も探し求めることをやめない、相手にも探し求め続けるためのお手伝いをする、
それがサポーターの最も大きな役目だと、私は思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
