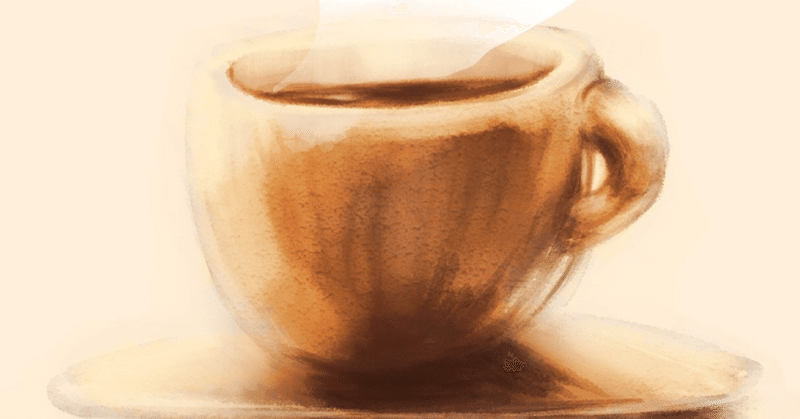
幽霊執事の家カフェ推理 第四話・マーメイドのパルフェ11
外からは離れの室内は見えない。ある程度の音も、遮られている。
しかし、複数の人間が言い争う声はかすかに聞こえてきた。
様子をうかがっていた香苗は、そっとその場を後にしようと歩きだした。
突然そこへ、見知らぬ男が現れた。燕尾服を着た、若い男だ。
服装のせいか、現実感がない。異様な雰囲気だった。
人が歩いてくる気配はまったくなかったのだが、彼は壁が現れたように断固として立っていた。
香苗は不気味に感じて背を向けた。しかし、男は彼女の前にまた現れた。
「どちらに行かれるのですか?」
香苗は、ひっと息をのんだ。そのまま男に気圧されして、後ろ手にドアへと戻っていく。
何の前触れもなく逃げ込むように離れへ入ってきた香苗に、塔子たちは驚いて振り返った。
香苗自身も、塔子たちがいることにびっくりしたようだ。だが、彼女はこの離れ自体には来慣れているように見えた。
塔子はこの時点ではそこまで気づかずに、漠然とした違和感だけを抱いた。
室田が、あっと声をあげた。
「あ、あの、これは」
言いかけた彼を、香苗はキッと睨みつけた。
麻美は初め、香苗がイヴを助けに来たのだと思った。
「香苗さん」
安心したような麻美の声を聞いたとき、塔子はまた何か違うものを感じていた。
香苗は何かに押しこまれるような形でここに入ってきた。そのとき一瞬だが、恐怖の表情が見えた。彼女は何を恐れたのか。
それがわかったとき、塔子はすべてを悟った。
だが塔子が何か言う前に、室田がうろたえてしゃべりだした。
「わ、私が彼らを呼んだわけじゃない。信じてくれ」
明らかに香苗に向かって言っている。
香苗は室田に対してため息をつくと、ソファに座るイヴをちらりと見た。
その目があまりにいつもと違うので、隣にいた麻美は驚いた。
室田は必死に香苗に訴えかけていた。
「なぜか知られてたんだ。でも私は、約束は破っていない。もちろん、イヴくんを殴ったりもしてない」
イヴが頭を押さえてうつむいているので、誤解されまいと弁明しているようだ。
「殴るよりひでえことしてんじゃねえか、てめえはよ!」
大志がまた怒鳴った。が、つかみかかる様子まではないので、塔子はそのまま黙っていた。
「何なんですか、約束って・・・」
麻美が怯えた声で言って、香苗と室田を交互に見た。
塔子は息をついて答えた。
「イヴくんがなぜハチミツをあんなに怖がるのか、ご存知なんですよね。香苗さん」
麻美だけでなく大志も、塔子の言葉にえっと息をのんだ。
塔子はズキズキ痛む頭をなだめながら、続けた。
「室田さんのイヴくんへの仕打ちは、単なる性的虐待ではありませんよね。あなたがイヴくんを室田さんに売っていた。違いますか」
麻美も大志も、信じられないといった顔で香苗を見た。彼女のイヴに対する献身ぶりは誰もが知っていたのだ。
「・・・最初は、ココアで寝かせてたのよ。その方が本人も楽だしね」
香苗は観念したのか、いつもより低い声で言った。これが、彼女の地声らしかった。
「でも、そのうち知恵つけたのか飲まなくなって。その男も、起きてないと人形みたいでつまらないって言いだしたし」
香苗は忌々しげに室田を見た。室田はその眼差しが心外だと言わんばかりに目を見開いた。
「金額に見合う価値を求めるのは当然だろう。私がいくら払ったと思ってるんだ。今日だって、一枚脱ぐのにあんなに手間かけさせて・・・あんたがしつけてないからだろ」
麻美は身を震わせて、室田とイヴを交互に見ていた。塔子は、イヴがココアは眠くなるからいりませんと言っていたのを思い出した。
初めは睡眠薬を仕込んだココアを飲ませて、室田に預けていたのだろう。それなら何をされたか本人は覚えていないし、騙せると甘くみていたが、そのうちイヴはいつもココアで眠くなることに気づく。
ココアを拒むようになったイヴに対し、ついに香苗はそのまま室田に売り渡すという暴挙に出たのだ。
「そういえばイヴ、仕事がまだあるってカフェに来なかったことがある」
大志が絞り出すような声で香苗に言った。その目つきに、香苗は後ずさった。
「食堂終わったのに、変だなと思ったんだ。あんた・・・仕事って言って、こんなことやらせてたのか?」
彼の手が、爪が白くなるほどきつく拳をつくっているのを塔子は見た。
大志はイヴを見下ろしたあと、香苗と室田をまとめて睨めつけた。
「あんたら、イヴの前で自分が何言ってるか、理解してんのか?どうせこいつはわかんねえと思ってんだろ。こいつになら何しても、何言ってもいいって。その根性が、一番許せねえんだよ」
室田は目を伏せ、香苗は荒々しくため息をついた。
「何のために?何でこんなこと」
麻美が泣き出しそうな声で香苗に訊いた。キャリアもあり、いつも美しくキラキラしている香苗は、お金にも困っていないはずだ。
「もちろんビジネスもあるわ。この人は払いがいいからね」
「ビジネス?!」
声を荒げた大志を無視し、香苗はバレたくなかったからその分上乗せしてたんだろうけど、と低くなった声で毒づいた。
それから、ふっと遠くを見るように窓のない壁を眺めた。
「でもね。一番の理由は、均さんと幸せになるためよ」
その言葉に、誰もが当惑した。
香苗は、その奥に天国があるかのように天井を見上げていた。
「私は、愛されたいの。均さんに大切にされて、二人で生きていきたい。それだけの価値がある女よ」
彼女の声は、いつも塔子たちが聞く美しい音色に戻っていた。 だが、すぐにそれは金切り声に変わった。
「この私が、母親になるわけないじゃない!ましてこんな、いい年の障害者!社会のお荷物が、少しは役に立ったんだからいいでしょ」
塔子は呆然と香苗の叫びを聞いていた。
「私はね、均さんの唯一無二の相手よ。クリスマスイヴを結婚記念日にして、毎年毎年、幸せを重ねていきたい」
にも関わらず、その日はイヴの誕生日でもあるのだ。
「そいつのことを考えなきゃならない記念日なんて、地獄でしかないのよ」
憎々しげに指をさされ、イヴはまばたきして隣の麻美を見た。麻美は目を潤ませて首を横に振ると、イヴの手にそっと触れた。
香苗はつき続けてきた嘘を脱ぎ去り、本心を吐き散らかしていた。
「私がママの代わり?冗談じゃない。私は、彼が選んだたったひとりの女性。私たち二人の世界に、そいつは邪魔なの。精神を病んで、さっさと施設にでも入ってほしかったのよ」
香苗にとって室田の存在は、願ってもない幸運だった。その誰にも言えない趣味を見抜いた彼女は、彼をそそのかしてイヴを売った。
イヴの心に深い傷を負わせ、トラウマを植えつけるためだけに。
とても普通には生活できない精神状態になるまで追いつめて、均の、いや香苗にとっては彼女と均の家から、追放するために。
眠っている間に何が起きていたのかも、動画を見せてやるつもりだった。このことがパパを悲しませる罪であり、イヴがどんなに汚れたのか、懇切丁寧に説明しながら。
彼を、壊すために。
この点についてだけはココアを飲まなくなったことで手間が省ける、香苗は平然とそう言った。
「もうやめてあげて!」
麻美は叫んだ。
「香苗さん・・・あなた、何言ってるんですか?」
イヴの背中を撫でながら、泣き声で訴えた。
「あなたに何がわかるの」
香苗は穏やかな笑みすら浮かべていた。
「毎日毎日こいつのお守りをして・・・均さんと過ごす何倍もの時間よ。外でも、いい母親を演じなくちゃいけない。嘘をついて気を遣って。気が狂いそう」
またその声が高ぶり始めた。
彼女がやってきたことの辛さは、塔子にもまったく想像できないわけではなかった。自分が同じようにできるかと問われたら、イエスとは言い切れない。
でも、と塔子は思った。
絶対に共感はできない。
「均さんと結ばれるために、私は必死でやってきた。それなのに・・・!この気持ちを少しでもわかろうとしたことがある?いらないのよこんな子!室田がどう遊ぼうと傷つけようと、知ったことじゃないわ」
一気にまくし立てた香苗の声が響き終わると、室内に静寂が訪れた。
それを破ったのは、入り口から聞こえた声だった。
「ぜひ、知りたいね」
呆然とした顔で均が入ってくるのを、塔子たちは驚いて見つめた。
なぜ彼がここにいるのか、わかる者は誰もいなかった。
途端に香苗は真っ青になった。
均の惚けたような目は室内を見渡し、泣き出した彼女を通過して、最後にイヴに止まった。
イヴは均に気持ちを読ませないかのように、険しくも柔らかくもない透明さで彼を見つめ返していた。
そのあまりに澄んだ瞳から、均は何一つ見抜けずにいたのだ。
イヴが一生懸命に伝えようとしていたことも、自分が知らず知らずのうちに、香苗に理想の女神像を押しつけていたことさえも。
自分が思うのと同じように、香苗もイヴを大切にしてくれると思い込んでいた。他人の子ども、それも障がいを抱えた成人男性を、実の親と同じ温度で愛することがどれほど難しいか、考えもしなかったのだ。
また、香苗が法外に高価なバッグを持っていても、ブランドなどさほど知らない彼には気づきようもない。彼女が会うたびに新しい服を着ていても、違和感はなかった。むしろ自分に会うためにおしゃれしてくれていると嬉しく感じていた。
働く女性の収入事情がどれほどのものなのか考えたこともない均は、それらがとても普通に買えるものではないということを知らずにいた。
すべて、息子を売って稼いだ金から出ていたのだ。
均は、もはや自身を糾弾するより他に、なすすべを持たなかった。
突然、大志が口を開いた。
「イヴ、言ってましたよ。この世界は優しいってパパが言ってたから、怖がらずにお仕事がんばるって」
その声は怒りに震えていた。
塔子は慄然とした。父親の言葉は、イヴの心に温かく残っていたはずなのだ。それをまさか、彼自身を食い物にする場所で聞くことになるとは。
大志は、均を臆することなく見据えた。静かに抑えた声で続ける。
「こいつ・・・この子の体には、発疹がいっぱいあるんすよ。アレルギーなんかじゃない、ストレスだ。お父さん、あんた・・・知ってました?イヴと風呂に入ってやったことありますか?」
均は、自分が注いできたイヴへの愛情が足元から崩れゆくのを感じた。
香苗は血の気の失せた顔で均を見つめ続けたが、もう彼と視線が交わることはなかった。
大志は悲しそうにイヴを見下ろした。
「こいつ、いつもリトルマーメイドの英語を暗唱してるんですよ。俺にはさっぱりわかんないけど。・・・子どもの頃の思い出だからだよ」
均はうめいた。
「覚えています。この子は、リトルマーメイドの絵本が大好きでした」
発達の遅いイヴに、均は亡き妻とともに根気よく絵本を読み聞かせていた時期があった。細かいストーリーはイヴにはわからない。それでも、両親が注いでくれたぬくもりは覚えていたのだろう。イヴは嬉しそうに、絵本を読んでと繰り返しせがんだ。
均は、妻のジェニファーが彼にかけていた言葉を思い出した。
「ほら、このマーメイドも脚の代わりに尾ひれがあって、イヴやママたちと違うでしょう?でも、ちゃんと人間と仲良くできるの。だからイヴも、他の人と違っていていいんだよ」
彼女はイギリス人で、よく英語の本を読み聞かせながらイヴにいろいろな話をしていた。
均はあてのない懺悔をするように、思い出をイヴに向かって話し続けた。イヴは首を傾け、パパ、と呟いた。いつもより難しい言葉を使う均の話を、どこまで理解したかはわからない。
塔子は思う。どう見てもイヴは外国人には見えない。派手さはないが端正な、日本人らしい顔立ちだ。
でもその目は、時々透明な青みを帯びる。
「イヴ・・・。私は、何も見えていなかったんだな」
均は震える声で言った。大志はまだ険しい顔のまま、頷いた。
「そばに、行ってやれよ」
彼の荒い言葉を気にする者は、もはや誰もいなかった。この瞬間、彼は絶対的に正しかったからだ。
均はしっかりとした足どりでイヴに近づいた。それから彼の前に膝をついて、彼を抱きしめた。
「ごめんな、イヴ」
均はそれ以上、説明も弁解もしなかった。イヴはいつものように、透き通った目をぱちぱちさせていた。
その夜、白い羽根のような粉雪が降った。それは均と香苗、イヴがつい先日テーブルを囲んだ家に、やがて重く積もっていった。
#小説
#連載小説
#執事
#家カフェ
#おうちごはん
#読書
#ミステリー
#推理小説
#執事
#幽霊
#グルメ小説
#ミステリー小説
#社会
#しごと
#社会の不条理
#独身女性
#生き方
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
