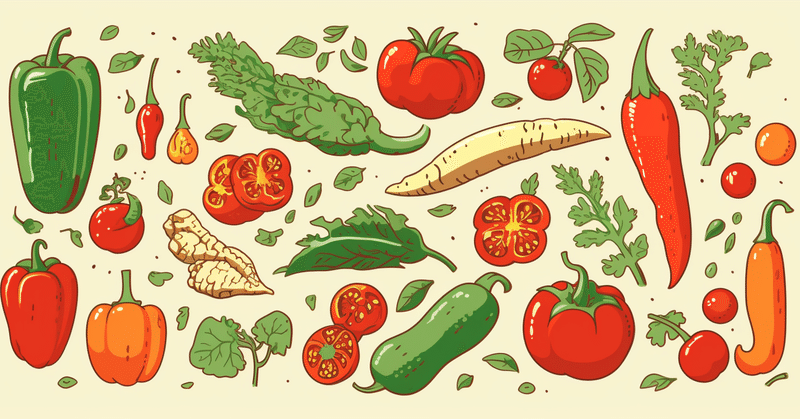
『野菜大王』と『文具大王』最終章
ネロがくれたもの
放課後、防災無線が地域の方々へ児童の下校見守りをお願いしていた。康太も普段の道を下校していた。前にはサッカー部の先輩が女子に囲まれて歩いている。先輩はエースストライカーで勉強も学年でトップクラス、康太とは比べ物にならないヒーローだ。網に入ったサッカーボールを左の肩から下げて、右手でペン回しをしながら歩く姿は格好が良い。そんな平和な風景に、突然春風が襲い掛かった。クルクルと先輩の右手で回っていたシャープペンシルが風にあおられ地面に落ちてしまった。コロコロ転がったペンは、康太の目の前で網のふたが付いた側溝に落ちた。康太が側溝をのぞき込むと、ペンはふたを外せば手で取れる位置に引っかかっていた。
「先輩! 網のふたを外せば取れますよ」
康太はここに居る六年生皆と自分が協力すればふたを外す事は造作もない事だと思った。
「良いよ。どうせ百円だから君に上げるよ」そう言うと先輩たちはキャッキャと楽しげに話しながら行ってしまった。
「どうせ百円? でもネロにとっては宝物なんだ!」
康太は心でそう叫んでいた。そして、網のふたを外そうと渾身の力で引っ張り上げた。でも、康太一人の力では鉄製の網は重た過ぎた。
「どうせ百円でも、これを作った人は大変な思いで作ったんだー」思い切り引き上げた。網のふたは少しだけ浮いた。その時、しわくちゃな大人の手が康太に力を貸してくれた。大人の力でふたは外れた。康太は、這いつくばってペンを拾い上げた。
「ありかとうございます」ペンを手にしてお礼を言った康太の前には校長先生が立っていた。
「君は物作りに携わる人々に感謝が出来る思いやりの心を持った素晴らしい児童(こ)ですね五年二組の山村康太君」
校長先生は嬉しそうに康太を見ていた。
「校長先生」
そう言いながら先生の顔を見た康太の頭の中に、突然フラシュバックが起きた。
ここに居る校長先生と、夕べ出会った野菜大王とは似ても似つかない顔なのに思いやりという言葉で康太には同じ人のように感じたのだ。
康太の頭の中には、夕べの出来事が次から次へと映画のように映し出されてきた。僕もファームへ行きますと言ったネロ、ネロの家では何を育てているの? と康太か聞いた時に、もう寝ようと寝返りをうったネロ、ネロの家、そして畑。その畑で育てていた野菜。
「ピーマンだ! ネロはピーマンの育て方を知っていたんだ」
世の中を変える武器は思いやりと言う武器しかない! と言った野菜大王の言葉が繰り返し、繰り返し、康太の頭の中に響いた。
「そうだよ! そうだよな! ネロ! ネロ! ネロ!」
いきなり叫んだ康太。その声にびっくりしている校長先生に、康太は深々とお辞儀をすると走り出した。
「そうなんだよ、ネロはピーマンの育て方を知っていたんだよな。知っていて僕を一人にしない為に、野菜大王と文具大王に嘘を吐いたんだよな」
康太は息が切れるのも忘れて走った。走りながら溢れ出る涙を何度も拭った。
「ただいま」
玄関を入ると一気に階段を駆け上がり、ベッドの横に置いてあった作業着のポケットをまさぐった。
「あった」
ポケットには、夕べネロが書いた住所が残っていた。康太は机の引き出しを開くと、使っていないノートや文房具を集め出した。
「これじゃ足りないよ」
一階に降りるとレストランの厨房で食器を洗っていた母親に向かって言った。
「お母さん! 預けてあった今年のお年玉出して」
「康太。突然どうしたの?」
「早く出して」
「何に使うの?」
「文房具を買うんだ!」
「いくら?」
「全部!」
「無駄遣いをするんじゃありませんよ」
「無駄じゃない! 大切な事なんだ!」
康太はそのお金を握り締めると一目散に走り出した。康太がもらった今年のお年玉は、近くの百円ショップで全て文房具やノートに変わった。
「どうしちゃったのかしら?」
「私も今朝、お父さんと呼ばれてびっくりしたよ」
「昨夜、何かあったのかしら? 見た事もない服がベッドの横に置いてあったのよ」
「みずみずしいピーマンを急に持って来たんだ。あれはどうしたのだろう? 今日は予約もないし、早く店を閉めて、夕食は店で食べる事にして康太とゆっくり話をしよう」
康太が大きな袋を引きずるようにして帰ってきた。
「ただいま」
「お帰り。康太! 夕飯は何が食べたい?」
「ピーマンの肉詰め! お父さんのデミグラスソースで」
そう言い残して康太は階段に向かった。
「どこ行くの?」
「宿題やる」
「やっぱりおかしい」
自分の部屋で康太は、買って来た文房具やノートに、今まで自分が無駄にしてきてしまった物を加えた。康太が宿題を終えた時「ご飯ですよ!」海苔の佃煮のコマーシャルの台詞が聞こえた。康太は大きく重たい袋を持って店に移動した。テーブルにはピーマンの肉詰めが置かれていた。
「今朝、康太が持って来てくれたピーマンだ」
あんなに嫌いだったピーマンを、本当に食べられるのかふたりは半信半疑で康太を見つめた。フォークで押さえてナイフで切って大口でピーマンの肉詰めを頬張る康太に、ふたりの目はパチクリ・パチクリ。
「美味しいね! やっぱりお父さんのソースは最高だ! 師匠にも食べさせたいよ」
「ところで康太。このピーマンはどこで手に入れたのかな?」
「僕が育てた」康太はピーマンを口に運びながら簡単に答えた。
「康太が育てたのか」
学校の授業で栽培したと解釈した。
「あの作業着はどうしたの?」
その問いにも康太はまたあっさり答えた。
「記念にもらった」
「誰に?」
「師匠に」
農業体験で農家の人が記念に下さったのだと解釈された。
「こんなに美味しいピーマンを育てられる師匠なら今度お連れしなさい。パ、いや、おお父さんがご馳走するから」
自分をお父さんと言うのに戸惑っていた父だった。
「無理かな」
康太はこれもまたあっさり答えた。
「忙しいのか」
「今となってはどこにいるか分からない」
康太の返事に嘘はなかった。
「宿題は終わったの?」
「算数はね。特別授業の宿題はこれから」
「特別授業の宿題って?」
「戦争を始めない為には如何したら良いかを家族と話をするの」
「難しい宿題だね」両親は戸惑いを隠せなかった。
「簡単だよ。最高の武器を使えば良いんだ」
「武器だなんて野蛮な事を言わないでよ」
「野蛮じゃないよ。だからその武器を使いたいので、お父さんとお母さんにお願いがあります」
「どうした? かしこまって」
父は夕食の和やかな顔から真面目な顔になった。
「これを送ってもらいたいのだけれど」
康太は、集めた文房具とノートをテーブルの上に出して
「これが僕の武器なんだ」
と言った。
「送るってどこへ?」
「あそこ」康太はネロを指差した。
「世界に学校を増やそう会に送るの?」
「そこを通して出来れば、この住所に送ってほしいの」
康太はポケットからネロが書いてくれたメモを出した。
「なんて書いてあるのかしら?」
「分からない。でも、カンボジアの文字。会の人なら分かると思うんだけれど、駄目かな?」
真剣な康太に親として息子の成長を感じた父親は優しく頷いた。
「送り主は山村康太で良いのかい?」
「僕で良いのだけれど、この通りに書いて欲しい」
康太は自分で書いたメモを渡した。そこには康太の住所と名前が漢字で開いてあり、さらにカタカナでルビが打ってあった。
「分かった、会の事務局に頼んでみるけれど、確実にこの住所に届くかは分からないぞ」
「カンボジアの農村部に届けばそれで良い」康太はポスターのネロを見ていた。
ありがとう
疲れているはずなのに康太は今日も眠れなかった。夜中になって人々が眠りについた頃だろうか康太の耳にまたあの童謡が聞こえてきた。
〽かごめ、かごめ、籠の名の鳥は、いついつ出やる夜明けの晩に、鶴と亀が滑った、後ろの正面だーあれ?
歌が終わると次は聞きなれた声だ。
「文具大王!」ガジャ!
「文具大王!」ガジャ!
「文具大王!」ガジャ!
康太は窓を開けてのぞいて見た。鉛筆の化け物が列を成して行進している。真ん中の籠にはサッカー部の先輩が入れられていた。
「ごめんなさい! もうしないですから勘弁して下さい」
「文具大王!」ガジャ!
「文具大王!」ガジャ!
「文具大王!」ガジャ!
先輩の泣き叫ぶ声を、化け物たちは勿論無視をして、シャープペンシルのような宇宙船に乗り込んでいった。そして消えた。
「有罪だな」
康太はそう呟くと文具大王の顔を思い浮かべながら静かに眠りについた。
翌日の放課後、いつもの帰り道、先輩と取り巻きの女子が、昨日シャープペンシルを落とした側溝を覗き込んでいた。康太はその光景を横目で見ながら通り過ぎた。(昨日のシャープペンシルはそこにはないよ。今頃カンボジアに向かっているかな)康太は心で呟いた。
二週間後、康太が学校から帰ると赤色と青色の縁取りが付いた封筒が机の上に置いてあった。
「お母さん、これは何?」
「手紙が届いていますよ、エアーメール。たぶんカンボジアからかな」
康太は封筒の宛先を見てもこれが自分の住所である事すら分からなかった。勿論差出人もしかりだ。
ただ、差出人の最後の行に書かれていた文字だけは康太にも読めた。そこには、こう書いてあった。
【アリガトウ、エンピツネロ】
了
最後まで読んでいただきありがとうございます。これ原作にどなたか漫画を描いてくれませんか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
