
吉田塾日記#11【FPM:田中知之さん】
クリエイティブサロン吉田塾
山梨県富士吉田市、富士山のお膝元でひらかれるクリエイティブサロン吉田塾。毎回、さまざまな業界の第一線で活躍するクリエイターをゲストに迎え、“ここでしか聴けない話”を語ってもらう。れもんらいふ代表、アートディレクターの千原徹也さんが主宰する空間です。第十一回のゲストはDJ / 音楽プロデューサーであるFPMの田中知之さん。

とにかく夢中になった90分でした。田中さんと千原さんのカルチャーの話は、飛び出したキーワードから二人の脳内リンクがタブをひらき、次々と新しいエピソードへと展開してゆく。京都METRO、ピチカート・ファイヴ、信藤三雄、渋谷系、東京オリンピック、アイスクリームフィーバー……二人の対話は美しく、芳醇な音楽のように、複雑性を帯びながらも雅な一本のラインを描いて広がってゆく。
クリエイター“千原徹也”の人生とことばを記録してきたわたしとしては、かけがえのない時間となりました。千原さんのクリエーションは「デザイン、ファッション、映画」のカクテルで成立しています。その中で、常に彼はカルチャーの重要性を説いてきました。“千原徹也”を形成するエッセンス。その意味が、ようやく理解できました。

それは、田中知之さんだからこそ、ひらかれた扉だったような気がします。“渋谷系”というカルチャーが生まれ、育まれていったその背景。当事者としてのその景色をどう見ていたか。クリエイターたちはその土壌から、どのように茎を伸ばし、葉を広げ、豊かな実を結んだのか。
渋谷系はまだ終わっていない。今を活躍するクリエイターたちに連綿と受け継がれ、その一つとして今年公開される映画『アイスクリームフィーバー』へとつながっている。千原さんが監督し、田中さんがサウンドトラックを担います。

クローズドだからこその熱気のある空間とエピソードの数々。実際に語られた話はほとんどここには書けません。まさに、“ここでしか聴けない話”。
ささやかですが、二人の対話の模様をお届けします。
クリエイティブの中で、何度も何度もやり直すプロセスはあって然るべきだ。オリンピックの時も、何度も意見交換しながら、時に喧々諤々となりながらも最終的にはハグをして終わった。
*
京都と渋谷系
千原:僕は当時、一般的なファンと同じ立ち位置で、京都のCLUB METROに田中知之さんや大沢伸一さんのDJの時に遊びに行っていた。隔月でピチカート・ファイヴの小西康陽さんがゲストにいらしてましたよね。
田中:はい、頻繁にお呼びして、京都や大阪でいろんなイベントをやりました。そのご縁で、僕がファンタスティック・プラスチック・マシーンを名乗ることになった。ソニーからリリースする3枚のコンピレーションCDの企画に「一緒にやろう」と声をかけていただいた。
その内の1枚が映画音楽のコンピレーション。そこで田中さんが選曲したものが映画『Fantastic Plastic Machine』のサウンドトラック。1970年に制作されたとあるサーフィン映画のタイトルだった。
田中:小西さんは最初このサントラをご存知なく、お聞かせするととても興味を抱いてくださった。音楽もそうですが、「ファンタスティック・プラスチック・マシーン」ということばに強い反応を示して、「ファンタスティック・プラスチック・マシーンという名前のバンドがあるといいよね」と小西さんが仰って、そのことばを真に受けて僕が名乗ることにした。
そこから「今度ピチカート・ファイヴでアルバムを出すからその中でデビューしなよ」と。
1995年、ピチカート・ファイヴのアルバム『ロマンティーク 96』内に、Fantastic Plastic Machine=FPM 名義の楽曲『ジェット機のハウス』が収録されメジャーデビュー。
田中:一般的には考えられない。ピチカート・ファイヴのアルバムに一曲だけFPM名義の楽曲が収録されている。小西さんは、そういうことを考えるのがほんと天才的としか言いようがない。そして、そのアルバムのアートディレクションをされたのが信藤三雄さん。
──ちょうど先日、信藤三雄さんの追悼パーティーがあった。
2023年2月10日、アートディレクター/映像ディレクター/フォトグラファー/映画監督/書家の信藤三雄氏は永眠した。3月20日(みつおの日)、『1日限りのSEE YOU !320展』と題して追悼パーティーがひらかれた。
会場では、元ピチカート・ファイヴの野宮真紀、コーネリアスの小山田圭吾、クレイジーケンバンド、オリジナルラブ、UA…と、そうそうたる面々がステージに立った。田中さんもDJとして故人を偲ぶ会を盛り立て、千原さんも関係者として招かれた。
田中:“渋谷系”は、一般的に音楽ジャンルを指すことばですが、実は音楽ジャンルに留まらない。渋谷系は、アートディレクションを含めたカルチャーとして生まれたことばだと思っている。その中心人物が信藤三雄さん。
千原:僕にとっては、信藤さんはアートディレクターの大先輩で、ユーミン、ピチカート・ファイヴ、Mr.Children、コーネリアス……さまざまなアーティストのCDジャケットをデザインされた人。一つの時代をつくられた人ですよね。
千原:今までの作品が展示されている会場を見回してみると、僕がこれまでに買ってきたものばかりがそこにあって。僕の撮った写真を見た妻が「自分の家を撮ったんじゃないの?」というくらい。すべてが思い出だったので、目頭が熱くなりました。
田中:渋谷系に最も影響を受けながらその遺伝子を次世代に伝えてくれているアートディレクターが千原くんだと思っていて。あのパーティーでも千原くんが完全にキーパーソンになっていた。
*
キーワードは“渋谷系”
当時、海外のメディアから取材を受けた時、どのメディアもおしなべて“渋谷系”ということばを使用した。

田中:“渋谷系”ということばが海を渡り国外へと広がってゆく現場を当事者として見せてもらった。今でこそ世界的に有名なフェスになりましたが、カリフォルニアの砂漠地帯で開催されるコーチェラの初回に僕とコーネリアスの小山田くんは出演している。2022年にはきゃりーぱみゅぱみゅさんが出演されて。
先日きゃりーちゃんが結婚された際のウェディングフォトのディレクションをしたのが千原くんなんだよね。
きゃりーちゃんと葉山奨之くんの結婚が今日発表になりました。
— Tetsuya Chihara / 千原徹也 (@thechihara) March 21, 2023
結婚報告写真をきゃりーちゃんとアイデアを出し合って組み上げて行くのが本当に楽しかった!
2人を囲む空間が幸せすぎました。
これからも一緒にクリエイションしましょう〜!
きゃりーちゃん、奨之くん本当におめでとうー!@pamyurin pic.twitter.com/0UgvIDfeZb
田中:4、5年前、千原くんにお会いした時に「はじめまして」と挨拶すると「はじめましてじゃないです」と言われた。理由を聞くと、昔京都のレコード屋で僕がサインをしたという。実際、千原くんの事務所に行った時にそのレコードが飾ってあって驚いた。
千原くんにサインをしたちょうど同じくらいの時期に、ニューヨークへ向かう飛行機の中でとある若者に声をかけられた。「ニューヨークに勉強に行くんです」と言うので、僕は「今からDJやるから遊びにおいでよ」と誘った。その彼が、後のきゃりーぱみゅぱみゅちゃんのライブ演出や美術デザインを担当する増田セバスチャン。
そこで、すべてがつながる。
渋谷系、千原くん、増田セバスチャン、きゃりーちゃん……
あれから25年──四半世紀経っているにもかかわらず、今なお脈々と受け継がれている。

音楽との出会い方は、ここ数年で大きく変わった。今でこそGoogleで検索すればデータベースがあり、クリックすれば簡単に手に入る。しかし、当時は実際にレコード屋に足を運ばなければ出会うことができない。おっかなびっくり視聴する。その体験と共に新しい音楽を発見してゆく。世界中でそのようなことが繰り広げられていた。
田中:当時、たとえばアメリカの地方都市のレコード屋さんのスタッフが一生かけて一枚見るかどうかわからないレコードが、渋谷のレコード屋には何枚もあった。一枚店頭から売れると、裏からストックが補充される。世界中の音楽が渋谷に集まっていた。
コギャル、チーマー、渋谷系のカルチャー……街自体があらゆる文化とマテリアルのメルティングポットだった。あの時代、渋谷を中心に音楽が世界をつないでいた。
田中:そして今、渋谷系をオマージュするような映画を千原くんが撮った。その映画のサウンドトラックを僕が制作させてもらっている。不思議なご縁です。
千原:新しいモノを取り入れながら、渋谷系のオマージュを表現しました。音楽は田中さん、そして、エンディング曲はまだ発表されていないのですが…
田中:ちょっとびっくりするような人なんですよ。なんと映画公開日(7月14日)にその7インチ盤が発売される。

*
サンプリング文化
「“渋谷系”はヘルベチカ・ボールドの字間でできている」と言えば言い過ぎかもですが、グルーヴィジョンズの伊藤弘さんも多用したヘルベチカ・ボールドとはタイポグラフィであり、王道の書体──
海外で日本のシティポップがブームになって久しい。この10年で山下達郎や松任谷由実など1970~80年代に日本で人気だったさまざまな盤がリバイバルされている。次に訪れるブームは90年代の渋谷系の楽曲ではないかと田中さんは予想する。
田中:あまり大きな声では言えないのですが、渋谷系の音楽は旺盛にサンプリングを取り入れている。それは、僕たちだけでなく当時のジャパニーズヒップホップ、ひいては世界中のアーティストに言えることなのですが。サンプリングを使用している楽曲は、著作権の関係でSpotifyやApple Musicにはあがっていない。
その辺りの楽曲が、今後レコード屋で高値になると予想しています。今、底値なので買うべきだと思います。
千原:配信できない音源のCDが高値で売買されるようになってゆく。この話って、まだ世間的には求められていないところですよね。
でも、サンプリングという文化が当時のおもしろさじゃないですか。サンプリング曲の元ネタを知っているということが、センスや知識だったと思うんですけど。

田中:いわゆる“引用”ですよね。パクリではなく、引用。僕は、リスペクトがあるものが引用だと思っています。
それは、渋谷系の根本にある思想。音楽だけでなく、信藤三雄さんのアートディレクションにもすべて元ネタがある。「ここから引用するのか!」というセンスまで含めて、渋谷系のカルチャーだった。
千原:音楽もそうなのですが、信藤三雄さんのジャケットが好きだったのは、60年代のCDジャケットや映画のポスターからの引用が取り入れられていて、そこからまた過去の歴史を知る楽しさがあった。
*
“渋谷系”第一幕の終焉
2001年3月31日、ピチカート・ファイヴは解散した。同年、911が起こる。時代が変わる瞬間だった。

千原:あそこが、ある種、“渋谷系”としての一区切りだったように思います。渋谷系や京都の文化、そこで培った人たちが本格的にメジャーシーンへ飛び出していった。
田中:あの時、僕、“禁渋谷”をしたんです。渋谷に行くとダメな気がした。人間、弱いものでレコード屋に行くとそこに陳列されているレコードのキャプションを読み「そうか、これが良い音楽なんだ」と盲信してしまう。渋谷の文化があまりに芳醇で、影響を受け過ぎてしまう。だから、渋谷から影響を受けることを一旦ストップして、自分の中で情報をセレクトしはじめた。
同年、田中さんは日本コロムビアからエイベックスへと移籍し、アルバム『beautiful.』をリリースする。
田中:もちろん“渋谷感”のようなものはすべて拭いきれてはいないですが、ディレクションとしては大きく変わった。
2000年代、リミックスのバブル期が到来する。バブル経済は90年代初頭に崩壊するが、音楽界のバブルはそこから5、6年後に訪れる。エイベックスは隆盛を極め、世の中ではCDが飛ぶように売れた。
田中:その恩恵が、我々DJにも流れ込んできて、そこでリミックスの仕事が増えた。僕たちの方からもリミックスを依頼する。あの当時はいろいろなことを考えていました。リミックスといってもDJのような人に依頼するのではなく、たとえば東京スカパラダイスオーケストラや冨田ラボさんなどに声をかけたり。
また、ダフト・パンクのギ=マニュエル・ド・オメン=クリストとのリミックスを実現。基本的に彼らはリミックスをほとんど請負わない。おそらく日本人で唯一の実例。
FPMの「Philosophy」という曲のRemixをDaft PunkのGuy-Manuel de Homem-Christoの別名義であるLe Knight Clubにお願いした。17年前の話。今聴いてもめちゃくちゃかっこいい。寡作な彼らだから大変光栄なことだと改めて思う。 pic.twitter.com/BXd3Hb8CkK
— Tomoyuki Tanaka (@tomoyukitanaka) February 23, 2021
田中:あと結局、リミックスとしては受けてもらえなかったけれどラーメンズの小林賢太郎くんに依頼したり。「さすがにリミックスはできないけれど、何かやりましょう」と言って仲良くなった。(2008年、小林賢太郎と共にユニットSymmetrySを結成)
千原:FPMの田中さんやラーメンズの小林賢太郎さんやコーネリアスの小山田さんたちがオリンピックの開会式に辿り着くというのは一入ですね。
*
東京オリンピック

2021年、田中さんは東京2020オリンピックの開会式/閉会式の音楽監督に就任(2020年東京パラリンピック開会式も同様)。渋谷系のカルチャーを育ててきた当事者たちが東京オリンピックのクリエイティブメンバーとして起用される。
千原:あの時は直前のアクシデントで大変でしたね。
田中:大変でしたけれど、僕はそれをひっくるめておもしろかった。いろんな人から「火中の栗を拾っていただきありがとうございました」と言われるのですが、そんなこと全然思っていなくて。予算がない状態の中で、いろんな方の協力の元、あそこまで辿り着くことができた。
いろんな方が辞めたり、辞めさせられたりする。蒸し返すつもりはないですが、僕にとってそれらは不幸な出来事でしかなく。その方々に恨みもなければ、むしろ「僕たちがかばいきれなくて申し訳ない」という気持ちしかない。
クリエイティブに携わった現場の人間たちは、誰一人みなさんから後ろ指を差されるようなことはしていない。日々ひたむきにベストな状況を目指して、幾多の困難が次々と襲ってくる中で粛々と準備を進め、開会式と閉会式を迎えたことをお伝えしたい。
東京オリンピックは準備段階からさまざまなアクシデントが起こる中、進めれらた。コロナウィルスという世界的なパンデミックと重なったことは言うまでもない。最初の大きな問題としては、ロゴデザインの変更を余儀なくされたところにはじまる。
千原:ロゴデザインを担当した佐野研二郎さんはグラフィックデザイン業界ではスター的存在で。その方がつくったデザインが「パクリだ」という話になり、世間から批判されて大炎上した。今でも僕はデザインとしては佐野さんのロゴの方が優れていると思っています。
みなさんにお伝えしておきたいことは、ロゴデザインというものはいかにシンプルにモノを届けるかということが大事で。シンプルさを追求すればするほど似たモノはどこかに転がっていたりする。それが「パクリだ」と言うのは、別の話に変わっていく。僕はあれはパクリではないと思っているんですよ。
田中:その辺りは繊細で難しい問題ですよね。パクリ、オマージュ、引用、サンプリング…いろんな表現がある。それらは一つひとつまったく違うものなのですが、なかなか明言できないものでもある。
僕は「かっこいいは正義だ」と思っている。結局、その「かっこいいは正義」が通らなくなってしまった世の中になってしまったのかもしれない。それは、つまらない世界でしょう。
あらゆるものは、すべて過去からの引用ですよね。アートも、料理も、ファッションも、すべて引用から生み出される。まったくのゼロイチを新しくつくることなんて不可能に近い。
千原:洋服は「パクり、パクられ」みたいなところがありますよね。パリコレに見に行き、国内ブランドがそれと同じようなモノをつくる。
田中:そういうものだから、なかなか一概には言えない。結局、すべてにおいてダメになってしまった。
千原:僕は1964年の東京オリンピックで亀倉雄策さんのつくったあのロゴこそすばらしいと思っています。おそらく、今までに開催されたオリンピックでもナンバーワンのデザインで、あれを超えることはできないのではないでしょうか。日の丸と五輪。特色の金赤にゴールド。完璧なデザインです。
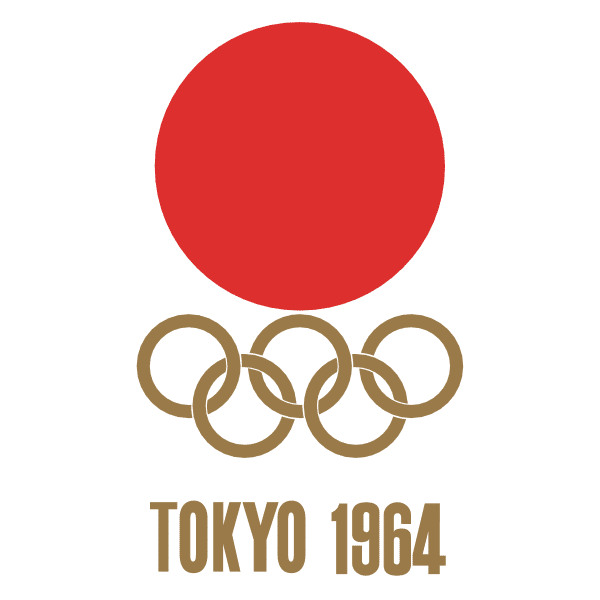
「僕は、リスペクトがあるものが引用だと思っています」
田中さんは、トークショーの中でそう言った。渋谷系はサンプリング文化であり、そこには知性と美意識が求められる。SNS時代、つくり手はもちろんのこと、鑑賞者もまたリスペクトと教養を養っていかなくてはいいモノは生まれない。受取り手の知性と品性の欠如が、有能なクリエイターの可能性を消すことにもつながる。
“渋谷系”というカルチャーの土壌が、なぜここまで豊かに育ったのかを考えることは、これから何かを生み出す者にとって重要なテーマだ。
*
アイスクリームフィーバー

2023年7月14日。“渋谷系”のDNAを受け継いだ千原さんの監督作品『アイスクリームフィーバー』が公開される。サウンドトラックはFPMの田中知之さん。渋谷系のリバイバルと共に、このカルチャーの第二幕がはじまるのかもしれない。
田中:並々ならぬこだわりでつくられている。「映画制作をデザインする」というキャッチコピーがあり、千原くんは映画をデザインしているんですよ。だから僕も単に映像に音楽をはめるだけじゃなく、音楽をデザインしなければならなかった。
音楽をつくるだけではない。デザインとして消化・昇華しなければならない。二つの「ショウカ」が必要で、それができたことが何よりの喜びだったし、大変勉強になりました。
次回の講義は五月二十七日。ゲスト講師はデイリーフレッシュ株式会社代表取締役/アートディレクターの秋山具義さんです。

チケットの購入はこちらからどうぞ。会場用とオンライン用、二種類から選べます。
+
そして、わたしも制作にかかわっている本塾の主宰、千原徹也さんの著書『これはデザインではない』もチェックよろしくお願いします。
いいなと思ったら応援しよう!

