
「私たちのラルゴ」 / 掌編小説

朝家を出て、私は駅前で事故に遭った。
前日は帰宅が遅くなり、私が勝手に書斎と呼んでいる四畳半の小さな洋間で書類の整理をし、それらが済んだのは日付けが変わった後だった。
妻はもう休んでいるようで、何だか眠りを妨げるような気がした私は、シャワーを浴び書斎のリクライニングチェアでブランケットにくるまって仮眠する事にしたのだった。
近頃、私達夫婦は少しぎくしゃくしている。
特に大喧嘩をしたとか、そのような理由となるものがあった訳ではない。
ただ何となくお互いの心の中にゆとりが感じられずにいたし、それぞれが必要以上に忙しい振りをして、向き合うべきものから敢えて目を背けているような気がしていた。
いつしか単調な共同生活をしている事が当たり前となっていたが、その感覚は麻痺や飽和に近い気がするのだ。
何か一つ、大切なものを手の中から砂浜に落としてしまい、しかし砂の中に埋もれたそれを探す作業そのものに倦怠感を感じているような...またいつの間にかその何かは埋まっている場所さえ定かでは無くなってしまった。
例えるなら、そんな感じだろうか。

私はこの日も自分で珈琲を淹れたが、これもいつからか私の日課になっていた。
二人分を淹れるのではなく、私は私の飲む分だけを毎朝淹れていた。
しばらくして起きてリビングにやって来た妻の恵莉子は、これも日課になった自然な仕草で自分が飲む分の紅茶を淹れていた。
「おはよう」
「...おはよう。昨夜も遅かったのね」
「うん。起こしたら悪いと思ってね、書類整理をした後にそのまま書斎で寝たよ。君も忙しそうだな」
「そうね、バタバタしてるわ」
食卓に向き合って座りながら交わす会話は毎日代わり映えが無く、それでも会話があるという事は良い事なのだろうと私は思う。
「...パンしかないわ」
「うん、今日はいいよ」
「そう」
妻は椅子から立ち上がり、自分の食べる分を焼き始めた。
「恵莉子...君は、私が居なくなっても一人で逞しく生きていけそうだな」
何故か、私の口からそんな言葉が滑り出た。
「えっ、何て?」
妻は半分聞こえていなかったのか、怪訝な顔をして聞き返した。
私は妻の名前を口にした事が久しぶりのような気がして、その事に少し戸惑いを感じていた。
「いや、何でもないよ。じゃ、行ってくる」
私は鞄を掴んで立ち上がり、玄関でくたびれた革靴を履いた。
「行ってらっしゃい」
リビングから、妻の声が小さく私に届いた。
理由の分からない気まずさもあり、私はいつもより少し早目に家を出た。
向かい風が冷たい。
駅に向かう人々は皆揃って俯き加減になり、そんな人々に混じり学生が颯爽と自転車で通学している。
そんな学生の一人が目の前の交差点を信号無視しようとして、私は声にならない叫びを上げた。
彼は自転車の前かごに入れた鞄から何かを取り出そうとしており、右折してきた車に気付いていなかった。
危ないと思ったのは一瞬の事で、学生を避けた車が速度を保ちながら私の方に向かって突っ込んできたのだが、こんな時はやけにはっきりと見えるもので、その運転手が学生を避ける寸前まで脇見運転をしていた事を私は目にしていた。
そして私は撥ねられた。
冷たいアスファルトの上に投げ出され、くたびれた靴の片方が弧を描いて飛んで行くのを私は感じた。
ざわめく朝の交差点。
私は生暖かいものが流れ出る感触を身体中に感じながら、そのまま気を失った。

私は病院に運ばれ、集中治療室に寝かされているようだった。
医師や看護士達が私の周りで慌ただしくしており、私はそんな眺めを私自身とその上の視点から同時に目にしていた。
それは不思議な感覚だったし、どうやら私は死ぬのではないかと思った。
私の身体はたくさんの管で機械と繋がっており、素人目にもそれらは危険な状態だと感じられた。
私が事故に遭ってからどれくらいの時間が経過していたのかは分からないが、やがてストレッチャーに乗せられた私は何故か集中治療室から出される事になった。
もう身体中から管が抜かれていたし、ストレッチャーを押す看護士達は既に私に無関心のように見えた。
看護士が出入口の壁の一部を足で蹴るとドアは開き、そんな仕組みになっているのかと私は他人事のように感心した。
外の通路の長椅子に、なんとも言えない表情をした妻の姿があった。
なんとも言えないのはストレッチャーの上の私の身体も同じで、ひどく蒼い色をして置物のように横たわっていた。
ああ、死ぬなと思った。
駆け寄ろうとした妻は看護師に阻止され、私の容態について説明を受けていた。
私は妻が駆け寄ろうとしてくれた事が嬉しかった。
僅かに視界が滲んで感じられた。
ああ、もう終わりなんだな...53年、思ったより短かったなぁ。
さよならだよ、恵莉子...君なら一人でも大丈夫だ、さよなら...。
「いやっ、あなたっ!!」
そう叫ぶ妻の声が通路に乱反射し、私の目の前は暗転した。

...そんな、夢を見ていた。
やけに臨場感溢れる夢で、リクライニングチェアから身を起こした私は額の冷や汗を拭った。
身体中を手で触れてみたが特に変化は無く、私は安堵した。
書斎の小さな窓に掛けたカーテンの隙間から、朝の光が射し込んでいた。
私は窓を開いて新鮮な空気を吸い込み、ブランケットを畳み直して椅子の上にそっと置いた。
冬の朝の空気は冷えた金属の表面のように私の肌に触れ、私は窓を閉めて洗面所で身支度をしようと書斎を出た。
クローゼットから取り出したシャツに着替え、ジャケットを手にしてリビングに入ると珈琲の香りがした。
珍しく妻が珈琲を淹れており、いつもメイクを済ませてからリビングに現れる妻がこの日は寝起きのままの姿だった。
「やぁ、おはよう。今朝は早いね」
「あ、おはよう...」
くぐもったような声で応えた妻の表情は無造作に乱れた髪でよく見えなかったが、少し瞳が潤んでいるようにも見えた。
「どうかしたのかい?」
「ねぇ、今から用意するから、食べましょう...一緒に」
「...そうか、悪いね」
私の問には答えず妻はやや早口でそう返し、いそいそとカップに珈琲を注いで私の前に置いた。
「おや、ありがとう」
妻は自分のカップにも珈琲の残りを注いでいて、二人分淹れていたのだと私は初めて気が付いた。
「君が朝から珈琲なんて、ちょっと珍しいね」
「今朝は...そんな気分なの」
少し気まずそうにした妻の背後ではコンロの上の鍋が微かに白い湯気をたてており、何か温かいものを用意しようとしていた様子だった。
私がその湯気を眺めていると、
「パンしかないけど...何かスープでも作るわ。まだ早いから、時間大丈夫よね?」
張り詰めたような顔で妻が言った。
「うん、特に急いでないから」
「良かった...。急にこんな事言うと変に思われるかも知れないけど....」
「なに?」
「今朝だけは...どうしても、あなたが出掛けるのを一秒でも遅らせたいのよ」
カップを両手で包みながら、妻は吐き出すようにそう言った。
「恵莉子...君は、私が居なくなっても一人で逞しく生きていけそうかい?」
私がそう言い終わらないうちに、妻はハッとした表情を見せた。
「どうもね、私は君が居なくなるとやっていけない気がするんだ」
私は努めて笑顔でそう付け足した。
「そんなの...無理に決まってるじゃない、私だって...」
「なら良かった、私達夫婦は両想いだ...あ、湯が沸いてる」
「やだ、忘れてた...!」
...私は、私が今朝見た夢を、妻も見たに違いないと思った。
目の前のテーブルの上にあるカップはちぐはぐで、元は確かペアだったような記憶がある。
片方が割れたり欠けたりして、それぞれが好みの物を別々に買ってきたのでこんな姿になっていた。
私は今日の帰り、どこかでペアのカップを買って来ようと思った。

くたびれた革靴を、玄関で履く。
「なぁ、恵莉子。今夜食べたい物をリクエストしてもいいかな?それとも、久しぶりにどこかで食べようか?」
私は見送りに来た妻にそう尋ねた。
「何がいい?私作るわ。外食は、また週末にでもとっておきましょうよ」
靴べらを使う私のすぐ後ろで、少し弾んだ妻の声がする。
「じゃあ、そうしよう。私は今夜、野菜がたくさん入った鍋でも君とつつきたいな。君も、食べたい魚なんかを入れたらいい」
「分かったわ、そうしましょう。あなた、春菊が好きよね?」
「いいね、楽しみにしてるよ」
私は立ち上がり、振り返って妻の髪を撫でた。
そこには15年程遡ったような表情の妻が立っていた。
「じゃ、行ってくる」
「行ってらっしゃい、今夜楽しみにしてるから」
私は妻に笑顔を返し、ゆっくりと歩み出して玄関のドアを開けた。
毎朝の私達の間に流れていた少し硬質で慌ただしいものが、温度と丸みを得て緩やかに流れを変えたように、私には感じられた。
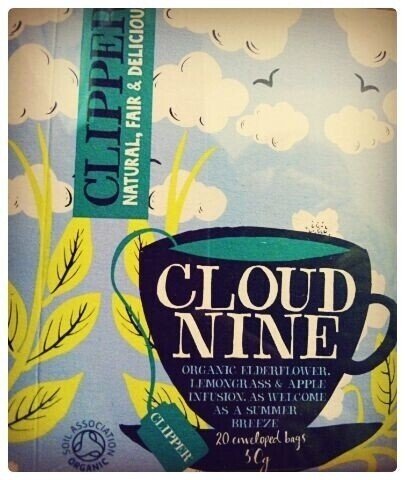
.+*:゚+。.✩ ☆。.:*・゜
過去作品より。
写真は適当なものがなく、発表当時の古いもののままです。
「夢オチを機に変わる」...そんな話だが、元は部分的に「夢で見せられた」というちょっと不思議な経緯が。
話の前後を繋げ一つの掌編にしたのだが、何処かの誰か...何か心に感じるものがある、そんな縁のある方に届くことを願って📝
...今宵、今年初めての望月です🌝
