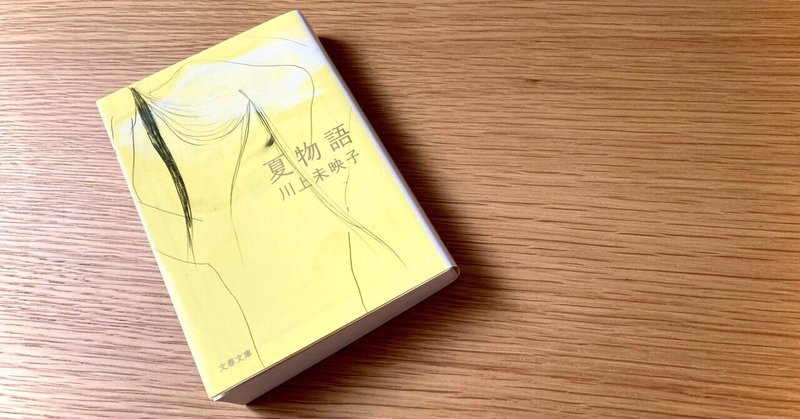
川上未映子『夏物語』感想
小説というのは膨大な量の文章がひとつの塊になって形を成しているためにその一部をどう説明しても全てを読み切らない限りはそれを説明したことにはならないのだと思いました。
今回読んだのは川上未映子さんの『夏物語』。2019年の7月に単行本が発行、今年の8月に文庫本化されました。本屋で手に取ってみると思っていたより厚みがあって少し怯みました。最近、ページ数の多い本をあまり読み切れていなかったので多分どこかで挫折して途中で読めなくなってしまうと思っていました。
実際は全くの逆で、読む以外の時間が惜しいくらい、隙間の時間を見つけては読み進めるほどに没頭して読み切ってしまいました。この感覚は中学生の夏以来で、文字がするすると入ってきます。こんなに滑らかにたくさんの言葉が入ってくるのは久しぶりでした。
しかし物語はその滑らかさとは相対して殴りかかってきます。初めて読む本が『夏物語』だったらその奔流に溺れていたでしょう。いままでの読書の体験が激しい流れの中でも立ち続ける体力をつけてくれたように思っています。
『夏物語』の登場人物たちはまるで一度会ったことがある人物かのようにビジュアルとして頭の中に現れ、物語の中を闊歩します。フィクションであるのに実在性を感じさせ、それは物語の迫真さをさらに増していきます。本を開くと別の世界がそこにある気がしてくるのです。
こんな緻密な物語を一体何年かけて書いたのだろうと、その年月の厚みを思いました。仮に1ヶ月で書き上げたとしても、それはとてつもない密度を持っているでしょうし、年単位の時間がかかっているとすれば、果てしないようにも思えるその執筆作業の末に生まれたこの小説は出産によって生まれてくる子どもにも似たような側面を持っているのではないかと思いました。
この本の中にはひとつの世界があると、そう思いました。小説を書くことはひとつの世界をどれほど緻密に作れるかにかかっているのではないかとさえ思いました。読んでいる間、主人公の隣でずっとその生きざまを見ているように感じられました。
だからこそ一緒になって喜んだり傷ついたりしました。傷は何度も抉られ、その度にどうにか自分の精神を本から引き剥がして、これは本当に自分が傷ついているわけではないと言い聞かせなくては主人公と一緒に奈落にさえ落ちてしまいます。これは読者である自分に責任があって、生きて読み終えなければなりません。
この、本から自分の精神を引き剥がすのが中学生の頃は全くできませんでした。それが小説でフィクションだと分かっていても頭のどこかで現実とほとんどイコールなのだと思い込んでいたのです。
だからもうあの中学生の頃の読書体験とは似ているようで違います。中学生の自分にはなかった知識や経験が糧となって自分の足で立ったまま読み切れたような感じがしました。
本は書く人だけでなく読む人にも努力を求めるのでしょう。読む人間を試すように物語がそこにあります。
追記
この感想を書いている時にはすっかり忘れていたが、物語の終盤で友だちの出産の話を思い出した。1年前、自分の出産の話をたくさん話してくれた。
友だちの妊娠を知るまで、本当の意味で子どもが生まれてくることにあまり良い感覚を抱いていなかった。まさに善百合子の考え方が僕が中学生の頃に思った感覚そのもので、生まれる意志もなく生まれてきたのに生きて苦しまなくてはいけないのかと思っていた。
でも、友だちの妊娠を知った時、もうすぐ子どもが生まれてくると知った時、僕はいままでに感じたことのない感覚で「嬉しい」と思い、その感覚はなぜかあたたかかった。自分も子どもを生みたいと、その時は本気で思っていた。
生まれる意志もなく生まれてきたことに変わりはない。生まれてしまえば人間としてそれ相応の痛みを受ける時もあると思う。生まれるって、生むって、なに。僕はいまだにそれがよく分かっていないし、善百合子の考えは昔の自分の考えにとてもよく似ていて、そしていまも残って自分の根底のどこかに流れていて、善百合子の絶望は簡単には希望に転じないのだとよく分かる。
夏目夏子の考え方も善百合子の考え方も、どちらも僕の中にある感じがする。混ざり合っている。善百合子に救われてほしかった。それは過去の自分が救われることとほぼ一緒だからだ。過去の自分を救うことはいまの自分を救うこととほぼ同じなのだと、最近何度も思う。
もしよろしければサポートお願いいたします。
