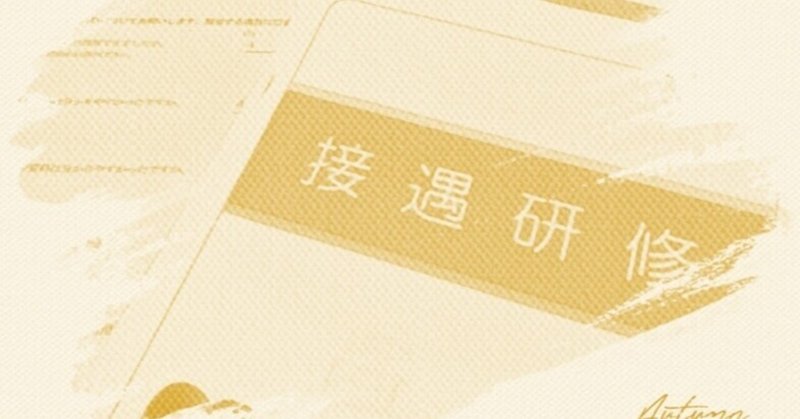
接遇研修、社会人一年生のつもりで…
今日は、人権研修でした。私は、障がいのある人が利用する事業所を経営しています。私たち支援者は、定期的に人権に関する研修を受講することが義務付けられています。今年は「接遇」というテーマで研修を実施しました。
実践に活かすための研修
今年度の研修は、新しい試みをしました。従来の研修は、私が講師を務めたり、近隣の事業所の方に来ていただいたり、個々で研修センターが企画する研修に参加していました。それに対して、今年度の研修は、コンサルティング機関を利用し、自分たちの法人の実情に応じた研修を組み立ててもらいました。
また、研修の目標は、確実に実践ができることです。そこで、今後は、同じテーマで同じ講師で、学びを深めていきます。受講することが目的ではなく、実践に活かすことが目的です。
社会人一年生の気持ちで…
研修では「接遇」というテーマの中に、社会性や社会人としてのマナーを盛り込んでいます。私たちは、障がいのある人たちの支援をしています。支援者の仕事は、利用者本人へのかかわりだけでなく、地域社会との窓口になります。また、専門職同士の多職種連携が求められます。そこで、上手に連携するための心得を習得することが必要です。
今回は、初回なので、あいさつや名刺交換、電話対応、メールの打ち方などからスタートします。受講する支援者は、20代から60代まで幅広い層がいます。しかし、全員が初心に戻って、社会人一年生として受講します。

支援者都合の支援をしないために
初歩からスタートする理由は、支援者は、専門性が高い反面、社会性に欠けることが指摘されることにあります。とくに私の法人は、成り立ちが小規模の自主運営から始まっています。小規模事業所だったころは、連携ではなく自分たちで完結でした。まだサービスが整っていなかったという時代背景もあります。他機関と調整することなく、支援をしていました。しかし、時代は変わりました。それぞれが持ち味を活かして連携しなければいけません。
また、グループホームは、家庭的なかかわりが中心です。自分たちのホームのことしか見えなくなります。その結果、そのホーム特有のルールができます。それは、支援者の価値が優先された、つまりは支援がしやすいルールです。利用者目線のルールではありません。また、支援者が身内のようにかかわり、兄貴分のように上から目線になることがあります。そのため今回は、基礎から見直します。
法人のスタンダードマナーを作る
今回の研修は、社会と通じること、失礼のないやり取り、そこがポイントです。また、この研修から、法人のスタンダードマナーを作ります。そのため、全員が一度に受講することが理想です。しかし、日常業務があるため一度に受講することができません。来月、同じ内容で半分の職員が受講します。私も、来月に受講します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
