
「北欧のメルカリ」にサービスデザイナー/UXデザイナーとして就職して1年半の感想
僕は現在Schibstedという、北欧のメディア+テックのコングロマリットでサービスデザイナー/UXデザイナーとして働いている。この会社には2021年の2月から在籍しているが、就職して1年半以上が経過したので、その感想を公開できる範囲で書く。
フィンランドで働くということについては以前、IDBMの先輩である国枝さんからインタビューしていただいた記事もあるが、今回はもう少し深堀した業務内容や、ソフト面の感想といった部分も交えてまとめてみたい。
(国枝さんからインタビューいただいた記事はこちら→)
会社組織の構成
Schibstedの本体はノルウェーにあり、オスロの証券取引所にて上場している。
"北欧のメルカリ”と言っても実はサービスは1つだけではなく「北欧各国におけるメルカリ的サービス」を全て保有し、開発・運営している。ノルウェーではFINN、スウェーデンではBlocket、デンマークではdbaとBilbasen、フィンランドではToriとOikotieに分かれている。
また、この会社にはメディアの柱もあり、ノルウェーとスウェーデンにいたら無視することはできないニュース媒体であるAftenposten, VG, Aftonbladet, Svenska Dagbladet等も保有している。(他にも多数のビジネスエリアがあるものの、当記事では割愛する)

サービスはそれぞれのブランドでそれぞれの国でオペレーションされているが、丸っと一つの組織として戦略設定や必要な情報共有、運営がなされている。ファンクションによっては国を横断してチームを組んでやる仕事もある。自分を例に挙げると、自分はフィンランドのデザインチームに所属していながら北欧全体のデザインチームにも属し、北欧全体の不動産マーケット部門にも属しているというマトリクス型の組織編成だ。
デザイナーとしての仕事
僕はフィンランドの不動産情報サイトであるOikotieを作っている。肩書きはサービスデザイナー/UXデザイナーであり、双方の役割を兼務している。
サービスデザイナーとしての役割と業務内容
簡単に言うとユーザーがどういう課題を抱き、我々がどういうサービスを提供できるかの機会発見を経て、戦略レベルに関与して事業開発を進める仕事だ。細かなグラフィックやインタラクションデザインよりも、幅広い視点からサービス全体を俯瞰し、良い顧客体験を提供することを目標としている。
広く理解されている職種定義上のサービスデザイナーとしてする仕事は(多分)どこの国のIT企業と比べてもそこまで特別なことはしていないと思うが、具体的にすることを挙げると以下のようなことをしている。
1. デザインスプリント等ワークショップのファシリテート
新しいビジネスや大幅なUXの変更を検討した際、チーム内でデザインスプリントをファシリテートした。5日間かけてやる「ガチデザインスプリント」もやったものの、何人ものメンバーを動員して1週間ワークショップをやるのがスケジュール的に難しい(無理ゲー)部分もあり、2日間でやる「省略型スプリント」も行った。その他にも様々なワークショップをファシリテートし「自分一人の」よりも「チームの力を引き出して」良いアウトプットを出すという点に重心を置く。
2. ユーザーインタビューの設計と分析
定性的データ収集の一般的な手法であるが、実際のユーザーの洞察を得るためにユーザーインタビューを計画して行ない、分析してエンパシーマップ等に落とし込み、価値のあるインサイトを導き出す。
3. サービスブループリントの作成
これは外部コンサルタントの力も借りて出来たことなのだが、不動産バイヤーのジャーニーを最初から最後まで俯瞰してまとめたサービスブループリントもゼロから作成した。「家を買う」や「家を売る」という行為があまり日常的に行われるものでなく、且つ、大きな金額とリスクを伴うものであるため、これを定義してユーザーのエンド・ツー・エンドの行動を包括的に視覚化できたのは良かった。
4. 顧客満足度の測定と改善
製品の中に簡易アンケートを表示して顧客満足度を測り、製品改善ポイントを洗い出したりもする。これは一度やれば終わりというものでもなく、継続的にまわしている。
5. プロトタイプの各種テスト
これはサービスデザイナーのする仕事なのかUXデザイナーの担当なのか意見が分かれるかもしれないが、色々な形でユーザーテストも行う。実際のユーザーにプロトタイプをテストする場合もあれば、簡略化してデザインチーム内でやる場合もあるし、製品に実際に組み込んでABテストを行うこともある。その時によってベストな方法を選ぶ。
UXデザイナーとしての役割と業務内容
1. サイトや画面のUIデザイン
UXデザイナーとしては製品機能を実際にfigmaを使用して詳細な画面デザインまで落とし込み、エンジニアと共同して開発を行なっていく。
2. デザインシステムの構築
残念ながら今の組織には「デザインシステム担当」のデザイナーが存在するだけの贅沢はできないため、僕もデザインシステムの構築と改善に貢献している。
上記サービスデザイン/UXデザインの解説は僕の業務内容の一部であり、各手法の具体的な解説等は割愛するが、定性的・定量的、双方のデータを駆使して良いサービス作りを目指している、とまとめることができる。
「IT系のデザイナーとして」特別なことはしていないが、書き出してみると「何でも屋」に近いゼネラリストデザイナーなんだなということに気がつく。
デザインチームの構成について
フィンランドではデザイナーは合計で(2022年9月現在)10人前後いる。Toriを担当する人とOikotieを担当する人に分かれ、それぞれのチームに"派遣"されていく。週に1度、デザイナーミーティングでみんな集まり、それぞれ情報共有や互いの状況を報告しあう。会社ではSlackを使っていて随時連絡を取り合っている。北欧全体ではデザイナーは60〜70人近くいて、月に一度の頻度でオンライン会議/イベントがある。
働いてみた所感
「すごく働きやすい」というのがストレートな感想だが、できるだけ客観的に長所と短所を絞り出す。
良いところ
1. 自分の仕事が多数の人々に影響する
僕が担当しているOikotieはフィンランド国内最大の不動産市場サイトなので、自分の仕事のアウトプットが多くの人に届く。インパクトを生む仕事に携われるのは嬉しい。一方で、ユーザーからのフィードバックも多数もらう。そしてその全てが良いフィードバックではなく、改善点は山のようにある。なので仕事としてはチャレンジングだと感じている。
2. リモートワークが許可されている
会社はフルリモートを許可している。最低必須出社日数もない。僕はマックス週1度の出社という頻度。かなりのレアキャラだが、完全リモートメインの社員も多い。コロナ後のリモートワールドになって以来、僕は30分の通勤すら面倒に感じるようになってしまった。
3. オフィス環境も快適
とはいえ、出社したらしたでメリットもたくさんある。オフィスには専属のバリスタが美味しい抹茶ラテをいれてくれるし、日替わりでシナモンロールや様々なおやつが振る舞われる。ヘルシンキ中央駅から徒歩5分、周囲にはあらゆるレストランが揃っていてランチの行き場所に困ったことはない。同僚もみんな良い人たちばかりなので雑談も弾む。チームはポジティブに励まし合えるし、建設的な批評をお互いに出せるのもありがたい。

4. 他国とのコラボの機会がある
北欧の他の国のチームとも共に仕事ができるのも良い。デザインチームとしての成熟度はノルウェーとスウェーデンが一番高く、やはり彼らと一緒に進める仕事はこちらも学びが多くて気持ちいい。
5. デザインの価値を会社が理解している
会社全体のデザインに対する価値の理解が深く、自分が製品とデザインにオーナーシップを持てるところもこの会社の良い所だ。僕が最も緊密に連携しているPM(プロジェクトマネージャー)が何ごとに関してもすぐに相談チャットを飛ばしてくるあたりも、デザインへの理解とデザイナーへの信頼を表していると思う。
悪いところ
「北欧では夏の1ヶ月間を丸っと休む」というのは大体のところ本当だ。7月はほぼ全てオフなので、その間はあまり仕事が進まない。ちょっとズラして休暇をとる社員がいた場合、そしてその社員の仕事が必要な場合、帰ってくるのを待つしかない。なので業務の進行がゆっくりすぎるかも、と感じることが無くもない。
とはいえ、これも「強いていえば」というレベルの話なので、それでも「別に良い」と思えば別に良いのかもしれない。

ワークライフバランスについて
フィンランドのIT企業でのワークライフバランスはやはり素晴らしいと実感する。日本の会社で働いていた時には夢にも見なかった、午後4時(たまに午後3時も)に終業。終業したら仕事パソコンと仕事スマホは一切見ない。完全OFFだ。仕事が終わったら後は自分の時間であり、家族の時間なのだ。残業という概念がない。これが常識なのであり、そうでないと逆に「効率の悪い変な奴だな」と思われる。

ここでは物理的に働いている時間は、僕が日本で仕事していた時よりも圧倒的に短い。それでもなぜか仕事は進んでいるし、働いていて成長している実感がある。
結局のところ、「やるべきことをやったらOK」ということなのだろう。日本では仕事の中身よりもその「体裁作り」にやたらと奔走していた気がする。「根回し」や「稟議」や「稟議のための根回しをするための飲みニケーション」など。今考えるともはや漫才だ。日本の生産性の低さに貢献していたのは自分だったのかもしれない。
意外なチャレンジ
これは意外でもなんでもないかもしれないが、言語の壁というものがあるのでそれについて触れておきたい。
会社では共通言語として英語が使用される。これはIT企業だから、というだけでなく、北欧各国を横断してオペレーションしている会社なのでどうしても共通言語を敷く必要性があるからだ。なので、フィンランド語が喋れなくても働ける(マーケティング職や営業職など、ローカルの顧客とやり取りする必要がある職種を除く)。IT企業に多い形式で、エンジニアやPM、デザイン職は現地語を喋れなくても採用されるし、十分活躍もできる。
しかし、特にサービスデザインではユーザーのインサイトを得るためインタビュー等のリサーチスキルが要求されるのだが、これは「調査をしているその国のローカル言語ができる」ということが前提にあると思う。例えばユーザーインタビューをする際、インタビューされる方は(普通)ローカルの言語の方が本音を出しやすいので、フィンランド語で出来た方が有利だ。UIデザインをする場合でも画面に表示する文や単語など、細かく気を配る必要がある(UXライティング)。これは日本や英語圏にいても同じだ。なので、サービスデザイナー/UXデザイナーとしての僕は"ネイティブによる翻訳作業”が必要になる。デザイナーとしてフィンランド語がネイティブでない、というのは実はディスアドバンテージだという現実と向き合っている。
フィランドのデザインチームのうち、僕以外は全員フィンランド人であり、フィンランド語ネイティブでないのは僕だけだ。なのでデザインチームミーティングは僕のためにわざわざ英語で行われる。
また、デザインチームでないミーティングでも僕一人だけが外人、というシチュエーションも多々ある。オンラインのミーティングで自分より先に既に何人か集まっていて、全員フィンランド人(参加ボタンを押す前に誰が入室済みか画面に表示される)だと、会議開始前のスモールトークはフィンランド語で行われている。そして僕がジョインした瞬間、英語に切り替えてくれるのがわかる。これはありがたいものの、申し訳なくなるのも正直な感想だ。なにせ会議参加者のマジョリティーはフィンランド人なのだ。普通に考えてもフィンランド語で会議した方が効率は良いはずだ。
ローカルの言語能力が低いので翻訳作業等、他者の助けを必要とする状況では自分の存在価値を人一倍発揮し、アピールしないといけないと思う。それがチャレンジだ。会議で発言することがなくても、必ず何かを発言する。質問やちょっとしたコメントでも良い。そこに外人である自分がいる意味・意義を出さなくてはいけないと思う。
学び
ドメインレベルでの学びが多くあると考える。
僕は不動産マーケットプレイスのサイトのサービスデザインを担っているため、現地の不動産ドメインの知識が少しばかりついた。その知識を使い、2021年に実際に中古アパートを購入した。
自分自身がデザインしているサイトの使いやすい部分、使いにくい部分も露骨に感じ取れた。結構究極のdog-feeding(自分が設計したものを自分で実際に試す)であった。

近況報告
2022年の5月にはオスロで北欧各国のデザインチームが集まるカンファレンスがあり、60名程のデザイナー仲間と知り合えた。

全体での交流会もあり、それぞれの担当ドメインに分かれてワークショップも行った。僕は不動産マーケット部門に所属しているので、ノルウェーとスウェーデンの不動産マーケット部門のデザイナー達と一緒にワークショップを行った。各国の不動産事情や規制の違いなども聞けたのも収穫だった。
また、一つ大きな気づきだったのは、ノルウェーにおいてFINN(ノルウェー版メルカリ)の存在感は圧倒的だということ。不動産の売買すらFINNが担っている。ノルウェー国内において競合はなく、市場を独占している。

FINNの一人のデザイナーが「デザイン学生はFINNで働くことに憧れるし、そこらの道端で(FINNのロゴの)この青色を見せれば誰もがFINNの色と答えるわ」とも言っていた。「ノルウェーでは我々が最強感」が滲み出ていた。肩で風を切って歩くその自信に恐れ入った。
この先
不動産事情の学びが多く、専門的な知識も身につけることができていると感じる。さらにドメインナレッジを深めたいと思う。
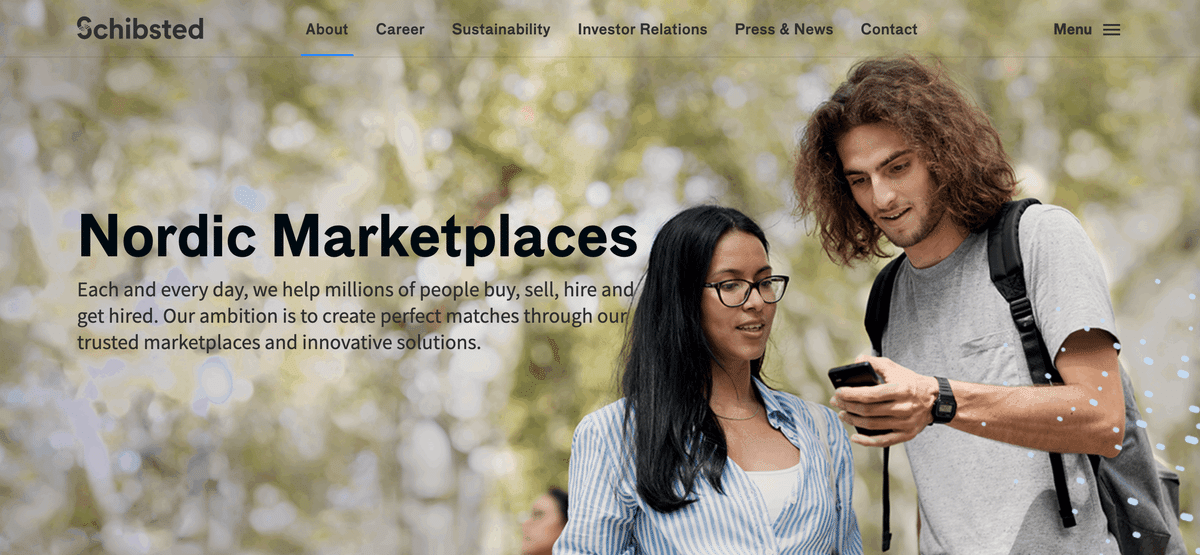
ここで公開できない情報も多いが、グロース産業の中にいる以上、変化は激しい。社会も組織も変わるときには大きく変わる。今の状況がずっと続くとも限らないが、この会社に入って良かったし、他の方にもオススメできる会社だと思う。宣伝にはなるが、エンジニア職やデザイナー職は常に募集している。何か質問があれば是非ご連絡いただけたらと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
