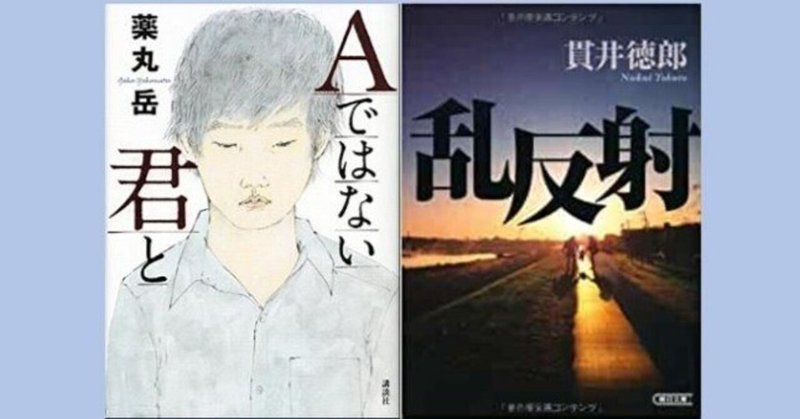
2022年に読んでグッときた小説
2022年も12月になり、そろそろ終わる。
今年は約30冊程度の小説を読んだ。ダン・ブラウンの「ダ・ヴィンチ・コード」シリーズなど、外国人作家の小説にも挑戦してみた。
2022年に読了し、かなり良かったと感じた作品は下記の2作。
①Aではない君と/薬丸岳(やくまるたけし)
②乱反射/貫井徳郎(ぬくいとくろう)
①は少年犯罪の話で、非常に重たい内容。
②は「風が吹けば桶屋が儲かる」を連想させる内容。
①の「Aではない君と」から記載していく。
※なるべく、ネタバレにならないよう配慮しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「Aではない君と」の「A」とは、少年犯罪の際の匿名の「少年A」のこと。
少年犯罪の加害者側をメインに描いた話。
ある日、会社員の父親に中学生の息子が逮捕されたと連絡が入る。
容疑の内容は同級生の殺人。殺人容疑の取り調べを進めていくうちに、殺された同級生から「いじめ」を受けていたことが明らかに。果たして、息子は同級生を殺してしまったのか。
「息子は同級生を本当に殺してしまったのか。」「殺人したとして、その動機は?」
この辺りが読み進めていくうちに、分かっていくわけだけど。
「物語の結末がどうなったか」ではなく、「読了して何を思ったか」が問われている作品。
加害者の父親目線(親目線)で書かれている小説であり、非常に心苦しい内容で考えさせられる。
実際に、少年の殺人は今の日本でも起こっているわけで。リアルにこのような事件があったのではないかと思わされた。
私自身、子供がいるわけではないが、、もし自分に子供がいたとして、殺人を犯してしまったと考えると…
殺人の動機にもよるけど、息子が殺人罪を犯した時に、親としてどういう行動をするのか。
遺族側の気持ちを第一に考えるのか。それとも、愛する息子のことを考えて「保身」的になってしまうのか。
言い方は悪いけど、加害者になることは紙一重なところが大きいかなと感じた。ほんのちょっとした些細なことで、人生って変わってしまうものだし。「いじめ」をするもされるも、小さなことから始まって大きくなるもの。
かなりリアルに描かれているので、高校生以下くらいまでのお子さんがいる親御さんには薦めてはならないのかな。逆に、子を持つ親御さんにこそ、お薦めすべき小説なのかな。何にせよ、加害者家族の苦しみが相当に感じられる作品である。
テーマが非常に重いこともあり、終わり方はスッキリとはしない。小説に楽しさを求める人には向かない作品。けど、胸をえぐられる分、かなり印象的な作品になると思う。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
著者の薬丸岳さんは、少年犯罪に精通している作家さん。「少年犯罪」について、勉強するという観点でも大変おすすめ。
「友罪」という作品も、少年犯罪を題材にしていて、「Aではない君と」と同様で考えさせられる内容。「友罪」は少年犯罪をしてしまった青年のその後の人生を書いた作品。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ここからは「乱反射」について。
読了後だが、「乱反射」の意味を調べてみた。中学の理科の用語だった。忘れていた。以下のとおり。
入射した光が不規則な方向に反射すること。鏡面(平面)のように、表面上の任意の1点で光学的な反射の法則を用いて反射光の方向を定めれば、他の点での反射光は改めて計算しなくても自動的に決まるような場合を正反射という。
要は凸凹の面だと、不規則に光は反射する。それが乱反射。
貫井徳郎さんの小説の中でも、「乱反射」はかなりの人気作品で。「乱反射」が1番好きだという声を目にする。私も貫井徳郎さんの小説を他に3、4冊ほど読んできたが、これが1番良かった印象。難点は文庫本で、600ページほどあるので少し長い。けど、サクサク読めると思う。
ある日、幼児が強風によって倒れた街路樹の下敷きになってしまう。病院に運ばれたが、死亡が確認される。
「不幸な事故」とも捉えられるが、本当にそうだったのか。幼児の父親は息子の死について、疑問を感じる。調べていくうちに、様々な人の「身勝手な行動」が明らかに。
街路樹伐採に反対する主婦、街路樹に犬のフンを放置する老人、犬のフンを処理しなかった市役所区員、救急外来を受けつけなかった夜間医師、軽い風邪で夜間診療を使う大学生 など… 彼ら彼女らの行動がまさかの事故に。
「風が吹けば桶屋が儲かる」を思わせる内容と冒頭に書いたが、この諺(ことわざ)の意味を知っているだろうか。語源は以下の通り。
①風が吹くと、目にゴミが入る。
②目にゴミが入ると失明する。
③失明した人は、三味線を仕事にする人が多い。(江戸時代当時は)
④三味線を作るうえでは、猫の皮が必要。
⑤猫が減るので、ネズミが増える。
⑥ネズミは桶をかじる。桶が不良になり桶の需要が増える。
⑦結果、桶屋が儲かる。
風が吹くことと桶屋が儲かることに、因果関係はない。要約すると、「全く関係ないことから、意外なところに影響がでる」という意味。
現代でも、語源と似たような連鎖の現象は起こっている。というより、毎日がその繰り返し。事柄A→事柄B→事柄C→事柄D………∞。これが無限大に繰り返されているのが人間社会
「乱反射」はまさにそうで。全く関係ないところから、結果的に幼児が大きな事故で亡くなってしまう。各自の小さな身勝手な行動が不慮の事故を起こすことって、私たちの生活でも起こりうる。
例えば、赤信号で横断歩道を渡る、満員電車の割り込み、ゴミのポイ捨て、歩きタバコ とか。
こういった小さな「罪」が積み重なって、大きい事故は起こるもの。
「ハインリッヒの法則」を耳にしたことがあるだろうか。
「1つの大きな事故の要因には、29の小さな事故があり、その背景には300の異常があるという法則」、「1:29:300の法則」とも言う。
たとえ、小さなモラル違反だったとしても、それが大事故に繋がってしまったら、一生後ろめたさを背負うことになってしまう。
自分の行動が誰かに悪い影響を与えていないか。軽い事でも、「まあいいか」で終わらせていいのか。自分への戒めの意味でも、非常に考えさせられる小説だった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「Aではない君と」と「乱反射」の2作品を取り上げてみた。
2作に共通しているのは、「身近に起きても不思議ではない」、「非常に考えさせられる」という2点だ。読んでいて、学生の頃の「道徳」の授業を思い出すかな。
この記事をきっかけに、今回の2作品を読んでいただけたら幸いだし、感想を聞いてみたいな。好きな小説の感想を語らう機会って、なかなかないし貴重な時間なので。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
